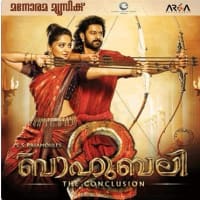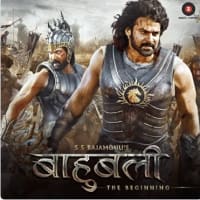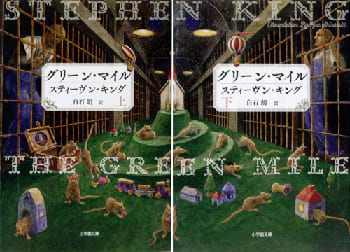
原作 スティーヴン・キング著
映画 フランク・ダラボン監督
僕はキングの小説はなんとなく読まず嫌いで、映画化されたものはちょぼちょぼ見ていたけれど、小説は短編の「霧」しか読んでなかった。
グリーンマイル - 予告編
映画版「グリーンマイル」はお伽話みたいだった。いまさらだけど小説をあらためて読んでみると、基本のお話は一緒でも、かなり手触りが違う。
小説では、「救済と呪いに何ら違いは無い」という大変印象的なセリフがポールによって語られる。「あっ」と思わず声が出た。つまらない言い方だが目からウロコ的な、いわばテーゼだった。この言葉はいくつかの受け取り方が出来ると思う。
まだ電気椅子で処刑が行われていた頃、世界恐慌時代のアメリカ。1935年、コールド・マウンテン刑務所に、輸送車のダンパーがかしぐ程の大きな体をした黒人コフィーが収監された。彼には不思議な癒やしの力があった。
コフィーは、何人かの者に肉体の回復を与え、非道な者に報いをもたらす。彼を理解した者達の嘆きをうけながらも無実の罪を引き受け、電気椅子にて昇天する。
コフィーの治癒を受けた、看守ポールは、「力」の一部を受けつぐこととなった。ポールは、妻に死をもたらした大事故をも生き延び、百十四歳にしてようやく自らの死を予感し、この本文である手記を書いた。あらましはこんな感じ。
信仰をベースにした現代の寓話、映画は特にそんな感じだった。(ポールとはパウロ、サウロのことであり、キリストの教えを広めた者なのだそうだ。(知りませんでした))
映画だけ見ていた僕が、小説を読んでちょっとした違和感をおぼえたのは、犬に顔を噛まれた少年のエピソード。主人公の看守ポールは、コフィーの犯したとされる罪に疑問をいだき、独自に関係者への聞き取りをはじめる。そこで出会った新聞記者の息子は、飼い犬から、ある日突然、生涯残るような深い傷を負わされた。従順でおとなしかった愛犬に。物語の主な筋にかかわらない一挿話としては、理不尽なまでに無残だ。小説と映画では全然意味合いが違う。
映画でも同様のエピソードは描かれるけれど、少年の傷は小説ほど絶望的ではなく、彼の父(映画では弁護士)がいう、「犬も黒人も、愛情をかけていても裏切られる」(だからコーフィの事を調べても無駄だ)というセリフでおさまりがついてしまう。小説版は、到底これでは収まらない内容を秘めているように思う。
善人や悪人、善行や悪行の積み重ねなど関係なく災厄はいきなりやってくる。神がいたとしてもその意図はあまりに不条理で理解など出来ない。小説ではいきなりこんな出来事を突きつけられる。(悪霊などの存在はこの小説では注意深く否定されている)読んでいてとにかびっくりする。
ポールとその妻が遭遇するあまりに凄惨な事故も、ポールの同僚たちがその後たどった運命なども同様だ。
改めて見比べて見ると、映画では、小説にある何かとんがったところが綺麗に丸められて、わかりやすい因果応報の大衆演劇になっている。少年を襲った犬は脈絡もなく何かに命じられたのだ。そういう不条理な恐怖が映画では欠けてしまっている。
物語にとっての、面白さの核は、作家の世界観にあると僕は思っている。
理不尽に無残な運命のあとに語られる「救済と呪いは本質的に同じものである」というテーゼは、これまで現実の事件や、優れた物語りに接しておぼろに感じていた事をズバッと言ってもらったように感じ感銘をうけた。こういう視点にふれることが出来ただけでもこの小説を読んだかいがあった。
コーフィの救済によって与えられた力ゆえに、愛する人の死を多く見なければならなかったポールが、自らの境遇に対してて発した言葉という理解で合っていると思う。けれど小説ではそれ以上に、吹き荒れる嵐のような不条理に輪郭を与えるようなところがあると思う。
本質的に人間の解釈を越えた世界で、まやかしの人間という視点さえどけてみれば、救済と呪いは本質的に同じものなのだ、ともとれる。作者はそこまでのことは言っていないのかもしれないが、僕はそう感じて衝撃をうけた。
悪人は、奇跡をなす者と善意の人々によって報いをえました、というのが映画で描かれた因果応報の世界。だが、悪人だけで無く善人にもひとしく、きまぐれな残酷で悲惨な運命が吹き荒れてゆくかもしれない。というのが小説で描かれていた世界だろうか。現実世界はまさしく後者のようであると思う。
理不尽な運命というのはキング作品には共通するものなのだそうだ。他の作品も読んでみようかな。
引用 小学館文庫版下巻 P425 「わたしは恐るべき真実を悟ったーー救済と呪いのあいだには、本質的なちがいなどなにひとつありはしない、と」