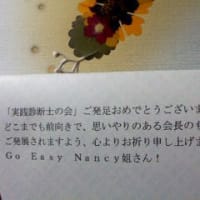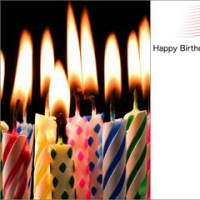読み終わってみて、サブタイトルの「企業の究極の目的とは何か」の、生産管理面での一応の提案が投げられている感があるが、その後のマネジメントについてはまだ思考プロセスの途中のような感がしてならない。続編に隠されているのだろうか?
読み終わってみて、サブタイトルの「企業の究極の目的とは何か」の、生産管理面での一応の提案が投げられている感があるが、その後のマネジメントについてはまだ思考プロセスの途中のような感がしてならない。続編に隠されているのだろうか? 運営管理で学んでいろんな手法。かんばん方式やQC7つ道具や、これはゼッタイ覚えなさい!とマークしたいろいろなことを一気に説明してくれた。こういった現在の運営管理に導入されている手法は、実はものすごい試行錯誤の末に生み出されたものであったのだなぁ・・・と。
運営管理で学んでいろんな手法。かんばん方式やQC7つ道具や、これはゼッタイ覚えなさい!とマークしたいろいろなことを一気に説明してくれた。こういった現在の運営管理に導入されている手法は、実はものすごい試行錯誤の末に生み出されたものであったのだなぁ・・・と。仕掛在庫は負債か資産か。。。とか。
本社でいじりまわす○○指標は現場で通じない。。。とか。
 ボーイスカウトのキャンプ(遠足)で一番歩くのが遅いハービーにちなんで、ボトルネック工程をハービーと名づけて、改善に試行錯誤するのだが、ラインバランスをとるだけではよくならない(どころか悪化する)と恩師は言う。スループット(through-put 処理量)に注目すべきだということに気づいていく過程が丁寧に書かれていて、生産現場を知らなくても次第に事態が飲み込めた。
ボーイスカウトのキャンプ(遠足)で一番歩くのが遅いハービーにちなんで、ボトルネック工程をハービーと名づけて、改善に試行錯誤するのだが、ラインバランスをとるだけではよくならない(どころか悪化する)と恩師は言う。スループット(through-put 処理量)に注目すべきだということに気づいていく過程が丁寧に書かれていて、生産現場を知らなくても次第に事態が飲み込めた。正月に弟1号が「注目すべきは付加価値に繋がる作業をしているかどうかだ」と言っていたのを思い出した。
 運営管理のテキストに着手するまえにこれを読んでいたらすごく違っただろうな~。後半、少しテキスト読みになってた(笑) 少しメモをとった。
運営管理のテキストに着手するまえにこれを読んでいたらすごく違っただろうな~。後半、少しテキスト読みになってた(笑) 少しメモをとった。
Step 1 ボトルネック(制約条件)を見つける
Step 2 ボトルネック(制約条件)をどう活用するか決める
Step 3 他の全てをStep2に従わせる
Step 4 ボトルネック(制約条件)の能力を高める
Step 5 Step4のボトルネック(制約条件)が解消されたらstep1に戻る
*尚、惰性を原因とする制約条件をはっせいさせてはならない
 If ~、Then ~ という思考プロセス
If ~、Then ~ という思考プロセス 『何を変える』『何に変える』『どうやって変える』
『何を変える』『何に変える』『どうやって変える』 究極の目的・・・自分の目的はなんだろう~。それはテーマが大きすぎかな。
究極の目的・・・自分の目的はなんだろう~。それはテーマが大きすぎかな。ということで、診断士試験に合格するという目標で考えてみた。
制約条件が変化していくってどういうことか? 最初は工場内での在庫過多等の問題があったのだが、それが改善されていくと制約条件は市場へと変わっていった。Swot分析だと内部環境の「弱み」が外部環境の「脅威」に移ったということか? あるいは5つの競争要因の6番目に社内の制約も加えて考えるべきか? なーんて。
自分もいまだ理解できない経済のグラフやいろいろ。でも部分的最適化に注目するのは後回しにすべきだなー。合格が目的なら、それに必要なことを優先。いやいや、診断士に何が求められているのかをみつける、理解するところが一番重要なんじゃないか? 中小企業が置かれている環境(マクロ的でもミクロ的でも)について、Nancyは何も知らないではないか。一歩二歩遅れているようなことじゃなく、根本的なところをおろそかにしていた。
 主人公の恩師のように、科学的な視点が必要かな。
主人公の恩師のように、科学的な視点が必要かな。精神論でどーのこーの言ってるのは、ちょっとエリアが違ったな~。
少なくとも、Nancyがこだわり過ぎていたのは確かだ。
おとといまで、予習予習に必死になっていたのが、可笑しい。
気分よく受講することが目標になってはいなかったか?
わからない授業が辛いから、そのことばかり考えていた
予習したところで、わからないことだらけなのに。。。(恥)
視点を変えて、これまで通り過ぎた過去問を見直してみようと思う。
予習・復習のやりかたもね。
少なくとも今までのNancyの考え方は間違えていた~
『何を変える』『何に変える』『どうやって変える』を考えてみたい。
 最後に、今朝の「経済羅針盤」で営業の常識を変えるというテーマが取り上げられていたが、そのことがオーバーラップしてきた。日本でここまで生産現場で生産性について改善が行われてきているのに、営業現場ではどうか?完全に出遅れてる感がある。この辺を提案に書けるかな?(猶予は1ヶ月)
最後に、今朝の「経済羅針盤」で営業の常識を変えるというテーマが取り上げられていたが、そのことがオーバーラップしてきた。日本でここまで生産現場で生産性について改善が行われてきているのに、営業現場ではどうか?完全に出遅れてる感がある。この辺を提案に書けるかな?(猶予は1ヶ月)