
「インテリアコーディネーター東京」主催の椅子の工場見学に参加してきた!
 川崎駅に午後集合!大型バスにて縫製工場→本社工場(他工程全て)を見学ののち、会社のプレゼンテーションがあり(沿革とポリシーなど)、懇親会という盛りだくさんな会だった。参加者は全員、インテリアコーディネーター有資格者なのだが、建築士、設計士、デザイナー、経営者、家具デザイナーなど様々な分野の方が参加されていた。Nancyにとっては、インテリアコーディネーターとしての初公式アクティブ!デビューとなった(笑)
川崎駅に午後集合!大型バスにて縫製工場→本社工場(他工程全て)を見学ののち、会社のプレゼンテーションがあり(沿革とポリシーなど)、懇親会という盛りだくさんな会だった。参加者は全員、インテリアコーディネーター有資格者なのだが、建築士、設計士、デザイナー、経営者、家具デザイナーなど様々な分野の方が参加されていた。Nancyにとっては、インテリアコーディネーターとしての初公式アクティブ!デビューとなった(笑)
 【インテリア的視点】
【インテリア的視点】
材料の歩留まり向上を追及すると職人技が必要。一見、工業品にみてる商品も実は職人の手作りであった事実に感銘。
牛革は牛の皮を背骨で真二つに切ったものがロールになった状態で仕入れられる。
独特の皮模様は実は細かい傷隠しの型押しであった。
ヨーロッパと日本での価値観の違い。どこで売るかによって仕上げを変えるという発想から、日本のコンシューマをeducateするという発想に転換!
ここでインテリアコーディネーターが活躍できるか?!
 【診断士的視点】
【診断士的視点】
椅子職人であった先代の意思を引き継ぎ、現社長、そして後継者である常務が会社をひっぱっていっている。3年前に大改革。下請けからの脱却。高級家具製造の技術を生かし、OEMを開始。50人いる社員・職人みなで自社の進む道をともに考え決めた。それは北欧家具という道。3年前から毎年デンマークに職人2人を武者修行に出し、感性を磨き技術を得るということをし、会社としてもデンマークの有名ブランドと提携を続けている。職人レベルのライセンスを取得、日本で唯一というものを確立。。
最大の得意技は、短納期だとも。事前打ち合わせ、すり合わせさえしておけば、中2日で納入が可能(業界一般では3週間~1ヶ月かかる)
完全受注生産に切り替えたため、仕掛在庫はゼロ。
短納期実現のために材料の在庫は抱えている。
取引先が後継者難により減少。設備と職人を譲り受けることでこれまで外注していた工程を取り入れている。
最近はインテリア関連雑誌と家具デザイナーとコラボした企画モノを展開。パブリシティ効果絶大。
「実験室」と呼ばれる場所があり、いろんな「実験」をしているのだそう。将来的に自社ブランド展開のための研究をしている。
 アグレッシブだったーーー。
アグレッシブだったーーー。
 川崎駅に午後集合!大型バスにて縫製工場→本社工場(他工程全て)を見学ののち、会社のプレゼンテーションがあり(沿革とポリシーなど)、懇親会という盛りだくさんな会だった。参加者は全員、インテリアコーディネーター有資格者なのだが、建築士、設計士、デザイナー、経営者、家具デザイナーなど様々な分野の方が参加されていた。Nancyにとっては、インテリアコーディネーターとしての初公式アクティブ!デビューとなった(笑)
川崎駅に午後集合!大型バスにて縫製工場→本社工場(他工程全て)を見学ののち、会社のプレゼンテーションがあり(沿革とポリシーなど)、懇親会という盛りだくさんな会だった。参加者は全員、インテリアコーディネーター有資格者なのだが、建築士、設計士、デザイナー、経営者、家具デザイナーなど様々な分野の方が参加されていた。Nancyにとっては、インテリアコーディネーターとしての初公式アクティブ!デビューとなった(笑) 【インテリア的視点】
【インテリア的視点】材料の歩留まり向上を追及すると職人技が必要。一見、工業品にみてる商品も実は職人の手作りであった事実に感銘。
牛革は牛の皮を背骨で真二つに切ったものがロールになった状態で仕入れられる。
独特の皮模様は実は細かい傷隠しの型押しであった。
ヨーロッパと日本での価値観の違い。どこで売るかによって仕上げを変えるという発想から、日本のコンシューマをeducateするという発想に転換!
ここでインテリアコーディネーターが活躍できるか?!
 【診断士的視点】
【診断士的視点】椅子職人であった先代の意思を引き継ぎ、現社長、そして後継者である常務が会社をひっぱっていっている。3年前に大改革。下請けからの脱却。高級家具製造の技術を生かし、OEMを開始。50人いる社員・職人みなで自社の進む道をともに考え決めた。それは北欧家具という道。3年前から毎年デンマークに職人2人を武者修行に出し、感性を磨き技術を得るということをし、会社としてもデンマークの有名ブランドと提携を続けている。職人レベルのライセンスを取得、日本で唯一というものを確立。。
最大の得意技は、短納期だとも。事前打ち合わせ、すり合わせさえしておけば、中2日で納入が可能(業界一般では3週間~1ヶ月かかる)
完全受注生産に切り替えたため、仕掛在庫はゼロ。
短納期実現のために材料の在庫は抱えている。
取引先が後継者難により減少。設備と職人を譲り受けることでこれまで外注していた工程を取り入れている。
最近はインテリア関連雑誌と家具デザイナーとコラボした企画モノを展開。パブリシティ効果絶大。
「実験室」と呼ばれる場所があり、いろんな「実験」をしているのだそう。将来的に自社ブランド展開のための研究をしている。
 アグレッシブだったーーー。
アグレッシブだったーーー。









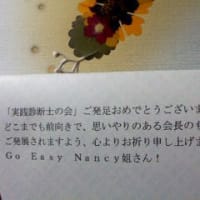
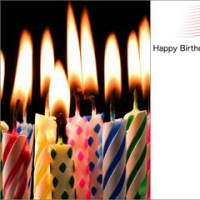



たぶん、この本社工場、川崎の工業団地内のところなら、
行ったことある会社ですYO--(間違っていたらごめ
んなシャイ)。
ところで、
OEMなら、まだ下請けかもねー。
うちの会社も、自社製品作っているけど、まだ売上の8割
は下請け仕事だYO。って、かんけーないか。。
下請けからの脱却って、とてつもなく難しくすぐにでき
ることじゃないよ。その会社さん(違うかもしれない
けど 合ってたらその社長と話ししたことある)なら、
いけそーだけどね。
ちなみに、製品在庫がないんだよね。 仕掛在庫はあっ
た気がするが。。
診断士視点だったので。。。すんません。
瀋陽は、3月上旬に行ってきまーす。
楽しみでーす)^o^(
それにしても良い会社ですね。
・後継者がいる
・組織全体としての意識改革ができている
・全社的な方向性が一致している
・人材開発に力を入れている
・ドメイン設定が明確
・受注、生産方式の転換
・コミュニティー戦略
・研究開発を行っている
・将来の自社ブランド戦略を見据えている
ただ、
設備と人材の受け入れで、固定費が膨らまないのか?が心配なところ。
自分的には、まだまだ診断士として必要なキーワードがスンナリ頭から出てこないのが問題ということを再認識させられました。
JFEのウラのほうって感じでしょうか。。。(笑)
私もOEMならまだ下請けだよねーーって思ったので、質問をしてみたのですが、下請けとOEMはベツモノという考えで動いていらっしゃいました~
家具の山を見て、「これって在庫ですか??」って質問したところ、「ウチは在庫ゼロ」とのご回答。お客様からあづかった家具でこれからリフォーム作業に取り掛かる家具たちとの説明でした。そっか、だからこれは製品在庫がゼロで、仕掛かり在庫があるということか。。。そーだそーだ(^_^;)
両方の視点ごちゃまぜで、他の皆さんとはズレタ質問いっぱいしてしまったけれど、社員一丸となっている気迫が凄かったです~。
プレゼンの時に、大きな高級椅子が運ばれてきて、コレを作れるようになることが社員全員の目指すものだとおっしゃってました。感動しました。その椅子がデンマークで製造されている映像も見せていただき、デザイナーの目指したコンセプトとその意思を引き継ぎ形にする職人魂みたいな部分に心打たれました~。
ここまで明確な目標があると、がんばれちゃいますよねーー。本当に、いい経験をさせてもらいました!
瀋陽出張、おいしいものいっぱい食べてきてくださいねっ。3月はまだ寒いかも~
大連経由でもしお時間があるのでしたら、「海鮮料理」だけは逃すことなく、食べてくださいね。(食べることばっか、考えてるぅ)
「OEM」とは、御社に素晴らしい製品がありますが、ラベルだけ張り替えさせていただいて、弊社で販売させていただけませんか?ということ。
「下請け」とは、弊社で設計した図面があるので、御社で作って納品していただけませんか?ということ。
と、噛み砕いて理解してるんですが、どうでしょうか?
とりあえず、私達の共通言語として中小企業が主人公という立場で考えると。。
自社の素晴らしい部品を自社にて販売するだけでは生産能力が余ってしまっているので、自社名を出さず、御社製品に自社部品を納入させてもらうのがOEM。
下請けは、元々親子もどき関係があるなかで、親方から「これ作れー」の号令に従い、作って納品する。
と思ってました。
ちなみに、この会社は
①OEM 国内外の有名メーカーのカタログ商品を請負製造している。短納期に対応するために、材料のストックを抱えている。
②家具のリフォーム 個別受注している。
ヨーロッパの有名ブランド品についてライセンスを取得しており、国内で正規リフォームできるのは当社だけという強みもある。。。
以前は親方的会社1社の下請けとしての仕事が全体の8割以上だったのに比べ、①60%、残り②という風に変革したのだそうです。
その有名ブランドというのが、ホント中途半端じゃない有名さで、本場と強いコネクションを各レベルで構築しているところに凄みと本気度を感じちゃいました。職人レベル、営業レベル、経営者レベル、それぞれのレベルで親密なおつきあいを展開しているそうです。
誘っていただいたので来年あたりにはプチ参加させてもらおうかと思ってたりして。。。(笑) 実現したら、超ひさびさの欧州ということになります。
一応ネットで調べると
--- OEM ---
Original Equipment Manufacturer
相手先ブランドで販売される製品を製造すること。また、製造するメーカー。
OEMメーカーから製品の供給を受けたメーカーは、自社ブランドでその製品を販売する。製造の委託を受けたメーカーは、相手先のブランドと販売力を活かして生産量を向上させることができる。
---
・相手先の販売力を活かす
・生産量を向上させる
の2点が味噌だと思いました。
--- 下請け ---
下請けは、色々な定義があるようなのですので割愛。
いろいろ調べてくださりありがとうございます。
上の問いかけについて、いろいろ考えていたのですが、閉鎖してしまった下請けの設備とヒトを引き受けること自体をマイナス要因として考えないほうがいいのかなぁっと思っています。要はどこまで活用できるかかと。すでに償却も済んでいる設備とノウハウ蓄積された人材は宝物(コアコンピタンス)になりえますしねっ。
この椅子工場のように、材料/素材そのものが高いという事情もあり、機械加工にすると歩留まりが悪くなるので、職人技で素材を余りなく利用することを重要視していました。
昔からあることなのに、形骸視されがちだったこういったことが、実は高付加価値化へのひとつのアプローチなのかも知れない。個人的にはヒジョーに共感持てるコンセプトですー。