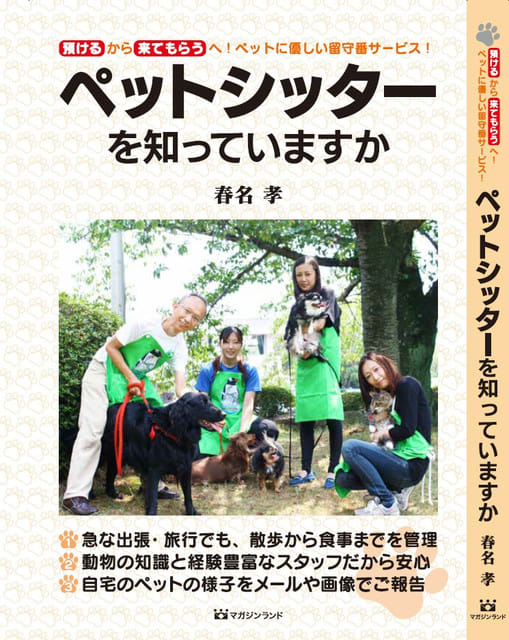前回は本の第3章までについて、何を元に文章を書いたのかをご紹介しました。今回はその続きです。
第4章「ペットシッターであり続けるために」では、僕が普段どんな方針で仕事をしているのか、作業では具体的にどんな注意をしているのか、などを記載しています。僕としてはかなり本音を吐露した部分であり、書くのに少し勇気がいりました。
本文でも書いていますが、僕はこの本を、読んで実のあるものにしたいと強く願っていました。あたりさわりのない内容では、結局誰のためにもならないと思ったからです。だから勇気を持って書き進めました。結果として、おそらく他のペットシッターさんが書かないような独自性のある内容になったと自負しています。本を読んだ方から、「春名さんの人柄が現れていますね」と言われたことがありますが、おそらくこの章のことではないかと思います。また、「こんなところにまで気を配っているんですね」と言われたこともあります。これはおそらく、メールや報告文での言葉遣いのあたりかと思います。
口頭で伝えるのと違い、文章でのやりとりは思わぬ誤解を生じることがあります。そして、そのことに無自覚な人もけっこういます。それでも、他人からもらったメールの言葉がやけに冷たく感じられたり、詰問されているような気持ちになったことは誰にでもあるかと思います。ネットでの議論なども、ほんの些細な言葉のチョイスが原因だったりします。ペットシッターは他の仕事に比べてなお一層、信用が第一であり、すこしでも嫌な気分を持たれてしまえば次の依頼が来ないことにもなります。そのあたりは充分すぎるくらいに気をつけて作業をしており、本章ではそのことを詳しくご紹介しました。
この第4章にも、元になった文書があります。スタッフの研修用に作ったいくつかの資料の中に、ペットシッター・ジェントリーの基本方針をまとめたものがあります。これは、スタッフが研修をほぼ完了し、これから開業するという時点で、最後の研修として使うものです。
ペットシッター・ジェントリーの一員として働いてもらう以上、僕の考えていることを伝え、共有してもらう必要があります。文書では、基本理念からはじめ、それを元にした具体的な作業例がまとめてあります。研修では、この資料を基に口頭でいくつか補充をするのですが、それらをすべて含めて文章化していきました。
第5章「お客様やペットとのふれあい」では、仕事を始めてからの体験、お客様からいただいたお言葉、それらから得た教訓や信念を紹介しています。心に刻みつけられるような出来事はずっと忘れないものですので、それらを忠実に文章化していきました。お客様からのお言葉は、Webサイトに掲載しているものをほぼそのまま使いました。
巻末の「おわりに」では、ペットシッターの将来や、これから続けていくにあたって思うこと、などを随想的に書きました。報告書の見本を2種類、添付してありますが、これはどちらも実際にお客様に提出したものを、お客様の氏名をイニシャルにした以外はそのまま載せています。
これで元になった資料の紹介は終わりです。次回からはいよいよ、出版に向けてどういうアクションを起こしていったのかを、お伝えしていきますね。