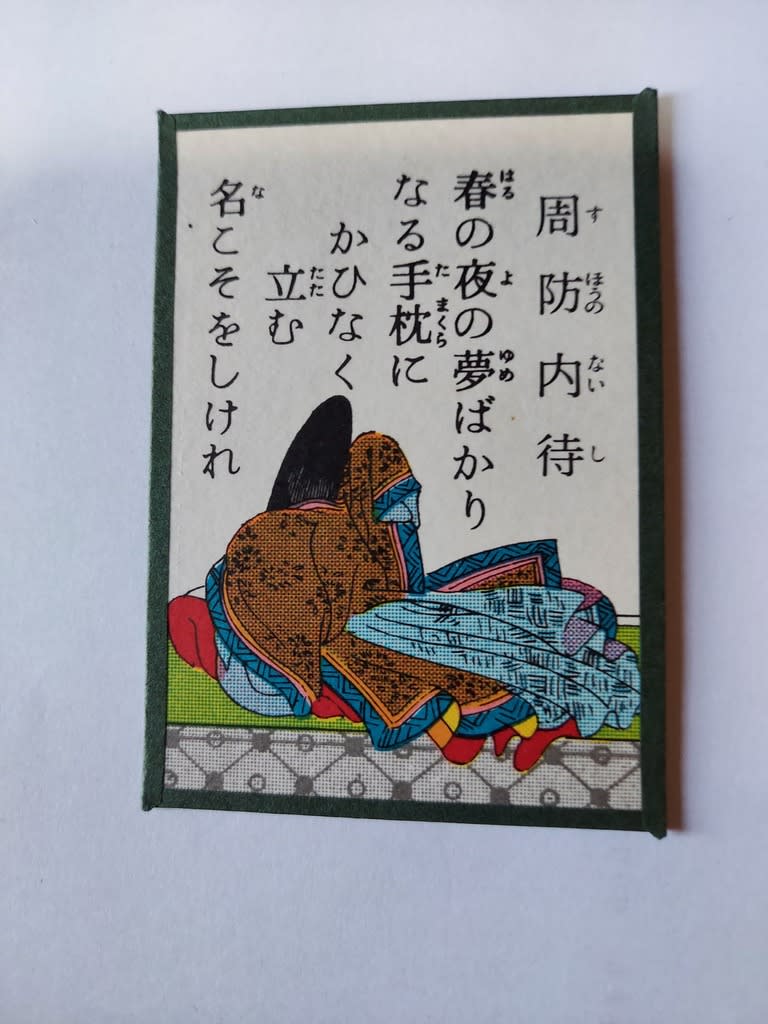第七十首

さびしさに 宿をたち出でて ながむれば
いづこも同じ 秋の夕暮れ
良暹法師
(生没年不詳) 詳しい伝記は不明。比叡山の僧で、祇園社の別当。洛北・大原に隠棲、晩年は雲林院に住んだという。
部位 四季(秋) 出典 後拾遺集
主題
ものみなが秋の夕暮れの寂寥をたたえている感慨
歌意
あまりの寂しさに、庵の外に出て辺りを物思いにふけりながら眺めてみると、私の心が悲しみに沈んでいるせいだろうか、どこもおなじように寂しい秋の夕暮れであるなあ。
おそらく定家は、この良暹の歌に、新古今的寂寥の美へとつながるものを感じとっていたのであろう。
「この淋しさは、まだ純粋に西行的のものだと言えない」と言われるが、すでに『百人一首』の歌としては、「寂寥に澄み通ってゆく淋しさ」の方向に鑑賞されていたといえよう。
天台宗祇園別当。長元から康平にかけて、源経頼・素意法師・橘俊綱らと交わる。山城大原に移り住んだ頃に詠んだ歌のようです。『後拾遺集』以下に三十二首入集。