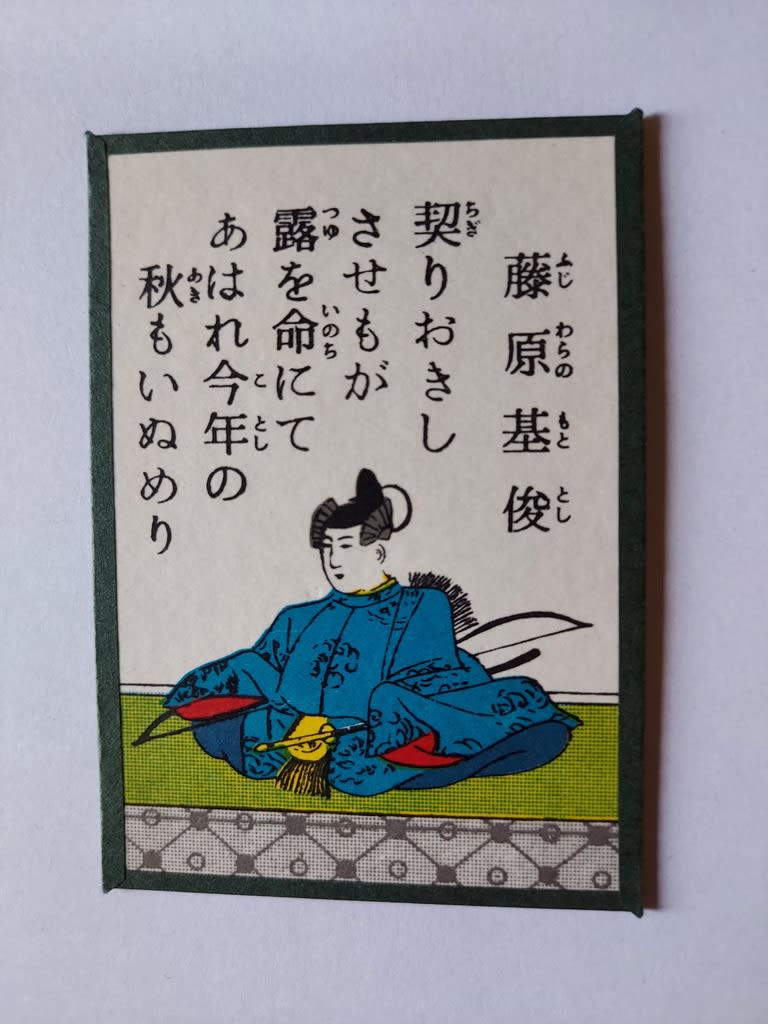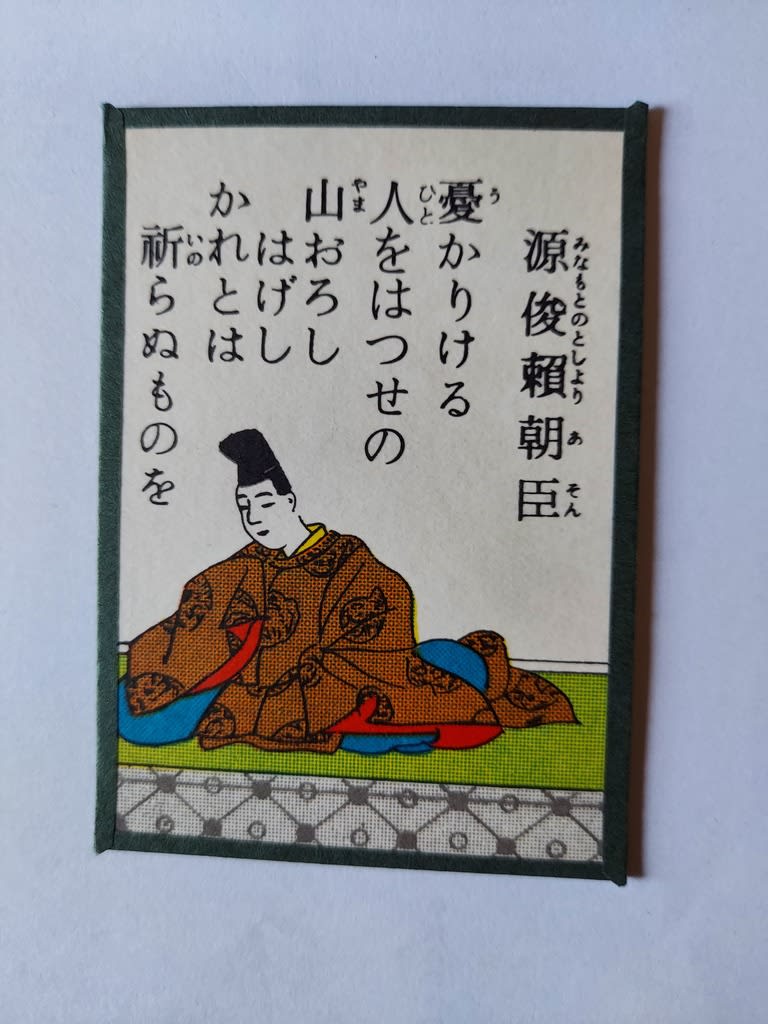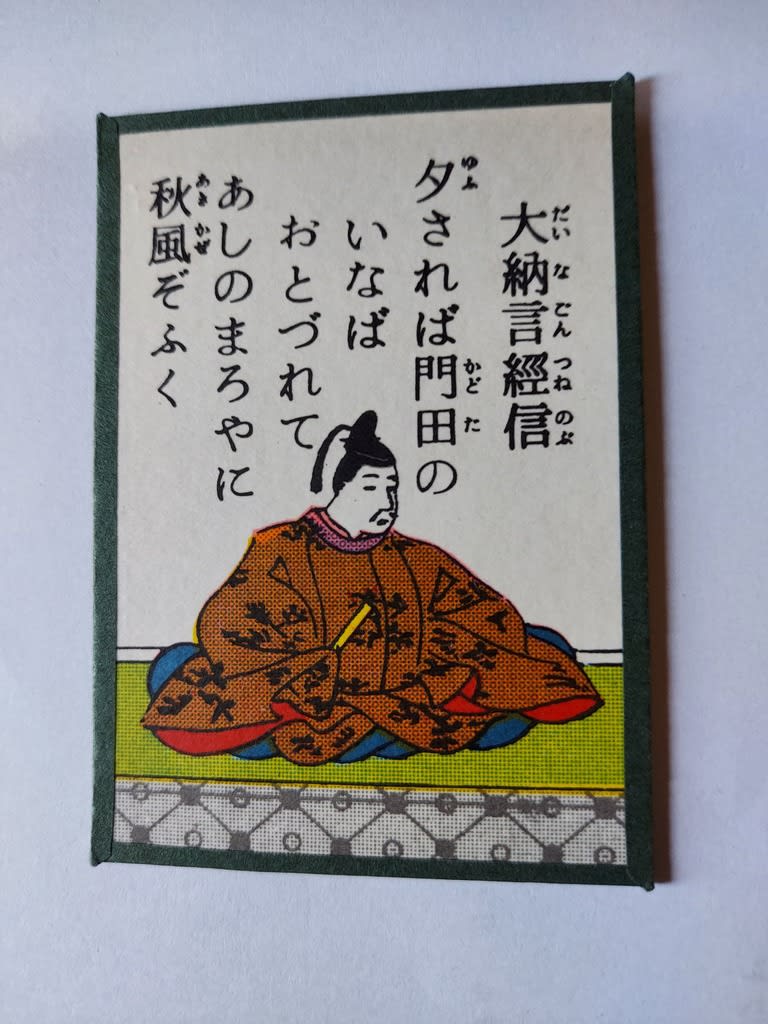第八十首

長からむ 心も知らず 黒髪の
乱れてけさは 物をこそ思へ
待賢門院堀河
(生没年不詳) 父は神祇伯源顕仲。待賢門院に仕えて堀河と呼ばれた。門院の出家に伴い自らも出家した
部位 恋 出典 千載集
主題
契りを結んだ翌朝の、心変わりを案じる恋の物思い
歌意
末永く愛してくれると誓ったあなたの心が分からないので、一夜逢って別れた今朝の私の心はこの寝乱れた黒髪のように物思いで乱れていることですよ。
末永くいつまでも変らないお心かも知れないけれど。
後朝の恋の歌。『久安百首』の一首であるが、男からの歌にこたえて返歌を送るという想定のもとによまれている。黒髪の寝乱れた官能的な美しさと、愛するがゆえに疑いとなり思い乱れる女心の嘆きを巧みに、しかも実感をこめてよんでいる。
俊成が、高く評価している女流歌人の一人であった。
『金葉集』以下に、六十五首入集。