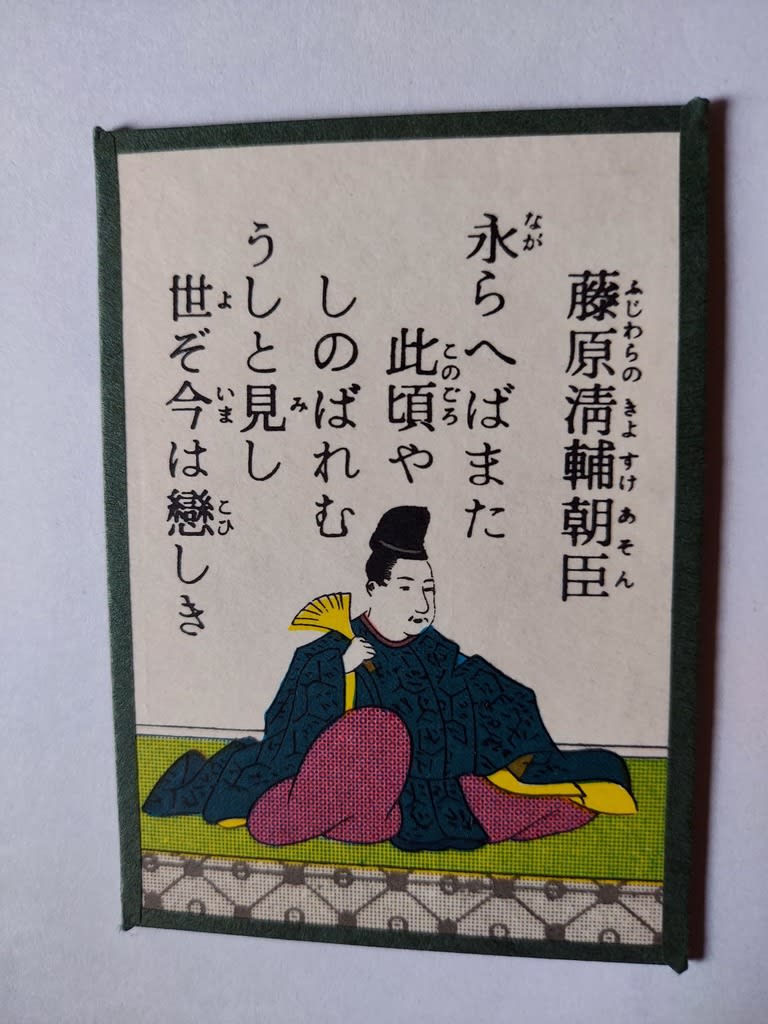第九十首

見せばやな 雄島のあまの 袖だにも
濡れにぞ濡れし 色は変はらず
殷富門院大輔
(生没年不詳) 父は藤原信成。殷富門院(後白河院皇女亮子内親王)に仕え、門院の出家に従い出家した。
部位 恋 出典 千載集
主題
相手のつれなさを嘆き、つらさを訴える恋の心情
歌意
ああ、あの人に見せたいものよ。雄島の漁師の袖でさえ、どれほど波しぶきで濡れに濡れたとしても色が変わらないというのに、私の袖はもう涙ですっかり色が変わっている。
「見せばやな」見せたいものですよ。「あま」は漁夫。あの雄島の漁夫でさえ、濡れることは私の袖と同じく、ひどく濡れているけれど。色までは変わっていませんのに。
鈴木知太郎氏が、「松島やをしまが磯はあさりせし海士の袖こそかくはぬれしか」(後拾遺集、恋四)という本歌の、「帰結とした所を、むしろ起点において構想したもののようで、そこには本歌には見られない一つの屈折と趣向がある」といい、誇張は多いという批評もかえりみながら、結局はその修辞をひめて、「すこぶる巧みな手法と言わざるを得ない」と、当時の歌の世界の中に立ちいって鑑賞されている。
『千載集』以下勅撰集入集六十五首。