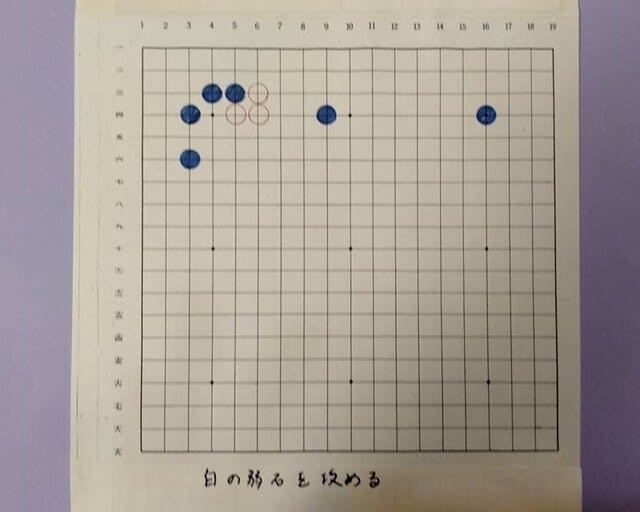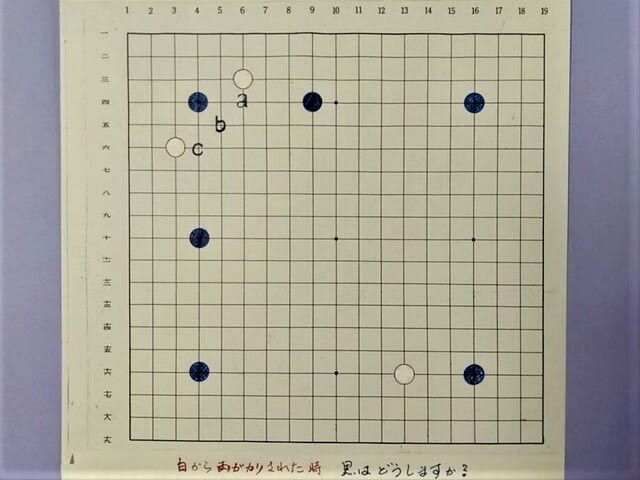

【あなたが有段者なら、ツケをオススメします】
わたしが黒を持ったら
aと打つでしょうね
図は「ツケノビ定石」のひとつですが
黒石が「9の四」で辺の星より
一路左に寄っていますね
「二間幅の四線」で
ほどよい攻めの着点です
白8が「アキ三角」の愚形で
外に脱出しなければならず
黒が一本取ったカタチです
黒は左辺が雄大ですし
上辺にも地が期待できます
◇
黒cはオススメできません
白8が「5の八」でなく
「5の九」のトビで脱出できます
上辺にできる黒地が小さいのも
気に入りません
◇
なお、ツケノビ定石は
ほかにも変化が多く
AI出現で、さらにややこしくなり
とても基本定石だけで対処できません
級位の皆さんは
相手の石にクッツケないで
スッと中央に頭を出すほうが
勝ちにつながりやすいと思います
「身の丈にあった手」を試し
「プロの打ち方」を試し
いろいろやってみましょう
ナントカの一つ覚えは
進歩を妨げるだけです
いろいろやって苦労すれば
状況に応じて石が打てるようになり
免許皆伝(初段)に近づきます
アタマヲヤワラカク!
役に立つ、立たないの意味では
このあたりが碁の滋養なのですから
そう、アマ高段に頑固者は稀ですね