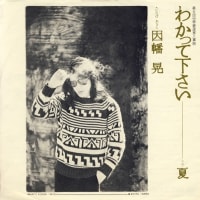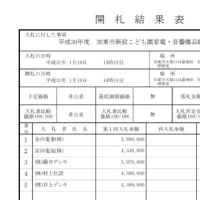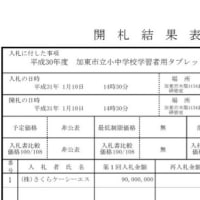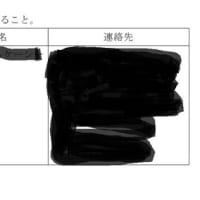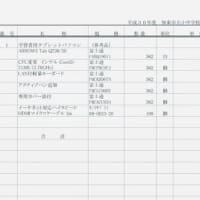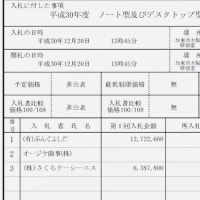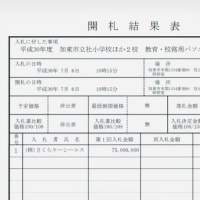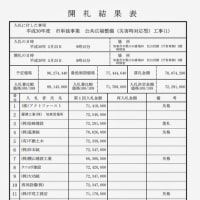昨日勉強に来ていると書きましたが、一般的な会計学の入門の勉強会で、宿題のレポートがあり、保存する方法が思い当たらなかったのでここにコピーして貼り付けることにしました。こういう文章は恥ずかしいのでいつもはこっそりと保存しているのですけれど。
私は兵庫県の加東市というところで市議会議員をしており、公会計のあり方の論議から会計学に興味を持ち、今回この講座を取った。
今年5月、自治体の財政健全化法が国会で可決され、自治体のバランスシートの作成が義務付けられるようになった。総務省のガイドラインに従って作成されるものだが、できた財務諸表が「使えない」という話もよく聞かれる。また、東京都で作成した発生主義による複式簿記の会計方式の方が優れているのに、東京都と総務省の綱引きの関係で総務省方式を全国の基準にしたなどという話も聞かれる。私自身はこういった議論についていけていないが、少しでもこういった議論を理解できるようになっていければ、と思っている。
自治体のバランスシートを考える上での一つの問題として、地方交付税の交付税算入といった問題がある。たとえば、下水道を整備する際には「後で元利償還金の50%を地方交付税で国が措置しますから、自治体で借金をして作っておいてください。」というようなやり方である。これを、現在のバランスシートでは丸々地方の負債として計上している。
統一した総務省方式の指針がなかったころは、これら「後で国が面倒をみますから」と言った部分を、資産に計上してバランスシートを作成した自治体もあったのだが、総務省は「後で交付税でみると言っても、交付税の計算式に算入するということであり、現金を給付するわけではないのだから、資産に計上したりしないように。書きたい場合はバランスシートに注記する形で行うように」という指示をしたりしている。
また、最近よく取り上げられる「実質公債費比率」も、借金の返済のみに注目した指標であることを念頭におかねばならない。たとえば、最近は「下水道の借金の返済期間は25年だが、償却期間は44年なので、44年ローンに切り替えましょう」という起債が認められるようになった。これを採用すると、当面の返済額は減るので「実質公債費比率」は減ることになる。また、全体の事業費を拡張していくと、分母が膨れ上がっていくので公債費比率は減少するという話も聞かれる。
私の加東市でも、実質公債費比率が危険水域の25%を超えるようになっていく見込みである。しかし、これは無駄な事業を極力やらず、過去の借金を一生懸命減らしている結果であるとも言え、いわゆる「自治体破綻」の状態とは違う。(恐らく資金は回っていると思う。)先述したように、小手先の手は打てるが、私は打つべきでないと思っている。
最後に昨日のビデオの感想だが、外郭団体ができる意味の議論で一つ踏み込んでほしかったな、と思うところがある。それは、あれらの事業を現在のように団体委託で事業を行っている場合、事業を委託料として物件費に計上しているが、直営でやると職員の人件費として計上しなければならない。現在の「職員の数・人件費を減らす」といった課題の最も簡単な解決法があの外郭団体なのである。(注:職員を正職員からアルバイトに切り替えても、費目が人件費から物件費に移る)こういった点をふまえずに、人件費が減ったという数字だけ追いかけるのは非常に危険だと思う。あともう一点、法律上直営より外郭団体のほうが議会のチェックがかなり緩いというのも外郭団体増加の原因だと思う。
いずれにしても、数字の意味を読み解く力が非常に重要だと思う。
私は兵庫県の加東市というところで市議会議員をしており、公会計のあり方の論議から会計学に興味を持ち、今回この講座を取った。
今年5月、自治体の財政健全化法が国会で可決され、自治体のバランスシートの作成が義務付けられるようになった。総務省のガイドラインに従って作成されるものだが、できた財務諸表が「使えない」という話もよく聞かれる。また、東京都で作成した発生主義による複式簿記の会計方式の方が優れているのに、東京都と総務省の綱引きの関係で総務省方式を全国の基準にしたなどという話も聞かれる。私自身はこういった議論についていけていないが、少しでもこういった議論を理解できるようになっていければ、と思っている。
自治体のバランスシートを考える上での一つの問題として、地方交付税の交付税算入といった問題がある。たとえば、下水道を整備する際には「後で元利償還金の50%を地方交付税で国が措置しますから、自治体で借金をして作っておいてください。」というようなやり方である。これを、現在のバランスシートでは丸々地方の負債として計上している。
統一した総務省方式の指針がなかったころは、これら「後で国が面倒をみますから」と言った部分を、資産に計上してバランスシートを作成した自治体もあったのだが、総務省は「後で交付税でみると言っても、交付税の計算式に算入するということであり、現金を給付するわけではないのだから、資産に計上したりしないように。書きたい場合はバランスシートに注記する形で行うように」という指示をしたりしている。
また、最近よく取り上げられる「実質公債費比率」も、借金の返済のみに注目した指標であることを念頭におかねばならない。たとえば、最近は「下水道の借金の返済期間は25年だが、償却期間は44年なので、44年ローンに切り替えましょう」という起債が認められるようになった。これを採用すると、当面の返済額は減るので「実質公債費比率」は減ることになる。また、全体の事業費を拡張していくと、分母が膨れ上がっていくので公債費比率は減少するという話も聞かれる。
私の加東市でも、実質公債費比率が危険水域の25%を超えるようになっていく見込みである。しかし、これは無駄な事業を極力やらず、過去の借金を一生懸命減らしている結果であるとも言え、いわゆる「自治体破綻」の状態とは違う。(恐らく資金は回っていると思う。)先述したように、小手先の手は打てるが、私は打つべきでないと思っている。
最後に昨日のビデオの感想だが、外郭団体ができる意味の議論で一つ踏み込んでほしかったな、と思うところがある。それは、あれらの事業を現在のように団体委託で事業を行っている場合、事業を委託料として物件費に計上しているが、直営でやると職員の人件費として計上しなければならない。現在の「職員の数・人件費を減らす」といった課題の最も簡単な解決法があの外郭団体なのである。(注:職員を正職員からアルバイトに切り替えても、費目が人件費から物件費に移る)こういった点をふまえずに、人件費が減ったという数字だけ追いかけるのは非常に危険だと思う。あともう一点、法律上直営より外郭団体のほうが議会のチェックがかなり緩いというのも外郭団体増加の原因だと思う。
いずれにしても、数字の意味を読み解く力が非常に重要だと思う。