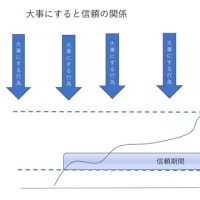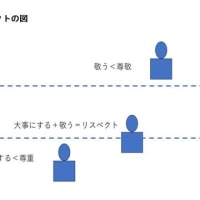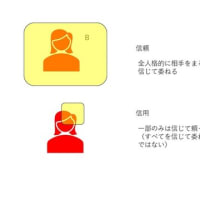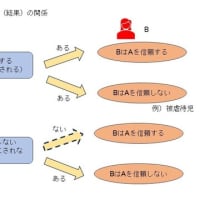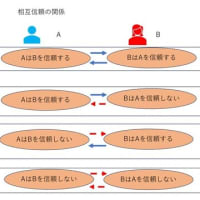昨日(2014/9/3)、デジタル教科書教材協議会(DiTT)主催の、「小学生に反転授業は可能か?」というシンポジウムに参加しました。
2014年度から市内の小学校で反転授業を開始した佐賀県武雄市の代田昭久氏および、2012年から取り組んでいる宮城県富谷町立東向陽台小学校の佐藤靖泰氏の基調講演ならびにパネルディスカッションでしsた。
詳細については、日経パソコンの記事や、教育とICT Onlineでレポートされています。
また、当日の動画は、ニコニコ動画のこちらでタイムシフト視聴ができます(ログインが必要)。
ここでは、記事に補足する事項や感想を述べたいと思います。
■武雄市の取組について
今回の発表の取り組みは2014年5月~7月にかけてのもので、武雄市内全11小学校(3年生以上)、600回にわたる反転授業の報告。
発表から、武雄市の教育行政サイドが市内全小学校と提携企業(教材づくり)をうまく連携させているように見受けられました。
こうした全学校への一斉導入という方式は予算もかかるので、計画的かつ緻密な連携が不可欠です。特に、先生方も新しい授業方式でとまどいもあるため、効果の測定や保護者への通知や連絡、不安の解消などいろいろとすべきことがあることがわかりました。
特に反転授業では、家庭でのタブレット端末を使った学習があるため、保護者サイドでは、「家庭での学習習慣が今はないのに、自ら予習するようになるのか?」「私たちが勉強を教える負担が増えるのではないか?」「ネット依存や有害サイト接続」などに関する不安を感じており、こうした不安に対して丁寧に説明していくことが理解には重要なようです。
生徒の反応はおおむね良いというアンケート結果がでていること(詳しくは上記記事)、またタブレットの予習率が100%であることが報告されていましたが、これは驚きました。
数人で1台というのと、一人1台というのでは、インパクトがやはり違うなという印象だそうです。
また、各授業でも先生の工夫が加速しているということで、体育や音楽で自分で録画・録音するなどが一人一台により生まれているとのことです。テクノロジーが入ることのインパクトが大きく、端末の種類はそれほど関係ないのではと代田さんはおっしゃっていました。
「反転授業」というネーミングは、反旗を翻すというように捉えられるとマイナスなので、ネーミングを先生方に募集して決めたそうです。その結果、こんにち武雄式反転授業は、SMILE(School Movies Innovate the Live Education)と呼ばれています。
武雄市では、常にデータを取りながら、ICT導入が目的化しないように
1)児童がより意欲的に授業に臨めるように事前知識をもつこと
2)予習時に事前テストをし、完全習得学習をめざす(動画を見っぱなしにさせない)
3)授業が始まる前には教員が学習者の実態を正確に把握して、授業に臨むようにする
4)対面授業では、協働的な問題解決を育成することを主眼とする
といった取り組み方をしているようです。
企業と協働で予習教材をつくっている理由としては、「先生方が一緒につくる環境をつくるのが物理的に難しい事」「授業の中に企業の英知が入るようにすること」「先生と企業で協働することで、協働的に問題解決するスキルを先生方にもみにつけてもらうこと」などが目的としてあったようです。どうしても先生方だけで取り組みをした場合、2-6-2の法則でとても熱心に取り組む人とそうでない人の差が大きくなるという点なども考慮しているようです。
教材のつくり方や共有の仕方などについては、上記記事のとおりです。
今後の課題としては、
・どの教科でどの程度実施するか
・動画コンテンツをどうつくり続けるか
・予習できない子の対処(いまのところはない)
・対面での高次学習をどのように評価するのか
・今後の教師の役割
などがあげられるそうです。
なお、1つの解決方法として、”土曜てらこや”を佐賀大学生や地元の高校生のサポートによって開催し、学習が遅れがちな児童のセイフティネットにしているそうです。
■宮城県富谷町立東向陽台小学校の佐藤靖泰先生の取組み
こちらは、町をあげて、小学校をあげて というのではなく、あくまで佐藤先生個人の取組ということです。ただし、企業や大学などの協力のもとで進めているとのこと。
反転授業導入前は、授業の時間配分は、導入10分 展開25分 まとめ10分という構成であったが、これではなかなか理解が深まることまで行かないし、協働で問題解決というところまで届かない。そこで反転授業を知り、取り入れたということです。
佐藤先生の授業で特徴的なのは、反転授業の予習動画を観て、各自が自分のノートをつかって、まとめを行ってくることを義務付けている点だと思いました。
つまり、家庭ではわかったこと、わからなかったことなをノートづくりすることによって、調べる、まとめるを自分ペースで行い知識確認していきます。
そして、教室では、適用問題を解いたり知識確認をしたり、課題解決にあてます。
保護者の声として、
「分からないところを何度も見直せ、復習にも活用できたようである」
「予習の手段として直接先生の解説を聴けるというのがいい」
児童の声として、
「他人の考えにつられず、自分の意見をいえるようになった」
「家で明日の勉強ができるので、次の日は必ずわかるので楽になった」
「家で予習する癖がついた」
「みんなが自分の考えを持っているので、まとめをするときに達成感がある」
ここで注目すべきは、それぞれの個人の理解は違うことを教室で認識することができ、それをまとめる面白さを児童が知ったということにあると思います。
その他、先生が感じる成果として、
「ポストテストを行ったときの知識・理解・技能の到達度が高くなった」
「家庭学習の時間が増加した」
などがあげられるといいます。
反転授業が教師に突きつけるものは、
・教師に必要となってくる能力
1対多の教授型一斉授業ではなく、アクションラーニングや学び合い、教えあい、授業をデザインする力、効率の良い授業展開が要求される
・子どもの状態を把握する力
内発的に高まっているのか、外発的な仕掛けが必要なのかを見極め、アンダーマイニング効果(内発的動機づけによって行われた行為に対して、報酬を与えるなどの外発的動機づけを行うことによって、動機づけが低減する現象)を回避することも大切。
■シンポジウム
質疑応答がありましたが、課題として共通にあったのは、
・先生の役割が変わるし、子どもの意識も変わらないといけない
・先生方の研修はやっていくが、子供たちに議論をうまくさせるためのテクニックを教員が身に着ける必要がある。
・意見を出したらコンフリクトがおこるのはいわば当然であるが、いままでの日本の教育だとあえて対立がおきると抑え込もうとしていた。そのへんを異なる意見が出ても友達関係は変わらないと言ったことも教えていく(ピースフルスクールの導入)
・反転授業、やるとなったら教材作りの負担や機材の問題は相変わらずあるだろう。
先生の役割変化に対応できるのか?
・教材共有システムがあるといいが、最近は勝手に動画をアップする人が増えた。こういうものを使うには、統一した使いやすいプラットフォームが必要。
・例えば、公式を教える場合、それ自体を教えるのは是か非か? 先生の役割はどこまでか? どちらが正解かはすぐに出ない問題。
■さいごにひとこと
代田さん)いまいちど、教育にたずさわる人は、「いい先生とはどんな先生か」を考えて欲しい。すぐに正解を教えてくれる先生ではなくなったはず。
佐藤さん)日本の先生は頑張っている。もっと努力が効果的を生むような方法をさらに考えていきたい。今やっている頑張りをサポートする役割をしたい。授業の在り方が今後、中心になるだろう。
■福島より感想
主に大学などで実践が報告されつつある反転授業。
小学校では実際どうなのか興味がありました。
今回のテーマは、小学校に反転授業は可能か? というタイトルでしたが、お二人の実践者の結論からは、可能であるという結論のようです。ただし、両報告とも、相当の取組や体制が保障されているもとでの実践なので、全国展開がいきなりできるかというと、環境整備などを含めてまだ時間はかかりそうです。行政や家庭の理解なども不可欠であることがわかります。
また、小学校低学年の導入については、まだ例がないためにわからないのと、先生方の授業デザインや予習教材の工夫やその負担などについては未知数の部分がまだあるということや、先生の役割が明確に変わっているけれど、そのフォローはなされているのかという疑問もあるので、今後も注視していきたいと思います。
2014年度から市内の小学校で反転授業を開始した佐賀県武雄市の代田昭久氏および、2012年から取り組んでいる宮城県富谷町立東向陽台小学校の佐藤靖泰氏の基調講演ならびにパネルディスカッションでしsた。
詳細については、日経パソコンの記事や、教育とICT Onlineでレポートされています。
また、当日の動画は、ニコニコ動画のこちらでタイムシフト視聴ができます(ログインが必要)。
ここでは、記事に補足する事項や感想を述べたいと思います。
■武雄市の取組について
今回の発表の取り組みは2014年5月~7月にかけてのもので、武雄市内全11小学校(3年生以上)、600回にわたる反転授業の報告。
発表から、武雄市の教育行政サイドが市内全小学校と提携企業(教材づくり)をうまく連携させているように見受けられました。
こうした全学校への一斉導入という方式は予算もかかるので、計画的かつ緻密な連携が不可欠です。特に、先生方も新しい授業方式でとまどいもあるため、効果の測定や保護者への通知や連絡、不安の解消などいろいろとすべきことがあることがわかりました。
特に反転授業では、家庭でのタブレット端末を使った学習があるため、保護者サイドでは、「家庭での学習習慣が今はないのに、自ら予習するようになるのか?」「私たちが勉強を教える負担が増えるのではないか?」「ネット依存や有害サイト接続」などに関する不安を感じており、こうした不安に対して丁寧に説明していくことが理解には重要なようです。
生徒の反応はおおむね良いというアンケート結果がでていること(詳しくは上記記事)、またタブレットの予習率が100%であることが報告されていましたが、これは驚きました。
数人で1台というのと、一人1台というのでは、インパクトがやはり違うなという印象だそうです。
また、各授業でも先生の工夫が加速しているということで、体育や音楽で自分で録画・録音するなどが一人一台により生まれているとのことです。テクノロジーが入ることのインパクトが大きく、端末の種類はそれほど関係ないのではと代田さんはおっしゃっていました。
「反転授業」というネーミングは、反旗を翻すというように捉えられるとマイナスなので、ネーミングを先生方に募集して決めたそうです。その結果、こんにち武雄式反転授業は、SMILE(School Movies Innovate the Live Education)と呼ばれています。
武雄市では、常にデータを取りながら、ICT導入が目的化しないように
1)児童がより意欲的に授業に臨めるように事前知識をもつこと
2)予習時に事前テストをし、完全習得学習をめざす(動画を見っぱなしにさせない)
3)授業が始まる前には教員が学習者の実態を正確に把握して、授業に臨むようにする
4)対面授業では、協働的な問題解決を育成することを主眼とする
といった取り組み方をしているようです。
企業と協働で予習教材をつくっている理由としては、「先生方が一緒につくる環境をつくるのが物理的に難しい事」「授業の中に企業の英知が入るようにすること」「先生と企業で協働することで、協働的に問題解決するスキルを先生方にもみにつけてもらうこと」などが目的としてあったようです。どうしても先生方だけで取り組みをした場合、2-6-2の法則でとても熱心に取り組む人とそうでない人の差が大きくなるという点なども考慮しているようです。
教材のつくり方や共有の仕方などについては、上記記事のとおりです。
今後の課題としては、
・どの教科でどの程度実施するか
・動画コンテンツをどうつくり続けるか
・予習できない子の対処(いまのところはない)
・対面での高次学習をどのように評価するのか
・今後の教師の役割
などがあげられるそうです。
なお、1つの解決方法として、”土曜てらこや”を佐賀大学生や地元の高校生のサポートによって開催し、学習が遅れがちな児童のセイフティネットにしているそうです。
■宮城県富谷町立東向陽台小学校の佐藤靖泰先生の取組み
こちらは、町をあげて、小学校をあげて というのではなく、あくまで佐藤先生個人の取組ということです。ただし、企業や大学などの協力のもとで進めているとのこと。
反転授業導入前は、授業の時間配分は、導入10分 展開25分 まとめ10分という構成であったが、これではなかなか理解が深まることまで行かないし、協働で問題解決というところまで届かない。そこで反転授業を知り、取り入れたということです。
佐藤先生の授業で特徴的なのは、反転授業の予習動画を観て、各自が自分のノートをつかって、まとめを行ってくることを義務付けている点だと思いました。
つまり、家庭ではわかったこと、わからなかったことなをノートづくりすることによって、調べる、まとめるを自分ペースで行い知識確認していきます。
そして、教室では、適用問題を解いたり知識確認をしたり、課題解決にあてます。
保護者の声として、
「分からないところを何度も見直せ、復習にも活用できたようである」
「予習の手段として直接先生の解説を聴けるというのがいい」
児童の声として、
「他人の考えにつられず、自分の意見をいえるようになった」
「家で明日の勉強ができるので、次の日は必ずわかるので楽になった」
「家で予習する癖がついた」
「みんなが自分の考えを持っているので、まとめをするときに達成感がある」
ここで注目すべきは、それぞれの個人の理解は違うことを教室で認識することができ、それをまとめる面白さを児童が知ったということにあると思います。
その他、先生が感じる成果として、
「ポストテストを行ったときの知識・理解・技能の到達度が高くなった」
「家庭学習の時間が増加した」
などがあげられるといいます。
反転授業が教師に突きつけるものは、
・教師に必要となってくる能力
1対多の教授型一斉授業ではなく、アクションラーニングや学び合い、教えあい、授業をデザインする力、効率の良い授業展開が要求される
・子どもの状態を把握する力
内発的に高まっているのか、外発的な仕掛けが必要なのかを見極め、アンダーマイニング効果(内発的動機づけによって行われた行為に対して、報酬を与えるなどの外発的動機づけを行うことによって、動機づけが低減する現象)を回避することも大切。
■シンポジウム
質疑応答がありましたが、課題として共通にあったのは、
・先生の役割が変わるし、子どもの意識も変わらないといけない
・先生方の研修はやっていくが、子供たちに議論をうまくさせるためのテクニックを教員が身に着ける必要がある。
・意見を出したらコンフリクトがおこるのはいわば当然であるが、いままでの日本の教育だとあえて対立がおきると抑え込もうとしていた。そのへんを異なる意見が出ても友達関係は変わらないと言ったことも教えていく(ピースフルスクールの導入)
・反転授業、やるとなったら教材作りの負担や機材の問題は相変わらずあるだろう。
先生の役割変化に対応できるのか?
・教材共有システムがあるといいが、最近は勝手に動画をアップする人が増えた。こういうものを使うには、統一した使いやすいプラットフォームが必要。
・例えば、公式を教える場合、それ自体を教えるのは是か非か? 先生の役割はどこまでか? どちらが正解かはすぐに出ない問題。
■さいごにひとこと
代田さん)いまいちど、教育にたずさわる人は、「いい先生とはどんな先生か」を考えて欲しい。すぐに正解を教えてくれる先生ではなくなったはず。
佐藤さん)日本の先生は頑張っている。もっと努力が効果的を生むような方法をさらに考えていきたい。今やっている頑張りをサポートする役割をしたい。授業の在り方が今後、中心になるだろう。
■福島より感想
主に大学などで実践が報告されつつある反転授業。
小学校では実際どうなのか興味がありました。
今回のテーマは、小学校に反転授業は可能か? というタイトルでしたが、お二人の実践者の結論からは、可能であるという結論のようです。ただし、両報告とも、相当の取組や体制が保障されているもとでの実践なので、全国展開がいきなりできるかというと、環境整備などを含めてまだ時間はかかりそうです。行政や家庭の理解なども不可欠であることがわかります。
また、小学校低学年の導入については、まだ例がないためにわからないのと、先生方の授業デザインや予習教材の工夫やその負担などについては未知数の部分がまだあるということや、先生の役割が明確に変わっているけれど、そのフォローはなされているのかという疑問もあるので、今後も注視していきたいと思います。