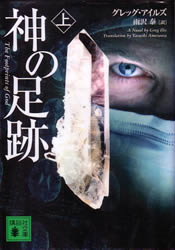・「砂漠の狐を狩れ」/スティーヴン・プレスフィールド
イギリスが第二次大戦に参戦したのはわたしが大学生の頃だった。当時の若者は、今すぐにでも戦争に参加して国のために働きたいと思っていた。わたしが入隊したのは国王近衛竜騎兵連隊、いわゆる戦車梯団である。わたしは戦車を率い、砂まみれになりながらアフリカ戦線を戦っていた。
敵側のドイツ軍には恐ろしく有能な将軍がいた。「砂漠の狐」の異名を取る、エルヴィン・ロンメル将軍である。指揮官でありながら最前線に立つことも少なくはなく、直接兵士たちを鼓舞するときもあるという。その動きは統率されていて、常に相手の虚をつき、わがイギリス軍の戦線を後退させていく。
この北アフリカ戦線でわたしは学んだことがある。この砂漠の戦場では常に指揮系統は混乱し、満足な補給もないままに戦いは続いていく。そんな現場で生き残るために、わたしたち兵士は互いに団結しあった。時には本部からの命令を無視することもあった。利用できるものはなんでも利用した。昨日壊れて放置されていた戦車が、今日は敵側に渡って使われている…そんな光景も日常的だった。
そんなわたしに新たな配属命令が下った。長距離砂漠挺身隊(LRDG)という隠密部隊で、軽装備で敵軍奥地まで潜入し、敵将ロンメルの首を討つという作戦内容だった。戦車からトラックに乗り換え、無補給で果てしない砂漠を突き進んでいく…。それはまさに大海原を航海するようなものだった。常に残り燃料を計算しながら、位置を確認し、砂に埋もれた自動車をかき出す。この死の行軍で、わたしは次第に指揮官としての能力を開花させていった。それと同時に人間の本質、戦争の本質、戦いあうことの空しさも。そしてついに、わたしは思いがけないめぐり合わせでロンメルと対峙することになったのだが…?
ロンメル将軍と長距離砂漠挺身隊の話は史実に基づいたもので、この挺身隊が後のSAS(アンディ・マクナブのあのシリーズでおなじみの)につながっているようだ。ドイツのロンメル将軍もこの作品で知ったんだけど、彼は古典的な騎士道精神にのっとった戦いぶりで敵国からも人気が高く、ある種神格化されていたようだ。
彼はナチ党の熱心な信望者というわけでもユダヤ人差別主義者というわけでもなくて、アフリカでの敗戦後は本国へ戻され、そこでヒトラーの暗殺容疑にかけられて生涯を閉じてしまう。で、このアフリカ戦線を破ったのがイギリスのモントゴメリー将軍で、これがハーツオブアイアン2の曲名「Montgomery's March」になっているわけか。うん、なるほどこれで思考のピースが繋がってきたよ…!
砂漠という極地での戦いで、敵味方間にある種の「ルール」が出来上がってくるのが面白いところ。例えば炎上する戦車から脱出している間は攻撃しない、とか。砂漠を横断するための燃料集積場が自然に出来上がってくるところとか。主人公のわたしも、ただがむしゃらに敵を倒したいという気負いはなく、敵の仕掛けてくる奇襲と布陣にあっぱれと思いながら、こちらも手持ちの物資で裏をかいていく。
そんな暗黙のルールが、ラストのロンメルとの出会いにつながっていく。進軍中にばったり出くわした、負傷したドイツ兵の一団。隊員たちは銃に手をかけるが、隊長のわたしは極限の思考の中で思いとどまる。トラックに負傷兵を乗せ、近くのドイツ軍の基地に向かう。言葉は通じなくとも、両者無言の会話によって負傷兵は一命を取りとめる。この感動的なシーンによって、主人公のわたしは罪を許されたんだと思う。かつて自分の命を守るために、護送車に乗ったイタリア兵の一団を一方的に虐殺してしまったことを…。
あとは兵器に関するもうひとつ覚え書き。ドイツ軍は88ミリ砲という対空砲を持っていて、対戦車砲としても使われるこの大砲に、砂漠のイギリス軍はとても手を焼いていたそうな。こちらの射程外から撃ってくる上に、どんな戦車も一撃で破壊されてしまうという。そんなロンメル軍に、知恵と勇気だけで(無謀にも)戦っていくわたしと大学の先輩の将校の前半パートも面白いです。
イギリスが第二次大戦に参戦したのはわたしが大学生の頃だった。当時の若者は、今すぐにでも戦争に参加して国のために働きたいと思っていた。わたしが入隊したのは国王近衛竜騎兵連隊、いわゆる戦車梯団である。わたしは戦車を率い、砂まみれになりながらアフリカ戦線を戦っていた。
敵側のドイツ軍には恐ろしく有能な将軍がいた。「砂漠の狐」の異名を取る、エルヴィン・ロンメル将軍である。指揮官でありながら最前線に立つことも少なくはなく、直接兵士たちを鼓舞するときもあるという。その動きは統率されていて、常に相手の虚をつき、わがイギリス軍の戦線を後退させていく。
この北アフリカ戦線でわたしは学んだことがある。この砂漠の戦場では常に指揮系統は混乱し、満足な補給もないままに戦いは続いていく。そんな現場で生き残るために、わたしたち兵士は互いに団結しあった。時には本部からの命令を無視することもあった。利用できるものはなんでも利用した。昨日壊れて放置されていた戦車が、今日は敵側に渡って使われている…そんな光景も日常的だった。
そんなわたしに新たな配属命令が下った。長距離砂漠挺身隊(LRDG)という隠密部隊で、軽装備で敵軍奥地まで潜入し、敵将ロンメルの首を討つという作戦内容だった。戦車からトラックに乗り換え、無補給で果てしない砂漠を突き進んでいく…。それはまさに大海原を航海するようなものだった。常に残り燃料を計算しながら、位置を確認し、砂に埋もれた自動車をかき出す。この死の行軍で、わたしは次第に指揮官としての能力を開花させていった。それと同時に人間の本質、戦争の本質、戦いあうことの空しさも。そしてついに、わたしは思いがけないめぐり合わせでロンメルと対峙することになったのだが…?
ロンメル将軍と長距離砂漠挺身隊の話は史実に基づいたもので、この挺身隊が後のSAS(アンディ・マクナブのあのシリーズでおなじみの)につながっているようだ。ドイツのロンメル将軍もこの作品で知ったんだけど、彼は古典的な騎士道精神にのっとった戦いぶりで敵国からも人気が高く、ある種神格化されていたようだ。
彼はナチ党の熱心な信望者というわけでもユダヤ人差別主義者というわけでもなくて、アフリカでの敗戦後は本国へ戻され、そこでヒトラーの暗殺容疑にかけられて生涯を閉じてしまう。で、このアフリカ戦線を破ったのがイギリスのモントゴメリー将軍で、これがハーツオブアイアン2の曲名「Montgomery's March」になっているわけか。うん、なるほどこれで思考のピースが繋がってきたよ…!
砂漠という極地での戦いで、敵味方間にある種の「ルール」が出来上がってくるのが面白いところ。例えば炎上する戦車から脱出している間は攻撃しない、とか。砂漠を横断するための燃料集積場が自然に出来上がってくるところとか。主人公のわたしも、ただがむしゃらに敵を倒したいという気負いはなく、敵の仕掛けてくる奇襲と布陣にあっぱれと思いながら、こちらも手持ちの物資で裏をかいていく。
そんな暗黙のルールが、ラストのロンメルとの出会いにつながっていく。進軍中にばったり出くわした、負傷したドイツ兵の一団。隊員たちは銃に手をかけるが、隊長のわたしは極限の思考の中で思いとどまる。トラックに負傷兵を乗せ、近くのドイツ軍の基地に向かう。言葉は通じなくとも、両者無言の会話によって負傷兵は一命を取りとめる。この感動的なシーンによって、主人公のわたしは罪を許されたんだと思う。かつて自分の命を守るために、護送車に乗ったイタリア兵の一団を一方的に虐殺してしまったことを…。
あとは兵器に関するもうひとつ覚え書き。ドイツ軍は88ミリ砲という対空砲を持っていて、対戦車砲としても使われるこの大砲に、砂漠のイギリス軍はとても手を焼いていたそうな。こちらの射程外から撃ってくる上に、どんな戦車も一撃で破壊されてしまうという。そんなロンメル軍に、知恵と勇気だけで(無謀にも)戦っていくわたしと大学の先輩の将校の前半パートも面白いです。