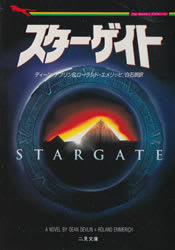スターゲイト/デブリン&エメリッヒ
若きエジプト考古学者ダニエルは、いささか常識からは飛躍した自説を持つことから、学界からは冷遇されていた。今日もまた講演会でピラミッドに関する自説を説くも、古参の学者からは見向きもされず、バカバカしさのあまりほぼ全員が途中退出してしまう結果に。
講演後、出席していた見慣れない老婦人が話しかけてきた。自分のプロジェクトにダニエルの力が必要だと。この老婦人こそ、1920年代にエジプトで発掘された謎の遺物の発見者であるラングフォード博士の娘であり、発見と同時に起きた事故の体験者でもある。
例の遺物はその後、軍によって管理され、研究は現在も秘密裏に続けられていたのだった。プロジェクトはまさに最終段階で、そのためにダニエルの古代エジプト言語の知識が必要だった。
軍の目論見とダニエルの翻訳の通り、これは時空を旅する転送装置・スターゲートであり、彼は先行隊としてスターゲートの旅に同行することになった。学者であるダニエルは軍の強行的な態度は好きになれず、嫌々ながらの同行ではあったが、古代エジプトへの興味は隠しきれない。
こうしてラングフォード女史からはなむけのペンダントを受け取り、スターゲートによって見知らぬ場所へと転送された一行。しかし、どうやらスターゲートの転送は一方通行の様で、ここから地球へ戻ることができないと分かるや、ダニエルへの風当たりは強くなっていくのだったが…。
映画化されている通りに、あらすじだけ見ればまさにジュール・ヴェルヌのような王道的な冒険SFなんだけど、やっぱりそこはSFというか、SF小説特有のフックがあって、物語が本格的に始まるまでに一縄筋ではいかないところがある。まあぶっちゃけ文体が読みにくいというか、ストーリーラインが整頓されていないというか。現代の感覚からすると、もうこれだけでアウトのような気がしないでもない。
さて、ピラミッドのようで微妙に地球のピラミッドと違うような場所にワープされたダニエルたちは、原住民とのコンタクトを果たすのだが、そこはある意味ディストピア的な世界になっていた。彼らは文字を禁じられ、原始的な器具で石英鉱石を採掘し、太陽神ラーに絶対服従を誓っている。
原住民はダニエルたちをラーの使いではないと知り、ひどく困惑しているようである。一行をどう扱ったらよいものかと思案しているうちに、砂嵐が彼らの街を襲い、彼らの神である太陽神ラーが姿を現した。たちまちパニックと化す街…それほどまでに彼らの恐れる太陽神ラーとは、一体何者なのだろうか?
全体を俯瞰してみると、暴君に長年支配されている原住民の街に、現代から主人公たちがやってきて、力を合わせて旧体制を倒す…みたいな入れ子の中に入れ子が入っているような物語の構造なんだけど、やはりというか、全容が見えてくるまでがあんまり面白くないんだよね…。繰り返しになってしまうけど、そこがSFらしさ、といってしまうのも多少暴論気味なところはある。まあ、つまらなくはない、とは思う。
若きエジプト考古学者ダニエルは、いささか常識からは飛躍した自説を持つことから、学界からは冷遇されていた。今日もまた講演会でピラミッドに関する自説を説くも、古参の学者からは見向きもされず、バカバカしさのあまりほぼ全員が途中退出してしまう結果に。
講演後、出席していた見慣れない老婦人が話しかけてきた。自分のプロジェクトにダニエルの力が必要だと。この老婦人こそ、1920年代にエジプトで発掘された謎の遺物の発見者であるラングフォード博士の娘であり、発見と同時に起きた事故の体験者でもある。
例の遺物はその後、軍によって管理され、研究は現在も秘密裏に続けられていたのだった。プロジェクトはまさに最終段階で、そのためにダニエルの古代エジプト言語の知識が必要だった。
軍の目論見とダニエルの翻訳の通り、これは時空を旅する転送装置・スターゲートであり、彼は先行隊としてスターゲートの旅に同行することになった。学者であるダニエルは軍の強行的な態度は好きになれず、嫌々ながらの同行ではあったが、古代エジプトへの興味は隠しきれない。
こうしてラングフォード女史からはなむけのペンダントを受け取り、スターゲートによって見知らぬ場所へと転送された一行。しかし、どうやらスターゲートの転送は一方通行の様で、ここから地球へ戻ることができないと分かるや、ダニエルへの風当たりは強くなっていくのだったが…。
映画化されている通りに、あらすじだけ見ればまさにジュール・ヴェルヌのような王道的な冒険SFなんだけど、やっぱりそこはSFというか、SF小説特有のフックがあって、物語が本格的に始まるまでに一縄筋ではいかないところがある。まあぶっちゃけ文体が読みにくいというか、ストーリーラインが整頓されていないというか。現代の感覚からすると、もうこれだけでアウトのような気がしないでもない。
さて、ピラミッドのようで微妙に地球のピラミッドと違うような場所にワープされたダニエルたちは、原住民とのコンタクトを果たすのだが、そこはある意味ディストピア的な世界になっていた。彼らは文字を禁じられ、原始的な器具で石英鉱石を採掘し、太陽神ラーに絶対服従を誓っている。
原住民はダニエルたちをラーの使いではないと知り、ひどく困惑しているようである。一行をどう扱ったらよいものかと思案しているうちに、砂嵐が彼らの街を襲い、彼らの神である太陽神ラーが姿を現した。たちまちパニックと化す街…それほどまでに彼らの恐れる太陽神ラーとは、一体何者なのだろうか?
全体を俯瞰してみると、暴君に長年支配されている原住民の街に、現代から主人公たちがやってきて、力を合わせて旧体制を倒す…みたいな入れ子の中に入れ子が入っているような物語の構造なんだけど、やはりというか、全容が見えてくるまでがあんまり面白くないんだよね…。繰り返しになってしまうけど、そこがSFらしさ、といってしまうのも多少暴論気味なところはある。まあ、つまらなくはない、とは思う。