大ケヤキがある川内村の、
さる旧家に
水石という宝があったという。
大人の握りこぶしぐらいでゴツゴツしており、
固まった溶岩のような感じだったらしい。
石には、小さな穴があいており、
傾けると、この穴から糸のように水が出てくる。
1回に出てくる量は、椀で半杯分ぐらいだが、
1刻もすると、また水がたまって再び流れ出てきた。
水石から出た水はわずかなにごりがあるが、
それ以外は井戸水と変わらず、無味無臭。
飲んでも、身体に害もなかったと。
いつでも、どんなときでも。
水石さえあれば、一家が渇きに苦しむことがない。
この家の人々は、常々そう言って
石を神棚に上げて大切に守ってきた。
ところで。
この家の跡取りがもらった若い嫁は
水石が不思議でならなかった。
人がいないときに、そっと石にさわってみたりしていたが、
そのうち、中がどうなっているのか知りたくてたまらなくなった。
そこで、ある日思い切って、
こっそり石を下ろして、
小づかで穴をがりがりと削って石の中心部を見ようとした。
水石は硬く、なかなか穴は大きくならなかったが、
夢中で削っていると、
やがて、穴から細かく泡立った粘液があふれ、
糸を引いて垂れだした。
さあ、どうしようと、
嫁が慌てている間も、
とろとろと粘液が流れ、
その液体にまじって、
親指の頭ほどの、白くて目のない魚が
穴からつるりと飛び出した。
見ていると、
地に落ちた魚は、ぴたぴたと暴れたが、
すぐに土のくぼみから、土中へもぐり、姿を消した。
それきり。
嫁が穴をうがった家宝の水石からは、
1滴も水が出なくなってしまったという。
そして、
水石の水を涸らした嫁は、
じき、里に帰されたと。
★★★★
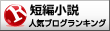
短編小説 ブログランキングへ
お手数おかけしますが、できればご協力を。
さる旧家に
水石という宝があったという。
大人の握りこぶしぐらいでゴツゴツしており、
固まった溶岩のような感じだったらしい。
石には、小さな穴があいており、
傾けると、この穴から糸のように水が出てくる。
1回に出てくる量は、椀で半杯分ぐらいだが、
1刻もすると、また水がたまって再び流れ出てきた。
水石から出た水はわずかなにごりがあるが、
それ以外は井戸水と変わらず、無味無臭。
飲んでも、身体に害もなかったと。
いつでも、どんなときでも。
水石さえあれば、一家が渇きに苦しむことがない。
この家の人々は、常々そう言って
石を神棚に上げて大切に守ってきた。
ところで。
この家の跡取りがもらった若い嫁は
水石が不思議でならなかった。
人がいないときに、そっと石にさわってみたりしていたが、
そのうち、中がどうなっているのか知りたくてたまらなくなった。
そこで、ある日思い切って、
こっそり石を下ろして、
小づかで穴をがりがりと削って石の中心部を見ようとした。
水石は硬く、なかなか穴は大きくならなかったが、
夢中で削っていると、
やがて、穴から細かく泡立った粘液があふれ、
糸を引いて垂れだした。
さあ、どうしようと、
嫁が慌てている間も、
とろとろと粘液が流れ、
その液体にまじって、
親指の頭ほどの、白くて目のない魚が
穴からつるりと飛び出した。
見ていると、
地に落ちた魚は、ぴたぴたと暴れたが、
すぐに土のくぼみから、土中へもぐり、姿を消した。
それきり。
嫁が穴をうがった家宝の水石からは、
1滴も水が出なくなってしまったという。
そして、
水石の水を涸らした嫁は、
じき、里に帰されたと。
★★★★
短編小説 ブログランキングへ
お手数おかけしますが、できればご協力を。









