お母さに言われて、
山にバンカイを取りに行った清っこが、
道に迷ってしまった。
遠くでカラスの声がするだけで、
山中に人の気配は全くない。
日が沈み、
当たりはどんどん暗くなっていく。
このままでは帰れなくて、山で一晩過ごすことになる。
へたすると、
山の化け物に食われるかもしれない。
あせった清っこが、薄暗くなってきた山の斜面を
つんのめるようにして駆け下りて、
ひょいと前方を見ると、
薄闇のなかに、何かが白く光っていた。
おそるおそる白い光に近づいて見たところ
それは満開のコブシの花だったと。
暗くなると、コブシの花は
白く光るものだと、
お母さに聞いていたけれど、
あれは本当だった。
コブシの木のそばに細い道が見つかった。
その道をたどり、
1本のコブシから、次のコブシへと、
淡い白光を目当てに道をたどって、
清っこはようやく村へ帰ることができた。
「あとでお母さに聞いたんども、
ワラシが山で迷子にならないように、
村では代々、道しるべのかわりに、
コブシの木を植えていたそんだ」
コブシに救われて、無事に家へ帰れた。
あの木々を植えた村の人たちの心づかいが
なんともありがたかった。
赤岳のふもとにある、
コブシが満開の村で。
お清婆さまは、そんな話をしてくれた。
★★★
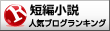
短編小説 ブログランキングへ
どうかよろしくお願い致しぁんす。
薄墨もようやく春が近づきました。
山にバンカイを取りに行った清っこが、
道に迷ってしまった。
遠くでカラスの声がするだけで、
山中に人の気配は全くない。
日が沈み、
当たりはどんどん暗くなっていく。
このままでは帰れなくて、山で一晩過ごすことになる。
へたすると、
山の化け物に食われるかもしれない。
あせった清っこが、薄暗くなってきた山の斜面を
つんのめるようにして駆け下りて、
ひょいと前方を見ると、
薄闇のなかに、何かが白く光っていた。
おそるおそる白い光に近づいて見たところ
それは満開のコブシの花だったと。
暗くなると、コブシの花は
白く光るものだと、
お母さに聞いていたけれど、
あれは本当だった。
コブシの木のそばに細い道が見つかった。
その道をたどり、
1本のコブシから、次のコブシへと、
淡い白光を目当てに道をたどって、
清っこはようやく村へ帰ることができた。
「あとでお母さに聞いたんども、
ワラシが山で迷子にならないように、
村では代々、道しるべのかわりに、
コブシの木を植えていたそんだ」
コブシに救われて、無事に家へ帰れた。
あの木々を植えた村の人たちの心づかいが
なんともありがたかった。
赤岳のふもとにある、
コブシが満開の村で。
お清婆さまは、そんな話をしてくれた。
★★★
短編小説 ブログランキングへ
どうかよろしくお願い致しぁんす。
薄墨もようやく春が近づきました。









