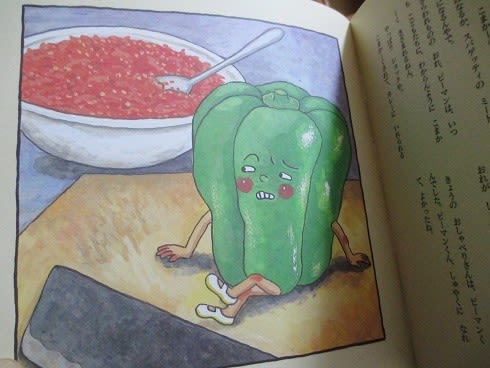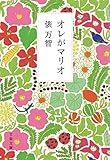平成時代もあと10日あまり。
なんだか“何かが変わる実感”もないままに
5月1日を迎えそうです。
ということで、昭和の終わりから平成の始まりを
ドキュメントのように書かれた本を読みました。
システム屋としては、年号の修正対応などもしたわけで
Xデーを迎えるまでの、それなりの心構えをしていました。
まあ、そのあたりは以前書いたはずなので割愛しますが。
この本は、天皇陛下が崩御される2、3年前からを
時系列的に綴っているものです。
昭和天皇が体調を崩されての手術であったり、
その後の様子、そしてご危篤となった1月6日のこと。
宮内庁、政府、街の様子、
それぞれの視点で取材されていました。
ほとんどの国民にとっては当然初体験であった天皇陛下の崩御。
あの日の早朝のことはフジテレビだったか
ワタシ、ずっとビデオに録画をしておりましたね。
東京の狛江でワンルームマンションで暮らしていた頃です。
平成の終わりとは違う、自粛モードの日々。
今回の退位に伴う改元とはまったく違う世間。
この30年前のことが懐かしく甦ってきました。
でも、今年はチャラチャラしたイベント、
特にカウントダウンなんぞがありそうで、
厳粛さのかけらもなさそうだなあ。
ま、おめでたい、ってことで良しとするか。
 |
ドキュメント 昭和が終わった日 |
| 佐野 眞一 | |
| 文藝春秋 |
そして、もう一冊。
著者のルポがなかなか読み応えあったので、
図書館のネット検索をしていたら、
こんな著書を見つけたので借りちゃいました。
いきなりこんな表紙です(^^;)
 |
別海から来た女――木嶋佳苗 悪魔祓いの百日裁判 |
| 佐野 眞一 | |
| 講談社 |
そう、結婚詐欺だけでなくお金を搾取したあとに
男性を練炭殺害した例の女の裁判記録のルポです。
こういったルポは、裁判を軸として
周辺の取材による事件の経緯や被告の経歴などが書かれ、
半ば好奇心でも読むものですが、
何だか別世界のことのようでもあるものの、
同じ人間なのだと考えるとホントに恐怖を感じるものです。
で、この“事件”のことはともかく…この表紙(^^;)
図書館で借りる本というのは、
たいていカバーフイルムで覆われています。
ワタシも子供らが小さい時に自宅の絵本を保護していました。
で、このフイルム。
当然のように透明です。
おわかりですね(^^;)
電車の中でこの本を読むときに、
この表紙がモロ見えなのです(^^;)
このオッサン、木嶋佳苗の本を読んでいるのか、と。
例えば吊革につかまってこの本を胸辺りで広げる、
座席に座っている人には表紙の全貌が見えるわけですよ。
そう、表紙からの続きのように裏表紙も含めて!
いやあ、困った困った、インパクトが強すぎて。
書店の平積みでもきっと目立ったのだろうなあ。
座席に座って読む際には
なるべく表紙を水平に下に向けていましたが。
まあ、それでも隠し隠し
何とか通勤時に読み終えました。
この著者のルポ、
悪く言えば三面記事を掘り下げているような感じもあり、
でも直接的な関係だけでない周辺事情も取材されて
興味深いものが多いようです。
今後もノンフィクション、ちょこちょこ借りるとするか。