ホーンに憧れ、直熱管(真空管)に憧れ、製作した物です。
2インチドライバー(ホーン)に直熱管(845シングル)駆動 私の憧れでしたので、この音を体験すべく自作に走り、今までこの音を追求すべく色々挑戦(造り直しや変更)しやっと満足の音作りが出来ましたので、発表しました。
この、システムで難問だった事が下記の点です。
1. ホーンドライバーは、効率が高く(約110Db)、直熱管のシングル駆動ではノイズの問題が有ります、
(現在のスピーカー(85Db程度)では、全く問題なし)
この対策に苦労しました。 何度か造り直し結局電源分離型が一番良いと悟り、製作しました。 ノイズの少ない音は格別です。
2. ホーンドライバーの音を生かすため、アンプに入力トラス、出力管をトランスドライブにし、コントロールアンプ等も、トランス出力にこだわりました。
現在の、オール自作のシステムです。

アンプは、マルチアンプで構成しています。
中高域には、真空管845シングルトランスドライブ、電源分離型です。
写真ラックの左側上部です。 電源は、左一番下に設置しています。(総重量 約40Kg)
低域には、真空管300B PPのトランスドライブ、電源分離型です。
写真ラックの右側上部です。 電源は、右一番下に設置しています。(総重量 約40Kg)
チャンネルディバイダーは、真空管12AU7 PPトランス送り出し トランスドライブで、出力600Ω送り出しです。 約500HZクロスです。
写真左側中段で、右側が専用電源部です。(総重量 約15Kg)
スピーカーはユニットを購入、ボックスやホーンは自作です。
ウファー(JBL2220B) ミッド(JBL2450J) ツィター(JBL2405)を使用しています。 (総重量 方チャンネル約100Kg)
ラックも集成材で自作です。(総重量 約30Kg)
重くて移動が大変です。

部屋の反対側に設置の、自作コントロールアンプ、自作イコライザーアンプ、自作ラックです。
(レコードプレーヤー、CDプレーヤーはメーカー製です。)
コントロールアンプは、真空管6JD8、パラSEPP回路のトランス送り出しです
イコライザーアンプは、真空管12AX7のSEPP、CR型、別で電源(コントロールアンプより引き出し)

音質としては、ホーンの音を真空管(トランスドライブ)でネットワークを入れず(スピーカーの元へコイル、コンデンサーを入れることによる、
位相崩れやインピーダンスの変化による音質への影響)を無くした音は、非常に良いものです。
この音にあこがれ、深入りした結果で非常に満足しています。
現在では、この様なシステムはメーカー製では構築出来ません、 自作と言う事で(コスト度外視)でしょうか、現在の音作りとは別もので、
若い時あこがれていた音を手に入れ満足している所です。
興味のある人何人かに来て頂いて試聴していますが、最初の一言は綺麗な音質で、長時間聞いても疲れ無いと言っています。
このブログで、紹介したシステムの製作過程を紹介しています。 興味のある方は見てください。(堅い話になっていますが)
2インチドライバー(ホーン)に直熱管(845シングル)駆動 私の憧れでしたので、この音を体験すべく自作に走り、今までこの音を追求すべく色々挑戦(造り直しや変更)しやっと満足の音作りが出来ましたので、発表しました。
この、システムで難問だった事が下記の点です。
1. ホーンドライバーは、効率が高く(約110Db)、直熱管のシングル駆動ではノイズの問題が有ります、
(現在のスピーカー(85Db程度)では、全く問題なし)
この対策に苦労しました。 何度か造り直し結局電源分離型が一番良いと悟り、製作しました。 ノイズの少ない音は格別です。
2. ホーンドライバーの音を生かすため、アンプに入力トラス、出力管をトランスドライブにし、コントロールアンプ等も、トランス出力にこだわりました。
現在の、オール自作のシステムです。

アンプは、マルチアンプで構成しています。
中高域には、真空管845シングルトランスドライブ、電源分離型です。
写真ラックの左側上部です。 電源は、左一番下に設置しています。(総重量 約40Kg)
低域には、真空管300B PPのトランスドライブ、電源分離型です。
写真ラックの右側上部です。 電源は、右一番下に設置しています。(総重量 約40Kg)
チャンネルディバイダーは、真空管12AU7 PPトランス送り出し トランスドライブで、出力600Ω送り出しです。 約500HZクロスです。
写真左側中段で、右側が専用電源部です。(総重量 約15Kg)
スピーカーはユニットを購入、ボックスやホーンは自作です。
ウファー(JBL2220B) ミッド(JBL2450J) ツィター(JBL2405)を使用しています。 (総重量 方チャンネル約100Kg)
ラックも集成材で自作です。(総重量 約30Kg)
重くて移動が大変です。

部屋の反対側に設置の、自作コントロールアンプ、自作イコライザーアンプ、自作ラックです。
(レコードプレーヤー、CDプレーヤーはメーカー製です。)
コントロールアンプは、真空管6JD8、パラSEPP回路のトランス送り出しです
イコライザーアンプは、真空管12AX7のSEPP、CR型、別で電源(コントロールアンプより引き出し)

音質としては、ホーンの音を真空管(トランスドライブ)でネットワークを入れず(スピーカーの元へコイル、コンデンサーを入れることによる、
位相崩れやインピーダンスの変化による音質への影響)を無くした音は、非常に良いものです。
この音にあこがれ、深入りした結果で非常に満足しています。
現在では、この様なシステムはメーカー製では構築出来ません、 自作と言う事で(コスト度外視)でしょうか、現在の音作りとは別もので、
若い時あこがれていた音を手に入れ満足している所です。
興味のある人何人かに来て頂いて試聴していますが、最初の一言は綺麗な音質で、長時間聞いても疲れ無いと言っています。
このブログで、紹介したシステムの製作過程を紹介しています。 興味のある方は見てください。(堅い話になっていますが)











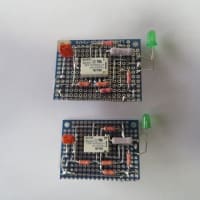








ホーンは、JBL2350を予定しています。
500Hz以上が適正ですから、クロスは500Hzにした方がいいのでしょうか?
私は、2420から2450まで使用経験が有ります。
800hzから500hzにクロスを変更と1インチより2インチにし、一番感じたことは、中域の音質の変化です。
特に、音声は変化が大きく感じました。良い方向にです。
このブログにも書いていますが、木製ホーンも良いですよ。
http://audio-heritage.jp/JBL/unit/2205.html
によれば、推奨クロスは800hzとなっています。
問題ないのでしょうか?
クロスは、この様なスピーカーを使用なら、300hzでも良いと思います。 ただし、中域ドライバーの再生問題は考慮する必要が有りますが。
高域ドライバー(ツイター)は、低域を入れすぎると焼損しますので注意が必要です。
2445と2205は500hzで大丈夫です。
クロスは、人間が感じる帯域を極力離す事が、理想です。(定位や歪を感じやすい場所から離す)
私の偏見かも判りませんが?
スピーカーにしてもアンプにしても、この世界はいい加減な物が多いです。
メーカーにしても、コスト的に無理や技術的に無理でも、そんなことは一切言わず、何かの高度な理由を付けて売ります。
スピーカーにしてもネットワークや、アンプにしても見える所は立派ですが、内部はちゃちな物です(基盤のコネクター配線等)。
2205は、なるべくしたの方でクロスしたほうが、良いと思います。 コーンが重くできているため(低域稼ぎ)。
2441でしたね。 2441も同じで、大丈夫です。
私はローコストで自作オーディオを楽しんでいます。
> 1. ホーンドライバーは、効率が高く(約110Db)、直熱管のシングル駆動ではノイズの問題が有ります、・・・
ホーンのノイズをアンプのノイズ低減で解決されたとのことですが、私は別の方法で逃げ?ました。ウーファーが95dB、ホーンドライバーが106dBでその能率の差をチャンデバの高音側のボリュームを絞ることで補っていましたが、ノイズが大きく不満でした。
ある時にひらめきましたのが、ホーン用のアンプとホーンの間にセメント抵抗で作製した約9dBの固定式のアッテネータを挿入して、チャンデバで高音の信号をしぼらないという方法です。これで現在は満足していますがこの方法による問題点等がございましたら、ご指摘をお願いします。
直熱管は、どうしてもノイズの低減が一番難しい所だと思っています。
私は、アンプとスピーカーの間に何も入れない事にこだわりが有ります。
特に、ウファーは論外ですがミッドレンジは中域ですから、一番音質を感じ取る帯域です。
抵抗もダンピングに影響しますので入れない様にしています。
ツイターは、入れても良いかな?
ですから、アンプの方で直熱管の音質を生かすため、私なりの対応は電源部とアンプ部の分離です。
トランスやチョークの磁気漏れに対する影響が無くせました。 また、回路インピーダンスを小さくする事も考えました。(これに対しては、コントロールアンプの駆動力の問題も有りますが)
結構苦労しましたが、アンプでの解決が本筋だと思います。
効率の違いによる、音量の調整は、チャンネルディバイダーの出力調整と、バワーアンプの入力調整で行っています。
なお、チャンデバの出力2w程度でインピーダンスは600Ωとして、パワーアンプの入力調整は、定インピーダンスアッテネーターとしています。
私もアンプでの解決が本筋だと思います。
私の場合は、低音、中高音共にTrアンプで、アンプ自体のノイズはさほど大きいものではなかったので、アンプとホーンの間に固定式アッテネータを入れるという方法を採りました。ユニットに能率差がある場合にはどこかでアッテネーションをしなければなりませんが、この方法ですと容易にS/N比を大きくすることができます。固定式アッテネータ挿入によるビビッド感の低下を心配しましたが、私の駄耳ではわかりませんでした。
固定式アッテネータはL型で合成インピーダンスはホーンユニットの公称インピーダンスに合わせました。ダンピングの問題はあるとは思いますが、安易な方法としてはよいのではないかと思っています。
尚、私も真空管アンプを愛用していますので、貴ブログで勉強させていただきたいと考えています。
ありがとうございました。