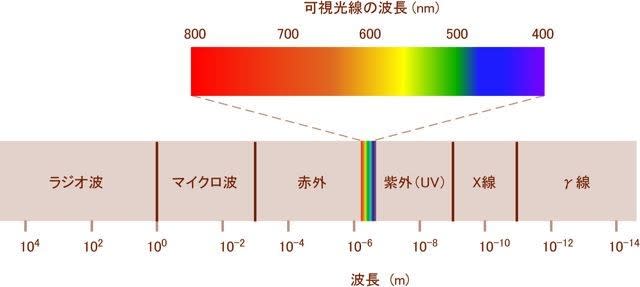以前友人から「木綿豆腐と絹ごし豆腐どっち派ですか?」と聞かれました。
意外と木綿豆腐と絹ごし豆腐がどっちがどっちなのかと自分の中であまり区別がついておらず毎回友人に聞いたり調べて買って食べたりします笑
ざっくりとした違いは製造方法や栄養価、適した料理が異なるようです。
いい機会なので明確な違いを調べてみました。
そもそも豆腐とは熱い豆乳を『にがり』などの凝固剤で固めたものをさします。
☆木綿豆腐とは?☆
木綿豆腐は豆乳を凝固剤(にがり)で固めたものを一度崩し、木綿の布を敷いた穴の開いた型箱に入れて圧力をかけて水分を抜いて作ります。
歯ごたえがあり、凝縮された大豆の旨みを感じられます。
栄養価も非常に高く、タンパク質、脂質、カルシウム、マグネシウム、鉄、リン、食物繊維などが数多く含まれており、植物性タンパク質やカルシウムなど大豆本来の栄養素を多く摂りたい場合は、木綿豆腐を選ぶと良いそうです。
調理した際、崩れにくいのが特徴的で焼いて田楽、揚げて揚げ出し豆腐が適しています。また中身に隙間があり味が染みやすいので煮物にすると非常に美味しくなります。

☆絹ごし豆腐とは?☆
乳を穴のない型箱に入れて凝固剤を投入し、水分は抜かずプリンのようにそのまま固めます。
つるっとした喉越しが特徴ですね。
栄養価は水溶性の栄養成分であるカリウム、ビタミンB群などが水分と一緒に残り、木綿豆腐よりも多く含まれます。
柔らかいのが特徴的なので冷奴や味噌汁の具にぴったりです。

普段何気なく食べている豆腐ですが、木綿豆腐と絹ごし豆腐でこんなにも違いがあるんですね!
皆さんも豆腐を食べる際は、栄養価や料理などをよく知ってから調理してみては如何でしょうか?