
厳冬期の草原で建設資材を入手するのは不可能に近い。 10日以上の旅をして 定着民の社会 =多くは万里の長城南の農耕村落= に赴き購入か、略奪するかしか方法がない。 表土は凍り、粘土ですら作れない。 勢い、手持ちの家畜の皮・骨 等しかないので これらは建設資材とは言えぬ であろう。 だが、蒙古高原は北庭都護府・可敦城の砦に入った諸将は苦難を苦難と感じない若さがあった。 新しい世界の創造に燃えていたと言える。 北辺から南下した契丹人の帝国である遼王朝の太祖耶律阿保機の末子である耶律牙里果の7世の子孫に当たる耶律大石に 遼王国は壊滅しようとしている最中 彼等全員が心服し、彼の意を推し量って行動する集団であった。
耶律大石は、28歳の時に科挙で状元となって翰林院へ進み翰林応奉に就いた。 太祖耶律阿保機が王朝の根幹として、開闢以降、中華の諸制度を政経の範とした。 模倣した制度の内、科挙制度は若き秀英たちが目指した最高の学位資格である。 官僚登用試験でもあるこの科挙に応試するだけでも名誉であった。 大石はその科挙の状元である。 第一等の成績を修めた者のみに与えられる称号が状元。 大石はそれを得ていた。 遼王朝開闢以来、100年にして やっと誕生した駿馬であった。 北遼皇帝・天錫帝の傍に登籠すれば。 軍事の天才でもあった。 また、彼の人柄に多くの才人が自ずと集まり、多くの異能者が彼の指示の下で働く喜びを覚えていた。
耶律大石が飛躍の足掛かりに選んだこの地・北庭都護府可敦城は遼王朝が管理していた北方の遊牧民・蒙古族との交易の為に設けられた要塞である。 しかし、遼の衰退・崩壊に伴い見捨てられ、自然の為すままであった。 故意に人が破壊しない限り、木材は乾燥地帯では朽ち果てにくい。 例えば、長城の日干し煉瓦など 砂に埋没するだけで風雨による崩落はない。 また、蒙古草原の遊牧民の生活燃料は家畜の糞であり、木材の薪など使おうという発想すら持っていない。

開城祝いをした翌朝、大石の下に何亨理と耶律遥が思案顔で訪れてきて、 「統師殿、朝一番に見回ってきて思うのですが、 布と釘があれば 寒さを防ぐ手当てができます。 ついては 私に10名の兵と馬30頭を貸し与えてください。 西夏の鳥海に行けば、見知りの商人がおります。 往きは四日、帰りの六日と集荷に四日、二週間の旅程ですが、その間に曹舜が木材を整理し、表土は硬いでしょうが氷った土を掘り起し、西側に擁壁を築き上げるのは容易でしょうから畢厳劉にこの作業を お命じ下さい。 全体の指揮は遥殿にお願いしたいのです・・・・」
「よく気が付く、西側に擁壁を工夫して建造すれば、直ちに兵馬の畜舎が設けられると共に砦の防御の補強が一石二鳥と完備できるな。 して、鳥海に向かう馬と兵はそれで十分かな それと、遥よ 物見やぐらを考えて貰いたい。 木材は西側の柵の残材を工夫するとして・・・・・」
「物見やぐらまでは・・・・ はい、直ちに、・・・・・革紐が・・・・耶律磨魯古の知恵を借りましょう。 亨理殿、革紐の数量を出立前までにお知らせします」
緊急に必要とする資材の打ち合わせは済んでいたのであろう。 翌日の早朝には何亨理が10名の兵と共に、早駆で南西に向かって行った。 馬の吐く息が白い。 馬上の将兵は毛皮の防寒衣で個々の判別などできない状態で離れた行った。 耶律遥は耶律磨魯古が指揮する20名の若者に混じり、大声で激を飛ばしながら木材の片付け始めている。 体を動かさなければ寒さに耐え切れないようだ。 全員が生き生きと汗を流し始めた。 曹舜と畢厳劉は城内の縄張りを行っいる。 砦内の木材を仕分けてせいりが終われば、縄張りに従って凍てつく表土を掘り起し 擁壁を築く作業に取り掛かるのであろう。 活気づいた城内を一巡した大石は楚詞とチムギを伴い、遠駆けに出た。 周辺の地形を調べる目的であろう。

日増しに城内は整備され、 西側の壁も積まれていく。 掘り下げられた場所は馬の繋ぎ場に成っていく。 穏やかな日が続き 作業は捗り、砦の活気は一段と増して行く。 時折、 大石は長と話し合っている。 長の名はボインバット。 娘と男が二人いた。 先日の羊の頭を捧げ持ってきた子供であろう。 長には嫁いだ娘がいた。 馬駆け15日の北にいるとの話である。 他に、夫婦もの四組が住んでいる。 若者は二人だけだった。 若者はすぐに兵士に溶け込み、作業に精を出すようになっている。 老夫婦のこどもであろう。 三組の夫婦の子度は皆幼く、乳飲み子が一人いた。 長の夫人が大石たちの食事を作ってくれるようになっていた。
大石は遠駆けを日課のように出かけている。 その前後にはチムギと楚詞が赴くままに馬を操る姿があった。 燕京で育ったチムギは馬と一体となって疾走する喜悦が解り出したのであろう、戯れるように楚詞と競い、一人で駆け、あるいは 楚詞と共歩している。 大石はそれを楽しそうに眺めていた。 二人は夕刻に帰ることが多く成っていた。

【前ページへの以降は右側袖欄の最新記載記事をクリック願います】
※;下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます=ウィキペディア=に移行
----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------
【壺公夢想;紀行随筆】 http://thubokou.wordpress.com
【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/
【 疑心暗鬼;探検随筆】 http:// bogoda.jugem.jp/
【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/
・・・・・・山を彷徨は法悦、その写真を見るは極楽 憂さを忘るる歓天喜地である・・・・・
森のなかえ
================================================













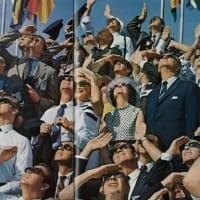



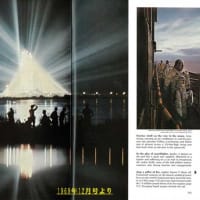
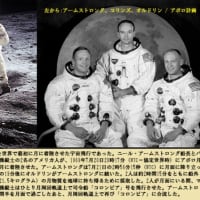
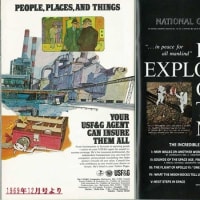
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます