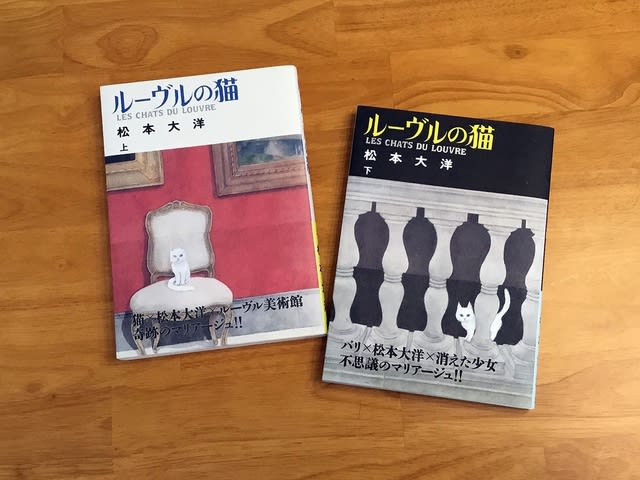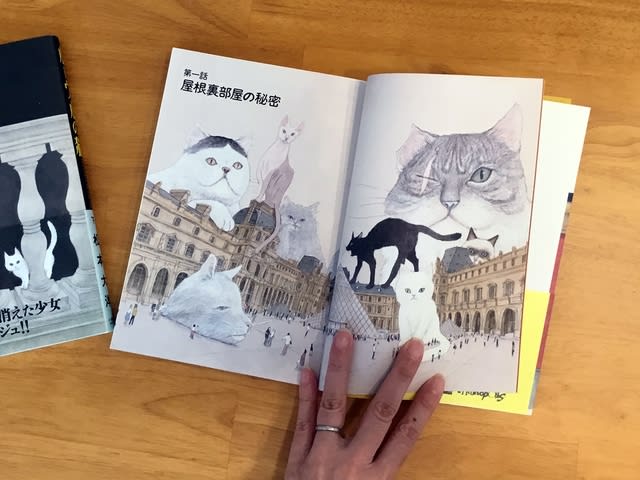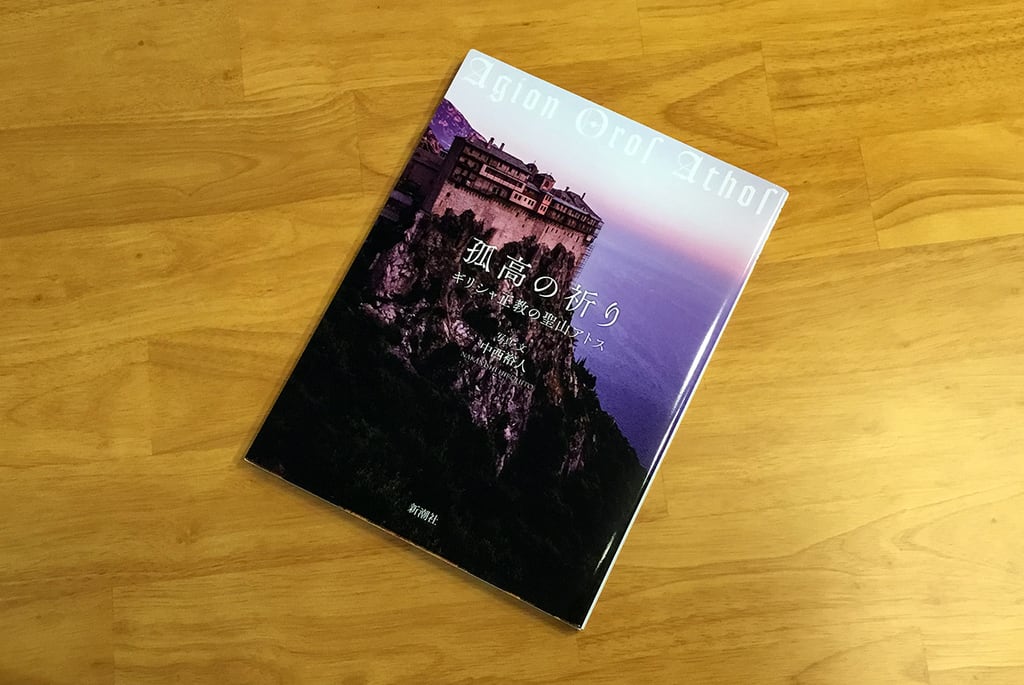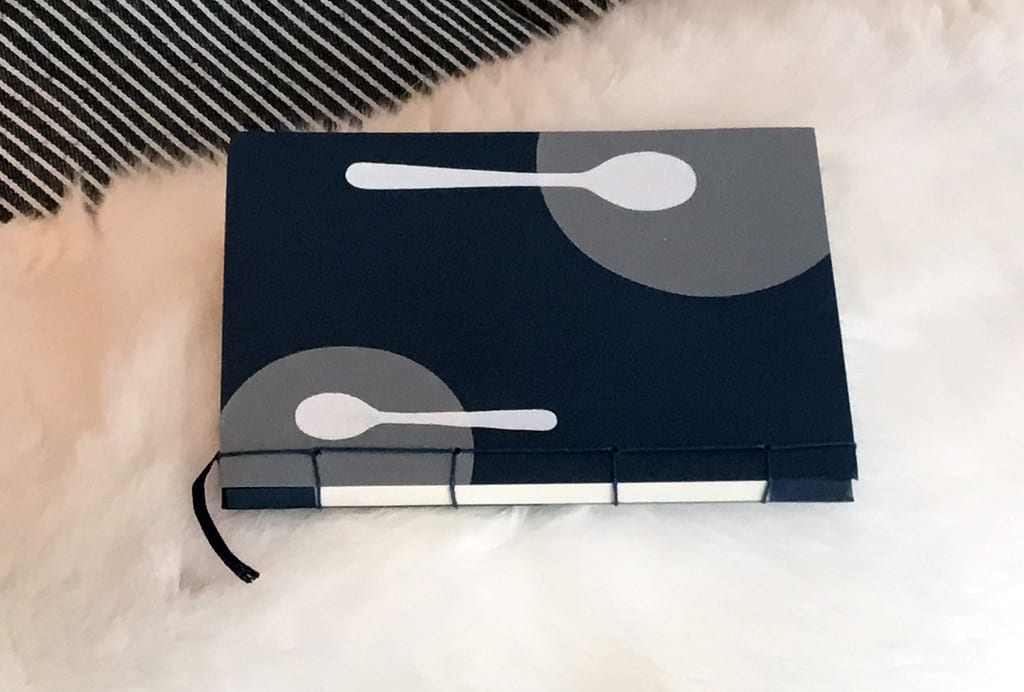7〜8年前まで実家で犬を飼っていました。
雌の黒柴で、名前は「ひでか」。

成犬になってから、とある事情で引きとったのですが
最初仕方なく飼い始めたものの、そのうち家族は全員メロメロに。
ひでかにとってすでに家を出ていてたまにしか姿を見せない私は、
ただのお客さん扱いで完全に格下認定されており、
なんとなく「ひでかさん」と呼んでおりました。
その後だんだん「ひでかちん」になりましたが ( ^ω^ )

引き取ったのは実家にいる弟で、
その時に新しい名前を用意したらしいのですが
前の飼い主が、血統書に書かれていた名前「秀華号」から
「ひでか」と呼んでいたので
その名前で呼ばないと完全無視を決め込むひでかさん。
弟はとうとう根負けし、
結局、名前は秀華(ひでか)のままとなりました。

2歳の頃家に来て、14歳で息を引き取るまで
家族みんなに愛されたひでかさん。
黒くて大きかったせいか、
何度教えても、はるは「男の子」だと思っていました 笑
そんなひでかさんを思い出す本があります。

『犬を飼う そして…猫を飼う』(谷口ジロー)
だんだん歩けなくなり、寝たきりになったひでかさん。
病院にも連れて行けなくなり、電話で獣医さんとやりとりしながら
1年以上続いた介護生活を経て、息を引き取りました。
このマンガの飼い犬、「タムタム」の最期の様子が
ひでかさんととても似ているのです。
動物を飼うってこういうことなんだ、という
覚悟を問われている気がします。
そしてもう一つ、これはひでかさんと関係ないのですが
犬が出てくる、すごく好きな話があって。

『いくえみ綾 THE BEST』に収録されている、
二話目の『My dear B・F(ボーイフレンド)』。
余命僅かとなった老犬が、最後に神様に叶えてもらった願いとは…

このお話、別の単行本に載っていて、どの本だったか思い出せなかったのですが
BESTに入っていると知り、買い直しました。
何回読んでも泣ける。。。
青春なんてとうの昔の出来事ですが
こういうのはいくつになってもいいですね。。。
私の言うことはあまり聞いてくれないひでかさんでしたが
私が母(秀華が一番好きな人)と仲が良いのをちゃんと知っていて、
本当は嫌だけど、しぶしぶ、仕方ないな〜といった感じで
私とも散歩に行ってくれたものでした (´ー`)
実家の郵便受けには家族全員の名前が書いてあるのですが、
ひでかさんを溺愛する父が、いつの間にか
「秀華」というシールを作って一番下に貼ったのです。
うちは家族全員、平凡な、よくある名前で
わたしにいたっては、ひらがな。
優秀の「秀」と豪華の「華」という
家族の誰よりも画数の多い、立派な名前が並んでいたからなのか
(違うかもしれませんが)
ある日、
「秀華さんはいらっしゃいますか」と電話があり
「秀華はうちの犬ですけど」と母が答えたら
「ガチャ、ツーツーツー…」
速攻で切れたそうです 笑
誰だか知らないけど、
犬の名前だと思わないよねぇ
沢山の思い出をくれたひでかさんのことは
また今度書ければと思います ^ ^
最後はいつものネコたち (ФωФ)