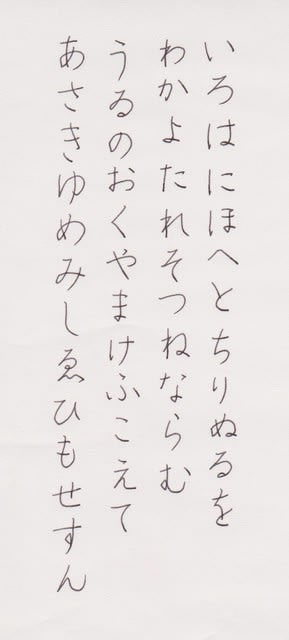三首めです。
足引きの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む 柿本人麿
歌意
長く垂れ下がった山鳥の尾のように長い長い秋の夜を
私はたった一人で寝ることになるのだろうか
これは、恋の歌だったのですね!!(無知!)
恋しい人に逢えず、秋の夜長をひとり寂しく過ごさねばならない
という、恋のわびしさ、悲しみを詠んだ歌なのです^^
恋の歌だと思うと俄然興味が増しますね!!
ちなみに、山鳥というのは昼間は一緒にいる雌雄が
夜には谷を隔てて別々に寝るという習慣があるのだそうで(ナゼ??)
そんな山鳥にひとり寝の寂しさと重ねてるのだそうで・・・
うーん、奥が深いです!!
柿本人麿は私でも名前はよく知ってますね。名前だけは・・(TT)
さきの持統天皇に仕えていた宮廷歌人と言われてますが、素顔は不明だとか。
謎の男!!!
でも伝説的歌人として伝えられているのだそうです。
三十六歌仙の一人だと・・・・
え?36人って結構多くない?
伝説的といいながらベスト10にも入ってないん?
って思ってしまった私ですが・・
別にランク付けされてるわけじゃないんですよね。
すごい人だということで^^
(後でわかったんですが、「柿本人麻呂」と書くほうが一般的なようですね。
どちらも間違いではないようですが。
手習い帳テキストに「麿」となっていたのでそのまま書いています・・・)
今回はひらがなが多くて、わりと書きやすかったですね。
「鳥」が最初バランス取れなかったですが
書いてるうちになかなか決まってきました^^(自己満足です)
「寝」が一番難しかったです。
小さい部品がたくさん入ってる文字は
大きさと位置で全然違う字に見えてしまう・・
書いてるうちになんの字を書いてるのかわからなくなったり・・・(><)
でもまあ、なんとか許せる程度には落ち着いてきたような・・ダメなような・・
完璧!って納得できるまで・・と思うと
いつまでたっても終われないので
そこそこ満足という段階でOKにすることにしました! ←明らかな妥協・・・

「足」がバランス悪~(><)上の「口」が大きすぎましたね。
「引」もバランス悪いなぁ・・縦棒が歪んでるし(TT)
「鳥」はまあまあかな・・・真ん中の横棒が短かったけど!!
「寝」はやっぱりなんかイマイチですねぇ・・・
お手本見ながら真似してるつもりなのに、なんでこんなに違うのかな。
うーん・・・
でもまあ、これだけ書けたら私にしては上等でしょう!!
と、いつもの甘々評価しておきます^^
(そんな甘いことだから上達しないんだよ・・)←心の声(*>ω<*)ゞ
足引きの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む 柿本人麿
歌意
長く垂れ下がった山鳥の尾のように長い長い秋の夜を
私はたった一人で寝ることになるのだろうか
これは、恋の歌だったのですね!!(無知!)
恋しい人に逢えず、秋の夜長をひとり寂しく過ごさねばならない
という、恋のわびしさ、悲しみを詠んだ歌なのです^^
恋の歌だと思うと俄然興味が増しますね!!
ちなみに、山鳥というのは昼間は一緒にいる雌雄が
夜には谷を隔てて別々に寝るという習慣があるのだそうで(ナゼ??)
そんな山鳥にひとり寝の寂しさと重ねてるのだそうで・・・
うーん、奥が深いです!!
柿本人麿は私でも名前はよく知ってますね。名前だけは・・(TT)
さきの持統天皇に仕えていた宮廷歌人と言われてますが、素顔は不明だとか。
謎の男!!!
でも伝説的歌人として伝えられているのだそうです。
三十六歌仙の一人だと・・・・
え?36人って結構多くない?
伝説的といいながらベスト10にも入ってないん?
って思ってしまった私ですが・・
別にランク付けされてるわけじゃないんですよね。
すごい人だということで^^
(後でわかったんですが、「柿本人麻呂」と書くほうが一般的なようですね。
どちらも間違いではないようですが。
手習い帳テキストに「麿」となっていたのでそのまま書いています・・・)
今回はひらがなが多くて、わりと書きやすかったですね。
「鳥」が最初バランス取れなかったですが
書いてるうちになかなか決まってきました^^(自己満足です)
「寝」が一番難しかったです。
小さい部品がたくさん入ってる文字は
大きさと位置で全然違う字に見えてしまう・・
書いてるうちになんの字を書いてるのかわからなくなったり・・・(><)
でもまあ、なんとか許せる程度には落ち着いてきたような・・ダメなような・・
完璧!って納得できるまで・・と思うと
いつまでたっても終われないので
そこそこ満足という段階でOKにすることにしました! ←明らかな妥協・・・

「足」がバランス悪~(><)上の「口」が大きすぎましたね。
「引」もバランス悪いなぁ・・縦棒が歪んでるし(TT)
「鳥」はまあまあかな・・・真ん中の横棒が短かったけど!!
「寝」はやっぱりなんかイマイチですねぇ・・・
お手本見ながら真似してるつもりなのに、なんでこんなに違うのかな。
うーん・・・
でもまあ、これだけ書けたら私にしては上等でしょう!!
と、いつもの甘々評価しておきます^^
(そんな甘いことだから上達しないんだよ・・)←心の声(*>ω<*)ゞ