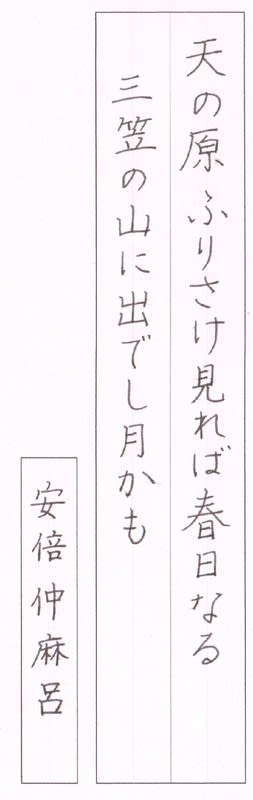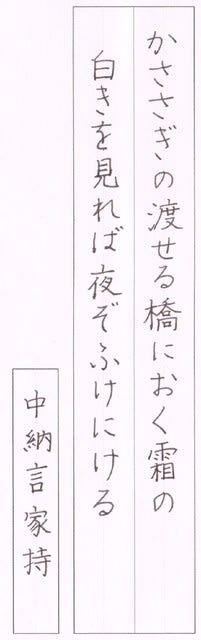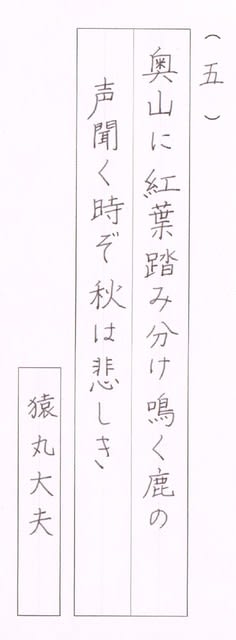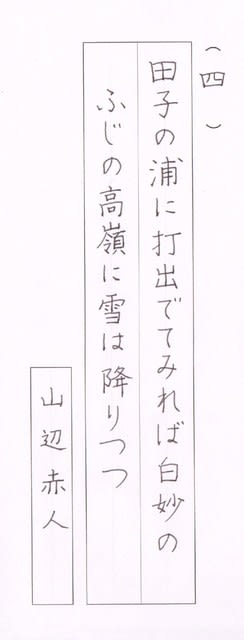八首めです。
わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり 喜撰法師
歌意
私の庵は都の東南の宇治山にあって、このように心のどかに暮らしている。
なのに、私がこの世をつらいと思って「うぢ」山に住んでいるのだろうと
世間の人は言っているようだ
「うぢ山」は「宇治」と「憂し」の掛詞になっています。
世間では自分のことを、世の中を憂しと感じて隠棲しているように
言っているみたいだけど
私は何の憂いもなく心のどかに暮らしてるんだよ~
って感じで、世俗から離れて自由気ままに生きる楽しさと
ユーモアたっぷりに詠んだ、オシャレで明るい歌なのですね。
「しかぞすむ」の「しか」とは「このように」という意味で
「このように暮らしている」となるのですね。
てっきり「鹿が住んでる」・・だと思いました(><)
喜撰法師という方はもちろん私は知りませんでしたが
実際、宇治山の僧という以外経歴不明らしいです。
六歌仙の一人!
おお!今まで出てきた三十六歌仙より上な感じがする!
六歌仙は「古今和歌集」に記されているそうで
私も知ってる紀貫之さんが選んだのだそうです。
僧正遍照・在原業平・文屋康秀・喜撰法師・小野小町・大友黒主の六人。
百人一首は大友黒主以外が登場しています。
これから出てきますね^^
調べてみると紀貫之は、この六人を選んだくせに
結構ボロクソに批評してるのが面白かったです^^
彼にとっては柿本人麻呂と山部赤人が偉大な歌人だったのだって。
まあ全体の中ではこの六人がいい線いってるけど
偉大な二人に比べたらまだまだや!って感じだったのかな(*^_^*)
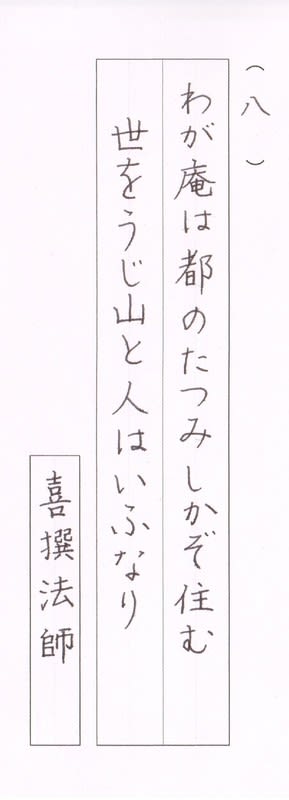
今回結構うまく書けた!!!
「うぢ山」だけ失敗したな~・・・
なんて思ってたのですが
意外と書けてないなぁ・・・(意外とって・・)
ひらがなが続くと特に中心が揃わないんですよねぇ・・・
どうしたらちゃんと揃うのかなぁ・・・・
練習あるのみ!ですね!!(≧▽≦)b
※って思ってたら「うぢ山」を間違って「うじ山」って書いてた!!
字の上手下手以前の問題でした・・・(><)
・・ちょっとはいいとこ書いてテンションアップしとこう!
「庵」はなかなかカッコよく書けてる気がします!
「都」と「住」もなかなかかな・・・
「人」は左払いをもっとシッカリ書いたほうがいいですね!
ひらがなは・・「わが」がいい!
どうも「つ」と「し」が苦手です・・・
単純な線なのに・・書いていつも「あちゃ-」てなる(*>ω<*)ゞ
それと「と」が中心ずれるんですよねぇ・・・
まだまだ問題山積です!!
わが庵は 都のたつみ しかぞすむ 世をうぢ山と 人はいふなり 喜撰法師
歌意
私の庵は都の東南の宇治山にあって、このように心のどかに暮らしている。
なのに、私がこの世をつらいと思って「うぢ」山に住んでいるのだろうと
世間の人は言っているようだ
「うぢ山」は「宇治」と「憂し」の掛詞になっています。
世間では自分のことを、世の中を憂しと感じて隠棲しているように
言っているみたいだけど
私は何の憂いもなく心のどかに暮らしてるんだよ~
って感じで、世俗から離れて自由気ままに生きる楽しさと
ユーモアたっぷりに詠んだ、オシャレで明るい歌なのですね。
「しかぞすむ」の「しか」とは「このように」という意味で
「このように暮らしている」となるのですね。
てっきり「鹿が住んでる」・・だと思いました(><)
喜撰法師という方はもちろん私は知りませんでしたが
実際、宇治山の僧という以外経歴不明らしいです。
六歌仙の一人!
おお!今まで出てきた三十六歌仙より上な感じがする!
六歌仙は「古今和歌集」に記されているそうで
私も知ってる紀貫之さんが選んだのだそうです。
僧正遍照・在原業平・文屋康秀・喜撰法師・小野小町・大友黒主の六人。
百人一首は大友黒主以外が登場しています。
これから出てきますね^^
調べてみると紀貫之は、この六人を選んだくせに
結構ボロクソに批評してるのが面白かったです^^
彼にとっては柿本人麻呂と山部赤人が偉大な歌人だったのだって。
まあ全体の中ではこの六人がいい線いってるけど
偉大な二人に比べたらまだまだや!って感じだったのかな(*^_^*)
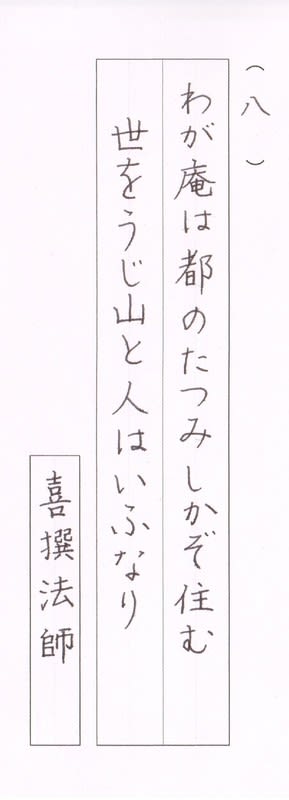
今回結構うまく書けた!!!
「うぢ山」だけ失敗したな~・・・
なんて思ってたのですが
意外と書けてないなぁ・・・(意外とって・・)
ひらがなが続くと特に中心が揃わないんですよねぇ・・・
どうしたらちゃんと揃うのかなぁ・・・・
練習あるのみ!ですね!!(≧▽≦)b
※って思ってたら「うぢ山」を間違って「うじ山」って書いてた!!
字の上手下手以前の問題でした・・・(><)
・・ちょっとはいいとこ書いてテンションアップしとこう!
「庵」はなかなかカッコよく書けてる気がします!
「都」と「住」もなかなかかな・・・
「人」は左払いをもっとシッカリ書いたほうがいいですね!
ひらがなは・・「わが」がいい!
どうも「つ」と「し」が苦手です・・・
単純な線なのに・・書いていつも「あちゃ-」てなる(*>ω<*)ゞ
それと「と」が中心ずれるんですよねぇ・・・
まだまだ問題山積です!!