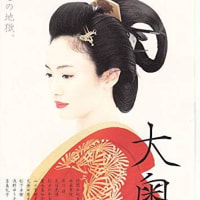この時期、お正月の準備として『鏡餅』を作るという方もいらっしゃると思います。我が家でも祖父母が健在であったころは、お餅をついて自家製の『鏡餅』を作っていました。
最近では既製品で間に合わせるようになりましたが、大勢で寄り集まって餅米を蒸かしたり、臼と杵でお餅をつく様はとても壮観だったという記憶があります。
『鏡餅』がいつから我が国に登場したかは定かではないものの、平安時代に紫式部によって書かれた「源氏物語」にはその存在が記載されています。
紫の上が姫君の歯固めの祝いをするシーンで「『鏡餅』を取り加え、新年の祝い言を交わして戯れ合っているところに源氏の君が現われる」という場面です。
ただし、当時は『鏡餅』を神棚や床の間などに供える習慣はありませんでした。現在のような形になったのは室町時代からで、武家では床の間に甲冑とともに『鏡餅』を飾ったといいます。
江戸時代になると民家では円形や菱瓢箪型の餅を供える習慣ができていました。そのころの『鏡餅』は現代のような「白」ではなく、黒米を用いた「黒い鏡餅」だったのです。
「餅といえば白いもの」というイメージがある現代人からすると違和感がありますが、江戸初期の庶民は日常的にも古代米のような黒米飯を食べていたので不自然ではなかったのですね。
--------------------------------------------------------------------