先日、里山の仲間と一緒に裏山の探索をしました。いつもの尾根沿いの道を沢に向かって降りていく途中、谷の向こう側からカモシカ君が私たちの方をじっと見ていました。「おーい、元気かい?」「かしこそうなカモシカだねぇ~」と口々に大きな声をかけて手を振ると、カモシカ君は首をブルブルと横に振って応えてくれました。褒められたので、ちょっとはずかしそうにしてました。「おーい、美味そうなカモシカだね、とって食べてしまうぞ~」と言うと、今度はプイと向こうの方を向いて知らん顔をして草を食べ始めました。ウッソーって言われそうですが、これ、本当の話なんです。しばらく、ワイワイ言いながら、観察していると、君たちとはこれ以上付き合っておれまっせんていう感じでゆっくりと森の中に消えました。
このあたりの里山は紅葉はまだもう少しです。ヌルデとウルシだけは早々と紅い化粧をし始めました。
リンドウとセンブリの花が咲いていました。
沢に降りてしばらく歩いたところで、船長さんがイワナを見つけて、なんと素手で捕まえてしまいました。もちろん、そっと逃がしてあげましたよ。



この羽は友人のYさんからのいただきもの。ヤマドリの尾羽。山を散策中に見つけたそうです。
ヤマドリは林道を車で移動しているときに6-7羽群がっているのに出会ったことがあってびっくりしたことがあります。
数年前に面白い経験をしました。ヒノキ植林地の枝打ち作業に行った時のことです。人気のない林道を隔てた向こう側の薮まじりの林の中から、チェンソーをかける時の音が短くブルンブルンと鳴っています。しかし、いつまでたっても、ブルンブルンと初爆ばかりでエンジンがかからないのです。下手なキコリさんだなぁ~、チョークを戻さないといけないのになーなんて考えていると、そのうちに音が止んでそれきりになりました。どうやらエンジンをかけるのをあきらめてしまったようです。何年かしてからこのエンジンをかける時のような音はヤマドリのホロウチ(母衣打)だとわかりました。野鳥図鑑によると母衣打という言葉はこの音を昔の人は「ほろほろ」と聞いたことに由来するといわれています。
雄が翼を激しく震わせて出す音で声音の分析から1秒間に14回羽を震わせているそうです。
雌の気を引くために鳴らすとか。
本年の7月ごろに裏山の森の入り口付近で、長さ22cmのちょっと大きめの羽を拾いました。持ち主はどんな鳥だろうと興味があったので持ち帰って、鳥の羽図鑑で調べると、なんとフクロウの羽でした。長さからすると初列風切羽のようです。片側11枚あるうちの1枚だと思われます。羽毛の表面は柔らかい毛が密生していてビロードのようです。
先日トチの実を拾いに近くの山に行ってきましたが、カケスの羽根が落ちていました。羽根がたくさん散乱していて、鷹にやられたのかもしれません。
野鳥の羽図鑑によると、上の写真は「次列風切」、下の写真は「大雨覆」だそうです。
青い色が階段状になっています。一つ一つの青の部分は白⇒濃紺のグラデーションになっていて実物は写真よりず~っときれいです。


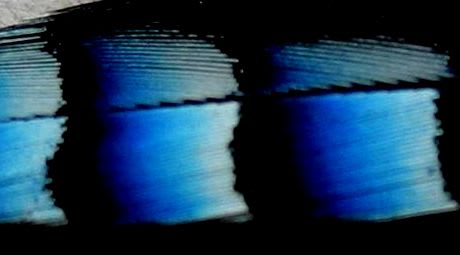
今日は暖かい一日。森で落ち葉の上で羽根を休めているヒメギフチョウの写真を撮ることができました。今まで、時々見かけることはありましたが、カメラをもっていなかったり、あまりにも飛翔が早すぎて撮る機会に恵まれませんでした。今日は午後から出かけたのが良かったと思います。どうも午前中のヒメギフチョウは活発ですが、午後は羽根を休めたり、吸蜜をしたりゆったり飛んでいるような気がします。カタクリもたくさん咲いていました。



森を散歩していたら、ルリボシカミキリを見つけた。よく見ると、カビにおかされていて
関節から白いものがふき出ている。でもまだ生きているらしく、わずかに長いヒゲを左右させている。飛ぼうとして鞘翅の下にある薄い羽根を拡げようとしているが、もうそんな力は残っていない。この昆虫にとって恐ろしいカビは天敵糸状菌Beauveriaという病原菌だ。感染するとこのカビ菌に徐々に水分を奪われて1-2週間で昆虫は100%死に至るという。
ボーベリア菌にはbassiana種、tenella種、brongniartii種などが知られていて、その一部は微生物農薬として製剤化されているというから驚きだ。
↓↓
(http://www.idemitsu.co.jp/agri/product/microbe/insecticide/vaiorisa.html)
特にbrongniartii種はカミキリムシ類にだけ効果があって、他の昆虫(例えば、ミツバチやカイコほか益虫)には感染しないという。これはイチジクや桑栽培農家にとって厄介なゴマダラカミキリやキボシカミキリの駆除に使われている。bassiana種はマツノザイセンチュウの媒介をするとされるマツノマダラカミキリにも効果があるという。
もう秋だというのに、遅めの夏キノコ、卵茸をたくさん見つけました。毎年いくつかは見つけますが、あちこちにたくさん生えているのは本年の気候のせいでしょうか? 森で見つけた時にはハッとする鮮やかさ、傘もスジ状の線がきれいですし、柄のだんだら模様もなんとも言えません。
んでこのキノコは観賞するだけでも素晴らしいのですが、ありがたく持って帰ることにします。
水を張ったボールにキノコを入れて、そこにトウガラシを入れて虫出しをします。おっと、トウガラシが無い!! そこで、黒コショウの粒をいれたら、なんと小さなキノコ虫がわやわや出てきました。











































