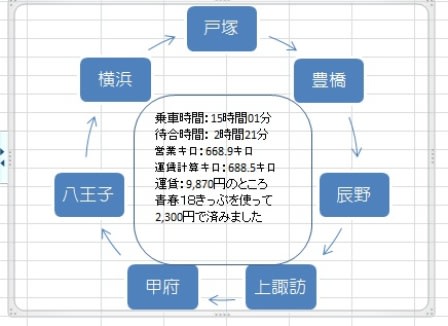老人会の旅行で行った富士五湖の一つ、
西湖のほとりにある癒しの里の水車を撮った。
駆け足の観光旅行ゆえ、見学時間は僅かであるが、
こんな素敵な施設があるとは知らなかった。
こんどはプライベートで訪れてみたい場所だ、
入場料が350円とは驚くべき安さだ。
私たちは団体割引だったので300円を支払った。
今から約50年前に土石流の災害で集落は
被災し、その後、復旧された過程でこのような
施設を作ったとのことで、施設で働いている
人たちは集落の住民らしい。
その人たちの接客態度が素晴らしく、
名前のとおり、まさしく癒されるような
感じの応対ぶりだった。