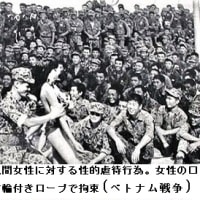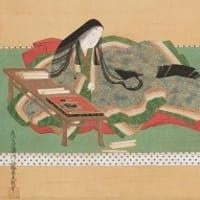源氏物語:宇治の橋姫 「橋姫」とは誰なのか
馬場あき子氏著作「日本の恋の歌」~貴公子たちの恋~
第三章 「古今集」の恋 からの抜粋簡略版 です。
狭筵(さむしろ)に衣片敷きこよいもや我を待つらむ宇治の橋姫
(わびしい狭筵の臥床(がしょう)にその衣を脱ぎ敷いて、今宵また私のことを待っているだろうよ、宇治の橋姫は)
本来は水神信仰に根差す橋姫だったともいわれる。宇治橋の近くには今も橋姫神社があるが、安産の神になっていてびっくりする。
「奥義抄」ではこの歌に対して、「橋姫の物語」という伝説を紹介している。それによれば、「二人の妻をもった男の元の妻の方が妊娠していて、七色の若布(わかめ)を食べたがったので海に採りにゆき、龍神の婿に取られて帰れなくなった。妻が海辺に訪ねてゆくと、夫がこの歌をうたいながら来て、一夜を明かした。妻は泣く泣く家に帰り、もう一人の妻にこのことを語ると、この妻も海辺に行ってみた。元の妻が言ったとおり、この歌をうたいつつ夫がやってきたが、妻は錯覚して、元の妻の方を男が愛していると思い、嫉妬して男につかみかかると、「をとこもいへも雪などのきゆるごとくにうせにけり」という結末である」
また顕昭の著の「袖仲抄(しゅうちゅうしょう)」には「姫大明神とて、宇治の橋下におはする神を申すにや」としている。橋の下に坐(いま)す橋神は、水神であるとともに地域の境を守る神であることが多いが、宇治の橋姫には通う男神があるところから、しだいに「待つ女」のイメージが生まれ、さまざまな比喩の場が開ける。
この歌の「宇治の橋姫」は「こよいもや」によって、通い慣れた女のもとを思いやっている歌だが、「狭筵(さむしろ)に衣片敷き」という、人待つ女の姿態のさびしさが具象的である上、「狭筵(さむしろ)」と「橋姫」のイメージが結びつくことによって、粗末な恋の床にある孤独な心のかたちが印象される。この歌では「我を待つらむ」とうたったあとに、そこに行こうとしたのか、行けないことを悲しんだのかは読者の空想にまかされている。
参考 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
橋姫は橋の守護神で、その名は古くから知られ、とくに宇治の橋姫の伝説は有名。『古今和歌集』に「さむしろに衣かたしき今宵もや我をまつらむ宇治の橋姫」の歌がみえ、当時橋姫にまつわる民間伝承のあったことがうかがえるが、その具体的な内容は明らかでない。『山城(やましろ)名跡志』所収の「古今為家(ためいえ)抄」には、宇治川のあたりに夫婦が住んでいたが、あるとき夫が竜宮へ宝をとりに行ったまま帰らなかった。妻は恋い悲しんで橋のほとりで死に、橋守明神になったと記している。
女性に対して嫉妬深いと語られるのが通例で、『奥儀抄』には、昔、妻を2人もつ男がいた。その1人が宇治の橋姫で、出産が近づいて和布(わかめ)を欲しがるので、夫がこれをとりに行き、竜王に捕らわれた。夫を捜しに出た橋姫は、浜辺の庵(いおり)で再会するが、夜明けに夫の姿が消える。もう1人の妻がこれを聞いて尋ねるが、夫が橋姫の歌をうたっているのを聞いてねたみ、夫にとりかかると、たちまち男も家も失せてしまったとあり、2人の女性の嫉妬による緊張感が描かれている。
橋姫の嫉妬に触れるのを恐れて、嫁入り行列が橋を避けて通る土地も各地にあった。山梨県西山梨郡(現甲府市)の国玉(くだま)の大橋では、橋の上で猿橋の話をすると怪異があるという。境を守る神として、道祖神との関係も深く、元来は男女二神の神で、橋の傍らに祀(まつ)られていたものと考えられる。
[野村純一氏]