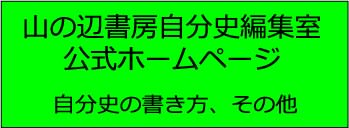★9月13日、自分史のブログ★
編集室より
★昨日までのAmazon電子書籍無料キャンペーン「平成の大洪水」ですが、多くの皆様にダウンロード購読頂き誠にありがとうございました。
「参考になった」「全て我が事として心の準備をしておく大切さを教えられた」「被災者の心構え、行動が参考になりました」など、感想メールを頂戴しましたことお礼申し上げます。
改めてノンフィクション・実話手記の重要性を認識した次第です。
――――――――――――――――――――――――――
★扠、自分史の作り方ご案内にもどります。本日は連載第9回目です。
連載第九回
時代が変わっても変わらないもの――人間の心
●感想文のなかの『こまやかな感情表現』『主人公の赤裸々さ』などは書き手が主人公を詳細に取材し同時に容赦なく丸裸にして書いたからだろうか?。
このように、自伝というからには書く本人の相当な覚悟が要る。覚悟といえば大げさだが、ただ真実と素直さで何の気負いもなく書けばいいのである。そうすれば必ず読み手に伝わるものだ。とりたてて屁理屈を並べる必要など何処にもない。あらためていうが、自伝・自分史は純文学如何を競うものではないこと。
わたしが実践している「文章描画法」であるが、難解なところなど一つもないといっている。そのかわり、最も大切なことは、くどいようだが真実を書くこと。
●情景描写は余分な形容など省略し短く書けばよい。肝心なのは、会話文である。前述の「夜の光」の如く、この会話にあらゆる情報が含まれている。時系列構成場面…そのなかで繰り広げられる会話の数々。これらは何の誇張もエエ恰好もない赤裸々な会話文であることが成功への鍵となる。
●この書き方について今一つピンとこない方は戯曲を見ていただきたい。例えば、文豪、菊池寛さんの「父帰る」など。わたしの「文章描画法」は或意味では自伝の戯曲バージョンでもあるのだ。
さて、自伝の画期的表現「文章描画法」については、このあたりで説明終了として、次に、初めて自伝・自費出版にチャレンジする方を対象に、自分史全盛期に制作頒布した「自費出版のための書き方ガイド」から主なところを抜粋して次に掲げる。
●これは、古い話で、一九八五年初版、一九九〇年第三刷として世に出したもの。沢山の人に読んで貰った。何故か教員OBの方々に人気があったのを覚えている。同時に勉強会も実施した。
●このガイドの内容は、描画法を考えるずっと前のことなので、通常といえば変ないい方であるが、自分史という言葉が世にデビューして間もない頃の常識的な記述方法である。
しかし、書くという基本には変わりがない。それで、原文のまま掲載する。少しでも参考になれば幸甚である。
時代の変遷とともに暮らす人間も変わる。当たり前のことだが、そのなかに「人間の真実」がある。
これ無くしては、いくら人工知能が発達しても害こそあれ益にはならない。
【復刻版】
「自費出版のための書き方ガイド」
★ようこそ……自分史の森へ
◇はじめに
● 用意するもの

A. 四百字詰原稿用紙(一冊50枚綴りのものが良い。又は、チラシなどの空白部分を活用してもよい)
B. 筆記具(文字がはっきり読み取れるものなら何でもよい)
C. 辞書
D. 横に細長い巻紙(人生年表を作成する為のもので、障子紙などが適している)
E. 信念(何がなんでも、最後まで書きつづけるんだという不動の心得)
●以上五つをご用意いただく。このうち、A.~D.は「物」ですから楽にそろえることができます。だが、E.の信念となると何処の文具店でも売っていない。非売品である。従って、筆者自らの力でつくり出し、用意しなければならぬ。これが、個々人に確実に用意されると、すでに目的の九割は達成されたといっても過言ではない。
●最初、書き始めてしばらくは気負っているので何とかガンバル。そのうち、なれないこともあって段々息切れが起こる。行き詰っってしまい、放り出したくなる。幾度か「もう、や~めた」と思う。そんなときは、今まで書いてきた内容がなんともつまらないように思えてくる。それで、益々イヤになってくる。結果、本当にやめよう、と考える。
せっかく一大決心しスタートをきったのだから、途中で放り出すのは実にもったいない。
「必ず完結するぞ。オレの一世一代の大事業だ。必ず本にしてみせる!」
こういう信念が是非とも必要となる。

●では、この不動の信念をどのようにして養うか……。
一つの方法として、
「絶えず、書き上げた時の喜び、本になったときの感動」
これらを頭に描きながら書きつづける。これが大きなはげみとなる。

●ものを書く、というのは、精神を主体とした特殊な知的作業であり、頭に浮かんだ事象を整然と組立て、それを、一定の約束事にそって、文字として一字一字原稿用紙のマス目に書き込むという非常に根気、忍耐を必要とする仕事である。

つづく
山の辺書房自分史編集室ホームページ http://web1.kcn.jp/y-pub
★山の辺書房自分史編集室発行、Amazon電子書籍のご案内
 |
改訂版 平成の大洪水: 未曾有の水害で生まれ故郷を無くした被災者の赤裸々な手記 |
| 杉岡 昇 | |
| 山の辺書房自分史編集室 |
 |
改訂版 膀胱がん闘病記: 人生ポジティブに生きよう |
| 杉岡 昇,よしい ふみと | |
| 山の辺書房 |
 |
大台ヶ原 妖怪伝説 |
| 向井 靖子,よしいふみと | |
| 山の辺書房 |
 |
癒しの山 大台ヶ原 : 開山行者の生涯 |
| 向井 靖子 | |
| 山の辺書房 |
 |
熊野の里山今昔噺: 紀州一揆 慶長一揆 その後 |
| 向井 靖子,よしい ふみと | |
| メーカー情報なし |
 |
悪魔の手引き: 短編小説 |
| 向井 靖子 | |
| 山の辺書房 |
 |
ど根性: 昭和繁盛記 (実話物語) |
| 下川殖久,向井靖徳 | |
| 山の辺書房 |
 |
まだ人間だった頃の脚本: シナリオの原点 |
| よしい ふみと | |
| 山の辺書房自分史編集室 |
 |
Kindle for PC (Windows) [ダウンロード] |
| Amazon.com Int'l Sales, Inc. | |
| Amazon.com Int'l Sales, Inc. |
★タブレットでお読みになる場合は下記の何れかで……
 |
Kindle Paperwhite 防水機能搭載 Wi-Fi 8GB 電子書籍リーダー |
| Amazon | |
| Amazon |
 |
Kindle (Newモデル) フロントライト搭載 Wi-Fi 4GB ブラック 広告つき 電子書籍リーダー |
| Amazon | |
| Amazon |
 |
Fire HD 10 タブレット (10インチHDディスプレイ) 32GB - Alexa搭載 |
| Amazon | |
| Amazon |