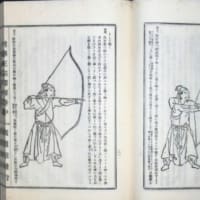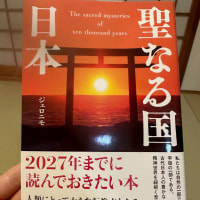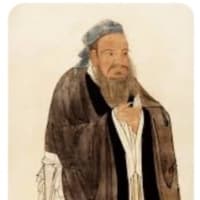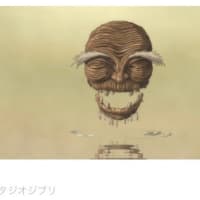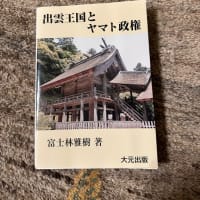榛名神社の御祭神の一柱はハニヤス神です。榛名神社参拝記については、また後日に。
埴安神(埴山姫命・埴山彦)のハニは赤土を表す古語であり、 古墳の副葬品にある埴輪 の「ハニ」です。赤土は太古神聖視された丹土のことです。
鳥居⛩️の朱は魔除けですが、神社の創建以前は、鳥居はなく神域は磐座や山などに祈りを捧げていました。だから、赤土は日本の神社を示す鳥居⛩️文化を一つ作ったようにも思演出ます。
赤土のハニは波爾とも書き、瀬織津姫や豊玉姫など水の女神に縁深い和邇(ワニ)氏と実は関係がありました。
神功皇后の子、応神天皇が和邇(ワニ)氏の娘、矢河枝比売(🟰菟道稚郎子の母にあたる御方)との婚礼時に詠まれたという歌に、ワニが赤土として出てきます。
「櫟井の和邇(ワニ)坂の土(に)を、初土は肌赤らけみ、しは土は丹黒きゆえ、三栗の、その中つ土を、かぶつく、真ひには当てず、眉書き、濃に書き垂れ、遇わしし女人、かもがと、我が見し子ら、かくもがと、我が見し子に、うたたけだに、向かいおるかも、い添いおるかも」
簡単にいうと、応神天皇は「こういう美しい女が欲しいと常々思っていた」という内容で、和邇氏の娘、矢河姫に惚れましたという恋歌です。
この歌にある、ワニの土(赤土🟰初めに掘った土?)や、しは土(丹黒い土🟰底の土)は、元々は魔除けに使われていたようで、人も化粧や入れ墨などに使用していたようです。ワニ氏の娘、矢河姫も使っていたのかもです。
魏志倭人伝の記述にも、倭人は入れ墨をしていたことが記されており、弥生時代には、「黥面文身(げいめんぶんしん)」という入れ墨の風俗がありました。

しかしながら、ある時から入れ墨は野蛮人がするものだと駆逐され差別されはじめます。
同様に、祭祀に使われていた銅鐸も鉄器を作るタタラ製法の到来によってなのか?姿を消します。鈴なりに鉄の生成を祈る銅鐸も、タタラで大量に作れるようになったら要らなくなったのかもですね。
これらの劇的な変化は、具体的な記録が無いの空白の古墳時代(3ー5世紀あたり)あたりにおこります。魏志倭人伝には、「倭国には牛や馬はいない」と書かれていますが、古墳には、馬具や甲冑が沢山出ています。

大陸から鉄の生成方法たたらと共に馬ももたらされ、生活が大きく変化したのが弥生→古墳時代なのかなと考えます。
祭祀に使われていた、銅鐸や銅剣は、弥生末から古墳時代にかけて戦いに使われる鉄剣へと姿をかえたのかもです。
馬と鉄剣は強いもの勝ちの時代の到来を表しているのかもしれません。
ハニヤス神は土の神様。農業の神様でもあります。土偶は縄文時代の土製の人形です。 女の人の形をしているとか言われています。

埴輪は、古墳時代の副葬品。素焼きの土器で,人,家,動物、刀の形などをしています。

イザナギとイザナミによる神産みにより様々な自然物の神々を誕生させる過程で、イザナミは火の神を生む際に大火傷をしてしまい、死に至ります。
イザナミはその死の間際の苦しみのなか、吐瀉物からは鉱山の神カナヤマヒコ、大便からは土の神ハニヤス、小便からは水の神ミヅハノメを生みます。
この神話の暗喩、火の神の出産を「タタラの到来」と考えると、それにより、砂鉄を得るため鉱山(カナヤマヒコ)が切り崩され、土砂崩れが起き(ハニヤス)や洪水(ミヅハノメ)がおき、イザナミ(大地の母、自然)が命尽きたと置き換えられる気がしました。
自然に祈り、祭祀をし、精神に重きをおく社会から、物質至上主義社会へ変わったことや、
また、祭祀をしていた女性が虐げられ男性優位社会に変わり、また、都合の悪いことは隠蔽され強いもの勝ちの社会へ変わっていったことも暗示しているのかも、、です。
少し妄想膨らみすぎました。。
神話は深くて面白いですね。今日はこのへんで😅👋