月曜日、振替で茶道の社中稽古に出席した。
前の週も月曜クラスに参加して、「次は行台子ネ

」と云われ、
しかも前の晩に先輩から「点前するのは二人だけ」と連絡

をもらった。
(つまり、先輩とワタシだけで、他は膝がダメだから見学のみと)
なので、ノートを見直して予習して、でも念のために灰匙セットも持参。
到着したら、唐銅の風炉の灰形が出来てないということで、急きょ円草に

そうだわなぁ

1週間前、唐銅の風炉に釜を懸けて稽古されていたから、
ワタシは九寸の土風炉と眉風炉の灰形を作った。
土曜日は稽古なかったから、金曜日に誰かが唐銅の灰形を作らないと、
月曜日は唐銅の風炉は使えないよなぁ

とは、心配していた。
やはり

灰形を作るには30分かかるからと、行台子は諦めて円草の準備。
(後からいらした先輩はも「えっ

円草の予習してないよ

)
まぁ、なんとかなるっしょ

ということで、稽古がスタート。
まずは炭手前をさせていただいた。
初炭をさせていただこうと思ったら、
姉弟子さん方が「それじゃ、つまんない

」
で、盆香合をさせていただいた。
座る位置が後ろになってしまって、ちょっと腰がひき気味。
(座ってから前へズリズリ

)
考えてみれば、この灰形は自分が作ったんだよなー

(金曜の方が使われているとはいえ

)
余裕で入ることが確認できて、ホッ

としていると、
先生が「五徳が高すぎる

」
筒釜だから羽落ちは風炉の上ラインより下がらないといけない

と。
(云われてみれば、こっちは釜合わせはせずに作ってた)
続いて、先輩が円草の点前。
予習してない分だけ不利ではあったけれど、所作は堂々として決まるのよねぇ。
見学している分には、なんとなく「そこは○○ではないでしょーか」と言える。
かと云って、自分の番になると完璧に出来るワケではなく~

ワタシも先輩が出来たところで、ぽかっと抜け落ちたりして

行台子の稽古は今シーズン出来なくなった分、円草は土曜日でもう1回可能性があるので、
もし、点前の稽古が出来たら、その時はガンバロっと

お昼ごはんのデザートが100%本蕨を使った蕨餅を御馳走になった。
姉弟子さんが差し入れてくださった。
葛粉の蕨餅と全然違う舌触り。滑らかで弾力がなくて軟らかい。
ちょっと、感動もの。
稽古の後は一人だけ居残って、唐銅の灰形を作らせていただいた。
今週末の土曜稽古は行台子をやる予定だ。
ワタシは欠席だけど、相弟子さんと行台子デビューをする若手さんのために、
せめて灰形だけは土曜クラス所属のワタシが作りたい

と思って。
(釜合わせも一応、した)

作っている時は見えなかったけど、写真撮ったら右向こうが曲がってるゼ

慌てて、ピンポイントで修正。

誰もいないのをよいことに、先週作った分の“使用後”もチェック撮影。
九寸の土風炉(使用前→使用後)

↓

眉風炉(使用前→使用後)

↓

なんか、壁切りのラインがシャープになっているような気がして。
自分ではシャープには切れてないという自覚はあるので、
「もしかして、金曜の姉弟子さんが作り直した?」という疑念(?)が

下手くそだから「こんなの、使いたくない

」と思われても仕方ないんだけど

化粧灰の撒き方が独特なので(←灰形教室で教わった巻き方)、容易に確認できる。
使用前と使用後の写真を見比べてみると、九寸の土風炉はそのまま使っていただいたみたい

眉風炉はたぶん、壁切りのトコだけ直されてる。(こんなに真っ直ぐに切れなかったもの)
化粧灰も撒かなかったけど、撒いてあった。(ワタシはこういう塊では撒かないし)
ま、しゃーないわね

先生の体調はよくないし、もう自ら灰形を作る状態ではないから、
弟子の誰かが作らないとならない。
社中の中で灰形を作れるのは自分を含めて2人か3人だけ。
いい機会だと思って、後半(8月~10月)も作らせていただこう

ちなみに、今月の社中稽古はこれで終わり。
次は8月下旬。
なんか、1学期の終業式が終わった気分。
淋しいというよりは、ホッとしている。
だって、暑くて通うのもしんどいから、単純に夏休みはウレシイ。
それに、“夏休み”でも灰形教室と湿し灰作り教室という夏期講習もあるしねー


にほんブログ村 
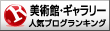 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
応援ヨロシク

致しマス

















 なので。
なので。
 立ち上げる気になれず、
立ち上げる気になれず、 から更新しようとしたら爆睡
から更新しようとしたら爆睡 しちゃった
しちゃった からの更新になっちゃった。
からの更新になっちゃった。
 致しマス
致しマス


 」と質問された。
」と質問された。 」
」


 」
」



 のねぇ
のねぇ


 )
)
 に目を通した上で、「この道具の位置はね~」と説明してくださる。
に目を通した上で、「この道具の位置はね~」と説明してくださる。 」と思って買った。
」と思って買った。 と思った。
と思った。
 」
」
 と心配しながら、初炭手前を見守る。
と心配しながら、初炭手前を見守る。 」と注意を受けた。
」と注意を受けた。 」。
」。

 が降る中を通院に寄り、上がった後の蒸し暑い中を歩いて汗ぐっしょり
が降る中を通院に寄り、上がった後の蒸し暑い中を歩いて汗ぐっしょり くらいのつもりで、
くらいのつもりで、 って。
って。 になっちゃったけど
になっちゃったけど
 )
) 」と仰る。
」と仰る。 という意欲がそこから感じられた。
という意欲がそこから感じられた。
 をもらった。
をもらった。 円草の予習してないよ
円草の予習してないよ 」
」











 で鍛えられたこともあり、
で鍛えられたこともあり、
 )
)






