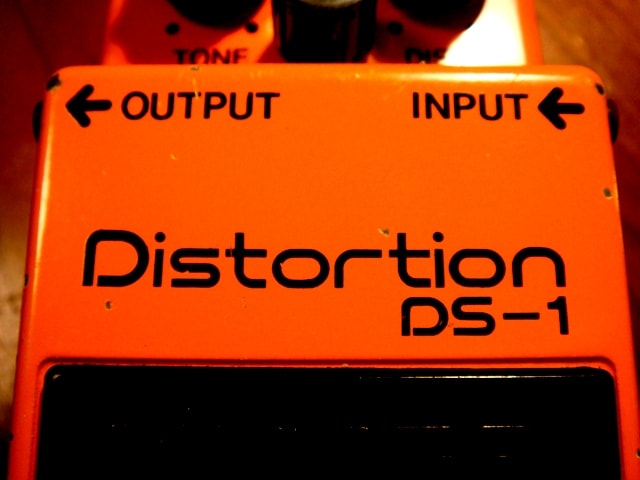80年代はワウペダル不遇の時代でしたが90年代になってVOXブランドのV-847がリイッシュされ瞬く間にワウはギタリストの足元に定番となりました。80年代後半にはブルースブームの再燃が始まりそれも追い風になり各社リリースラッシュとなった次第です。
ワウペダルもここ10年はモディファイ・改造の定番アイテムになり自作マニアはこぞってネタにし、トゥルーバイパスなる言葉をメジャーにしました。
そんな中、本家VOXから97年頃にオールシルバーボディーのV847SPが発売されます。外見は派手だが中身は定番V847と同じで音も同じ。今はハンドワイヤードシリーズまで出る始末ですがこの頃はまだ外見のチューンのみ。
実際には90年にリイッシュされたオリジナルV847を使い続けポット、パーツなどを取り替えながら20年以上使用してきましたがこのV847SPで当時のオリジナルを味わうことが可能になりました。変に着色しないオリジナルワウサウンド。音やせはお約束で実にファンキーな質感だ。クリーンでのトレブルの耳に痛い感じは心地よく「これぞワウ」という感じ。あまり手を加えたくないがポットギアを痛い部分から数段変えるだけで太いメローなブラックワウに変貌する。結局、基板やSWまで変えても元に戻した経験上、オリジナルが一番ということになりハイエンドワウはいまひとつ馴染まない。
結局のところワウ自体に求めるのが70年代の王道サウンドだから仕方ありません。ヘンドリックスの時代にはトゥルーバイパスなんていう言葉も無かったわけですから。
ポットにガリが出てくれば交換するくらいでしょうが、そのときにいろいろなポットや配線材に交換するのもちょっとしたお洒落を味わうことになりますね。
しかし、このシルバーワウはいつも磨いていないとならないのでライブ向きではないかも・・・。