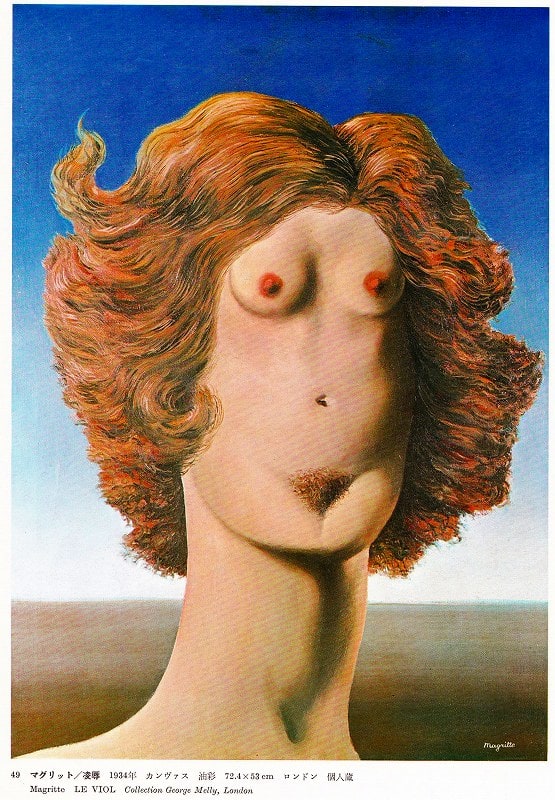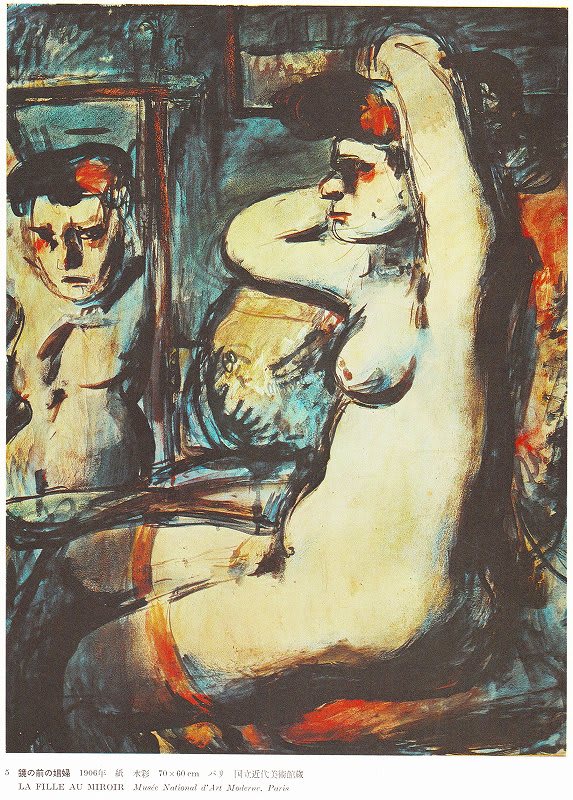(御殿山ヒルズにて)
ニッポン放送に続き再び新株予約権発行差止め
6月1日、東京地裁は、ニレコの取締役会が3月14日になした決議に基づいて現に手続き中の新株予約権の発行を仮に差止める決定を下した。これも先のニッポン放送の場合と類似した会社の現経営陣の取締役達が、自己の地位保身を主たる目的として、取締役会で新株予約権の発行を決議したことについて、裁判所がその発行を差止めた第二の事例として注目される。再びこのような事例に、東京地裁の良識が示された点、当然のことながら諸手を挙げて賛意を表したい。
今回のニレコの事例も、やはりもっぱら現経営陣の取締役達の自己保身を図った取締役会の私物化利用による新株予約権の発行の著しい濫用である点において、先のニッポン放送の場合と同じであるが、ただ違う点は、先のニッポン放送の場合は、現にライブドアの買占めが発生したのを知って、これに対抗して、慌てて泥縄式に取締役会の権限を濫用し、なりふり構わず大量の新株予約権を現在の株主を無視して、フジテレビに第三者割当て発行したのに対し、今回のニレコの場合は、現在は全く会社の経営支配権に争いが生じていない場面において、将来万一、会社の株式の敵対的買占めによって経営支配権を争う株主が出現し、現在の取締役の地位が脅かされることにならないとはいえないことを懸念し、あらかじめそういう事態を想定して、取締役会の決議により、現在の株主に対し、1対2の割合で新株予約権を無償で発行し、将来もし、誰かが、20%以上の株式を保有する事態が発生した暁には、その新株予約権を有する現在の株主は、1株につき1円の払込価額をもって、その新株予約権を行使できるものとした点においてやや異なるところがあるにしても、しかし、これも、まさに明らかに現取締役の地位保身を主たる目的とした事前の買占め対抗策であることには変わりはない。
したがって、将来、このニレコの新株予約権が全部行使された暁には、この新株予約権の割り当て基準日である平成17年3月31日以降(正確には権利落日である同月28日以降)に、ニレコの株式を取得した一般株主も買占株主もいずれも、持株比率が一挙に約3分の1までに希釈されるという大な不利益を蒙ることになるわけである。こうした買占株主に対する将来に予想される絶大な阻止効果は、ニッポン放送の場合と何ら異なるところはない。
東京地裁は、この今回のニレコの新株予約権発行差止仮処分命令申立に対して、本件新株予約権は、その発行について株主総会の意思を反映させる仕組みとして欠けるところがないとはいえず、また、新株予約権の行使条件の成就に関する取締役会の恣意的判断の防止が担保される仕組みとなっているとまではいえないし、さらに、その発行により買収とは無関係の株主に不測の損害を与えるものでないということはできないと認定した上で、次のように述べている。
「会社支配権の争奪は、不適任な経営者を排除し、合理的な企業経営を可能とするという側面も有しており、一概に否定されるべきものではないし、仮に好ましくない者が株主となることを阻止する必要があるというのであれば、定款に株式譲渡制限を設けることによってこれを達成することができるのであり、このような制限を設けずに株式を公開した以上、支配権の争奪が起こり得ることは当然甘受すべきものである。そもそも、不適切な敵対的買収を防止するためには、収益性を改善し、株主を重視した経営を行うなど、真摯な経営努力により企業価値を高めることが重要であり、安易に新株予約権を利用した事前の対抗策を講じることは、かえって企業価値を損なうおそれすらあろう」
定款に株式譲渡制限を設けていない一切の株式会社(
会社法案では、「公開会社」と呼ぶことにした-2条5号)は、その株式が証券取引所に上場されていると否とを問わず、誰でも、何時でも、何株でも、自由に買うことも、売ることもできることが法律(現在では、商法、目下衆議院を通過し参議院で審議中であるが、予定どおり今国会で成立すれば、会社法)で強く保証されていることは、今更いうまでもないところである。そして、そういう時々刻々変動し、固定していないその時々の株主が、株主総会の多数決で、欠格事由のない者である限り、自由に、適任と考えた者を取締役に選任して、日常の業務執行を委任するが、当然、もし適任でないことが株主に判明した場合には、たとい任期中であろうとも、何時でも、理由なく、再び株主総会で解任することができることになっており、したがって、取締役はその時々の株主の多数の意思により、かつ、その時々の株主の多数の意思のみによって自由に選任、解任される仕組みとなっていることが、株式会社の制度の大きな特色の一つであることも言うまでもないところである。
したがって、こういう公開会社においては、取締役が、逆に、あつかましくも、その選任母体である株主の適否について、もっぱら自己の地位保身の目的をもって、取締役会の決議を利用し、何らかの影響を及ぼす措置を講ずることは、たといそれが一見取締役会の権限内の決議事項であるように見えても、原則としてすべて本質的に違法とされなければならないわけである。このような基本的な視座から、今回のニレコの事例のような事前買占対抗策の適否が、検討されなければならず、このニレコの事例は、今後に影響を及ぼす大変参考となるものがあると言える。
(この東京地裁の発行差止めの仮処分決定を不服として申し立てていた保全抗告について、東京高裁は、6月15日、抗告を認めず、東京地裁の仮処分を支持する決定を出した。これを受け、ニレコは、最高裁への特別抗告を断念し、16日から予定していた予約権発行の中止を決めた-6月16日、毎日新聞)。