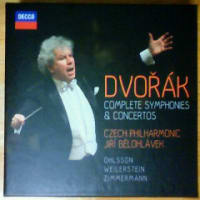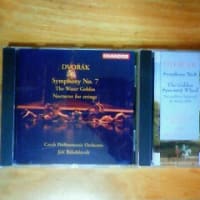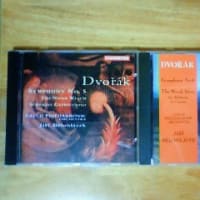神戸市立博物館で開催中(~12/7)の、「コロー 光と追憶の変奏曲」展を見て来ました。
この展覧会は、19世紀の前期から後半にかけて活躍し、後世の画家達にも多くの影響を与えたコローの作品約90点と、他の画家の作品を含め計約110点で、コローの画業を全般にわたりふりかえる内容となっています。
企画にはルーヴル美術館が全面協力し、ルーヴルからは30数点の作品が出品されています。
全体は6つの章に分けられ、初期から順に晩年までのコローの画業のあゆみと、それが後世の画家達に与えた影響を、実際に作品で確かめる事が出来ます。
以下長文ですが、感想をまとめてみました。
展覧会は、師のベルタン、ミシャロンの作品と、コローの初期作品の展示から始まります。
ベルタンやミシャロンの描き方は、外光の効果を生かす意図はありますが、この時代の普遍的な描き方にとどまっています。
当時、時代は17世紀から続いていたロココ文化の影響を少し残しつつ、産業革命やそれに伴う富裕な市民の台頭等、近代化の流れが強くなる中で、美術でも徐々に新しい表現を目指す動きが芽生えようとしていましたが、主流は依然として保守的・伝統的な描き方を維持しようとする勢力でした。
あくまで写実的な描き方、歴史画的な美しく風格ある仕上げ等、そうした観点でモチーフ・題材の選択や描き方にも当時はかなり制約があり、少しでも逸脱したものは、当時の画家が評価を得る代表的な場のサロンでは評価されませんでした。
コローは、遠近法の効果に、光が情景にもたらすさまざまな影響・効果をからめて、落ち着いて静かなたたずまいの古典的な情緒を残しながら、絵の中に多彩な表情があり見飽きる事のない、充実した描き方を実現しています。
コローの作品の中で特徴的であり、作品の性格にも大きな影響を与えているモチーフに、木の描写があります。
1820~1840年代といったかなり初期の段階から、流暢にしなやかに幹や枝は描き、葉は絵の具を薄くぼかして塗るのと筆のタッチを生かして点描風に描くのを巧みに組み合わせて描く、コローの典型的な木の描き方が見られます。
こうした、ぼかしを効果的に使って絵を演出するやり方は、コローの作品では後期に向かうほど、画中の全体にわたって駆使され、幻想的で優美な世界を描き出す事に成功しています。
しかし、こうした新しさを感じる描き方も、完全な独創から生まれたものではないと私は思います。なぜなら、コローに先立つ事数十年前、ロココの時代のフランスの、フラゴナールやヴァトーといった、ロココの代表的画家達も、作品全体の雰囲気は貴族趣味の強い前時代的な感じですが、絵の背景の風景等を、空気遠近法という以上にぼかしを駆使して描いている例が結構あるのです。ロココの貴族的な題材選択に加え、その描き方により、絵に夢見る様な優雅さがさらに強く加わる事になっています。
コローは、こうした前の時代の作品の特徴も、作品をたくさん見て、模写したり研究する事で、しっかりその長所をつかみ、それに自分の時代の新しい感覚をうまくミックスして、当世風の新しい優雅さの表現を模索し、提案したのだと思います。
私はコローの絵はもう30年近く見てきていますが、それでも今回新しい発見がありました。
彼が風景画で画中に人物を描く際、特に女性の場合、スカーフや衣服の色として、だいたい赤い色をワンポイント入れているのです。
風景画の場合、大抵は緑系の色が多い中で、この赤の小さなワンポイントがある訳で、これは補色の関係であり、色のコントラストの選択としては最も力強いものです。
これ位の時代の風景画の場合、人物は木々や建物と対置して描かれる事が多いのですが、コローの風景画の場合、人物の中にこの「赤いワンポイント」が加わる事で、人物の描写に強くなりすぎないが一定の主張が加わり、それが絵全体の構成やバランスを支える、控え目ながら結構重要なポイントとなっています。
なお展覧会では、初期や中期の作品の展示の中にも、晩年の作品が数点混ぜて展示してあり、年代に注目すれば、異なる時代の作品を見比べる事ができます。
後世の画家の作品としては、ドニやセザンヌ、ピサロ、モネ、シニャック、ドラン、ブラック、モンドリアン等といった、かなり多彩な顔ぶれの作品が展示されていました。
ドニの場合、コローと同じローマの景色を描いても、木々はまるで図案化した様な描き方で、全体の構図でも水平に広がる色の面の組み合わせによる画面の組み立てを強く意識させられます。
ドランの場合は、彼は20世紀初頭には過激な色使いと激しいタッチでフォーウ゛ィスムの一翼を担ったほどだったのですが、1920年代半ば頃からは一転、古典的な作風に変わっていきます。その転換の際、構図やモチーフの整え方として、コローの作品がかなり参考となり、激情的だったドランの描き方に落ち着きを与える事になったのがよくわかります。
また風景画の場合、コローの構図には、画面の中心に手前から奥に向かう道が描かれたものが多く、それも道がカーブして画面の左手に消えていっているように描いたものが多いですが、こうした描き方は実はセザンヌもよく描いています。
展示でも、よく似た構図のコローの作品と、セザンヌの作品を並べて、それがわかるように展示してありました。
他にもセザンヌの場合、前景に画面の端に枝を大きく伸ばす木を配して、それ越しに中景・遠景が見える様な描き方の風景画があります。
そうしたものは日本の浮世絵の構図との関連がよく言われていますが、今回の展示では実はコローも後期の作品の中でそうした描き方をよく用いていた事が紹介されています。セザンヌはこうしたコローの描き方をも参考にして、自作の充実と探求に役立てていた様です。
他にも、コローのぼかしや点描的タッチで描かれた木々の表現や、そうした木々が風景の中でカーテンの様に広がる事でもたらされる効果を、ピサロやモネ等次の世代の画家は、時々刻々と変わる光の表情とそれが情景に与える効果を逃さず描き出す為に各人なりのタッチや色彩の工夫を加えて新しい形で生かしている事も、展示を通じて理解できる事です。
初期・中期と、落ち着いていながら比較的色彩は豊かだったコローの絵は、1850年代後半以降、今回の展覧会でも言われている様に、全体的に灰色や茶褐色が目立つ様になります。
それが、コロー独特のタッチとも相まって、更に作品に幻想的な魅力を強めることになったのですが、後期の作品の場合、特に人物画においては、人物の衣装に赤や青、白といった、割と目立つ色が使われています。
これは前述した、風景画における人物を描き入れる際の「赤のワンポイント」と似ていますが、人物画のモデルの衣装の色なので色の面としてはある程度の大きさがあり、風景画の場合より一層強い効果・主張があるように思います。
コローの後期の人物画は、「真珠の少女」に代表される様な落ち着いた色合いが魅力の様に言われる事が多い印象がありましたが、実は画中には意外とこの様に鮮やかな色使いがなされており、この鮮やかな色を使うポイントをコローがよく心得て演出をしている事もあって、多くの人に強い魅力的印象を残しているのではないか、と感じました。
後期の作品では、実景の描写だけでなく、以前行った土地の景色の印象からヒントを得て、実景にこだわらず描いた作品も多く存在します。
コローは、実景を野外等でしっかりスケッチで描いたり油彩である程度まで描きましたが、最後の仕上げはほとんどアトリエで行い、アトリエで「推敲」の様な検討をして仕上げる事を大変大事にしていました。展示の説明文にも、作品ごとにその様な過程がわかる内容が簡潔に書かれています。
かつて訪れた場所の印象からイメージを展開して描かれた作品は、こうしたアトリエでの検討を更に発展させたものです。こうした描き方はやがて、自分が思い描いたイメージを基本に描くやり方(象徴主義等)の登場の下地にもなりました。
以上、大変長文になりましたが、今回のコロー展を見て感じた事をまとめさせて頂きました。
展覧会を見る前は、そんなにたくさんの感想は思いつかないのでは…と思っていたのですが、展覧会を見ると、コローがいかに自分の時代の前後の世代と強くつながり、また後進の画家たちの多くに強く影響したかが、実際の作品で確認・発見できたので、非常に多くの感想を抱くに至りました。
また私は約30年前にバルビゾン派の展覧会を見たのが、きちんと展覧会を見た最初でした。
今回の展示でも30年ぶりに見る作品が少しあり、約30年間の私の美術との関わりのあゆみと、その間の見方・考え方の変化・多様化を振り返って、感慨深く感じました。
この展覧会は、19世紀の前期から後半にかけて活躍し、後世の画家達にも多くの影響を与えたコローの作品約90点と、他の画家の作品を含め計約110点で、コローの画業を全般にわたりふりかえる内容となっています。
企画にはルーヴル美術館が全面協力し、ルーヴルからは30数点の作品が出品されています。
全体は6つの章に分けられ、初期から順に晩年までのコローの画業のあゆみと、それが後世の画家達に与えた影響を、実際に作品で確かめる事が出来ます。
以下長文ですが、感想をまとめてみました。
展覧会は、師のベルタン、ミシャロンの作品と、コローの初期作品の展示から始まります。
ベルタンやミシャロンの描き方は、外光の効果を生かす意図はありますが、この時代の普遍的な描き方にとどまっています。
当時、時代は17世紀から続いていたロココ文化の影響を少し残しつつ、産業革命やそれに伴う富裕な市民の台頭等、近代化の流れが強くなる中で、美術でも徐々に新しい表現を目指す動きが芽生えようとしていましたが、主流は依然として保守的・伝統的な描き方を維持しようとする勢力でした。
あくまで写実的な描き方、歴史画的な美しく風格ある仕上げ等、そうした観点でモチーフ・題材の選択や描き方にも当時はかなり制約があり、少しでも逸脱したものは、当時の画家が評価を得る代表的な場のサロンでは評価されませんでした。
コローは、遠近法の効果に、光が情景にもたらすさまざまな影響・効果をからめて、落ち着いて静かなたたずまいの古典的な情緒を残しながら、絵の中に多彩な表情があり見飽きる事のない、充実した描き方を実現しています。
コローの作品の中で特徴的であり、作品の性格にも大きな影響を与えているモチーフに、木の描写があります。
1820~1840年代といったかなり初期の段階から、流暢にしなやかに幹や枝は描き、葉は絵の具を薄くぼかして塗るのと筆のタッチを生かして点描風に描くのを巧みに組み合わせて描く、コローの典型的な木の描き方が見られます。
こうした、ぼかしを効果的に使って絵を演出するやり方は、コローの作品では後期に向かうほど、画中の全体にわたって駆使され、幻想的で優美な世界を描き出す事に成功しています。
しかし、こうした新しさを感じる描き方も、完全な独創から生まれたものではないと私は思います。なぜなら、コローに先立つ事数十年前、ロココの時代のフランスの、フラゴナールやヴァトーといった、ロココの代表的画家達も、作品全体の雰囲気は貴族趣味の強い前時代的な感じですが、絵の背景の風景等を、空気遠近法という以上にぼかしを駆使して描いている例が結構あるのです。ロココの貴族的な題材選択に加え、その描き方により、絵に夢見る様な優雅さがさらに強く加わる事になっています。
コローは、こうした前の時代の作品の特徴も、作品をたくさん見て、模写したり研究する事で、しっかりその長所をつかみ、それに自分の時代の新しい感覚をうまくミックスして、当世風の新しい優雅さの表現を模索し、提案したのだと思います。
私はコローの絵はもう30年近く見てきていますが、それでも今回新しい発見がありました。
彼が風景画で画中に人物を描く際、特に女性の場合、スカーフや衣服の色として、だいたい赤い色をワンポイント入れているのです。
風景画の場合、大抵は緑系の色が多い中で、この赤の小さなワンポイントがある訳で、これは補色の関係であり、色のコントラストの選択としては最も力強いものです。
これ位の時代の風景画の場合、人物は木々や建物と対置して描かれる事が多いのですが、コローの風景画の場合、人物の中にこの「赤いワンポイント」が加わる事で、人物の描写に強くなりすぎないが一定の主張が加わり、それが絵全体の構成やバランスを支える、控え目ながら結構重要なポイントとなっています。
なお展覧会では、初期や中期の作品の展示の中にも、晩年の作品が数点混ぜて展示してあり、年代に注目すれば、異なる時代の作品を見比べる事ができます。
後世の画家の作品としては、ドニやセザンヌ、ピサロ、モネ、シニャック、ドラン、ブラック、モンドリアン等といった、かなり多彩な顔ぶれの作品が展示されていました。
ドニの場合、コローと同じローマの景色を描いても、木々はまるで図案化した様な描き方で、全体の構図でも水平に広がる色の面の組み合わせによる画面の組み立てを強く意識させられます。
ドランの場合は、彼は20世紀初頭には過激な色使いと激しいタッチでフォーウ゛ィスムの一翼を担ったほどだったのですが、1920年代半ば頃からは一転、古典的な作風に変わっていきます。その転換の際、構図やモチーフの整え方として、コローの作品がかなり参考となり、激情的だったドランの描き方に落ち着きを与える事になったのがよくわかります。
また風景画の場合、コローの構図には、画面の中心に手前から奥に向かう道が描かれたものが多く、それも道がカーブして画面の左手に消えていっているように描いたものが多いですが、こうした描き方は実はセザンヌもよく描いています。
展示でも、よく似た構図のコローの作品と、セザンヌの作品を並べて、それがわかるように展示してありました。
他にもセザンヌの場合、前景に画面の端に枝を大きく伸ばす木を配して、それ越しに中景・遠景が見える様な描き方の風景画があります。
そうしたものは日本の浮世絵の構図との関連がよく言われていますが、今回の展示では実はコローも後期の作品の中でそうした描き方をよく用いていた事が紹介されています。セザンヌはこうしたコローの描き方をも参考にして、自作の充実と探求に役立てていた様です。
他にも、コローのぼかしや点描的タッチで描かれた木々の表現や、そうした木々が風景の中でカーテンの様に広がる事でもたらされる効果を、ピサロやモネ等次の世代の画家は、時々刻々と変わる光の表情とそれが情景に与える効果を逃さず描き出す為に各人なりのタッチや色彩の工夫を加えて新しい形で生かしている事も、展示を通じて理解できる事です。
初期・中期と、落ち着いていながら比較的色彩は豊かだったコローの絵は、1850年代後半以降、今回の展覧会でも言われている様に、全体的に灰色や茶褐色が目立つ様になります。
それが、コロー独特のタッチとも相まって、更に作品に幻想的な魅力を強めることになったのですが、後期の作品の場合、特に人物画においては、人物の衣装に赤や青、白といった、割と目立つ色が使われています。
これは前述した、風景画における人物を描き入れる際の「赤のワンポイント」と似ていますが、人物画のモデルの衣装の色なので色の面としてはある程度の大きさがあり、風景画の場合より一層強い効果・主張があるように思います。
コローの後期の人物画は、「真珠の少女」に代表される様な落ち着いた色合いが魅力の様に言われる事が多い印象がありましたが、実は画中には意外とこの様に鮮やかな色使いがなされており、この鮮やかな色を使うポイントをコローがよく心得て演出をしている事もあって、多くの人に強い魅力的印象を残しているのではないか、と感じました。
後期の作品では、実景の描写だけでなく、以前行った土地の景色の印象からヒントを得て、実景にこだわらず描いた作品も多く存在します。
コローは、実景を野外等でしっかりスケッチで描いたり油彩である程度まで描きましたが、最後の仕上げはほとんどアトリエで行い、アトリエで「推敲」の様な検討をして仕上げる事を大変大事にしていました。展示の説明文にも、作品ごとにその様な過程がわかる内容が簡潔に書かれています。
かつて訪れた場所の印象からイメージを展開して描かれた作品は、こうしたアトリエでの検討を更に発展させたものです。こうした描き方はやがて、自分が思い描いたイメージを基本に描くやり方(象徴主義等)の登場の下地にもなりました。
以上、大変長文になりましたが、今回のコロー展を見て感じた事をまとめさせて頂きました。
展覧会を見る前は、そんなにたくさんの感想は思いつかないのでは…と思っていたのですが、展覧会を見ると、コローがいかに自分の時代の前後の世代と強くつながり、また後進の画家たちの多くに強く影響したかが、実際の作品で確認・発見できたので、非常に多くの感想を抱くに至りました。
また私は約30年前にバルビゾン派の展覧会を見たのが、きちんと展覧会を見た最初でした。
今回の展示でも30年ぶりに見る作品が少しあり、約30年間の私の美術との関わりのあゆみと、その間の見方・考え方の変化・多様化を振り返って、感慨深く感じました。