


筑波鉄道は土浦駅を後にすると、常磐線と並走していたが、土浦駅の外れにあった“道路の上を跨ぐ架道橋”を調べたところ、常磐線側の橋梁の名称が“川口川橋梁”となっていたのを発見した。
川なんてどこにもないじゃんと思いつつ、“架道橋”の北側の全景に続いて南側を撮影しようと移動したところ、ここに川があった事を案内板がある広場で知った。
霞ヶ浦に面していた土浦の町では水運が発達したが、霞ヶ浦からの逆流や桜川の堤防の決壊による洪水に度々悩まされ、常磐線を霞ヶ浦湖岸に沿って敷設した後、川口川に閘門を設置したそうだ。
川口川は昭和51年に埋め立てられて、昭和60年に川の跡に道路が作られた事がわかり、“架道橋”の名称が“橋梁”だった疑問が氷解した。
ここまでわかった以上、水害から守った閘門を構成していた部品のモニュメントを素通りする訳にはいくまいと、廃線跡そっちのけで撮影が始まった。




















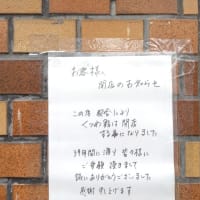






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます