こんにちは、のほせんです。
めずらしく、きのうにつづいての書き込みになりますが、
お読みいただければさいわいです。
さて、マスメディアの報道によれば、
18日の夕方に桜宮高校の女子生徒と名乗る女性から市教委のほうに電話があったという。
内容の概略は、
「橋下市長は、「生きているだけで丸もうけ」と言ったらしいが、いったいどういう真意なのか?
ならば、私が死ねばみんなが救われるんでしょうか?」と話したということである。・・・
- もっともな発言である。
その発言は橋下市長の向こうを張って一歩も引かぬ姿とみとめられよう。
そもそも橋下市長は、
桜宮高校体育科の生徒( つまり自殺しないで残された生徒のこと )が
鬱病を負わされることと同等な生き難さを背負わされつづけてきたことを、まったくわかっていないのだ。
(むろん日本中の市教委も根っからの役人根性が座っているだけの連中だから早いとこ「解散!」ねがいたいものだ。)
橋下市長が、「生きているだけで丸もうけ。」 と、
まるで 映画「大阪ハムレット」のセリフをパクったうえで、
「 チャンスはある。」 と くっつけた詐術は、憎らしいほど弁護士的な周到さではある。
だから、御用マスメディアやちょうちん文化人なら、「そうそう、そういうこと。」と肯定するところだろうが。・・・
だがしかし、いまの時代を見渡して、
いったいどこに、どんなチャンスがあるというのか!
軽々しくうそ寒い言葉を弄しても、庶民ははじめからお見通しだ。
庶民は おのれの前に、「まっとうなチャンスなど無いに等しい」のは承知のうえだ。
承知のうえで、
「生きてるだけで丸もうけ!」と、おかしみと哀しみをこめた合言葉が憤怒をこめて交わされているのだ。
生き難い時代のなかで、お互いをはげまし、ささえ合う精神が「大阪ハムレット」のメッセージにほかならない。
ひろく、大きい、
どこまでも限りなく やさしい大阪ハムレットの精神こそが
庶民の「個の尊厳」をさししめしているのだ。・・・・・
...................................
あなたの推薦クリックを毎回よろしく願います! ![]() へ!
へ!










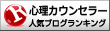






受験生の娘に聞かれ、
まったく答えることができませんでした。
すべてにわたってかんがえることをしている、
のほせん様ならお答えくださるのではないかと、
書き込ませていただきました。
よろしくおねがいいたします。
いつもわたしどものブログをお読みいただきありがとうございます。
わたしどものの、(心の病をふくめた)性格カウンセリングとは、
いわゆる性格というものが「心の病をふくめた、ものの考え方の総体」を意味するという認識から、
その人の性格= ものの考え方の不適合や不適応をとらえて改善に導こうとするものです。
そのことをふまえたうえで、個々の生き詰まる情況にみずからを立たせ、
このブログを通してみなさんに何ごとかをおつたえしようとするものです。
さて、お母様のご質問への回答になりますが、やはり
「絵画は文字よりもはるか昔」に描かれてきたとみとめられるでしょう。
「文字」は言葉が「話し言葉」から抽象性(たとえば目の前に見えないものをさす場合など)を獲得したときに、
しだいに「書き言葉」(概念の言葉)として形成されてきました。
話し言葉じたいは地球のあらゆる地域で発生してきましたが、
絵画はそれと並行するようにして表現されてきたとおもわれます。
お子様が美術の森にすすまれますことを
願ってやみません。
あらためてお礼の言葉をいただき恐縮です。
折角のお礼のお言葉ですが、
ちと照れますので
ご勘弁ねがいます。
そのかわりに
先の説明をすこし補足させていただくと、
言葉の抽象化(文字= 書き言葉)というのは、
単なる象形化から多様な意味をもたせるに至って、
ようやく人間が、
「何が、いつ、どこで、何を、なぜに、どうした」といった、
時間性と空間性を概念的につたえるべく欲求に到達したこと、
成熟してきたことの表現ともうせます。
絵を言葉で置き換えることはできませんね。
でも、沈黙した絵には、言葉の意味へと実現する前の言語の存在が満ちているように思われるのです。
今回は幼児の描く絵についてのお話ですが、
ひとが両親の性格(ものの考え方)をすりこまれることから免れないという規定の中で、
身近な外界を知覚しかつ少しは認識というものに至れるようになったとき、
その子供の可能性は限定的になるほかないでしょう。
しかし、胎児のときに地球の自然の系の気の遠くなるような過去の時空にさかのぼって最初の生物の位置に立ちもどり、
そこから一人ひとりがはるかな記憶の海をたどりながら成長を遂げ、誕生してくるという壮大なドラマは
なににも比べようもなく圧倒的で尊厳に満ちています。
お母さんが指摘されている「概念で表せない何か」を、
幼児は未明の海のなかからとりだしているのかも知れないですね。
それを言葉とか絵とか、私たちはいっているわけですね。
するとあるいは・・・・
文字というのは、まず絵として、考え出されたということかもしれませんね。
つづいてのお話をいただきました。
おっしゃるように、
「洞窟画などに見られるように
共通の対象を描きつらねることにより
つたえたい意味を表現することからはじまってきたとおもわれます。
そしてしだいに複雑な意味をよりよくつたえるために指示性のほうへ、
すなわち象形文字(たとえばシカと名ざしされて)の形成からさらにそれの抽象化にむかって、
書き言葉としての文字を必要とする共同社会の成熟にともなって、
社会的言語をうみだし、その文法を共有するようになったということでしょう。
子供が一心不乱に砂場で砂と水遊びをしています。山やトンネルを作って遊んでいるのね、行為の一面がその行為だとおもって私達は見てしまいます。
子供が水や砂を楽しんでいるのか、その皮膚感覚を楽しんでいるのか、その行為の多重性、境界の定かでないことは、なかなかにみることはありません。
洞窟壁画の伝わる画像の視覚性と、描画のタッチ(筆触)の伝わりにくい感覚性、なぜ、絵が、絵を描く人間が、この世に在るのでしょうか。
美大受験生のお母さんから こんどは、
「なぜ、絵を描く人が存在するのか」という命題をちょうだいしました。
この命題にもっともよく答えているのは、
吉本隆明氏の名著「言語にとって美とはなにか」でしょう。
この間からのわたしのお話は、
氏の論考では「指示表出」という他者につたえるための言葉の性質にしぼった部分です。
ところが言葉が表現されるときには、
そのひと固有の内面が同時に表出されるということ。
とりわけ本物の絵画や文学としてつきつめられた表現は、
その固有の「自己表出」が突出して表されるといえます。
時代を切り裂くような本質的な絵画や文学は、
「言葉でいい表わせないから、いわなければならない。これが文学者(詩人)の論理である。」し、
また、「絵画で描き表わせないから、描かなければならない。」
ものであります。
また、坂口安吾はつぎのようにいっています。・・
“ 生存の孤独とか、我々のふるさとというものは、このようにむごたらしく、救いのないものでありましょうか。
(中略)この暗黒の孤独には、どうしても救いがない。(中略) そうして最後に、
むごたらしいこと、救いがないということ、それだけが、唯一の救いなのですあります。
私は文学のふるさと、あるいは人間のふるさとを、ここに見ます。文学はここからはじまる-
- 私はそう思います。”
どんな前向きな社会改革によっても救うことのできない部分が、人間の心のうちにはある、
と気づいたとき、そこから文学がはじまるといってさしつかえないようにおもいます。
絵画もまた、社会の関係性のなかにあって、なお
ほとんど他者につたえることが不可能であるにもかかわらず、
個としての固有のなにごとかをとり出さざるを得ない者の苦悩のたたかいの表現といえるのではないでしょうか。・・・