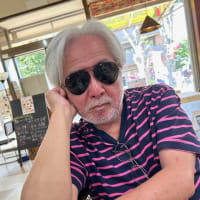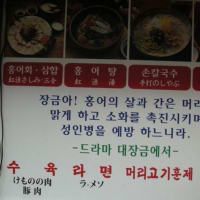【連載】半導体一筋60年⑤
微細化競争に負けた日本
釜原紘一(日本電子デバイス産業協会監事)

潮目が変わって日本は長期凋落へ!
1990年頃をピークに日本半導体のシェアは低下していき、今日に至るまで復活することなく落ち続けています。では何故こうなったのでしょうか。この原因として、いろいろな議論があります。例えば―-
①日米半導体協定の影響(韓国、台湾の台頭に有利に働いた)。
②ビジネスモデル(ファブレスとファンドリー、水平分業化)の変化に対応できなかった。
③半導体消費市場がAV関係から情報機器(パソコン、携帯電話等)へ変わったが、日本企業はその動きに取り残されている ガラパゴスの携帯電話は世界では売れない!
④経営の問題(スピードが遅い、投資せず内部留保を増やすのみで成長できない)。
ここではビジネスモデルの変化について説明しましょう。その為には半導体がどのようにして造られるのかを知ってもらう必要があります。これまで技術的な内容は出来るだけ避けてきましたが、しばらく我慢してお付き合いください。
半導体はどのように造るのか?
まずは半導体の材料です。半導体(Semiconductor)とは、電気抵抗率が絶縁体(ガラスやゴムのように電気を通さないもの)と導体(金属のように電気を通すもの)の中間に位置する物質です。
純粋な半導体は殆ど電気を通しませんが、不純物を少量入れると電気を通すようになります。この性質が大事なところで、半導体の本質となるものです。
半導体材料の代表的なものがシリコン(Si)です。他に化合物半導体(ガリウムヒ素GaAsなど)もありますが、後で必要に応じ説明することにしましょう。殆どの半導体製品はシリコンで造られています。
ところで、ここでひとつ断っておきますが、半導体という言葉は材料としての半導体と製品としての半導体の両方に使われます。どちらなのかは、文脈から判断するしかありません。
第1図にシリコンインゴット(柱状の塊)とシリコンウエハ(円盤状)を示します。シリコンは地球上に酸素に次いで多く含まれていますが、半導体材料としては高純度の単結晶が欠かせません。

▲第1図 シリコン(株式会社SUMCO のホームページより)
その純度は99.999999999%です。9が11個並んでいるので、「イレブンナイン」と呼ばれています。ウエハの直径は最大で300ミリ、厚さは約1ミリで、表面を鏡のように磨いて使用します。
純度はSiだけではなく、半導体を造るために必要な薬品、ガス、配管、治工具などあらゆるものが極限まできれいである必要があります。製造ラインはスーパークリーンルームの中につくられます。中で働く人も頭から足までつなぎの作業服を着なければなりません。部屋に入る時はエアーシャワーを浴びて入ります。
PN接合の形成
高純度シリコンは殆ど電気を流しません。しかし、リン(P)を加えると、N型半導体となり電気を通すようになります。また、ボロン(Bほうそ)を加えると、P型半導体となります。
シリコンにP型領域とN型領域をつくると、その境界にPN接合(PNジャンクション)ができます。PN接合がひとつだけのものをダイオード(整流素子)と呼び、電気の流れを交流から直流にする働きをします。すなわち、PからNへは電気が流れるが、NからPには電気が流れないという性質を利用したものです。
シリコンにPNP又はNPN構造をつくるとトランジスタができます。トランジスタはひとつの電極に小さな電流を流すと、別の電極に大きな電流が流れます(増幅作用と言います)。また電流を流したり止めたりするスイッチの働きもします。極めて荒っぽい説明なので、詳しい方は顔をしかめることでしょう。しかし、話の流れをスムーズにすることを優先しているとご理解ください。
さて、上述のダイオードやトランジスタは個別半導体(ディスクリート)と呼びます。そして、このトランジスタやダイード、更に抵抗やコンデンサなどをシリコンの中に作りこんで一つの回路を形成したものが集積回路(IC:Integrated Circuits)です。回路とはいろいろな電子部品を組み合わせて電子機器の働きをさせるものです。
では、いよいよ製造工程の話に移りましょう。半導体の製造工程にはウエハ工程と組み立て工程があります。
ウエハ工程と組み立て工程
シリコンに回路を形成する工程をウエハ工程(又は前工程)と言います。先ず、シリコンウエハを酸素中で熱してSi表面に酸化膜(Si0₂)をつくります。次に、酸化膜の上にフォトレジスト(感光剤)と呼ばれる粘度のある液体を垂らしつつ、ウエハを高速回転さて表面を薄い膜で覆います。
余談ですが、フォトレジストは日本メーカが高いシェアを持っており、数年前に日韓の間でレーダー照射事件があった時、このレジストの輸出を制限してサムスン電子が困るというような事がありました。
それはさておき、話を進めましょう。
回路パターンを描いたフォトマスク(ガラスマスク)を通して、露光装置によりフォトレジスト(以下レジストと呼ぶ)に光を当てると、レジスト上に回路パターンが形成されます。レジストに光の当たった部分は薬品に溶けないので(逆に光が当たった部分のみが溶けるタイプもあります)、露光の済んだシリコンウエハをエッチングする(現像液に相当する薬品に浸ける)と光の当たった部分だけが残り、その下の酸化膜も残ったままとなります。以上の工程をフォトリソグラフィと言います(第2図参照)。

▲第2図 フォトリソグラフィの概念図(筆者作成)
その後薬品やプラズマ放電によりフォトレジストを取り除きます。するとシリコンウエハ上には、酸化膜のパターンが残ります。そのシリコンウエハに熱拡散やイオン注入という手段でP型やN型の不純物を導入します。そうすると、酸化膜のない穴の部分を通って不純物がシリコン中に入ります。こうしてシリコン上に、P型領域やN型領域ができ回路ができます。
この工程を20~30回繰り返します。パターンの上にさらに別のパターン、例えばP型領域の一部にN型領域を形成する、という具合にして複雑な回路を形成していく訳です。最後にスパッタリングという方法で薄いアルミの層を形成します。このアルミ層は回路をつなぐ電極となります。ウエハプロセスだけで大体400~600工程あり、所用期間は1~2カ月かかります。

第3図 Amazonでも売ってるウエハプロセス完了のウエハ
ウエハ工程が終了したものを第3図に示します。碁盤の目のように沢山の四角が見えますが、この一つひとつがICで、この四角を切り離して製品とするのが「組み立て工程」です。ウエハ上の四角な小片(これをICチップ又は単にチップと言います)をダイヤモンド刃やワイヤーにより切り離します。これを「ダイシング工程」と呼びます(第4図参照)。

▲第4図 ダイシング(半導体製造装置協会のHPより)
バラバラになったチップをリードフレームと呼ばれる支持体に銀ペーストなどを使って貼り付けます。これを「ダイボンディング」と言います。チップ上の電極とリードフレーム上の電極を金線により結合させます。これを「ワイヤボンディング」と言います。そして出来上がったものをエポキシ樹脂で覆い固めます。これを「モールド封止」と言います(第5図~第7図参照)。

▲第5図 ダイボンド(マウンティング)(半導体製造装置協会のHPより)

▲第6図 ワイヤーボンディング(半導体製造装置協会のHPより)

▲第7図 モールド封止(半導体製造装置協会のHPより)
以上、半導体のできるまでを説明しました。あとテスト工程が残っていますが、今回は省略します。
日本の半導体が衰退してゆく一つの要因として、半導体の微細化競争に負けたことが上げられるでしょう。微細化のカギを握るのは上述のフォトリソグラフィ工程にありますが、日本はその工程での投資が続かず脱落したと私は思っています。では、何故投資が続けられないのでしょうか。それは次号以下で説明できればと思います。

【釜原紘一(かまはら こういち)さんのプロフィール】
昭和15(1940)年12月、高知県室戸市に生まれる。父親の仕事の関係で幼少期に福岡(博多)、東京(世田谷上馬)、埼玉(浦和)、新京(旧満洲国の首都、現在の中国吉林省・長春)などを転々とし、昭和19(1944)年に帰国、室戸市で終戦を迎える。小学2年の時に上京し、少年期から大学卒業までを東京で過ごす。昭和39(1964)年3月、早稲田大学理工学部応用物理学科を卒業。同年4月、三菱電機(株)に入社後、兵庫県伊丹市の半導体工場に配属され、電力用半導体の開発・設計・製造に携わる。昭和57(1982)年3月、福岡市に電力半導体工場が移転したことで福岡へ。昭和60(1985)年10月、電力半導体製造課長を最後に本社に移り、半導体マーケティング部長として半導体全般のグローバルな調査・分析に従事。同時に業界活動にも携わり、EIAJ(社団法人日本電子機械工業会)の調査統計委員長、中国半導体調査団団長、WSTS(世界半導体市場統計)日本協議会会長などを務めた。平成13(2001)年3月に定年退職後、社団法人日本半導体ベンチャー協会常務理事・事務局長に就任。平成25(2013)年10月、同協会が発展的解消となり、(一社)日本電子デバイス産業協会が発足すると同時に監事を拝命し今日に至る。白井市では白井稲門会副会長、白井シニアライオンズクラブ会長などを務めた。趣味は、音楽鑑賞(クラシックから演歌まで)、旅行(国内、海外)。好きな食べ物は、麺類(蕎麦、ラーメン、うどん、そうめん、パスタなど長いもの全般)とカツオのたたき(但しスーパーで売っているものは食べない)