
【連載】藤原雄介のちょっと寄り道㉗
夜明けのアザーン モロッコの旅①
テトゥアン(モロッコ)
1973年夏。身体の節々が痛い。寝不足で頭は朦朧としている。湿った潮風がシュラフ(寝袋)から出ている顔にまとわりつく。ここはアフリカ最北端モロッコにあるスペインの飛び地セウタ(Ceuta)だ。前夜、アルヘシラスからフェリーでジブラルタル海峡を渡ってセウタにたどり着いた。安宿を探しまわったが、どこにも空き室がなく、波止場近くの石畳の上で野宿する羽目になったのだ。
翌朝、目覚めてもアフリカの大地に足を踏み入れたという実感はなかった。セウタの景色は、アンダルシアとたいして変わっている訳ではないし、聞こえてくるのはアンダルシア訛りのスペイン語だ。しかし、オンボロバスに揺られて、セウタから一番近いモロッコの町テトゥアンに着いたら雰囲気が一変する。アンダルシア風の家が多いのだが、聞こえてくる言葉はスペイン語だけではなく、フランス語とベルベル語が混じってくる。
テトゥアンでのモロッコ最初の夜、セウタでの野宿の疲れのせいで、石畳より遙かに快適な安宿のベッドに倒れ込むとそのまま深い眠りに落ちた。しかし、日の出前に、モスクのミナレット(尖塔)に取り付けられた拡声器から流れるひび割れた大音声の「アザーン」にたたき起こされた。
アザーンとは、1日5回、イスラム教徒に礼拝の時刻を告げる呼びかけのことだ。「アッラーフ・アクバル(神は偉大なり)」で始まるアザーンは美しい抑揚の力強い男性の声で4分くらい続く。白状すると、「美しい抑揚」と感じたのは、数日経ってからのことである。初めて、日の出前のアザーンを聞いたときには、外国というより得体の知れぬ異世界に紛れ込んでしまったような感覚に捕らわれ、説明し難い恐怖にも似た感情を覚えた。
現在では、中東関係のニュースやYouTube等でアザーンの調べを耳にすることも珍しくはない。なんとなく、「ああ、あれか」と見当がつく方も多いのではないだろうか。しかし、今から50年前、アザーンに関する何の予備知識もないまま夜明け前に、意味不明の異教徒の祈りに眠り妨げられた時の衝撃は今でも鮮やかに覚えている。
テトゥアンの町を歩くと東洋人が珍しいのか、人々の視線が突き刺さって来る。アラブ世界に共通する事だが、強い目力で興味あるモノ、ヒトをなめ回すように凝視するのだ。視線を合わすことを躊躇いがちな日本人の感覚では、あまりに礼儀知らずに思えるが、その内慣れて来る。こちらも凝視には凝視で返すと、ニッコリ笑いかけて来たりする。悪気はないのだろう。異文化間コミュニケーションの難しさを理解するためのよい見本だ。
あるカフェに入ると、アブドゥッラーと名乗る店の主人が下手くそな英語で親しそうに話しかけてきた。欧州で、もう4ヶ月近く暮らして来たので、親しそうに近づいてくる輩にろくな奴はいないと骨身に沁みている。
用心深く間合い計りながら、しばらく話していると、彼の息子にメディナ(旧市街)を案内させると言う。こんな場合、後で「金をよこせ」となる場合が多いのだが、アブドゥッラーは一応レストランの主人で身許ははっきりしているし、悪人面でもないので、好意を受けることにした。
アブドゥッラーの息子は、10歳前後の丸刈りで褐色の肌、なかなかのハンサムだ。残念ながら名前は覚えていない。彼は、よそ者が一人ではなかなか入っていけない迷路の奥、旧王宮、要塞などを片言の英語とスペイン語で案内してくれた。
狭い路地には、サボテンの実、香辛料、銅板をハンマーで叩いて複雑な模様を刻んだ工芸品、駱駝の皮で作った財布やバッグなど様々な店が軒を並べている。狭い路地で客を呼び込む売り子が大声を張り上げる横を背中に大きな荷物を載せたロバが哲学者のような表情で、糞をボタボタ落としながら行き交う。それまで体験したことのない光景、匂い、音、色…五感に飛び込んでくる総てが蠱惑的だった。

▲生活感溢れる路地

▲「白い鳩」と呼ばれるテトゥアン

▲住宅街
テトゥアンは、元々イスラム色の強い町で、モロッコとアンダルシアの接点として栄えていたが、「レコンキスタ」の完遂により、キリスト教徒によって破壊された。「レコンキスタ」(Reconquista=領土回復運動)とは、キリスト教勢力がイベリア半島からイスラム勢力を追いだそうとした運動のことだ。レコンキスタは、718年から1492年まで辛抱強く続き、最終的にイスラム勢力を追い出すことに成功した。
現在のテトゥアンは、その後、イベリア半島を追われてモロッコに逃げ延びてきたイスラム教徒やユダヤ教徒によって再建されたものだ。17世紀に造られた5キロにわたる城壁で囲まれたメディナ(旧市街)は、アンダルシアとイスラムの文化が融合したエキゾチックな街並みで、世界遺産に登録されている。

▲ メディナ(旧市街)の城壁
日本語の「壁に耳あり障子に目あり」に該当するスペイン語は、’Hay moros en la costa (playa)’ である。直訳すると、「海岸にモーロ人がいる=気をつけろ、そばにヤバイ奴がいるぞ」だ。モーロ人(英語ではMoors=ムーア人)とは、北アフリカのイスラム教徒を指す言葉だ。
例えば、カフェで友達の悪口を言ったりしていると、誰かが、’Hay moros en la costa (playa)’と口走り、皆が我に返ったりする。スペイン人の脳裏から、800年に亘ってモーロ人に支配された記憶は、今も消えてはいないのだ。
テトゥアンを皮切りに、およそ1ヶ月に亘り、フェズ、メケネス、ラバト、カサブランカ、そしてマラケシュを放浪した。次回からこれらの街についても書いてみたい。
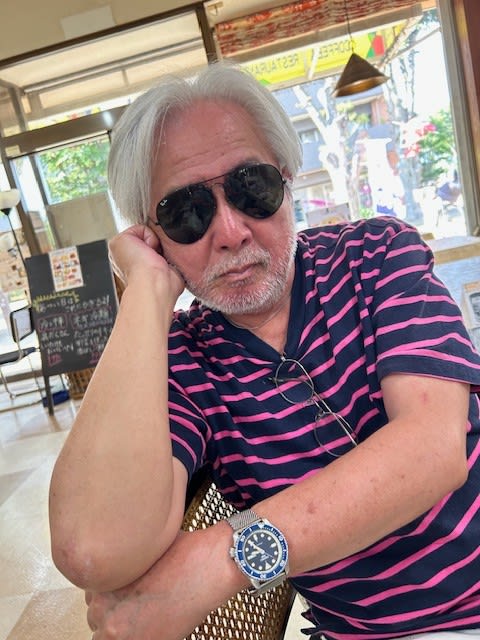
【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】
昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。
























