
期待感を高める会場入口のファザード
江戸時代と近代の日本画家のコレクションで定評のある東京・府中市美術館で「リアル 最大の奇抜」が行われています。毎年恒例の「春の江戸絵画まつり」として行われている展覧会で、京都の円山応挙、江戸の司馬江漢ら、時代を代表する写実派による“リアル”作品を味わうことができます。
江戸時代半ばでも西洋絵画の刺激がまだ少なく、日本ではリアルな絵画表現が斬新でした。そのリアル表現は京都と江戸でトーンが異なることが作品を通じて学ぶことができます。府中市美術館らしい味わい深い企画展です。
展覧会場の冒頭、大坂を拠点にリアルな猿の絵を描いた森狙仙(もりそせん)の「群獣図巻」が観客を出迎えます。トラ・テン・タヌキなど様々な動物を実に多様なポーズで描いています。
彼は円山応挙のように、徹底的にモチーフを観察していたことで知られています。それぞれのポーズは写真のように動いている瞬間をとらえていることが分かります。実際の動きを観察しないと描けないと思えるほどの迫力です。
円山応挙の「鯉図」も、鯉が水の中で向きを変えようとする瞬間をとらえています。この絵も鯉の動きを観察しない限り絶対に描けないと感じます。しかし魚なので水の中で動いています。応挙はどうやって観察したのでしょう?
江戸時代半ばの上方では、伊藤若冲や円山応挙によるリアルな表現がとても人気を集めていました。従来の日本画になかった写真のように人間の見た目に忠実な表現が支持されます。明治の「京都画壇」の源流となる新たな表現流派として定着します。
江戸のリアル表現は、より中国や西洋絵画の影響を感じます。この東西の違いは町の成り立ちの違いが大きいのではと、私は感じています。
京都は、公家・寺・町衆といった富裕層が絵のクライアントの中心層でした。武家がほとんどいないことから贅沢だと咎められることもありません。結果的に高額な絵が多く求められ、庶民が手を出せる作品は少なかったと考えられます。町が古くからあり、蓄積されてきた芸術表現から大きく外れることは好まれません。応挙や若冲の作品も写実表現は素晴らしいですが、一目見て日本画表現から外れていないことが分かります。
江戸は町の歴史は短く、蓄積されてきた芸術表現はありません。大名が高額な絵のクライアントでしたが、格式にこだわるため斬新な表現は好まれません。
江戸では時が経つにつれ中下級武士や庶民が芸術や文化の担い手の中心になっていきます。歴史がないため表現はとにかく自由です。またリーズナブルな価格帯が好まれます。浮世絵は、庶民が流行情報を得る雑誌や中下級武士が国元に持ち帰る江戸土産として爆発的に流行したものです。
江戸で中国や西洋絵画風のリアル表現が受けたのも、しがらみのなさが背景にあると考えられます。
司馬江漢(しばこうかん)は、当時のスーパー知識人だった平賀源内から刺激を受け、中国や西洋の写実表現を学びます。当時の最先端サイエンスだった蘭学にも通じ、油絵も描くようになります。
森狙仙や円山応挙の写実表現と異なり、一見して日本画には見えません。「円窓唐美人図」は窓から見える遠景を遠近法で描いており、西洋絵画の表現を見事にマスターしていることがわかります。女性の顔に少しはにかんだよう表情を描く表現も西洋的です。西洋風絵画の初期の作品として、とても見応えがあります。
ご紹介した作品の画像は、展覧会チラシPDFでご覧ください
【公式サイトの画像】 展覧会チラシPDF

新緑が美しくなる府中の森公園
府中市美術館は、広大な「東京都立府中の森公園」の一角にあります。新緑が美しい季節です。そんな素晴らしい季節に、江戸絵画の面白さを堪能できる展覧会です。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
府中市美術館で大成功を収めた展覧会の図録
府中市美術館 「春の江戸絵画まつり リアル 最大の奇抜」
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/kikakuten/kikakuitiran/real.html
主催:府中市美術館
会期:2018年3月10日(土)~5月6日(日)
原則休館日:月曜日
※4/8までの前期展示、4/10以降の後期展示でほとんどの展示作品が入れ替えされます。
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。

ビュールレさん、ようこそ六本木へ(赤いチョッキの少年)
東京・六本木の国立新美術館で「至上の印象派展 ビュールレ・コレクション」が行われています。印象派やポスト印象派の個人コレクションとしては世界最大級と言われており、画家たちの個性を満喫できる充実したコレクションです。
このコレクションはまもなく公的な美術館に一括寄贈されます。コレクションとしての最後のお披露目に世界各地を巡回しており、六本木にやってきました。欧米の個人コレクションは、質量ともに圧倒されますが、その中でも随一のものです。とても充実したたくさんの作品を見ることができます。
このコレクションを形成したのは、ドイツ生まれのスイスの実業家エミール・ゲオルク・ビュールレです。両大戦で武器商人として成功しますが、第二次大戦中にスイス政府により武器輸出が禁じられると民生品ビジネスに転じ、引き続き財を成します。入手作品がナチスによる強奪品とわかると元の持ち主に変換するなどフェアな姿勢にも努め、1937年から1956年にかけてコレクションを築き上げました。
1956年の彼の死後、チューリヒ湖畔の邸宅を美術館としてコレクションを公開していましたが、2008年に4点の傑作が強奪されます。4点はその後無事に戻ってきましたが、一般公開は規制されていました。最終的に自らの美術館での安全確保を断念し、すべてのコレクションを2020年にスイス最大のチューリヒ美術館に一括寄贈することになりました。
展覧会のチラシ・ポスターにも採用されているセザンヌの「赤いチョッキの少年」はコレクションの最高傑作の一つです。強奪された作品の一つでしたが、無事に戻ってきた強運の持ち主でもあります。物憂げな表情に見えますが、セザンヌらしく明るいタッチです。一方で、仏像のように無心の境地を表しているようにも見えます。人を惹きつけるオーラを感じます。
「アングル夫人の肖像」は、アングルが仲睦まじかった妻・マドレーヌを描いた肖像画です。アングルらしい古典に出てくる女神のように描かれています。アングルらしくなく筆が粗いことから「未完成品」と解説されていますが、かえって夫人が神格化されたような印象を与えます。とても魅力的です。
「ルーヴシエンヌの雪道」は、カミーユ・ピサロによって雪化粧した街並みが明るく描かれた作品です。ピサロの作品で雪の光景は多くありませんが、彼らしく日常の光景を素朴に描き出しているところに見栄えがあります。
「花とレモンのある静物」は、ピカソがナチス占領下のパリで描いた作品です。黒を多用した静物画は戦争の暗い影を感じさせます。一方きびきびしたキュビズム的幾何学模様と、主役の黄色いレモンが絵全体をとても引き締めています。
【公式サイト】 ご紹介した作品の画像が掲載されています

ミッドタウンから檜町公園に向かう道は桜の名所
六本木はすっかり、東京では上野と並ぶ美術館エリアとして定着しました。2018年の春は、六本木に横綱級のコレクションが来ています。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
国立新美術館
至上の印象派展 ビュールレ・コレクション
http://www.nact.jp/exhibition_special/2018/buehrle2018/
http://www.buehrle2018.jp/
主催:国立新美術館、東京新聞、NHK、NHKプロモーション
会期:2018年2月14日(水)~5月7日(月)
原則休館日:火曜日
※この展覧会は、東京・国立新美術館展の後、九州国立博物館、名古屋市美術館に巡回します。

岡崎も春本番
京都・岡崎公園の国立近代美術館で「明治150年展」が始まりました。展覧会は、明治時代の日本画と工芸の作品が、どのような時代背景で生み出されたのかを丁寧に解説しています。近年は「超絶技巧」と呼ばれ、超リアル表現で本物と見間違うような明治工芸が人気を集めていますが、それらが生み出された時代背景は案外知られていません。
今年2018年は明治になって150年の節目の年です。そんな節目の年に相応しい、美しい理由を学べる展覧会です。
都が東京に移った京都では衰退への危機感が強く、伝統的な日本画や工芸技術で新たな道を開拓しようとしていました。京都府画学校、現在の京都市立芸術大学が1880(明治13)年に創設され、日本画家を養成して京都の伝統文化を継承しようとします。
しかし東京遷都に伴って家族になった公家も東京へ移り、画家の成長を支えるパトロン自体が激減していました。そのため卒業生は画家として独り立ちできず、多くが工芸品や着物の下絵を描いて生計を建てていました。
会場には明治の京都画壇の秀作が展示されるとともに、そうした下絵も多数展示されています。下絵であっても立派な美術品として通用するものばかりです。
工芸品は明治の日本では重要な輸出品でもありました。幕末に開港して以来、西洋にはない美しさに関心を持った外国人たちが、日本美術を本国に紹介します。また日本政府も欧米で開かれた万国博覧会に工芸品・美術品を積極的に出展します。欧米で一大日本ブームが起こるのです。
明治の画家や工芸職人たちは、こうした海外需要に大いに支えられました。政府も画家や職人を育てようと、東京や京都で内国勧業博覧会を催し、美術工芸作品を出展させます。
陶磁器・七宝・ガラスといった窯業の世界でも、ドイツ人ワグネルがもたらした技術革新により、下絵の繊細な絵柄表現をほぼ正確に焼き付けることができるようになります。中国が清朝末期の混乱で陶磁器の輸出が滞っていたという幸運にも助けられ、焼物の輸出も飛躍的に増加します。
明治の日本の美術や工芸は、外国からの需要に大きくけん引されていた時代でもありました。どのような図案・デザイン・モチーフが外国人に好まれるかを研究し、新しい技術を活かして大量生産を行います。明治政府もデザイン帳である「温知図録」を作って品質の向上を図っていました。
この時代の工芸品はとてもリアルです。製造技術にしろ、表現力にしろ、飛躍的に進化していることがわかります。一方で日本人が好む“曖昧さ”が全くないことから、違和感を覚える人がいるかもしれません。
しかしそれが明治の日本が遺した美術工芸です。江戸時代以前の絵画や仏教美術が大量に海外に流出する中、工芸も輸出で近代化を推し進めました。明治の日本には、美術品の海外流出を食い止め、若手芸術家を育てるパトロンが国内にはまだ少なかったのです。

出品作のリアルさは本物を見てお確かめを
【画像出典】 公式サイト 展覧会チラシPDF
作品そのものの魅力はもちろん、まだ「極東の小さい島国」だった明治が、美術界にとってどのような時代だったのかがとてもよくわかります。ぜひお出かけください。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
現代とは性格が異なった明治の博覧会の意義とは
京都国立近代美術館「明治150年展 明治の日本画と工芸」
http://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2017/424.html
主催:京都国立近代美術館、京都新聞
会期:2018年3月20日(火)~5月20日(日)
原則休館日:月曜日
※4/22までの前期展示、4/24以降の後期展示で一部展示作品が入れ替えされます。
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。

明るい美術館の建物がさらにピカピカになりました
京都の北部、金閣寺の近くにある堂本印象(どうもといんしょう)美術館が、1年間のリニューアル工事を終えて再オープンしました。入口にカフェが設けられ、混雑することもあった館の前のバス乗り場が拡張されて利用しやすくなっています。印象自らが設計した明るい建物の外壁も、綺麗になってより明るくなりました。
リニューアルオープンを記念した展覧会には、館蔵品だけでなく全国から印象作品が集められました。まさに印象の代表作が勢ぞろいです。

印象が手掛けた障壁画マップが館内に掲示
堂本印象は、1891(明治24)年に京都市で生を受けました。大正時代に帝展に出品した「調鞠図」「木華開耶媛」などで評価を確立し、明るいタッチでエキゾチックな画風の日本画家として活躍します。
京都をはじめ全国の寺社・教会の障壁画も数多く手がけるようになります。宗教心の強かった彼は、仏画や障壁画を描く前に関連する経典を読みこなし、表現の研究に相当の時間を割いていました。東福寺・仏殿・天井画「蒼龍図」、仁和寺・黒書院・襖絵などがよく知られています。
戦後、彼の画風は大きく変わります。風俗画・風景画・抽象画を手掛けるようになります。日本画のように線ではなく、洋画のように色面で表現するようになります。日本画家と紹介しても理解できなくなるくらいの変容ですが、珍しいことではありません。戦後はモチーフや表現がとても多様になり、洋画/日本画と区別すること自体が困難になっています。
【公式サイト】 堂本印象について
印象は1966(昭和41)年、自らの作品を展示するために美術館を設立しました。1991年に美術館と所蔵作品は京都府に寄贈され、現在の京都府立堂本印象美術館となっています。
展覧会は、印象の画業人生を俯瞰できるようになっています。永青文庫蔵「調鞠図」は帝展で特選を得た彼の出世作です。中国の宮廷夫人が蹴鞠をしている様子がとてもエキゾチックに描かれています。正倉院に遺された天平絵画のような趣です。

木華開耶媛
【画像出典】公式サイト 展覧会チラシPDF
「木華開耶媛(このはなさくやひめ)」は印象作品では最も有名な作品の一つです。春の女神が満開の桜の下で春の訪れを楽しんでいる姿は、ボッティチェルリの「春」のように明るいオーラを発しています。とても元気になれる絵です。

椅子による二人
【画像出典】公式サイト 展覧会チラシPDF
「椅子による二人」を見ると、「木華開耶媛」と同じ作者とは思えません。1949(昭和24)年の作品です。まるで敗戦からの立ち直りに向かって社会を勇気づけるよう、団らんする母娘の様子が明るく描かれています。

交響
【画像出典】公式サイト 展覧会チラシPDF
「交響」は、印象が戦後挑んできた抽象画の傑作です。色の鮮やかさの中に、金粉のように繊細な点表現が加えられています。抽象絵画の創始者の一人であるカンディンスキーのコンポジション・シリーズを思い浮かべます。しかしこの絵はれっきとした日本画です。中心で目立つ黒い線模様は墨のように純粋な黒さが強調され、日本的な表現と抽象表現が見事に調和されています。
印象は、画風の変化がとても興味深い画家です。ピカソのようにころころ変わっています。そんな印象作品をたっぷり見ることができます。ぜひ春の京都・衣笠にお出かけください。

バス停も印象美術館のデザインにあわせ変身
立命館大学の通学者による混雑も緩和
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
堂本印象のすべてを館が編集
京都府立堂本印象美術館
リニューアルオープン記念展覧会「堂本印象 創造への挑戦」
http://insho-domoto.com/plan/new/current/index.html
主催:京都府、京都府立堂本印象美術館(指定管理者:公益財団法人京都文化財団)、京都新聞
会期:2018年3月21日(水・祝)~6月10日(日)
原則休館日:月曜日
※4/30までの前期と、5/2以降の後期で一部展示作品の入れ替えがあります。
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。

落ち着いた入口ファザード
大阪の都心の中之島に、朝日新聞の創業者・村山龍平のコレクションを所蔵する香雪(こうせつ)美術館の分館「中之島香雪美術館」がオープンしました。建て替えが進められていた朝日新聞社とフェスティバル・ホールのツインタワーに入居、とても訪問しやすい場所にあります。
オープンを記念して、重要文化財19点を含む日本と中国・朝鮮半島の古美術品を中心とした村山コレクションを一挙公開する展覧会が始まりました。数が多いため5期に分け1年かけて行われます。1回目となる「I 美術を愛して」は、村山龍平とゆかりの深い作品が選りすぐられて展示されます。ぜひ中之島へお出かけください。
中之島香雪美術館は最新の照明技術やガラスを用いています。ガラスはその存在を感じさせないほどに反射や映り込みがなく、気づかずに顔を作品に近づけておでこをぶつける人が多いことでしょう。中に収められた美術作品はとても見やすく、やさしい自然光に包まれているようです。ガラスケースの長さは50mを超え、圧巻の長さです。天井も高いことから面積の大きい絵画作品でも窮屈な思いをせずに鑑賞できます。
美術館が入居する中之島フェスティバルタワー・ウエストは、美術館を除いて1年前にオープンしていました。建物新築時にコンクリートから出るガスが美術品の退色を促進するため、新築美術館はこのガスを取り除く期間が必要となります。そのため建物竣工と同時にオープンできません。
「枯らし」と呼ばれるこの期間は技術向上で短くなっていますが、中之島香雪美術館でも1年かけています。入館料収入が得られない中で維持費ばかりが出ていくため、「枯らし」期間を短縮するさらなる技術向上を期待したいものです。
村山龍平が朝日新聞の経営を軌道に乗せた明治20年ごろ、日本の知識人の間では日本美術の海外流出を憂う声が大きくなっていました。寺や旧大名家などから売りに出された美術品がことごとく、日本ブームに沸いていた欧米人に買われていったためです。村山龍平も海外流出を憂いていた一人で、新聞で危機感を訴えながら、少しでも国内に作品を遺そうとコレクションを始めます。
南宋の画家・梁楷(りょうかい)による「布袋図(ほていず)」は、コレクション最初期の入手品です。村山龍平の思い入れの強い作品です。ふくよかなボディとはアンバランスな、ずる賢そうに表現された布袋様のお顔が、観る者に謎かけをしているような不思議な絵です。なぜか見つめてしまいます。東山御物の一品でした。展示順の最初に登場します。
【公式サイトの画像】 梁楷「布袋図」
原在中の「双鶴図」は、鶴の美しい羽根が凛として描かれた銘品です。とても緊張感があります。伝・周文の「瀟湘八景図屏風」は中国の山河のスケールの大きさを感じさせる水墨画です。中国の雄大な時間の流れもあわせて観るものに印象付けます。「東山遊楽図屏風」は江戸時代初期に京都の人々が遊興にふける様子が生き生きと描かれています。百人百様の着物のデザインがとても印象的です。
茶人としても名高かった村山龍平は、茶道具のコレクションにも愛情を注ぎます。「利休丸壺」茶入は利休の愛用品で、江戸時代に松平不昧によって再興格付けである「大名物(だいめいぶつ)」に認定されています。同じものは絶対に作れないと思えるほど、炎が立ち上るような妖艶な色の変化が円い壺を取りまいています。茶入れなのでとても小さいですが、とても存在感があります。
【公式サイトの画像】 利休丸壺茶入

館内に再現された茶室「玄庵」
神戸の美術館本館に隣接する旧村山家住宅にある茶室「玄庵」が、中之島香雪美術館内に露地と共に再現されています。村山龍平が明治時代に、京都の茶道家元・藪内家にある茶室「燕庵」の写しを、特別な許しを得て「玄庵」として建てたものです。茶室はほとんど一般公開されないため、内部構造やデザインの巧みさを見ることができる貴重なレプリカです。館内は茶室のみ、写真撮影OKです。
本館の展示スペースの関係で展示機会が限られていた作品にも、日の目をあてることができるようになります。これからどんな作品が登場してくるか、とても楽しみです。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
新聞王・村山龍平の生涯
中之島香雪美術館
開館記念展「珠玉の村山コレクション ~愛し、守り、伝えた~」
I 美術を愛して
http://www.kosetsu-museum.or.jp/nakanoshima/exhibition/2018_1/
主催:香雪美術館、朝日新聞社、朝日放送
会期:2018年3月21日(水・祝)~2018年4月22日(日)
原則休館日:月曜日
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。

所蔵作品の質の高さを感じさせる玄関のデザイン
【画像出典】佐賀県立博物館・美術館 公式サイト 館内ビュー
佐賀県立美術館は佐賀市の中心部にあり、女性画で著名な岡田三郎助(おかださぶろうすけ)のコレクションが充実しています。間もなく2018年4月1日からは、東京・恵比寿から館の敷地内に移築された彼のアトリエの公開が始まります。彼や周囲の画家の作品もあわせて紹介する展覧会も同時に始まります。明治150年の今年2018年は、薩長土肥でイベントが目白押しです。
岡田三郎助は1869(明治2)年に現在の佐賀市で生まれた洋画家です。黒田清輝を中心に発足した「白馬会」に参加し、印象派のような明るいタッチや女性ヌードなど、当時としては革新的な表現で主に大正時代に活躍しました。白馬会にはほぼ同世代の藤島武二や和田英作も参加しており、日本の近代洋画界をリードする存在でした。
彼は洋画家ですが、モデルの女性は和装がとても多いことが特徴です。肌を大胆にさらした描写やヌードもありますが、とても芸術的で気品のある画風です。切手になったことで特に有名なブリヂストン美術館所蔵の「婦人像」は、つつみを打つ凛とした女性の表情がとても印象的です。彼の画風がとてもよく表れています。
【公式サイトの画像】 ブリヂストン美術館「婦人像」
佐賀県立美術館には岡田三郎助の作品を入れ替えながら常設展示する「OKADA-ROOM」があります。室内の様子と展示作品は、インドアビューで行きたい方向に進み、見たい部分を拡大して見ることができます。
【公式サイト】 OKADA-ROOM インドアビュー
2018年3月17日(土)からは「温故維新-美・技のSAGA-」、2018年4月1日(日)からは「はじまりはここからー岡田三郎助と女性画家たちー」と2つの展覧会が始まります。いずれも岡田三郎助の作品をはじめ、彼と親交のあった画家、彼が育てた画家、佐賀ゆかりの画家たちの作品がたっぷりと展示されます。
肥前さが幕末維新博覧会特別展「温故維新-美・技のSAGA-」
会期:2018年3月17日(土)~5月13日(日)
http://biwaza-saga.com/onkoishin.html
肥前さが幕末維新博覧会特別展「はじまりはここからー岡田三郎助と女性画家たちー」
会期:2018年4月1日(日)~5月20日(日)
http://biwaza-saga.com/olada.html
佐賀県立美術館は県立博物館と建物がつながっていますが、博物館の隣に「岡田三郎助アトリエ」が移築されます。女性画家の三岸節子、いわさきちひろらが岡田三郎助から師事を受け、巣立っていったアトリエです。
【公式サイトへのリンク】 岡田三郎助アトリエ
岡田三郎助は1937(昭和12)年、藤島武二、竹内栖鳳、横山大観とともに第1回の文化勲章を受章します。その2年後にこの世を去りますが、大正から昭和にかけての日本の洋画界を支える存在でした。彼の作品が佐賀に集結しています。洋画ファンでなくとも必見のスポットです。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
美しい女性画を生み出した岡田の伝記
佐賀県立博物館・美術館
http://saga-museum.jp/museum/
原則休館日:月曜日(2019/1/15以降)、年末年始、展示替え期間
※美術館は2017/11/6~2018/3/16は工事のため休館です。
※展示作品は、展示期間が限られているものがあります。
※博物館・美術館は建物が連結し、一体運営されています。
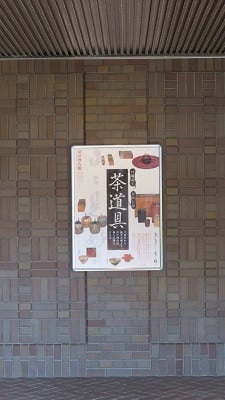
回廊の先に展示室があります
京都・鹿ケ谷の泉屋博古館で「付属品と楽しむ茶道具」展が始まりました。茶碗や釜など茶道具そのものだけでなく、箱書き・極め・袋など茶道具の価値を伝えたり、茶道具と合わせて鑑賞した「付属品」にもスポットをあてていることがこの展覧会の面白いところです。
後水尾天皇の「二条城行幸図屏風」と合わせ、江戸時代初期の茶の湯ワールドがとてもよくわかる展覧会です。
【公式サイトの画像】 二条城行幸図屏風
展示順の冒頭で、この館の“名物”である「二条城行幸図屏風」が出迎えてくれます。前期展示はレプリカですが、後期展示は原本が展示されます。最新技術を駆使した屏風のレプリカは、写真撮影したものをインクジェット出力し、表装の仕上げは職人が行っています。言われない限りレプリカとは気づかないレベルの出来栄えです。
一点数千万円のコストがかかりますが、長期展示に耐えない日本絵画の展示頻度を大きく高めることができる素晴らしい技術です。ぜひ応援したいものです。
この屏風のモチーフとなった後水尾天皇の行幸が行われたのは、1626(寛永3)年でした。後水尾天皇と秀忠の娘・和子夫妻を招く行幸を、徳川幕府の威信をかけて行ったものです。二条城の現在の姿は、この行幸のために改装されたものです。豊臣の世は終わったものの政治経済は安定し、京都は日本文化の中心となって繁栄を謳歌していました。
武家・公家・大寺院・富裕な町衆といった上流階級は、茶の湯を通じた交際を一層盛んにし、権威のある茶道具の需要が爆発的に増えた時代でもありました。しかし秀吉時代以前の東山御物を含む最高クラスは持ち主が手放すはずはなく、流通しません。この需給ギャップに応えたのが、作事家としても著名な小堀遠州こと小堀政一(こぼりまさかず)です。
千利休、古田織部、織田有楽斎と続く茶の湯界のリーダーは、寛永時代には小堀遠州がその地位を築いていました。遠州は自ら目を付けた名品に和歌や古典文学に因んだ名前、すなわち「銘」を付けて箱書きを行い、新たな“名物”として世に送り出します。そのため遠州の箱書きはとてもたくさん残されています。
【公式サイトの画像】 唐物文琳茶入 銘「若草」
唐物文琳茶入・銘「若草」は、遠州とも親交があり、家康~家光の三代に渡って将軍のブレーンとなった金地院崇伝(こんちいんすうでん)の旧蔵品です。江戸時代初期の茶道具の流行がどんなものであったか今に伝える銘品です。
本体の茶入れは赤い盆にのせられたとても小さな壺です。何重にも箱に入れられ、最後はスーツケースのような大きな箱に収まっています。箱書きが増える、茶入れを包む仕覆(しふく)が増える、その茶道具の鑑定書である「極め書き」が加わる、などの要因でどんどん箱の数が増えていった結果です。
大切なものは「包む」という日本文化の特徴を強く実感させる展示です。西洋文化では存在しない価値観で、箱書きを大切にすること自体がとても不思議がられます。西洋文化にはそのモノが積み重ねてきた縁起(経緯)により、モノの良し悪しを権威付けしようという価値観はありません。なぜそんなに日本と異なるのだろうと考えると、文化というものの奥行きの深さに改めて感服してしまいます。
【公式サイトの画像】 千宗旦「日々是好日」
三千家の祖・千宗旦による一行書「日々是好日」は、独特の筆跡がとてもオーラを発しています。千宗旦は権力者への仕官もせず、とてもストイックな茶の湯修行に打ち込んだことから「乞食宗旦」と呼ばれていました。ほぼ同世代で時代の寵児となった小堀遠州とは対照的です。筆跡に優雅さや豪放さは感じません。しかし僧が書いた書のように、字に魂を感じます。
後陽成天皇による一行書「雪月花」ほか、多くの書も展示されています。それぞれの筆者の生き様を感じることができます。茶会を盛り上げるために数寄者が蒐集に熱中した品々を見ていると、とてもマニアックにも感じます。しかし一品一品には確かな美しさがあります。そんな美しさを堪能できる展覧会です。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
茶道具管理のバイブル
泉屋博古館(京都)本館
「付属品とたのしむ茶道具 ~千宗旦から松平不昧まで、江戸時代の茶人の書とともに」
https://www.sen-oku.or.jp/kyoto/program/
主催:泉屋博古館
会期:2018年3月3日(土)~5月6日(日)
原則休館日:月曜日
※展示作品は、3/25までの前期と3/27以降の後期で一部入れ替えがあります。
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。

細見美術館が持つ見事なコレクションを披露する開館20周年記念展の第二弾、「抱一の花・其一の鳥」が始まりました。細見美術館の江戸琳派のコレクションは、若冲コレクションとともに日本でも有数です。
同じ琳派でも、宗達・光琳ら京都の絵師たちによる雅さとは異なる表現が江戸琳派の絵師にはあります。時代が後でもあり、画風がとても洗練されています。抱一は、京琳派や円山・四条派など偉大な先輩たちの作品をとても熱心に研究しました。江戸琳派の作品にはそんな研究成果がよく表れています。京琳派からどのように差別化を図ったのか、京都・岡崎に足を運んで確認してみてください。
展覧会は、タイトルにもつけられているように江戸琳派の二代巨頭・酒井抱一と鈴木其一の作品を中心に構成されています。春夏秋冬と季節を追って展示されています。植物と鳥をモチーフにした作品、いわゆる「花鳥図(かちょうず)」が多いことに気づかれる方も多いでしょう。
京琳派は植物と動物を一緒にモチーフにした作品は多くありません。しかし若冲や円山派など京琳派より後の京都画壇では「花鳥図」は珍しくはなくなります。
どうやったら光琳を上回る表現ができるのか、抱一は来る日も来る日も考えていたことでしょう。江戸琳派の画風は洗練されています。モチーフが持つ美しさを情緒豊かに表現しています。動植物を巧みに組み合わせ、季節感の表現を重視しています。抱一は俳人でもあり、俳句で言う季語を絵の中でどうやって表現するかを考えたのでしょう。
鈴木其一の「藤花図」は、藤棚から垂れ下がる満開の薄紫色の花を掛軸に一杯に描いています。余白は少なく藤の花の存在感がとても強調されています。藤が満開となる5月上旬の少し前にこの掛軸が床の間を飾っていると、ぽかぽか陽気が近づいていることをストレートに感じさせます。
しかし京で重視された雅さは表現にはありません。伝統的なやまと絵の平面的な描写ではなく、写実的です。京の貴族階級が喜ぶ特別な空間やモチーフを描いたものでもありません。江戸琳派は、モチーフ表現がとてもわかりやすくてカッコいいのです。
【公式サイトの画像】 展覧会チラシ裏面 鈴木其一「藤花図」
抱一の「雪中檜に小禽図」は、彼が京琳派や円山派をよく研究していたことを感じさせる作品です。ヒノキの枝葉に雪が積もっている描写は、円山応挙の「雪松図」の雪の描写を彷彿とさせます。スタイルよく伸びる幹はファッションモデルのようにすらりとしています。琳派の特徴的な技法「たらしこみ」をふんだんに用いることで、まさに木が生きていると感じさせる豊かな表情に仕上げています。
この絵にも優雅さは感じません。でも、とてもカッコいいのです。冬の床の間でいただく茶の味を、とても引き締めてくれるような絵です。
其一と並ぶ抱一の高弟だった池田孤邨(いけだこそん)の「四季草花流水図屛風」は、金碧画の中に光琳のような平面的な川を描いています。一方、草花の描写がとても写実的で洗練されています。京の雅と江戸の洒脱を一緒に詰め込んだようで、とても興味深い作品です。
【公式サイトの画像】 展覧会の見どころ
酒井抱一「雪中檜に小禽図」
池田孤邨「四季草花流水図屛風」
武家や豪商など、江戸のクライアントの好みがよくわかります。琳派は後世になるほどどんどん洗練されていく、このことがとてもよくわかる展覧会です。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
細見の琳派コレクションの集大成図録
細見美術館
開館20周年記念展II 細見コレクションの江戸絵画 「抱一の花・其一の鳥」
http://www.emuseum.or.jp/exhibition/ex058/index.html
主催:細見美術館、京都新聞
会期:2018年3月3日(土)~4月15日(日)
原則休館日:月曜日
※展示作品には、展示期間が限られているものがあります。
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。

ターナー展が三条通にやってきた
京都文化博物館で「ターナー展」が始まっています。ターナーはイギリスで最も尊敬される画家の一人で、空気と光を絶妙に表現した風景画にファンが少なくありません。
今回はスコットランド国立美術館の所有作を中心に世界中から作品が集められています。西洋絵画では珍しいターナーが得意とした水彩画には、油絵にはないほのぼの感があふれています。日本国内でターナー作品のコレクションで知られる郡山市立美術館からの出展作品も注目です。
イギリスは絵画に対する嗜好が、他の欧州諸国とは少し異なるところがあります。1つ目が「風景画」です。欧州では伝統的に歴史・宗教・肖像画が重視されましたが、それらは国王・領主・教会等の権力者からの依頼で制作されていました。風景画が一般的になったのは、19c後半にフランスで印象派が認められてからです。
それ以前の数少ない風景画家としては、17c半ばのオランダにロイスダールがいました。雄大な雲の表現で知られる彼は、貿易で大金持ちになった市民階級が好んだ風景画のニーズに応えました。また18c前半ヴェネツィアのカナレットは、観光土産としてまるで写真のような風景画を、工房を指揮して量産しました。彼が西洋画家の中でも指折りの多作で知られるのはこのためです。
ターナーの時代のイギリスも、オランダと同じく市民階級が台頭していました。市民階級が台頭すると、旅への郷愁を誘う風景画が流行します。日本の広重の浮世絵・東海道五十三次も同じです。ターナーはまさに風景画ニーズが大きくなる時代に生まれてきました。ターナーとほぼ同世代のイギリスの風景画家・コンスタブルが人気を博したのも、そうしたニーズに応えることができたためです。
イギリスの絵画嗜好の特徴の2つ目は「水彩画」です。水彩画は古くからありましたが、18cのイギリスでは、旅行土産・出版物への掲載・探検や測量の記録といったニーズで水彩画が大きく普及しました。油絵に比べてより早く大量に簡単に描けるからです。
ターナーはこのイギリス絵画の特徴である2つを極めた画家でした。2020年に発行される新ポンド紙幣に彼の自画像が採用されるようです。イギリス国内でどれ程の尊敬を集めているかがよくわかります。
【公式サイトの画像】 「風下側の海辺にいる漁師たち、時化模様」
ターナーは、イギリス国内はもちろん、欧州大陸各地を旅して風景をスケッチしました。中でも1819年のイタリア旅行で感じた明るい陽光は大いに彼を刺激したようです、以降、光をより際立たせる傾向が出てくるようになります。
「風下側の海辺にいる漁師たち」はイタリア旅行前の1802年の作品です。彼はロマン主義と言われるように、荒波と戦う漁師たちの姿を何ら美化することなく赤裸々に描いています。この時点ではまだ光の表現は際立って強くはありません。
【作品所蔵先公式サイトの画像】 東京富士美術館「ヘレヴーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号」
「ユトレヒトシティ号」は1832年の作品です。帆を一杯に掲げて力強く出航する船に、見事な光のスポットライトを当てています。彼は1851年に亡くなるまで、さらに光を強調して描くようになります。この光の使い方ゆえに、印象派の先駆者と言われることもあります。モネ達フランスの印象派の画家がどの程度ターナーの作品を見ていたか、いつか調べてみたいと思います。
他にもほのぼのとした水彩画や版画がとてもたくさん出品されています。
ぜひ足を運んでみてください。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
名作はなぜ名作に見えるのか?
京都文化博物館 「ターナー 風景の詩」展
http://www.bunpaku.or.jp/exhi_special_post/turner/
https://turner2018.com/
主催:京都府、京都文化博物館、毎日新聞社、MBS、京都新聞、スコットランド国立美術館群
会期:2018年2月17日(土)〜4月15日(日)
原則休館日:月曜日
※展示作品は、展示期間が限られているものがあります。
※この展覧会は、福岡(北九州市立美術館)展終了後、京都に巡回しました。京都展終了後は、東京(東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館)、福島(郡山市立美術館)に巡回します。

好奇心を刺激する京博の入口看板
京都国立博物館で、豪商から寄贈されたコレクションを展示する「豪商の蔵」展が始まっています。寄贈したのは、大阪南部の関西空港に近い貝塚で、大正時代に巨万の富を築いた廣海(ひろみ)家です。4棟もあった土蔵を6年かけて京博が調査し、寄贈手続きも完了したことからお披露目となりました。
書画、茶道具、婚礼調度品など富裕層の暮らしぶりを垣間見ることができます。また質の高い品揃えは家柄のよさを感じさせます。宴会用の器が数十人分揃っている姿は圧巻です。豪商のコレクションがまとまって寄贈されたことはとても意味があることがわかります。
貝塚は岸和田のすぐ南にあり、江戸時代は本願寺の貝塚御坊が治める寺内町(じないちょう)でした。寺が領地の自治を行う寺内町は、浄土真宗によく見られます。大阪・富田林御坊、奈良・今井御坊、三重・津(一身田)などが著名です。古い街並みが遺されていることも多く、富田林や今井は重伝建(重要伝統的建造物群保存地区)に指定されています。
廣海家は、幕末に肥料商から始め、大正時代に金融業で大きく発展しました。幕末から明治初期にかけて建てられた建物が800坪近い敷地にほぼ残っており、国の登録有形文化財に指定されています。今まで火災・戦災・家業の傾きといった美術品が失われる危機を自力で回避されてきましたが、これからは京博に居所を移して大切に守られることになります。
展示はコレクションのゆかりによって、6つの章に分かれています。第二章は茶の湯に関する展示です。交際の手段として、また数寄者としても少しずつ揃えたであろう茶道具は、質の高さを感じさせます。代々の主人が茶道具を大切にしていたことがわかります。伊藤若冲の「筍図」は茶会の際に床の間を飾ったのでしょう、茶室の雰囲気をより落ち着かせる深みのある作品です。
第三章は宴会用具です。椀や皿は、それ自体が美しくても1点だけなら中々目立ちません。廣海家では一度の宴会に必要な数十人分のセットをきちんと保管していたため、展示でも数十点の皿や椀が一堂に並べられています。座敷で大勢の客人が盛り上がっている様子が浮かんでくるようで、圧巻のビューです。
酒井抱一が尾形光琳作品の図録として出版した「光琳百図」に載っているデザインを用いた漆椀も展示されています。とても深みのある漆黒の上に、金色の蒔絵で上品に紋様が表現されています。このデザインを見るだけで、中に入っている吸い物をおいしいと感じさせる効果があると思える絶品です
第五章の嫁入り道具も素晴らしい展示です。展覧会チラシに採用された「四季草花図屏風」は、とても上品で暖かみがあります。華やかな婚礼の場でも存在感を発揮したことでしょう。江戸時代半ばに大坂で活躍した狩野派の絵師・大岡春卜の作品です。
【公式サイトの画像】 大岡春卜「四季草花図屏風」
京博館内の茶室で催される茶会に、今後廣海家から寄贈された茶道具が使われるそうです。京博のサイトをチェックしてみてください。
【公式サイト】 京都国立博物館|イベント

キヤノン綴プロジェクトも要チェック
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
京都国立博物館
特別企画 貝塚廣海家コレクション受贈記念
「豪商の蔵」 ─美しい暮らしの遺産─
http://www.kyohaku.go.jp/jp/project/hiromike_2018.html
会期:2018年2月3日(土)~3月18日(日)
原則休館日:月曜日
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。

西域を感じさせる造形美はエキゾチック
大阪市立東洋陶磁美術館で「唐代胡人俑(こじんよう)」展が行われています。「胡人」とは、中国から見た北方や西方を中心とした異民族を指します。「俑」とは被葬者をあの世で慰めるために墓に副葬された陶製の人形のことで、西安にある秦の始皇帝の「兵馬俑」が特に有名です。
この展覧会では、西安からさらに西の甘粛省で発見された唐時代の将軍の墓の出土品60点を、胡人俑を中心に展示しています。いかにも西域の民族を感じさせる顔の表情や衣装の造形美は、異民族の神秘性が表現されています。
漢民族を感じさせる兵馬俑とは明らかに異なり、奈良の正倉院に伝わる神楽面の趣の方により近しいことがわかります。実物のオーラを体験するまで、きっとワクワクすること間違いなしです。
シルクロードを通じた交易は長らくソグド人が中心でした。ソグド人は現在の中国の西隣の国・タジキスタンに住んでいた民族ですが、定住にこだわらずシルクロード全域で交易に携わっていました。
中国の漢民族は匈奴・突厥・ウイグルといった異民族の侵入にしばしば悩まされ、「万里の長城」を築いたことはよく知られています。ソグド人も異民族ですが、政治的に漢民族に対抗するようなことはしませんでした。それどころかペルシャ(現在のイラン)やトルコから明らかに中国文化とは異なる珍品をもたらしたことで、中国では好意的にとらえられていたようです。
ソグド人は多民族との同化が進んだため、現代ではほぼ民族として存在しません。しかしこの展覧会の胡人俑は、出土した時代や場所をふまえて、今はなきソグド人の文化や風俗を表現したものと考えても大きな間違いはないでしょう。

出品作品の画像
【画像出典】 展覧会チラシPDF
胡人俑の目の堀は深く鼻も高い、明らかにインド・ヨーロッパ系民族の顔です。ポーズもとても多様です。ガッツポーズ、どや顔、やったあ、現代の日本人の価値観では様々な意味が連想されます。しかし果たして何を示しているのかは作った人に聞かないとわかりません。
ミステリアスではありますが、どの胡人俑もとても生命力にあふれています。とても生活を楽しんでいたであろうことが想像できます。衣装もエキゾチックです。中国国内ではとても目立ったでしょう。1300年前の中国の異国情緒をリアルに現代に伝えてくれます。
胡人以外にもラクダなど様々な動物の俑も出展されています。ラクダはとても足が長く、唐三彩のラクダよりもスマートでカッコいいです。馬も筋肉美がリアルに表現されており、とても速く走れそうに見えます。ラクダも馬も、当時のソグド人にとって大切な交易商品でした。商品サンプルとして、中国にはない表現でいかにも目を引くよう造形したのかもしれません。
女性の俑も天平時代の吉祥天のように頬がとてもふくよかです。日本に残る天平絵画の表現が、西域の文化の影響を強く受けていることが確信できます。

国立国際美術館との連携企画「いまを表現する人間像」の展示
会場内では、近隣の国立国際美術館との連携企画で“現代の人間の像”が展示されています。ぜひ唐代胡人俑と表現の違いを見比べてください。ワクワク感に見事にこたえてくれる展覧会です。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
平山郁夫が考える玄奘の西域への旅
大阪市立東洋陶磁美術館
開館35周年記念・日中国交正常化45周年記念特別展
「唐代胡人俑―シルクロードを駆けた夢」
http://www.moco.or.jp/exhibition/current/?e=440
主催:大阪市立東洋陶磁美術館、甘粛省文物局、NHK大阪放送局、NHKプラネット近畿、朝日新聞社
会期:2017年12月16日(土)~2018年3月25日(日)
原則休館日:月曜日、2017/12/28~2018/1/4
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。

奈良博の冬恒例の「お水取り展」に、今年は「芦雪の襖絵」がプラス
関西のテレビ・新聞報道でほぼ100%「春の訪れを告げる」と枕詞がつけられる東大寺の「お水取り」は今年で1267回目です。奈良時代の752(天平勝宝4)年に始まって以来、一度も途絶えることなく続けられている宗教行事です。驚異的な持続性はおそらく世界一でしょう。
奈良国立博物館でもここ20年ほど、冬に特別陳列「お水取り」を行っています。お水取りは通称で正式には「修二会(しゅにえ)」と言いますが、とても奥が深い修二会を理解するにはもってこいの展示構成になっています。

お水取りで使われる「お松明」が入口を飾る
東新館2階の会場に入ると、僧侶の心地よい読経が聞こえてきます。会場の中心に二月堂の内陣が再現されており、修二会期間中の様々な儀式で読み上げられる声明が流されています。二月堂で普段お参りできるのは外陣だけです。内陣は絶対秘仏の「十一面観音」が納められており、修二会に参加する僧以外は入ることができません。荘厳で神秘的な修二会の儀式の様子がとてもよくわかります。
「十一面観音」は近世以降に絶対秘仏になったようで、誰もお姿を見たことはありません。そのため文化財指定もされておらず、日本トップクラスの究極の“絶対秘仏”の一つです。室町時代に描かれた「二月堂曼荼羅」からは、そのお姿を想像することができます。二月堂の真上に雲に乗って現れた観音様の子供のようなお顔が印象的です。チラシの表紙にも採用されています。
「二月堂修中過去帳(しゅうちゅうかこちょう)」と「二月堂神名帳(じんみょうちょう)」も積み重ねてきた歴史の重みを感じさせます。「過去帳」は東大寺や二月堂にゆかりのあった人の名前が奈良時代の創建当初から順に書き足されており、日本史の教科書のように次々と著名人の名前が現れます。展示されるのはこの中の一部ですが、仏師の運慶や快慶の名前も見えます。
「神名帳」は二月堂の守護神として勘定する日本中の神々のリストです。いずれも修二会期間中に延々と読み上げられ、その節やリズムの聞き心地にファンも少なくありません。
【公式サイトの画像】 「お水取り」主な出陳品
西新館2階は「薬師寺の名画」の会場です。「福寿院」は明治まで薬師寺にあった塔頭で、長澤芦雪と奈良で活躍した画僧・明誉古磵(みょうよこかん)による襖絵だけが薬師寺に伝わっています。薬師寺の鎮守・休ヶ岡八幡宮に伝わる「板絵神像」とともに修復作業を終え、公開されています。
奈良の寺にある江戸時代の襖絵が公開されている例はあまり多くなく、貴重な機会です。芦雪が代表作を残した南紀滞在後の作品で、「松虎図」の虎の目にはまさに芦雪らしい愛くるしさを感じることができます。古磵の「富士図」は、芦雪の「松虎図」の裏面に描かれていたものです。当時の上方の人がほとんど見たことがない富士山への郷愁を誘うように、山の精神性を強調して描かれています。
【公式サイトの画像】 「薬師寺の名画」主な出陳品
冬の奈良は空気がきれいです。山焼の名残が残る若草山が「黒く」見えるのは2月だけです。奈良博からよく見えます。ぜひ訪れてみてください。

山焼きで焦げた芝生が残る2月の若草山
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
日本の仏教寺院の法会の原点はとても奥が深い
奈良国立博物館 特別陳列「お水取り」
http://www.narahaku.go.jp/exhibition/2018toku/omizutori/2018omizutori_index.html
主催:奈良国立博物館、東大寺、仏教美術協会
会期:2018年2月6日(火)~3月14日(水)
原則休館日:2月19日(月)、2月26日(月)
※東大寺二月堂お松明期間中は月曜日も開館
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。
奈良国立博物館 特別陳列「薬師寺の名画 ―板絵神像と長沢芦雪筆旧福寿院障壁画―」
http://www.narahaku.go.jp/exhibition/2018toku/yakushiji/yakushiji_index.html
主催:奈良国立博物館、薬師寺
会期:2018年2月6日(火)~3月14日(水)
原則休館日:2月19日(月)、2月26日(月)
※東大寺二月堂お松明期間中は月曜日も開館
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。
 京都・岡崎にゴッホのシンボルカラー黄色が映える
京都国立近代美術館で「ゴッホ展」が始まりました。「巡りゆく日本の夢」とサブタイトルがつけられているように、ゴッホが憧れた日本、日本人が憧れたゴッホ、それぞれの関連性を丁寧に展示しているのが特徴です。
京都・岡崎にゴッホのシンボルカラー黄色が映える
京都国立近代美術館で「ゴッホ展」が始まりました。「巡りゆく日本の夢」とサブタイトルがつけられているように、ゴッホが憧れた日本、日本人が憧れたゴッホ、それぞれの関連性を丁寧に展示しているのが特徴です。
ゴッホ作品はともかく、ゴッホが影響を受けたと推測される浮世絵やゴッホに憧れた日本人画家の作品、また様々な手紙や書籍など、展示品はとても多岐にわたっています。
これら展示品は、ゴッホのコレクションで世界的に名高いオランダのファン・ゴッホ美術館とクレラー・ミュラー美術館、浮世絵コレクションで世界有数のパリのギメ東洋美術館など、世界中の美術館やコレクターから集められており、とても充実した展示内容になっています。
この展覧会は、ファン・ゴッホ美術館との「国際共同プロジェクト」です。最近の展覧会ではよく見られるようになった外国の美術館・博物館との共同企画の例です。昨年2017年では、あべのハルカス美術館の「北斎展」が大英博物館との共同プロジェクトでした。美術ファンが世界中で増えており、目も肥えてきていることから、より質の高い展覧会を目指す流れがグローバルに起こっていると言えます。
展示は物語のように時間の経過に沿って構成されています。物語はパリでの浮世絵との本格的な出会いから始まります。1886年に弟テオを頼ってパリにやって来たゴッホは、日本美術商として著名だったサミュエル(本名:ジークフリート)・ビングの店で大量の浮世絵を見る機会を得ます。
パリ時代の展示作品では、日本特集の雑誌の表紙をモチーフにした「花魁」で、着物の図柄をとても器用に描いていることが目を引きます。「カフェ・ル・タンブランのアゴスティーナ・セガトーリ」は、筆のタッチが繊細で、“ゴッホはこんな絵も描いたのか”と感じさせる作品です。
またサミュエル・ビングが発行した雑誌「芸術の日本」は、19世紀末の欧州人にとっての理想の日本像がとても美しく表現されています。100年以上前の雑誌ですが、とても保存状態がよく残されています。
【公式サイト】 紹介ゴッホ作品の画像
1888年にアルルに向かうのは、そこに日本のような理想郷があると考えたためでした。ゴッホの代表作「寝室」は、アルルでゴーギャンと共同生活していた「黄色い家」の中のゴッホの寝室です。鮮やかな色彩を平坦に色づけする浮世絵の手法で表現されています。「タラスコンの乗合馬車」も同様に平坦に描かれていますが、主題である馬車がプラモデルのように愛らしく見えてとても印象的です。
ゴッホの絵は1890年に亡くなるまでほとんど売れませんでしたが、20世紀になると売れ始めます。日本国内でも武者小路実篤らの白樺派が熱心に紹介したことでブームが起こりました。1920年代以降、ゴッホの終焉の地・オーヴェールで、ゴッホの主治医だったガシェの家に残されたゴッホ作品を見るために日本人画家が次々と訪れます。
展覧会では、このガシェ家訪問者の芳名録が展示されています。佐伯祐三ら洋画家だけでなく、土田麦僊・橋本関雪ら日本画家の名前も見えます。歌人の斎藤茂吉も訪れています。現代に続く日本人のゴッホ人気が始まった100年前の熱気がひしひしと伝わってきます。
 「森村泰昌、ゴッホの部屋を訪れる」
http://www.momak.go.jp/Japanese/news/2017/gogh-morimura.html
展覧会場の1つ上の階では、実物大のゴッホの寝室のレプリカが展示されています。自らの顔写真を西洋名画の自画像あてはめる作品で知られる森村泰昌の、映画の撮影用に造られたセットです。実によくできています。この作品は写真撮影OKですので、様々なスナップを楽しんでください。京都展限定です。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
「森村泰昌、ゴッホの部屋を訪れる」
http://www.momak.go.jp/Japanese/news/2017/gogh-morimura.html
展覧会場の1つ上の階では、実物大のゴッホの寝室のレプリカが展示されています。自らの顔写真を西洋名画の自画像あてはめる作品で知られる森村泰昌の、映画の撮影用に造られたセットです。実によくできています。この作品は写真撮影OKですので、様々なスナップを楽しんでください。京都展限定です。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
扱いに便利な貼ってはがせるシール式ポスター
京都国立近代美術館 「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」
http://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2017/423.html
http://gogh-japan.jp/
主催:京都国立近代美術館、NHK京都放送局、NHKプラネット近畿、京都新聞
会期:2018年1月20日(土)~3月4日(日)
原則休館日:月曜日
※一部の展示作品は、前期(~2/12)と後期(2/14~)で入れ替えがあります。
※この展覧会は、北海道立近代美術館と東京都美術館(いずれも終了)から巡回してきたものです。
※京都展終了後は、アムステルダムのファン・ゴッホ美術館に巡回します。

2009年オープンの新館は現代的なデザイン
大阪・池田の逸翁美術館で「開館60周年記念展 第五幕 応挙は雪松、呉春は白梅。」が始まりました。逸翁美術館は、阪急東宝グループの創始者・小林一三のコレクションを所蔵・展示する美術館です。「逸翁」とは、一三の雅号(がごう、本名と別につける風雅な相性)です。
開館60周年の昨年から今年2018年5月にかけて、ジャンル毎に6回に分け、コレクションの全貌を公開する展覧会を行っています。5回目は江戸絵画の円山派・四条派で、展覧会のチラシにもなっているように応挙の「雪中松図」、呉春(ごしゅん)の「白梅図」に見応えがあります。
【公式サイトの画像】 展覧会チラシ
円山派は、円山応挙を祖とし、弟子には長沢蘆雪・呉春らがいます。応挙は、伊藤若冲・与謝蕪村・池大雅・曾我蕭白ら同時代の京都で活躍した絵師の中でも、京都の町衆に圧倒的な人気がありました。見た目に忠実で遠近法をも用いた表現はわかりやすく、斬新だったのでしょう。知名度の高さから、応挙の弟子は数百人もいたという説もあるくらいです。
応挙が活躍した江戸時代半ばの18世紀後半以降、京都画壇はほぼ応挙の弟子たちによる流派で占められるといっても過言ではありません。竹内栖鳳・上村松園ら近代の画家を経て、現在まで連綿と続いています。
四条派は、応挙の弟子たちの中でも特に大きな流派でした。祖である呉春のもとにこれまた多くの弟子が集まったからです。彼らは四条通近辺に居を構えたことから「四条派」と呼ばれます。
呉春は当初は文人画の巨匠である与謝蕪村の弟子でしたが、蕪村の死後に応挙と出会います。蕪村のユーモアのある表現に応挙の写実性をミックスした画風を確立していき、応挙の死後は京都一の人気絵師となります。目の肥えた京都の町衆は、一世風靡した応挙の写生画に遊びの要素を加えた呉春を、次世代のスターとして支持したのです。
展覧会では、順路前半に円山派、後半に四条派の作品が展示されており、一括して語られがちな両派を対比できるよう構成されています。まず応挙の「月雁図」が目に留まります。飛んでいた雁が、飛行機の着陸のように、首を水平にして尾と足から着水する瞬間を描いたものです。実際の雁もこのように着水するため、応挙は徹底して観察したと考えられます。とにかく写生にこだわった応挙の個性がとてもよく出ている作品です。
応挙の「雪中松図」を見ると、「どこかで見たことがある」とお感じの方が多いでしょう。三井記念美術館蔵の国宝「雪松図屏風」の習作(練習に描いた作品)です。習作も松の枝についた雪の質感の表現はとても見事です。
「雪中松図」の向かい側には、呉春の代表作の重文「白梅図」があります。藍色に染めた糸を平織した画面に描いており、縦方向の織り目が夜のとばりを感じさせます。白梅は小さいながらもつぼみ・開花が丁寧に描き分けられており、幻想的ですがどこか洒脱さも感じさせます。
呉春の弟子で、実弟でもある松村景文(まつむらけいぶん)の花鳥画もおすすめです。写生画に耽美的な要素が加わっていることがわかります。他にも、円山派の長沢蘆雪・渡辺南岳・山口素絢、四条派の岡本豊彦・横山清暉らが出品されており、絵師たちの個性の違いと逸翁コレクションの奥の深さがよくわかります。
応挙は亀岡の農家の次男坊出身で、生真面目で娯楽には無頓着でした。一方の呉春は京都で小判を鋳造ずる金座の家に生まれた裕福な都会の“ぼん”で、俳諧・謡曲などもたしなみ社交的でした。両社の個性の違いはとても面白いです。呉春は一時期池田に滞在しており、一三も何か縁を感じたのやもしれません。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
逸翁と福岡市美術館が所蔵するほぼ同世代の二人の名経営者のコレクション集
逸翁美術館 「開館60周年記念展 第五幕 応挙は雪松、呉春は白梅。」
http://www.hankyu-bunka.or.jp/itsuo-museum/exhibition/1792/
主催:阪急文化財団
会期:2018年1月20日(土)~3月11日(日)
原則休館日:月曜日
※展示作品は、展示期間が限られているものがあります。
※この展覧会は、他会場への巡回はありません。

「小林一三ワールドII」展ポスターの顔はとても優しい
2017年から阪急グループでは、創設者の小林一三(こばやしいちぞう)の没後60年を記念して、様々なイベントを開催しています。2018年1月10日~15日には阪急百貨店うめだ本店で、一三のとても幅広い交友ネットワークを紹介した「小林一三ワールドII」展が開かれています。
一三は松下幸之助と並んで、現代に続く日本人の生活スタイルを創造した事業家です。驚くほどの各界の著名人との交流ネットワークがあり、育てたスター芸能人も数知れません。そうした事業・交友を通じて蓄積された娯楽文化は、まさに20世紀の日本人の生活スタイルの歴史でもあります。そんな一三が残した歴史をご紹介したいと思います。
うめだ阪急の「小林一三ワールドII」展のポスターには、花を生ける晩年の一三の写真が採用されています。花を持つ手はとても優しく、顔の表情もとても温和です。これだけの大企業の経営者と言うと、とても威厳のある顔を想像しますが、まったくそんなことはありません。
たれ目で人なつっこそうな顔を見ると、私は「おばさん」のように見えてなりません。「何が面白いか、どうやったら生活が便利になるか」という発想は、一般に男性よりも女性の方が長けています。一三は「何が面白いか、どうやったら生活が便利になるか」を事業として軌道に乗せました。女性的な発想がないと、ここまではできなかったように思えます。だからこそ「おばさん」に見えてならないのです。
一三の幅広い交流ネットワークから特に100人を選んで、うめだ阪急の展覧会や公式サイトで紹介しています。戦後の日本の映画界を盛り上げた女優たちの多くは宝塚歌劇団出身でした。扇千景は、自分の身の振り方を考えさせてくれたエピソードで、一三を「校長先生」と呼んでいます。他にも有馬稲子や原節子、越路吹雪など数多くのスター女優を育てたことが、とてもよくわかります
【公式サイト】 一三ネットワークの100人
当時のトップクラス文化人でもあった財界の大物との、茶道や事業を通じた交流も見事です。一三の郷里・山梨県の先輩実業家でもある東武鉄道の根津嘉一郎、荏原製作所の畠山一清、三井財閥の益田孝、川崎造船の松方幸次郎など、そうそうたるメンバーです。現代に多くのかけがえのない美術品を残した名経営者の審美眼から、一三は多くの価値観を吸収したことでしょう。
自ら開発した郊外住宅地の池田にある一三の旧邸は現在、「小林一三記念館」として公開されています。1937(昭和12)年建築の本館は、芸術と生活とを一体に楽しむ思いを込め「雅俗山荘」と名付けられています。外見は洋館ですが、内部は和洋を巧みに組み合わせた設えで、とても優しい空間になっています。一三の美的センスと人となりがよくわかります。
一三が蒐集した美術品は、2009年まで現・小林一三記念館で公開されていましたが、現在はすぐ近くの逸翁(いつおう)美術館に移されています。中世から江戸時代の日本絵画や茶道具を中心に、茶室に飾ると実に見事な作品が揃っています。
館の目玉でもある江戸時代半ばの呉春や与謝蕪村のコレクションは、「開館60周年記念展」として1月20日から公開されます。呉春の代表作である重文「白梅図屏風」ももちろん登場します。とても楽しみな展覧会です。
【公式サイト】 逸翁美術館開館60周年記念展 第五幕「応挙は雪松、呉春は白梅。」
新しいことを想像して人々に認めてもらうことのすばらしさを、教えてくれる偉大な人物です。何か迷いがあったような時でも、普通の時でも、ぜひ会いに行ってみてください。
うめだ阪急「小林一三ワールドII」展の入口の設えは人目をひく。とても上手。
こんなところがあったのか。
日本にも世界にも、唯一無二の「美」はたくさん。
自ら語る「顧客とは創造するものなり」の軌跡
小林一三について(阪急文化財団サイト)
http://www.hankyu-bunka.or.jp/about/itsuo/
小林一三記念館
http://www.hankyu-bunka.or.jp/kinenkan/





























