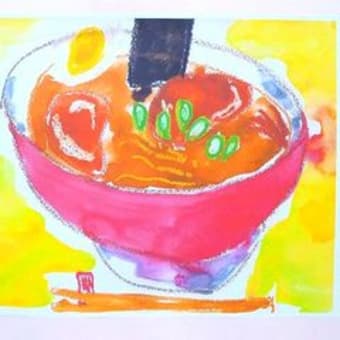3391.~方策を練る~
「知的障害・発達障害をもつ生徒さんの 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック・発達支援教室 Elephas(エレファース)
・・・明るく、楽しく、さわやかに・・・
~今日のElephasブログ:「状況や目標に合わせて」(2月20日)
おはようございます。所沢教室の増原です。
読解学習。ひとつ上のテキストへと移行したばかりの生徒さんには無理なくステップアップできるように、音読の前に読み聞かせをしたり、問題に該当する本文を一緒に確認し、キーワードや助詞に印をつける等のサポートをしていきます。
同じ課題を複数回繰り返すことで、やがて一人でもスムーズに取り組めるようになります。
また、小数の3桁同士の計算問題をミスなく進めていた生徒さんが、文章題になると答えが合わないということがありました。
原因は余白に筆算を書く際に、計算記号を最初の数字の下に書いてしまうことでした。
計算問題では筆算やマス目が書かれているので計算記号の位置に気がつかず、盲点になっていました。
そこで、数字を書いてから最後に記号を書くようにすると間違えることはなくなりました。
生徒さんの状況や目標に合わせ、たし算の発想ばかりでなくひき算の発想も取り入れながら、
準備、指導に当たっていかなくては、とあらためて思いました。
◇ワンポイント・メッセージ◇
そうですね。新しい課題に進ませるときには、十分、モデリングを行うことが肝要です。また、学習の躓きを正すためには、躓きの起因を把握することが肝要です。何れにしても生徒さんの個別の心情と認知・認識構造に基づいて指導の方策を練ること、これが講師としての技術の発揮しどころですね。