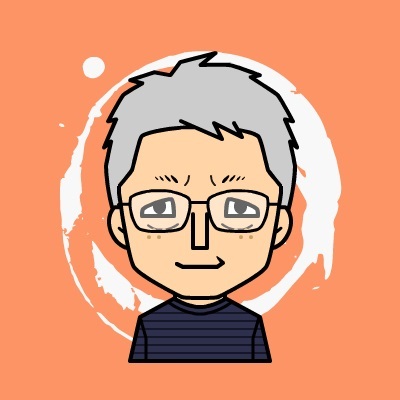NACS-J大阪連絡会の行事に参加しました。
阪急京都線・上牧駅から淀川河川敷に向かい、鵜殿の葦原を観察しました。
その時の一部です。
葦原に行くまでの途中です。
参加者の解説もあって、写した生き物です。
ムネアカアワフキだそうです。
小型のアワフキムシで、幼虫は各種のサクラの小枝に巣を作って中に潜みます。
成虫もサクラで見かけることが多いとあります。

カタバミです。
葉の赤いのをアカカタバミと言うと思っていましたが、花の中心が赤っぽいのをアカカタバミと言うそうです。
カタバミです。

アカカタバミです。

テントウムシです。
ナミテントウの赤型だと思います。

ギシギシの葉っぱをボロボロにしていたのは、コガタルリハムシの幼虫の様です。

黒色で、胸部に赤い紋があるのでキクスイカミキリかな。

いよいよ、河川敷です。
鵜殿の説明がありました。

鵜殿の葦原の葦は、雅楽の篳篥(ヒチリキ)の材料になっている貴重な存在と言う事です。
鵜殿のヨシは特別なヨシかと言うと、遺伝子的には大きな違いは無いそうで、生育環境なのだと言われていました。
太いヨシが出来るには、水環境のバランスが大事だと言う事で、この場所では、そうした管理(保護)が行われています。
なお、新名神高速道路の橋脚の工事が今年の秋から始まる事もあるそうです。
配慮はされると言いますが、来年からは、景観が変わって行きます。
オドリコソウが見られました。

ヒメオドリコソウとは大きさが違います。

アオダイショウの子供ですね。
捕まえたのは、高校生の女子たちです。

管理(導水により水環境を維持)された葦原です。

ノウルシが見られました。

乾燥した場所を歩く観察メンバーです。

ナナホシテントウです。

シデムシです。

お昼ご飯を食べた場所で見られたチュウシャクシギです。

ノアザミかな。紫色が鮮やかでした。

この日は、雨雲が近づいて来ていたので、早めに切りあげて、高槻の駅前で、ビールなどを楽しみました。
お疲れ様でした。