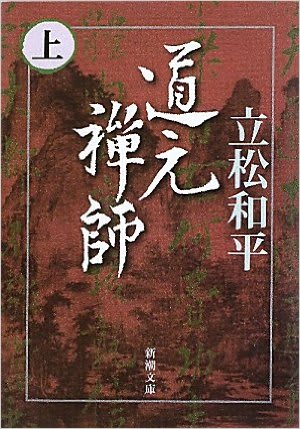手元に、観た映画のメモ帳が一冊ある。
高校1年が終わる頃から22歳の後半までの記録で、題名・監督・主演者と劇場が書いてある。
そのメモの一番初めが『無防備都市』(ロベルト・ロッセリーニ監督、1945年)である。
そして、その三日後が先日書いた『自転車泥棒』(ヴィットリオ・デ・シーカ監督、1948年)となっている。
当時は当然、ビデオもDVDもないから映画館以外で観ようとすれば、ほとんどがテレビとなる。
と言うわけで、この『無防備都市』もテレビで観た作品のひとつである。
第二次世界大戦の後半期、ナチス占領下のローマ。
レジスタンスの軍事リ-ダーであるマンフレディは、ナチス・親衛隊の追跡を逃れて同志のフランチェスコの家に逃げ込んだ。
彼は、500人の仲間のための軍事資金を調達しなければならないが、身動きが取れない。
そこで、シンパのピエトロ神父を橋渡しとして、資金調達はどうにか成功することができた。
翌日、フランチェスコと子連れのピナの結婚式の日。
マンフレディとフランチェスコがいる一帯のビルが親衛隊に包囲され、フランチェスコが捕まった事を知ったピナは、その護送車を追って・・・・
ピナが護送車を必死に追いかけ、無残にも射殺されるシーン。
映画後半の、捕えられたマンフレディに対する拷問。
それでも沈黙を守ったマンフレディ。
それを見続けるよう強制されるピエトロ神父。
そのドアの向こう側で、アルコールを飲んでカードをしているナチスの面々。
人が、自分のために執念を絡めて他人の命を弄ぶ。
ラスト、銃殺刑にされるピエトロ神父。
それを金網越しに見つめる子供たち。そして、無言のまま坂を下って行くこの子供たち。
再度観て、当時、脳裏に焼き付いたままの映像が、そのままここにあった。
神父の最期の言葉「神よ、彼らをお許しください」
しかし、この光景を見た子供たちはこの現実を許すことができるだろうか。
この子たちと共に、私も一緒になってこの作品を記憶し続けなければいけない。
高校1年が終わる頃から22歳の後半までの記録で、題名・監督・主演者と劇場が書いてある。
そのメモの一番初めが『無防備都市』(ロベルト・ロッセリーニ監督、1945年)である。
そして、その三日後が先日書いた『自転車泥棒』(ヴィットリオ・デ・シーカ監督、1948年)となっている。
当時は当然、ビデオもDVDもないから映画館以外で観ようとすれば、ほとんどがテレビとなる。
と言うわけで、この『無防備都市』もテレビで観た作品のひとつである。
第二次世界大戦の後半期、ナチス占領下のローマ。
レジスタンスの軍事リ-ダーであるマンフレディは、ナチス・親衛隊の追跡を逃れて同志のフランチェスコの家に逃げ込んだ。
彼は、500人の仲間のための軍事資金を調達しなければならないが、身動きが取れない。
そこで、シンパのピエトロ神父を橋渡しとして、資金調達はどうにか成功することができた。
翌日、フランチェスコと子連れのピナの結婚式の日。
マンフレディとフランチェスコがいる一帯のビルが親衛隊に包囲され、フランチェスコが捕まった事を知ったピナは、その護送車を追って・・・・
ピナが護送車を必死に追いかけ、無残にも射殺されるシーン。
映画後半の、捕えられたマンフレディに対する拷問。
それでも沈黙を守ったマンフレディ。
それを見続けるよう強制されるピエトロ神父。
そのドアの向こう側で、アルコールを飲んでカードをしているナチスの面々。
人が、自分のために執念を絡めて他人の命を弄ぶ。
ラスト、銃殺刑にされるピエトロ神父。
それを金網越しに見つめる子供たち。そして、無言のまま坂を下って行くこの子供たち。
再度観て、当時、脳裏に焼き付いたままの映像が、そのままここにあった。
神父の最期の言葉「神よ、彼らをお許しください」
しかし、この光景を見た子供たちはこの現実を許すことができるだろうか。
この子たちと共に、私も一緒になってこの作品を記憶し続けなければいけない。