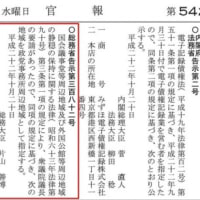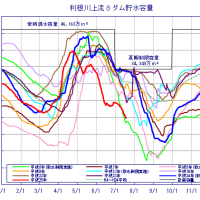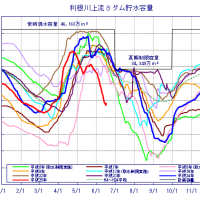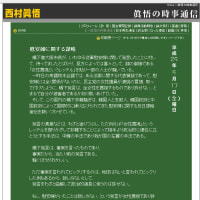櫻井よしこブログ:日本外交はなぜ失敗するのか。日露外交を成功に導く要因は何か Part.1
段階発展説であえて並べるならば、「力治国家」が最もプリミティブな段階だ。力治といっても、要は、法の適用に「力」の裏づけを必要とするという事だ。
次に「人治国家」だが、中国などでは、民には法を適用するが、高位者ほど法を超越し、特権を享受するのが地位上昇のインセンティブとなる。
英米がルールを決めることを重視するのは、ルールに従って「取引」を円滑化する事を重視するからだ。それだけでなく、ルールには成功と勝利の方程式が隠されている。英米では、ルールは、ビジネスを成功させるハイウェイみたいなものなのだ。
#だから、アジア諸国の開国にあたって、ルールの適用遵守を強要したわけだ。ルールの適用遵守が保てない国は、植民地とした。朝鮮に対する評価は最低だったが、日本が引き取ることには賛成した。中国については、疑問が残ったが、あまりに大きすぎ、日本の干渉は斥けられ、救済されてしまった。
ルールがあっても適用の保証がなく、人によってどうにでもなるのが中国。空気を読んで行動することの方が重視されるのが、腹芸の日本だ。
要するに、法の適用における方法論の差異のように思える。いかにして法を権威あらしめるか。力治国家では実力装置が、人治国家では人(高官)が、基準になる。法治国家は一番原則通りで法が基準(その代わり、代理人の交渉が勝負になる)、和治国家では空気が基準になる。和治は、ムラの道徳である。対立を回避する戦略としては有効だし、周り中がその方針だから、何とかなる。
でも、外国との付き合いでは全く意味をなさない。和治もだめ、人治は賄賂を意味するから付き合えない。従って、力治か法治しかない。ただアジアの諸国が植民地でなくなってしまったので、法治も容易なことではない。ロシア・朝鮮・韓国については、力治原理を重視するしかないだろう。
[人気blogランキングに投票]
ロシアを伊藤氏は、“法治国家”の米国、“人治国家”の中国、“和治国家”の日本に対比させて、“力治国家”(rule of violence)と規定する。violenceだから「暴治国家」のような気もするが、少なくとも実力一番では、暴力団に近い。北朝鮮も同じだし、中国も近代では同様じゃないかと思う。
段階発展説であえて並べるならば、「力治国家」が最もプリミティブな段階だ。力治といっても、要は、法の適用に「力」の裏づけを必要とするという事だ。
次に「人治国家」だが、中国などでは、民には法を適用するが、高位者ほど法を超越し、特権を享受するのが地位上昇のインセンティブとなる。
英米がルールを決めることを重視するのは、ルールに従って「取引」を円滑化する事を重視するからだ。それだけでなく、ルールには成功と勝利の方程式が隠されている。英米では、ルールは、ビジネスを成功させるハイウェイみたいなものなのだ。
#だから、アジア諸国の開国にあたって、ルールの適用遵守を強要したわけだ。ルールの適用遵守が保てない国は、植民地とした。朝鮮に対する評価は最低だったが、日本が引き取ることには賛成した。中国については、疑問が残ったが、あまりに大きすぎ、日本の干渉は斥けられ、救済されてしまった。
ルールがあっても適用の保証がなく、人によってどうにでもなるのが中国。空気を読んで行動することの方が重視されるのが、腹芸の日本だ。
要するに、法の適用における方法論の差異のように思える。いかにして法を権威あらしめるか。力治国家では実力装置が、人治国家では人(高官)が、基準になる。法治国家は一番原則通りで法が基準(その代わり、代理人の交渉が勝負になる)、和治国家では空気が基準になる。和治は、ムラの道徳である。対立を回避する戦略としては有効だし、周り中がその方針だから、何とかなる。
でも、外国との付き合いでは全く意味をなさない。和治もだめ、人治は賄賂を意味するから付き合えない。従って、力治か法治しかない。ただアジアの諸国が植民地でなくなってしまったので、法治も容易なことではない。ロシア・朝鮮・韓国については、力治原理を重視するしかないだろう。
[人気blogランキングに投票]