畜産システム研究会報 30号(2006)より改題転載
畜産システム研究会設立20周年を記念して
畜産システム研究会 会長 三谷克之輔
現場の問題は現場の方々とともに考え、学んでいこうという趣旨で活動を始めました畜産システム研究会は、皆様方のご協力とご支援のお陰で設立20周年を迎えることができました。ここに深く感謝し、厚くお礼申し上げます。
畜産システム研究会の初心
畜産システムという名称には、「畜産をシステムとして見る」という意味を持たせました。大学で研究教育を担当している立場からしますと、専門細分化に対する総合化、現場の問題解決につながる研究教育を専門領域として確立したいという願望が込められています。
現場のことを考えるには現場のデータ蓄積が大切ですから、研究会の活動としてはデータとソフトを共有し、会員が蓄積したデータを持ち寄って分析できる情報システムの構築をめざしました。設立当時はMS-DOSの時代でありソフト開発に対する要望も強く、一つのプロトタイプを「SBAR」というデータ管理ソフトとして実現することができました。
もう一つの活動は、酪農を牛乳資源だけではなく、牛肉資源としても最大限に活用する「乳肉複合システム」を確立していくことです。ヨーロッパはこの考え方で乳肉兼用種が飼育されていますが、わが国では北米型ホルスタイン種に和牛を交配することで、乳肉複合をシステムとして構築していこうとするものです。広島大学の農場では、ホルスタイン種に和牛を交配してF1を生産し、F1雌牛を繁殖に利用して生産した子牛(F1クロス)を肥育する試験を1975年から実施していましたので、これをプロトタイプとして現場で生産しながら情報交換をすることで個々の技術を検討し、その成果の一つとして「F1生産の理論と実践(肉牛新報社)」を出版することができました。
F1クロスの生産
F1生産は全国に普及定着しましたが、F1クロスの生産に至るハイブリッド生産システムはまだ全国的な規模では普及していません。鶏のハイブリッド生産に見られるように、牛においてもF1生産は肥育経営の企業化を促進してきました。F1クロスの生産を定着させるためには、種子(精液)の提供だけではなく、肥育素牛と飼育プログラムをセットにして提供していくことが必要なように思います。また、乳牛と同様に肉牛の繁殖も舎飼いで行う方法が一般的ですが、肉牛繁殖は基本的には資源の活用や維持管理の役割にあり、F1クロスの生産も放牧による資源管理を展開していくことを考える必要があるでしょう。
BSE問題への対応
わが国におけるBSEの発生は畜産界だけでなく社会にも大きな衝撃を与えました。BSEは食の安全・安心の視点から畜産を見直す機会となり、生産、流通、消費の関係を再構築していく作業が急速に進展しています。
畜産が社会に信頼されるためには、食の安全あるいはリスクに関して産、官、学、消費者が情報を双方向に共有する必要があります。「情報の共有」は研究会設立当初からの目的ですが、畜産経営の企業化が進行する中で、生産性の向上に必要な情報をオープンに共有することは困難になりました。しかし、食の安全・安心に関する情報はオープンに共有することで、信頼関係を構築することができます。研究会では信頼される畜産をめざし、BSE問題に取り組んでいます。
実学の伝統を受け継ぐ
この研究会の原点は、「現場の問題は現場の方々とともに考える」ことにあります。それは専門細分化し、現場から離れていく農学をなんとか現場につなぎとめたいという切実な思いが原動力になっています。その思いは、農家のために国産鶏を改良し健康なヒナを届けることにひたむきであった父の思いと重なり、またいつも農家とともに歩まれた恩師上坂章次先生の後姿とも重なります。現場研究の一番の専門家は生産者です。「犬馬難鬼魅易」と韓非子の言葉にありますように、現場研究は犬や馬を描くように身近でやさしいと思われがちですが、実は生産者や一般の人に評価されるのは大変で、一般の人には見えない実験科学の方がやさしいということもあります。現場の研究は時間がかかり、成果が認められることも少ないので、大学人が大学人を自己評価するシステムが定着すると、農学を現場につなぎとめるのはますます絶望的なように思われます。しかし、21年目からは事務局を実学の伝統を受け継ぐ京都大学にお引き受けいただくことになりました。生産者や市民に評価される研究に勢いがつき、現場を大切にする若い研究者が育つことを心より期待しています。
設計科学の展開の場
分業化と専門化の壁が現場を見え難くしています。大衆化した大学は、現実世界とつながらない教育研究によって、現実世界から遊離した学生を再生産するサイクルに入ったように思います。今、学術のあり方が問われています。自然科学と社会科学、基礎科学と応用科学といった枠を超えてこれらを融合し、日本学術会議が提唱しているように伝統的な分析的手法による認識科学と、ものを創り、管理する設計科学に再編し、発展していくことが必要だと思います。それは幼稚ながら、畜産システム研究会が求めてきたものであり、歩んできた道でもあります。これまでの研究会は、志はあれども暗中模索の活動の時代でしたが、設計科学の展開を意識した時代へとステップアップしていただきたいと思います。
牛に資源を管理させる
わが国の畜産関係者の間では、家畜を飼うために畜舎を建て、飼料を生産・給与し、糞尿を処理するといった「上げ膳据え膳」が常識となっています。雨が多いことや飼料用穀物を生産していない等が原因ですが、視点を変えて、雑草天国のわが国の里山を管理するために牛を飼うと考えたら、もう一つの畜産が見えてきます。
畜産システム研究会の「里山と牛ML」では、旭川市の斉藤晶牧場を自然の中に生きる牧場のモデルとして学んできました。斉藤晶牧場は酪農として見るより、牛に牧場を拓かせる造園業や不動産業と見ると、畜産の可能性が大きく魅力的に見えてきます。農業はかくあるべしという固定観念から石ころだらけの山を見つめると、厳しい環境に見えますが、自然の営みに身を置いて見直すと宝の山に変わったという斉藤晶さんの牧場は、農業が厳しい環境にあると悩む私たちに、パラダイムの転換が必要なことを教えてくれます。
科学には白紙に「図」を描くように、世界を均質化しグローバル化していく考え方が潜んでいますが、私たちは自然という「地」、歴史、文化、風土という「地」の中で生きています。「地」は場所または場、「図」は要素または関係子で説明することもできます。白紙に同じ牛の図を描く競争よりも、里山(地)と牛(図)の多様な関係を学び、自然の中に生きる畜産を共創していくことが、研究会の柱の一つとして成長していくことを期待しています。
今いる場所をより良い場所にして引き継ぐ
畜産システム研究会報第30号は設立20周年を記念して、今いる畜産の場所を認識し将来を展望するために、畜産システムと科学技術、自然の中に生きる畜産システム、食の安全・安心と畜産システムの3部構成にしました。
畜産の問題を解決していくためには、会員それぞれが所属する組織の当事者として活動される一方で、研究会に参加される場合も、「情報の収集」ではなく「情報の共有」を推進する当事者として活動していただきたいと思います。そのような会員の輪が大きくなることで、畜産が今いる場所を、次の世代にとってより良い魅力ある場所にして引き継ぐことができるのではないでしょうか。夢のある畜産を共に創っていきましょう。
畜産システム研究会設立20周年を記念して
畜産システム研究会 会長 三谷克之輔
現場の問題は現場の方々とともに考え、学んでいこうという趣旨で活動を始めました畜産システム研究会は、皆様方のご協力とご支援のお陰で設立20周年を迎えることができました。ここに深く感謝し、厚くお礼申し上げます。
畜産システム研究会の初心
畜産システムという名称には、「畜産をシステムとして見る」という意味を持たせました。大学で研究教育を担当している立場からしますと、専門細分化に対する総合化、現場の問題解決につながる研究教育を専門領域として確立したいという願望が込められています。
現場のことを考えるには現場のデータ蓄積が大切ですから、研究会の活動としてはデータとソフトを共有し、会員が蓄積したデータを持ち寄って分析できる情報システムの構築をめざしました。設立当時はMS-DOSの時代でありソフト開発に対する要望も強く、一つのプロトタイプを「SBAR」というデータ管理ソフトとして実現することができました。
もう一つの活動は、酪農を牛乳資源だけではなく、牛肉資源としても最大限に活用する「乳肉複合システム」を確立していくことです。ヨーロッパはこの考え方で乳肉兼用種が飼育されていますが、わが国では北米型ホルスタイン種に和牛を交配することで、乳肉複合をシステムとして構築していこうとするものです。広島大学の農場では、ホルスタイン種に和牛を交配してF1を生産し、F1雌牛を繁殖に利用して生産した子牛(F1クロス)を肥育する試験を1975年から実施していましたので、これをプロトタイプとして現場で生産しながら情報交換をすることで個々の技術を検討し、その成果の一つとして「F1生産の理論と実践(肉牛新報社)」を出版することができました。
F1クロスの生産
F1生産は全国に普及定着しましたが、F1クロスの生産に至るハイブリッド生産システムはまだ全国的な規模では普及していません。鶏のハイブリッド生産に見られるように、牛においてもF1生産は肥育経営の企業化を促進してきました。F1クロスの生産を定着させるためには、種子(精液)の提供だけではなく、肥育素牛と飼育プログラムをセットにして提供していくことが必要なように思います。また、乳牛と同様に肉牛の繁殖も舎飼いで行う方法が一般的ですが、肉牛繁殖は基本的には資源の活用や維持管理の役割にあり、F1クロスの生産も放牧による資源管理を展開していくことを考える必要があるでしょう。
BSE問題への対応
わが国におけるBSEの発生は畜産界だけでなく社会にも大きな衝撃を与えました。BSEは食の安全・安心の視点から畜産を見直す機会となり、生産、流通、消費の関係を再構築していく作業が急速に進展しています。
畜産が社会に信頼されるためには、食の安全あるいはリスクに関して産、官、学、消費者が情報を双方向に共有する必要があります。「情報の共有」は研究会設立当初からの目的ですが、畜産経営の企業化が進行する中で、生産性の向上に必要な情報をオープンに共有することは困難になりました。しかし、食の安全・安心に関する情報はオープンに共有することで、信頼関係を構築することができます。研究会では信頼される畜産をめざし、BSE問題に取り組んでいます。
実学の伝統を受け継ぐ
この研究会の原点は、「現場の問題は現場の方々とともに考える」ことにあります。それは専門細分化し、現場から離れていく農学をなんとか現場につなぎとめたいという切実な思いが原動力になっています。その思いは、農家のために国産鶏を改良し健康なヒナを届けることにひたむきであった父の思いと重なり、またいつも農家とともに歩まれた恩師上坂章次先生の後姿とも重なります。現場研究の一番の専門家は生産者です。「犬馬難鬼魅易」と韓非子の言葉にありますように、現場研究は犬や馬を描くように身近でやさしいと思われがちですが、実は生産者や一般の人に評価されるのは大変で、一般の人には見えない実験科学の方がやさしいということもあります。現場の研究は時間がかかり、成果が認められることも少ないので、大学人が大学人を自己評価するシステムが定着すると、農学を現場につなぎとめるのはますます絶望的なように思われます。しかし、21年目からは事務局を実学の伝統を受け継ぐ京都大学にお引き受けいただくことになりました。生産者や市民に評価される研究に勢いがつき、現場を大切にする若い研究者が育つことを心より期待しています。
設計科学の展開の場
分業化と専門化の壁が現場を見え難くしています。大衆化した大学は、現実世界とつながらない教育研究によって、現実世界から遊離した学生を再生産するサイクルに入ったように思います。今、学術のあり方が問われています。自然科学と社会科学、基礎科学と応用科学といった枠を超えてこれらを融合し、日本学術会議が提唱しているように伝統的な分析的手法による認識科学と、ものを創り、管理する設計科学に再編し、発展していくことが必要だと思います。それは幼稚ながら、畜産システム研究会が求めてきたものであり、歩んできた道でもあります。これまでの研究会は、志はあれども暗中模索の活動の時代でしたが、設計科学の展開を意識した時代へとステップアップしていただきたいと思います。
牛に資源を管理させる
わが国の畜産関係者の間では、家畜を飼うために畜舎を建て、飼料を生産・給与し、糞尿を処理するといった「上げ膳据え膳」が常識となっています。雨が多いことや飼料用穀物を生産していない等が原因ですが、視点を変えて、雑草天国のわが国の里山を管理するために牛を飼うと考えたら、もう一つの畜産が見えてきます。
畜産システム研究会の「里山と牛ML」では、旭川市の斉藤晶牧場を自然の中に生きる牧場のモデルとして学んできました。斉藤晶牧場は酪農として見るより、牛に牧場を拓かせる造園業や不動産業と見ると、畜産の可能性が大きく魅力的に見えてきます。農業はかくあるべしという固定観念から石ころだらけの山を見つめると、厳しい環境に見えますが、自然の営みに身を置いて見直すと宝の山に変わったという斉藤晶さんの牧場は、農業が厳しい環境にあると悩む私たちに、パラダイムの転換が必要なことを教えてくれます。
科学には白紙に「図」を描くように、世界を均質化しグローバル化していく考え方が潜んでいますが、私たちは自然という「地」、歴史、文化、風土という「地」の中で生きています。「地」は場所または場、「図」は要素または関係子で説明することもできます。白紙に同じ牛の図を描く競争よりも、里山(地)と牛(図)の多様な関係を学び、自然の中に生きる畜産を共創していくことが、研究会の柱の一つとして成長していくことを期待しています。
今いる場所をより良い場所にして引き継ぐ
畜産システム研究会報第30号は設立20周年を記念して、今いる畜産の場所を認識し将来を展望するために、畜産システムと科学技術、自然の中に生きる畜産システム、食の安全・安心と畜産システムの3部構成にしました。
畜産の問題を解決していくためには、会員それぞれが所属する組織の当事者として活動される一方で、研究会に参加される場合も、「情報の収集」ではなく「情報の共有」を推進する当事者として活動していただきたいと思います。そのような会員の輪が大きくなることで、畜産が今いる場所を、次の世代にとってより良い魅力ある場所にして引き継ぐことができるのではないでしょうか。夢のある畜産を共に創っていきましょう。










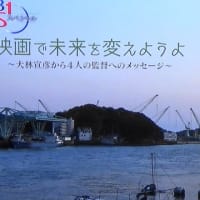



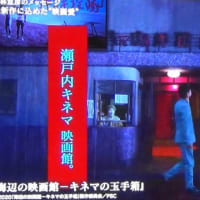
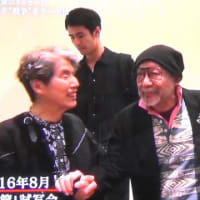

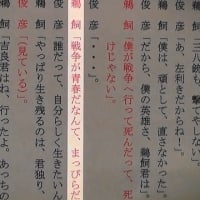



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます