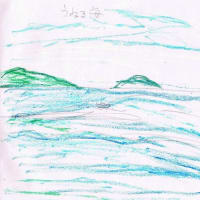先日TEDxHanedaという世界的なイベントに出演した。
https://youtu.be/QtMoRkvfB88
前から出たいと思っていたイベントに出演できたこと自体はもちろん「ヨカッタ」のだが、今回の出演でいろいろ見えてきたものがたくさんあり、私としてはそちらの感慨の方が大きい。
今このTEDというイベントは、日本でも若い人を中心に人気が高まっている。
一方、古い世代の人たちの間での認知度はけっして高くない。
もちろん、まだ新しいイベントだからということもあるだろうけれども、根本的にこのイベントの持つ性格が若い人たちにより共感を得易いということを、私自身が出演して明確に理解できたのも一つの収穫だった。
このイベントにはたくさんのスピーカーが出演する。
しかも、その一人一人の専門分野はありとあらゆるジャンルに渡っている。
今回も、私のような音楽家がいると思えば、紙ヒコーキのギネス記録を持つ人物とか(この方は、宇宙から紙ヒコーキを本気で飛ばそうと現在NASAと交渉しているそうだ)、ウェアラブルコンピューターを14年前から「絶対にこの時代が来る」と信じ眼鏡から時計からアクセサリーまで全身ウェアラブルコンピューターで暮らしてきた大学の先生(もちろんコンピューターの専門家)だとか、世界初の女性ルマン・レーサー、女性宇宙飛行士で有名な山崎直子さんとか、さまざまな分野のフロントランナーたちが、本当に短い時間で(6~12分ぐらいが時間の目安とされていた)個々の「主張」や「活動」をプレゼンした。
しかも、講演会やコンサートのように出演者のプロフィールはおろかスピーチ内容が記されたものすらないイベントだ。
だから、お客さんは「どんな人がどんな話をするのか」といった情報をほとんど持っていない。
こういうイベントは、これまでの日本にはまったくなかったものだ。
プロフィールといえば、私がクラシックコンサートに行くたびに不思議に思うことがある。
それは「クラシックのコンサートって、何で演奏者のプロフィールをあれだけ詳細に書くのかナ?」ということ。
だって、クラシック以外のコンサートで出演者の「プロフィール」などお目にかかったことがない(ポップスやロックのライブで演奏者のプロフィールを配るなんて聞いたことも見たこともない)。
しかも、そのプロフィール中にある「◯◯大学主席卒業とか◯◯コンクール優勝」だとかいう履歴がいかに「アテにならない」ものであるかということもイヤというほど体験してきた。
TEDでは「この人は一体どんな人で、どんな話をしてくれるのか」わからないところから出発する。
だからこそ、よりシンプルに、よりわかりやすく、説得力のあるプレゼンをしなければお客さんは「共感」してくれない。
しかも、自分の「自慢」や「上から目線」を受け付けないのもTEDのコンセプトの一つだ。
クラシック演奏家のプロフィールは、まさしくこの「自慢」に近いのでは、と思う。
演奏前に「さあどうだ。オレってすごいだろ」とミエを切っている(人もいる)。
だから、演奏を聴いて「なんだ、こんなもんかヨ」と失望することも多い(もちろん、逆の場合もあるが)。
今の若い世代が一番「うっとうしく思っていること」は、きっと日本社会のDNAの根本にある「上下意識」なのではないのだろうかと私は思っている。
全てを黙って了解し「上に従い、アウンの呼吸で生きていく」ことこそが最大の美徳とされる日本の社会そのものがきっと「うざったい」のだと思う。
ある意味、これこそが「ブラック」の正体なのではと私は思っている。
企業のバリューやトップのカリスマ性があればあるほど、この「ブラック度」は大きいのかもしれない。
黄門様の印籠ではないければ「これが目に入らぬか」では、まさしく「上下関係が絶対」の価値観を押し付けているようなもの。
ある意味「民主主義の否定」そのものではないのか(あれは江戸時代の話じゃないかと言うなかれ。ドラマ「水戸黄門」は、現代に作られ、現代の人間が拍手する、現代人のためのドラマだ)。
今回の TEDのテーマは「ボーダレス」。
これを「国際性」と理解してもいいし、「差別のない社会」と理解してもいいし、文字通り、「国境のない社会」と理解してもいいが、私は、日本のような「上下のタテ割社会ではないこと」と理解した(タテで仕切られればまわりはボーダーだらけになってしまう)。
私は、今の日本が一番真剣に取り組まなければいけないのは「多様性」だと思っている。
国連がテーマに取り上げている「生物多様性」がなぜ自然界に必要かと言えば、生物は「同じモノ(種)」だけでは絶滅してしまうからだ。
何か違うものが出現(突然変異もその一つ)してこないと、その種は滅びてしまうのだ。
人間社会だって同じこと。
「近親相姦」がヤバイことは猿だって知っている。
春先に猿山を追われた新しい猿の集団(赤ちゃん猿を背中に乗せた母猿もいる20匹ほどの集団)が私の自宅近くをうろついているのを毎年よく目撃する。
近親相姦を意図的に避けるためにどんどん集団を分派していくのだ。
ところが、日本人というのは多分これが一番苦手。
日本が抱えている「少子高齢化」問題の根本がここにあることに気づいている人は案外少ない。
日本は、ここ数年「人口減少問題」に悩まされているとメディアが煽っているけれども、アメリカ、フランス、イギリスなどの欧米先進国などで人口は逆に増えている。
なぜなのか。
その理由は簡単だ。
欧米諸国は、みんな「移民」を受け入れているからだ。
日本は移民を受け入れない国。
いつまでも「日本民族」の純潔性にこだわる国なので日本の人口はどんどん減るばかり。
「生物多様性」に追いついていないのだ。
このままでは日本人自体が「絶滅危惧種」になるのは目に見えている。
もちろん、この「移民制度」は日本人の意見を二分するぐらい微妙な問題だ。
けれども、国の成り立ちがそもそも「移民」で成り立っているアメリカやオーストラリアみたいな国は、最初から「多様性」が当たり前であり、人間には能力にも資力にも「差」があることが当然という前提で社会は成り立っている。
日本人は、不思議なことに、人間は一人一人「違う」ということをあまり認めようとしない。
「みんな同じ」だと思いたがる不思議な国なのだ。
少し前からこの国のリーダーは、「女性の力を」とか「地方の時代を」とか言っているけれど、「そう言わざるを得ない」からそう言っているだけのこと(だと私は思っている)。
なぜなら、女性の方が男性よりも「状況判断能力」に優れているし(男性は否定したがるかもしれないが)、地方が活性化しない限り日本は絶対に「沈没」してしまうからだ。
最近言われ始めた「遠距離介護」も同じこと。
こんなことは昔から皆さんやってきたわけで「今さら」なのだけれども、この「遠距離介護」は、高度成長期ぐらいから始まった「核家族」現象に根本原因がある。
田舎で、みんなが同じ家で何世代も仲良く暮らしていた昔であればこんな問題は絶対に起こらなかっただろうし、「少子化」も、あるいは「介護問題」だって、ひょっとしてこれほど深刻ではなかったかもしれない。
ただ、歴史の歯車はけっして逆回転しない。
将来を考えれば、一番のキーワードは、やはり「多様性」なのじゃないかと思う。
TEDの私のプレゼンに話を戻す。
TEDのお客さんは私が何者か?何を話しだすのかもまったくわかっていない。
ただ後ろのスクリーンに私の名前が大きく出るだけ。
だから、私は「見ておわかりのように私は音楽家です」というセリフからスピーチを始めた。
フルートを手に持っているんだから「わかるでしょ?」という訳だ。
ただ、みんなは音楽家が認知症の話をしだすとは思っていない。
だから、それを自然に理解させるように、まず私のオリジナル曲を演奏してその演奏の方法が認知症患者の人にとって大切なことだということを少しずつわからせていこうと思った(本当は『虹の彼方に』を演奏しようと思ったのだが、著作権がメンドくさいから「ヤメテくれ」とスタッフから言われた)。
例えば、これが私の講演会だったら、きっと私の長ったらしいプロフィールが印刷された資料があって、演目にも仰々しく「音楽と認知症」みたいなタイトルが掲げられているはずだ。
でも、TEDはそれをしない。
つまり、最初っからスピーカー一人一人は「裸」にされているのだ。
「裸」の自分がどれだけのことを主張できてどれだけ人を納得させられるのか。
それが TEDの醍醐味なのであって、けっして「上から目線ではない」というのはこのことを言っている。
どんなプレゼンでもプレゼンターは、よく文字情報や写真、図などを大きなスライドにして見せる。
写真、表、文字情報を見せた方が人々を理解させ易いからだ。
TEDでも、私以外の人は皆それをやっていた。
しかし、私はあえてスライドは何も用意しなかった。
私の武器は、「しゃべり」と「演奏」のみ。
それには二つの計算があった。
ステージにスピーカーが立ち、その背後のスクリーンに写真や文字が映る。
お客さんの目線はスクリーンに向う。
私はそれをさせたくなかったのだ。
絶えず「私だけを見て!」「私の話だけを聞いて!」「私の演奏を聴いて!」が一つ目の私の狙いだ。
二つ目は物理的な理由。
スピーカーは、スライドを調整する小さなリモコンを持たなければならない。
片手にフルート、片手にリモコンでは身動きが取れない。
今回のTEDのプレゼンポイントで大事なことだと思ったのは「その人にしか話せないことを話す」ということ。
紙ヒコーキを宇宙から飛ばす人。こんな人きっと世界に一人しかいないと思う。
14年前からウェアラブルコンピュータ人生を送っていた大学の先生。こんな人も滅多にいない。
今回同じステージに乗ったスピーカーの中で一番印象に残ったのは、世界初の女性ルマンレーサーの井原慶子さん。
ルマンはスピードレースではなく耐久レースなので、毎日いろんな人が交代で入れ替わりにチームとしてレースを行なう。
彼女自身が体験した「日本人だけのチーム」と「フランス人だけのチーム」の比較が印象的だった。
日本人だけのチームでは、女性ドライバーだからと彼女は最も難しいコースから外された。
つまり、「女性にこんな難しいコースは荷が重いだろう」という配慮から日本人チームは彼女を難コースから外したのだ。
しかし、フランス人チームの決断は真逆だった。
「慶子は女性だから適確なコース判断ができるはずだから、このコースは慶子にやってもらおう」と彼女をあえて最難関コースの担当に据えたのだ。
日本チームとフランスチームの対応の違いを見れば、日本人がいかに女性を差別しているかがよくわかる。
フランスチームは、まず男女の差別がないところからスタートする。
その上でどちらの能力が上かを客観的に判断して「慶子にやってもらう」という結論になる。
日本チームの「配慮」は見せかけのやさしさだ。
けっして女性を信用していないのは明らかだ。
今日本がしなければならないことは、このフランス人のやり方を真似ることではなく、まず「男女差別をなくす」ゼロベースに立つこと。
そこからどっちが優れているか、誰が優れているかを判断すれば良いだけのこと。
日本はまだスタートラインにすら立っていない。
遠距離介護もどうすれば良いのか。
子供も孫も両親と地方に住めば良いだけの話。
地方で何代もの家族が一緒に暮らしてお互いに介護したりされたりすれば良いだけの話だ。
そちらの方が絶対に今より「マシな介護生活」が送れるはずだ。
でも、それが許されないのは、今地方が「もぬけの殻」になってしまっているからだ。
日本の全ての地方都市から「シャッター通り」をなくし「仕事がたくさんある街」を作り出さない限り日本はやはりいずれ「沈没」してしまう(多様性のない社会は絶滅の途を辿るだけ)。
「女性の社会進出」も「地方再生」も「少子高齢化の解決」も、すべて「多様性」の問題だと私は思っている。
果たして日本は多様性国家になれるのだろうか。
https://youtu.be/QtMoRkvfB88
前から出たいと思っていたイベントに出演できたこと自体はもちろん「ヨカッタ」のだが、今回の出演でいろいろ見えてきたものがたくさんあり、私としてはそちらの感慨の方が大きい。
今このTEDというイベントは、日本でも若い人を中心に人気が高まっている。
一方、古い世代の人たちの間での認知度はけっして高くない。
もちろん、まだ新しいイベントだからということもあるだろうけれども、根本的にこのイベントの持つ性格が若い人たちにより共感を得易いということを、私自身が出演して明確に理解できたのも一つの収穫だった。
このイベントにはたくさんのスピーカーが出演する。
しかも、その一人一人の専門分野はありとあらゆるジャンルに渡っている。
今回も、私のような音楽家がいると思えば、紙ヒコーキのギネス記録を持つ人物とか(この方は、宇宙から紙ヒコーキを本気で飛ばそうと現在NASAと交渉しているそうだ)、ウェアラブルコンピューターを14年前から「絶対にこの時代が来る」と信じ眼鏡から時計からアクセサリーまで全身ウェアラブルコンピューターで暮らしてきた大学の先生(もちろんコンピューターの専門家)だとか、世界初の女性ルマン・レーサー、女性宇宙飛行士で有名な山崎直子さんとか、さまざまな分野のフロントランナーたちが、本当に短い時間で(6~12分ぐらいが時間の目安とされていた)個々の「主張」や「活動」をプレゼンした。
しかも、講演会やコンサートのように出演者のプロフィールはおろかスピーチ内容が記されたものすらないイベントだ。
だから、お客さんは「どんな人がどんな話をするのか」といった情報をほとんど持っていない。
こういうイベントは、これまでの日本にはまったくなかったものだ。
プロフィールといえば、私がクラシックコンサートに行くたびに不思議に思うことがある。
それは「クラシックのコンサートって、何で演奏者のプロフィールをあれだけ詳細に書くのかナ?」ということ。
だって、クラシック以外のコンサートで出演者の「プロフィール」などお目にかかったことがない(ポップスやロックのライブで演奏者のプロフィールを配るなんて聞いたことも見たこともない)。
しかも、そのプロフィール中にある「◯◯大学主席卒業とか◯◯コンクール優勝」だとかいう履歴がいかに「アテにならない」ものであるかということもイヤというほど体験してきた。
TEDでは「この人は一体どんな人で、どんな話をしてくれるのか」わからないところから出発する。
だからこそ、よりシンプルに、よりわかりやすく、説得力のあるプレゼンをしなければお客さんは「共感」してくれない。
しかも、自分の「自慢」や「上から目線」を受け付けないのもTEDのコンセプトの一つだ。
クラシック演奏家のプロフィールは、まさしくこの「自慢」に近いのでは、と思う。
演奏前に「さあどうだ。オレってすごいだろ」とミエを切っている(人もいる)。
だから、演奏を聴いて「なんだ、こんなもんかヨ」と失望することも多い(もちろん、逆の場合もあるが)。
今の若い世代が一番「うっとうしく思っていること」は、きっと日本社会のDNAの根本にある「上下意識」なのではないのだろうかと私は思っている。
全てを黙って了解し「上に従い、アウンの呼吸で生きていく」ことこそが最大の美徳とされる日本の社会そのものがきっと「うざったい」のだと思う。
ある意味、これこそが「ブラック」の正体なのではと私は思っている。
企業のバリューやトップのカリスマ性があればあるほど、この「ブラック度」は大きいのかもしれない。
黄門様の印籠ではないければ「これが目に入らぬか」では、まさしく「上下関係が絶対」の価値観を押し付けているようなもの。
ある意味「民主主義の否定」そのものではないのか(あれは江戸時代の話じゃないかと言うなかれ。ドラマ「水戸黄門」は、現代に作られ、現代の人間が拍手する、現代人のためのドラマだ)。
今回の TEDのテーマは「ボーダレス」。
これを「国際性」と理解してもいいし、「差別のない社会」と理解してもいいし、文字通り、「国境のない社会」と理解してもいいが、私は、日本のような「上下のタテ割社会ではないこと」と理解した(タテで仕切られればまわりはボーダーだらけになってしまう)。
私は、今の日本が一番真剣に取り組まなければいけないのは「多様性」だと思っている。
国連がテーマに取り上げている「生物多様性」がなぜ自然界に必要かと言えば、生物は「同じモノ(種)」だけでは絶滅してしまうからだ。
何か違うものが出現(突然変異もその一つ)してこないと、その種は滅びてしまうのだ。
人間社会だって同じこと。
「近親相姦」がヤバイことは猿だって知っている。
春先に猿山を追われた新しい猿の集団(赤ちゃん猿を背中に乗せた母猿もいる20匹ほどの集団)が私の自宅近くをうろついているのを毎年よく目撃する。
近親相姦を意図的に避けるためにどんどん集団を分派していくのだ。
ところが、日本人というのは多分これが一番苦手。
日本が抱えている「少子高齢化」問題の根本がここにあることに気づいている人は案外少ない。
日本は、ここ数年「人口減少問題」に悩まされているとメディアが煽っているけれども、アメリカ、フランス、イギリスなどの欧米先進国などで人口は逆に増えている。
なぜなのか。
その理由は簡単だ。
欧米諸国は、みんな「移民」を受け入れているからだ。
日本は移民を受け入れない国。
いつまでも「日本民族」の純潔性にこだわる国なので日本の人口はどんどん減るばかり。
「生物多様性」に追いついていないのだ。
このままでは日本人自体が「絶滅危惧種」になるのは目に見えている。
もちろん、この「移民制度」は日本人の意見を二分するぐらい微妙な問題だ。
けれども、国の成り立ちがそもそも「移民」で成り立っているアメリカやオーストラリアみたいな国は、最初から「多様性」が当たり前であり、人間には能力にも資力にも「差」があることが当然という前提で社会は成り立っている。
日本人は、不思議なことに、人間は一人一人「違う」ということをあまり認めようとしない。
「みんな同じ」だと思いたがる不思議な国なのだ。
少し前からこの国のリーダーは、「女性の力を」とか「地方の時代を」とか言っているけれど、「そう言わざるを得ない」からそう言っているだけのこと(だと私は思っている)。
なぜなら、女性の方が男性よりも「状況判断能力」に優れているし(男性は否定したがるかもしれないが)、地方が活性化しない限り日本は絶対に「沈没」してしまうからだ。
最近言われ始めた「遠距離介護」も同じこと。
こんなことは昔から皆さんやってきたわけで「今さら」なのだけれども、この「遠距離介護」は、高度成長期ぐらいから始まった「核家族」現象に根本原因がある。
田舎で、みんなが同じ家で何世代も仲良く暮らしていた昔であればこんな問題は絶対に起こらなかっただろうし、「少子化」も、あるいは「介護問題」だって、ひょっとしてこれほど深刻ではなかったかもしれない。
ただ、歴史の歯車はけっして逆回転しない。
将来を考えれば、一番のキーワードは、やはり「多様性」なのじゃないかと思う。
TEDの私のプレゼンに話を戻す。
TEDのお客さんは私が何者か?何を話しだすのかもまったくわかっていない。
ただ後ろのスクリーンに私の名前が大きく出るだけ。
だから、私は「見ておわかりのように私は音楽家です」というセリフからスピーチを始めた。
フルートを手に持っているんだから「わかるでしょ?」という訳だ。
ただ、みんなは音楽家が認知症の話をしだすとは思っていない。
だから、それを自然に理解させるように、まず私のオリジナル曲を演奏してその演奏の方法が認知症患者の人にとって大切なことだということを少しずつわからせていこうと思った(本当は『虹の彼方に』を演奏しようと思ったのだが、著作権がメンドくさいから「ヤメテくれ」とスタッフから言われた)。
例えば、これが私の講演会だったら、きっと私の長ったらしいプロフィールが印刷された資料があって、演目にも仰々しく「音楽と認知症」みたいなタイトルが掲げられているはずだ。
でも、TEDはそれをしない。
つまり、最初っからスピーカー一人一人は「裸」にされているのだ。
「裸」の自分がどれだけのことを主張できてどれだけ人を納得させられるのか。
それが TEDの醍醐味なのであって、けっして「上から目線ではない」というのはこのことを言っている。
どんなプレゼンでもプレゼンターは、よく文字情報や写真、図などを大きなスライドにして見せる。
写真、表、文字情報を見せた方が人々を理解させ易いからだ。
TEDでも、私以外の人は皆それをやっていた。
しかし、私はあえてスライドは何も用意しなかった。
私の武器は、「しゃべり」と「演奏」のみ。
それには二つの計算があった。
ステージにスピーカーが立ち、その背後のスクリーンに写真や文字が映る。
お客さんの目線はスクリーンに向う。
私はそれをさせたくなかったのだ。
絶えず「私だけを見て!」「私の話だけを聞いて!」「私の演奏を聴いて!」が一つ目の私の狙いだ。
二つ目は物理的な理由。
スピーカーは、スライドを調整する小さなリモコンを持たなければならない。
片手にフルート、片手にリモコンでは身動きが取れない。
今回のTEDのプレゼンポイントで大事なことだと思ったのは「その人にしか話せないことを話す」ということ。
紙ヒコーキを宇宙から飛ばす人。こんな人きっと世界に一人しかいないと思う。
14年前からウェアラブルコンピュータ人生を送っていた大学の先生。こんな人も滅多にいない。
今回同じステージに乗ったスピーカーの中で一番印象に残ったのは、世界初の女性ルマンレーサーの井原慶子さん。
ルマンはスピードレースではなく耐久レースなので、毎日いろんな人が交代で入れ替わりにチームとしてレースを行なう。
彼女自身が体験した「日本人だけのチーム」と「フランス人だけのチーム」の比較が印象的だった。
日本人だけのチームでは、女性ドライバーだからと彼女は最も難しいコースから外された。
つまり、「女性にこんな難しいコースは荷が重いだろう」という配慮から日本人チームは彼女を難コースから外したのだ。
しかし、フランス人チームの決断は真逆だった。
「慶子は女性だから適確なコース判断ができるはずだから、このコースは慶子にやってもらおう」と彼女をあえて最難関コースの担当に据えたのだ。
日本チームとフランスチームの対応の違いを見れば、日本人がいかに女性を差別しているかがよくわかる。
フランスチームは、まず男女の差別がないところからスタートする。
その上でどちらの能力が上かを客観的に判断して「慶子にやってもらう」という結論になる。
日本チームの「配慮」は見せかけのやさしさだ。
けっして女性を信用していないのは明らかだ。
今日本がしなければならないことは、このフランス人のやり方を真似ることではなく、まず「男女差別をなくす」ゼロベースに立つこと。
そこからどっちが優れているか、誰が優れているかを判断すれば良いだけのこと。
日本はまだスタートラインにすら立っていない。
遠距離介護もどうすれば良いのか。
子供も孫も両親と地方に住めば良いだけの話。
地方で何代もの家族が一緒に暮らしてお互いに介護したりされたりすれば良いだけの話だ。
そちらの方が絶対に今より「マシな介護生活」が送れるはずだ。
でも、それが許されないのは、今地方が「もぬけの殻」になってしまっているからだ。
日本の全ての地方都市から「シャッター通り」をなくし「仕事がたくさんある街」を作り出さない限り日本はやはりいずれ「沈没」してしまう(多様性のない社会は絶滅の途を辿るだけ)。
「女性の社会進出」も「地方再生」も「少子高齢化の解決」も、すべて「多様性」の問題だと私は思っている。
果たして日本は多様性国家になれるのだろうか。