「国土交通省はハイブリッド車や電気自動車などエンジン音のしない自動車は危険なので、低速で走行中はエンジン音に相当する『人工音』を発生させるよう義務づける対策案を提出した」
プリウスやインサイト、i-MiEVといったハイブリッド車や電気自動車は低速走行時の音が小さすぎて危ないのだという。
自動車が来ているかどうか分からないから事故になる、という発想だ。
彼らいわく、電気自動車に乗ったら、
「ぶ~~んぶ~~ん」
と音立てよ。
これではまるで幼児の玩具。
車のエンジン音が無くなって静かになると多くのメリットがある。
例えば住宅街の騒音が減る。
幹線道路沿いは言うに及ばず、夜間はほとんど物音のしない住宅地はちょっとしたノイズが気にかかることがある。
自動車がゆっくり走っていたり、エンジンを動かしたまま一時停車していても問題になることがある。
自動車騒音に敏感なところでは大歓迎のはずだ。
アイドリング時も静かだと「停止時はエンジンのスイッチを切ってください」なんていうコンビニやファミレスのカンバンも不要になる。
ビジネスの幅が広がる可能性さえある。
静かだから車内での会話も快適だ。
カーステレオの音もエンジンノイズなしで聞ける。
全ての車が電気自動車になると「音発生器」が無ければ暴走族の爆音に悩まされることもない。
静かだから歩行者にとって危ないんじゃない?
という反論もあろう。
そういう人にはさらにひとつ反論したい。
「んじゃ、自転車もきっと危ないね。」
と。
自転車で街中を走っていて、もしも歩行者が前方を歩いていたり、危険が予測されたら「チャリンチャリン」とベルを鳴らす。
自動車なら「ブー!」とか「ファーン!」とかクラクションを鳴らす。
2つの違いは音の大小。そして音のデザインの違い。
自転車のチャリンはビックリしないが、自動車のファーンには驚くことが少なくない。
結局、静かな自動車には静かなベルのようなお洒落な警告音。
四六時中ダミーエンジン音を鳴らせ、というような無粋な法律案は学生時代まともな遊びもしたことのない東大、京大、阪大あたりを卒業した役人ならではの発想だと思われる。
そういえば国交相のアイデアの取りまとめは東京大学の某教授。
本郷通りが静かになったら化学の世界でもノーベル賞受賞者ぐらいだせるようになるかもしれませんぞ、東大さん。まずは街の音デザインを考えてみてはいかがかな。
プリウスやインサイト、i-MiEVといったハイブリッド車や電気自動車は低速走行時の音が小さすぎて危ないのだという。
自動車が来ているかどうか分からないから事故になる、という発想だ。
彼らいわく、電気自動車に乗ったら、
「ぶ~~んぶ~~ん」
と音立てよ。
これではまるで幼児の玩具。
車のエンジン音が無くなって静かになると多くのメリットがある。
例えば住宅街の騒音が減る。
幹線道路沿いは言うに及ばず、夜間はほとんど物音のしない住宅地はちょっとしたノイズが気にかかることがある。
自動車がゆっくり走っていたり、エンジンを動かしたまま一時停車していても問題になることがある。
自動車騒音に敏感なところでは大歓迎のはずだ。
アイドリング時も静かだと「停止時はエンジンのスイッチを切ってください」なんていうコンビニやファミレスのカンバンも不要になる。
ビジネスの幅が広がる可能性さえある。
静かだから車内での会話も快適だ。
カーステレオの音もエンジンノイズなしで聞ける。
全ての車が電気自動車になると「音発生器」が無ければ暴走族の爆音に悩まされることもない。
静かだから歩行者にとって危ないんじゃない?
という反論もあろう。
そういう人にはさらにひとつ反論したい。
「んじゃ、自転車もきっと危ないね。」
と。
自転車で街中を走っていて、もしも歩行者が前方を歩いていたり、危険が予測されたら「チャリンチャリン」とベルを鳴らす。
自動車なら「ブー!」とか「ファーン!」とかクラクションを鳴らす。
2つの違いは音の大小。そして音のデザインの違い。
自転車のチャリンはビックリしないが、自動車のファーンには驚くことが少なくない。
結局、静かな自動車には静かなベルのようなお洒落な警告音。
四六時中ダミーエンジン音を鳴らせ、というような無粋な法律案は学生時代まともな遊びもしたことのない東大、京大、阪大あたりを卒業した役人ならではの発想だと思われる。
そういえば国交相のアイデアの取りまとめは東京大学の某教授。
本郷通りが静かになったら化学の世界でもノーベル賞受賞者ぐらいだせるようになるかもしれませんぞ、東大さん。まずは街の音デザインを考えてみてはいかがかな。










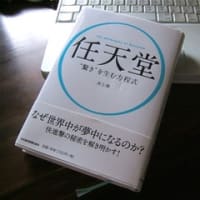








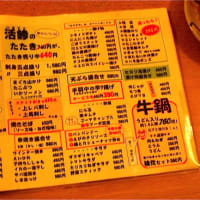
車の前照灯は、周りを照らして運転者の視界を確保するだけではなく、周囲に自車の存在を知らしめる役目もあります。警察が(この季節は特に)「早目のライト点灯を」と呼びかけるのはこの為ですよね。
音をメインに周りの状況を察知している人にとっては、数tもある鉄の塊が、音も無く時速数十キロで直ぐ脇を通過していくのは確かに恐怖を感じる事と思います。運転者からは自車の周囲に視覚障碍者が居るかどうかの判別に意識を集中し続けるわけにも行きませんし、視覚障碍者の方も、傍に寄られてから音を出されてもビックリするのは同じ事。結局、のべつまくなし「エコカーのお通りだい」と云う音を出し続けてもらわなければ、怖くて町を歩けないと云う事になるわけです。
電気自動車が世に出始めた当初は「とっても静かです」が謳い文句の一つでした。しかし数が増えてくると、「静かな事はメリットだけじゃない」という事が解ってきた、という事でしょう。
「音のデザイン」と云う着目点は確かにハッとさせられましたし、「対策案は結局【音を出す】なのか」とちょっとガッカリなニュースではありますね。
猶、
>「んじゃ、自転車もきっと危ないね。」
>自転車のチャリンはビックリしないが、自動車のファーンには驚くことが少なくない。
に関して。実際のところ自転車も危ないです。自動車のソレは言うまでも無く、自転車のチャリンにビックリさせられる事もあります。反論としてはいささか弱いと感じますが、いかがでしょうか。
今回のニュース記事の中で最も気にかかるのは、なんでもかんでも行政で規制をかけよう、ルールを作ろうという姿勢です。
ハイブリッドカーや電気自動車の音に関しては、確かに静かすぎて視覚に障害のある人だけではなく一般の人にも接近してくるのが分かりにくいかも知れません。
しかし、たとえば小排気量のエンジン車でも低速走行の時は周りの音に影響されるとほとんど走行音の聞き取れないものもあります。
こういうものはどうなんでしょう。
運転者というのは歩行者がどのような人であろうと注意を払う義務があります。
エコ自動車も幹線道路で通常速度で走っている時はモーター音やサポートするエンジン音、タイヤが路面と接触している音などがあり、わざわざ音を出す必要はありません。
むしろ低速というか徐行している際に鳴らす警笛に配慮を加えるべきです。
例えば最近の電車には大小2種類の警笛音を持っているものがあるようです。
私の勝手な想像ですが、対象が近くにある場合と遠くにある場合に対する配慮だと思います。
自動車にも同様の音に対する配慮が必要ではないかと。
いや、自動車だからもっと必要だと思います。
このような種類の音に関する配慮は行政が手を出し法律を作る範疇ではなく、消費者からの意見を吸い上げるメーカーが取るべき考えであると思います。
行政は意見するだけで充分ではないでしょうか。
メーカーの方が行政よりも『事故」を恐れます。
より真剣に考えることはいうまでもありません。
自転車に関しても同様で、運転するものが歩行者などに注意を払うのが義務です。
最近よく報道される自転車による事故は。この歩行者に対する自転車運転者の配慮に欠けたものが目につくように思います。
私も先日JR飯田橋駅近くの坂道で自転車事故を検証している現場に通りかかりました。
もし自転車に音を鳴らしながら走るようにというルールが出来たら、自転車愛好家はもとより一般消費者からもクレームが出ることでしょう。
静かなエコ自動車に対する人工走行音の義務づけ。
新しいものに対するアレルギー反応と行政のちょっと行き過ぎのような気がします。