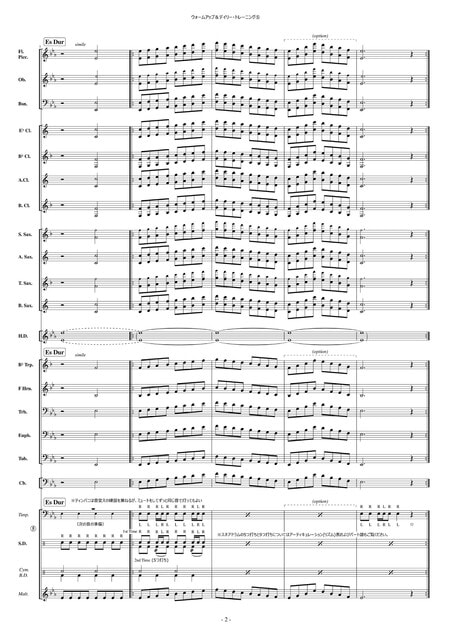二月の「与勇輝展」以来七か月ぶりに展覧会へ。
国立西洋美術館で開催中の「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」です。

◆久しぶりの国立西洋美術館
コロナの影響で3月の開催が延期になったときは、もう見られないかと思っていたので本当によかったです。

◆日時指定のチケットで入場(11時~)
入場してからさらに会場入り口で1列に並んでいったん待機。時間を空けて5~6人ずつ入ります。
ここで10分弱かかりましたが、展示室に入ったところがいちばん混みますから仕方ないですね。

◆会場入り口の窓
「西洋絵画史の教科書」と解説にあるとおり、ルネサンスのボッティチェリからポスト印象派のゴッホまで、西洋絵画の流れがよくわかる展示構成と名作の数々でした。

◆レンブラント「34歳の自画像」

◆フェルメール「ヴァージナルの前に座る若い女性」
こんな巨匠たちの作品が普通に並んでいるのはすごいことです。

◆カナレット「ヴェネツィア:大運河のレガッタ」
これはぜひ実物を間近で見てもらいたい大作です。

◆ムリーリョ「窓枠に身を乗り出した農民の少年」
ムリーリョの描く子どもの絵、好きです。表情が素晴らしい。

◆ターナー「ポリュフェモスを嘲るオデュッセウス」
よく見ると空や海にいろいろな仕掛けがありました。

◆ゴーガン「花瓶の花」
ゴーガンの花の絵は初めて見ましたが意外と(?)いい。ちょっと日本画を思わせます。

◆ゴッホ「ひまわり」
たったいま完成したばかりでゴッホがここに居るのではないか?と思うような迫力!
ゴッホ特有のタッチと厚塗りの絵の具。
いままで見ていた写真や印刷とはまったくの別物。
いろいろな角度や距離から何回も見直しました。
個人的には七枚のひまわりの中でこれがいちばん気に入りました(全部実物を見たわけではありませんが)。
日時指定入場制ということで非常にゆったりと鑑賞することができました。
普通ならフェルメールやゴッホの前は人だかり。それが至近距離でじっくり見られる。
ずっとこのシステムを希望したいところですが、採算上無理でしょうか?
見終わった後のミュージアムショップも人数を区切りながらの入場制でした。時間に余裕を持って行くことをおすすめします。
(2020.09.24)