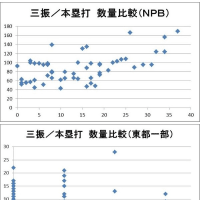人の五感の中で、嗅覚は知覚の境界がぼんやりしているためかとても奥深い世界だ。私たちはにおい、匂い、臭いと言葉を書き分けながら日々これらと接し、様々に反応し続けている。においの世界を現代の歌人はどのようにうたっているのだろうか。
においにはどんな特質があるのかを考えてみたい。
・だれも他人(ひと)の運命を生きることできず匂ひのない瓦礫の映像を見る
(米川千嘉子)
東日本大震災から。景や惨状のビジュアルはテレビ等の映像からしっかり理解できても、所詮は遠い世界の他人の体験でしかない。まして匂いは映像では伝わらないという虚無感と自責だ。
・ガスボンベ瓦避けつつあゆむ畔津波のあとの田は生臭し
(遠藤たか子)
被災地でボランティアした人に聞いたのだが、現場に立って何よりも初めに迫ってきた知覚が耐えきれないほどのこうした生臭さだったという。
・大便の溢れし便器より流れくる便の匂いは避難所に充つ
(田中拓也)
教師である作者は生徒たちを避難所まで引率した。断水のトイレから間断なく漂い来る不快臭は避難の不安をさらに大きくさせたことだろう。
視覚や聴覚はそこに居ずとも届いてくるが、嗅覚はそこにいる者にしかわからない。現場のリアル、それがにおいの持つ大きな特質である。
暮らしのにおい
短歌は小さな日常を描き出すのが得意な詩型である。においは暮らしのあらゆる場面に関わるので自然とそのシーンも多い。
・つぎつぎに匂ひ異なるなか歩む果実店薬局木材店のまへ
(尾崎左永子)
・ぎんなんの異臭漂ふ境内にましろき犬をみちびく少女
(小池光)
人は外を歩くだけでこうした様々なにおいに出会ってしまう。家での暮らしも同様だ。
・花冷えの夜に取りいだすヒーターは埃のにほひたてて点りぬ
(上田三四二)
・地表にてわれは小鼻をふくらませ腋臭のひとのシャツを洗へる
(辰己泰子)
使わない間にヒーターに付いた埃が焼けるにおい、腋臭のひとのシャツ…日常の小さなシーンがうまく切り取られている。
・餃子食べし美人と前後し店を出るきみもニンニクわれもニンニク
(岩田正)
・口臭はわれかとおもいはつなつの電車こみあうなかのひとりよ
(村木道彦)
お互いにニンニク臭いんだから気にしないという明るさが溢れている。対して二首めは気付かれて欲しくないにおい。自己の体臭を過剰に恐れる「自己臭症」という精神的な病があるが、作者はその入口にいたのかもしれない。
・苺食べて子のいき殊に甘く匂ふ夕明かり時を母に寄り添ひ
(五島美代子)
・給食で何を食べたかスプーンの匂い嗅ぐなり母というもの
(俵万智)
子の息のにおい、子の食べたもののにおい、母ならではの親密な距離感に深い思いがこもる。
・二十年二十度鋤く土の香のその新鮮を誰に告ぐべき
(時田則雄)
・刈りしとき匂ひし紫蘇が刈草を集むるときにふたたびにほふ
(石川不二子)
土の香、紫蘇の香…農作業中のにおい。対象にしっかり向き合っている感じがする。他にも汗、油、埃、排ガス、調理、消毒液等、仕事に関わるにおいは無数にあるだろう。
記憶とにおい
においには記憶を蘇らせる作用がある。
・いるはずのない君の香にふりむいておりぬふるさと夏の縁日
(俵万智)
・陽の匂うトマトを食めばじんわりと初夏のトマトのなかの亡き母
(田村広志)
・印肉の匂ひをかげば沸々と湧きいづるなり過去の不始末
(前川佐重郎)
不意に届いた君の香、トマトの匂いと母の思い出、始末書に拇印を押さされた苦い記憶。味覚や聴覚も記憶と結び付きやすいが、嗅覚はさらにその力が強い。古くは啄木が「垢じみし袷の襟よ/かなしくも/ふるさとの胡桃焼やくるにほひす」とうたう。
視覚と聴覚がともに不自由であったヘレン・ケラーは「匂いは私を何千マイルも離れた遠い地に運んでくれたり、これまでに生きてきたすべての年月を越えてタイム・スリップさせてくれる強力な魔法使い」と言ったという。
また、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』の中で、主人公がマドレーヌを紅茶に浸したとき、その香りが一瞬にして時空を越えて主人公を幼年時代に引き戻す場面がある。こうしたある特定のにおいによってそれに関係する記憶や感情が蘇る現象を「プルースト効果」と呼ぶそうだ。(平山令明「香りの科学(講談社)」)
記憶とにおいは脳細胞のどこかで直に混ざり合っている感じがする。
喩的なにおい
・今刈りし朝草のやうな匂ひして寄り来しときに乳房とがりゐき
(河野裕子)
・東西にのびて憩へるいもうとの四肢マシュマロのごとく匂へり
(辰巳泰子)
直喩としてのにおいである。刈りたての朝草やマシュマロはいずれも読み手に直感的に迫ってくる。近代では北原白秋の「君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ」が知られている。
隠喩的なにおいはどうだろう。
・こんなにも赤いものかと昇る日を両手に受けて嗅いでみた
(山崎方代)
・浅きから深きへ睡りがうつるとき夜の汀のにおいが籠る
(生沼義朗)
・軋みつつ回送電車去りてのちホームの先の闇かぐわしき
(谷岡亜紀)
朝日の匂い、夜の汀の匂い、かぐわしい闇。実際のにおいはよくわからないままに言葉から連想される抽象的なにおいの世界だ。
・渋滞のさなかラジオに聴きとめし木曾の民話は樹の香りせり
(桑原正紀)
・木箱より引きいだすとき雛らはこの家のくらがりの香をはなつ
(林和清)
樹の香はまだわかりやすいが、くらがりの香とはどんなにおいなのか。それでも何か言葉に内在するイメージとして脳に届いてくるものがあるのが不思議だ。
・ずるずると抜くどくだみのど(・)音とだ(・)音が臭いを発す
(武川忠一)
「どくだみ」という音韻から想像される臭いという捉え方がユニークだ。北原白秋の「どくだみの花のにほひを思ふとき青みて迫る君がまなざし」をも連想させる。
・帰り来し夫の背後に紺青(こんじょう)の夜あり水のにほひを もちて
(小島ゆかり)
・病むまへの身体が欲しい 雨あがりの土の匂ひしてゐた女のからだ
(河野裕子)
・危急種のウミスズメの保護訴ふる女子の生徒は海の匂いせり
(伊藤一彦)
人のにおいである。水、雨上がりの土、海の匂い。 体臭とはまた異質な、喩としてのにおい。人は実に様々なにおいをたてる。
・名を呼ばれ「はい」と答ふる学生のそれぞれの母語の梢が匂ふ
(大口玲子)
・国ことば語尾にゆたかに母音あり母音は海と日の匂いする
(高野公彦)
外国人に日本語を教えていた作者は、生徒たちそれぞれの持つ祖国語の訛りを「母語の梢が匂ふ」とうたう。二首めは方言が纏っている海と日の匂い。これも言葉のイメージがぴたりとにおいに重なる。
・わが未来まだ闘いの匂ひして標的とならん誰と誰と誰
(尾崎左永子)
「闘いの匂い」のエネルギッシュで野性的な響きが小気味よい。
・携帯の匂ひひたすら嗅ぐ猫よかぐはしきメールの数々知るや
(佐藤モニカ)
携帯の匂いではなく、中のメールに内在する匂いを見つめているのがおもしろい。
・あめいろの空をはがれてゆく雲にかすかに匂うセロファンテープ
(笹井宏之)
まず匂いでもってセロファンテープを思わせ、それで雲が貼られているというファンタジーだ。
かなり印象的な「におい」を紹介したい。
・我に應ふるわれの内部の聲眛(くら)し乾貝が水吸いてにほへる
(塚本邦雄)
下の句の不気味で不安めくにおいと上の句の心象との異質な取り合わせが詩的にしっかりと結ばれている。
・輪郭がまた痩せていた 水匂う出町柳に君が立ちいる
(永田紅)
「水匂う」がまるで出町柳の枕詞であるかのように響いてくるではないか。
・シャガール展閑散として会場に馬の臭いの充満したり
(岡部桂一郎)
「馬の絵」の視覚が「馬の臭い」に変容されて詩情が一気に広がってゆく。
嗅覚は隠喩的な世界と親和力がある。においとは空気中の揮発性の微粒子で、目に見えないぼんやりとした存在だ。そのために、においの出所とか周囲の様子、別の物等から想像するほかない。こうした想像力がつまり、歌人たちに喩の力を持ってこさせるのだろう。においが喩の力を得るとたちまちに奥行きある世界が立ち上がる。
色とにおい
・海に行く小石の道がほんのりとうす桃色に匂ふ夕暮れ
(佐佐木信綱)
・入り日さすあかり障子はばら色にうすら匂ひて蝿一つとぶ
(斎藤茂吉)
「色が匂う」になんと巧みな表現だと思ってしまいそうだが、それは間違いだ。吉本隆明は「匂いを讀む(光芒社)」で「にほい(匂ひ・薫ひ)」について「古語辞典(岩波書店版)」の「ニは丹で赤色の土、転じて赤色。ものの香りがほのぼのと立つ意。赤く色が映える。色に染まる。色美しく映える(略)」を紹介し、色彩の色がただよう状態と、我々の知る一般的な匂いのふたつの意味を述べ、「むらさきの日傘の色の匂ふゆえ遠くより来る君のしるしも(川田順)」等を紹介している。つまり「匂う」は文語では視覚的な表現、特に赤い色彩に用いられる。従ってこれらは元来の「匂ふ」の語義通りなのだ。また、吉本は『古今和歌集』の「色も香も昔の濃さににほへども植えけむ人の影ぞ恋しき(紀貫之)」を挙げ、「色」と「香」がともに「にほう」という言葉に源流があることも示している。
・窓いっぱい夕日にほへり耳遠き母がたかぶりものを言ふとき
(小島ゆかり)
この歌は母が昂ぶって話をする様子を窓いっぱいに夕日の色が広がる様に喩えたもので、「匂う」本来の語義を現代に持ちこんで蘇らせたともとれる。
現代のにおい
・フルーツのガムの香のする十歳とマリオのゲームに死につづけおり
(森田小夜子)
・「写真、一枚もないんだ、ごめんね」とチューインガムの匂いの夜に
(穂村弘)
・シャンプーの香りに満ちる傘の中 つぼみとはもしやこのようなもの
(早川志織)
ガムの香、シャンプーの香の現代的な軽い匂いは子供や若い女性によく似合う。
・私をジャムにしたならどのような香りが立つかブラウスを脱ぐ
(河野小百合)
突き抜けた女王のごときナルシシズムに圧倒させられる。
・ゴミ箱よりイチゴ香料の香は立ちて夜の空間の輪郭は濃し
(生沼義朗)
イチゴの香ではなくてイチゴ香料の香、つまり人工の匂いである。匂いでもって夜の空間に濃い輪郭を見た感性が鋭い。テレビで天然の果物の匂いと人工の匂い、どちらが本物か当てさせる実験を見たことがあるが、ほとんどの人が人工の匂いの方を本物と勘違いしていた。本物より本物ぽいがそれは偽の匂いなのだ。人工の匂いは強調されていて、対して天然は弱いから、弱い方が本物のはずなのだが、現代人はその根底の所からすでに人工の強い匂いに慣れきってしまっているためだろう。
・薄明のそこはかとなきあまき香は電気蚊取器はたまた妻子
(小池光)
・コピー用紙吐き出さむときかそかなる西瓜の甘き香はただよひぬ
(柚木圭也)
現代のテクノロジーが生み出した新しい匂い。蚊取り線香の香には情緒とノスタルジーを多分に感じるが、電子蚊取り器のにおいはどこかよそよそしい。二首め、コピー機から出るあのにおいとスイカの香が結び付いた意外性。
・言い訳の言い訳のその言い訳を柔軟剤の匂いの中で
(伴風花)
・すれちがうレノアのにおいやさしかり夜勤の人が薄暮れを来る
(佐藤華保理)
どこまでも重なってゆく言い訳を取り巻くように漂う柔軟剤の匂い…なんとやさしく透明感のある歌だろう。二首めの「レノア」も柔軟剤だが、調べてみると芳香剤的な機能が大きく付加されている。
昭和の終盤くらいからだろうか、やたらと臭いを消し去ろうとする社会に変わっていった。体臭などはあってはならぬものとされ、制汗剤や専用の石けんが当たり前になった。用便後の臭いを消すスプレーや便の臭いを減らす消臭食品まである。加齢臭へのエチケットがコマーシャルされ、体臭や口臭で周囲に嫌がられる「スメハラ」(スメルハラスメント)なる言葉も登場している。戦後から昭和中期頃にかけての暮らしのなかに溢れていた数多の臭いの総量を現代と比較すれば、もう天と地以上の差であろう。
かつて直木賞の選考委員を務めた黒岩重吾は選考会でよく「この登場人物は体臭がせえへん。安物の人形が動いてるみたいや」と言っていたという。私たちはもはやこうした強い臭いの世界まで戻ることはできない。これから先、今の我々が想像もつかないような新しいにおいも登場してくるのだろう。
※「短歌往来」2020年8月号に掲載されたものを加筆訂正。