ホソウ路で0.4Gをコントロールしようとすると、
「速度の管理」「ライン取り」がピタリでなければ実現しないが、
サーキット走行でタイヤグリップの上限付近なら
それ以上のGが出ない(勝手にリミッターが掛かる)から、
乱暴な運転をしてもGは揃っていると言える。
この時にライン取りと合致していれば良いタイムが出るはずだが、
タイヤのグリップの上限辺りでは、うまい使い方と、まずい使い方があるから、
そこを知る必要がある。
一つはフロントタイヤ、リヤタイヤにうまく荷重を掛ける事(ヨーコントロール)と、
もう一つ、タイヤのスリップアングル(舵角)の管理。
タイヤは進行方向に対して角度を付けていくと、横力(コーナリングフォース、CF)が発生します。
同時に抵抗(コーナリング抵抗、CR)がスリップアングルに比例して増えて行き、
進行方向に直角になった時、最大(フルブレーキと同じ)でほぼ直線のグラフになります。
CFの最大値の発生は“数度”のスリップアングル付近に丘のようにゆるやかなピークがあります。
つまりCFピーク付近は多少手を動かして舵角を変えてもグリップの変化を感じない領域があるのに対して
CRは指一本分動かして確実に変化します。
一番美味しいのはCFの最大値の出る領域の中のCR値の少ないスリップアングルと言う事になります。
指一本分切り過ぎた走りをすれば、増えたCRが旋回速度を下げ、駆動力を奪います。
グリップの高いタイヤ程、このCR値も大きく、スリップアングルに敏感になります。
タイムアタックに際して、気合を入れれば入れるほどタイムが落ちる(上がらない)又は、
コーナーに突っ込めば突っ込む程タイムが出ないのは、このCRの存在を知らないか、
甘く考えているから、オーバースピードでコーナーに進入した時、ハンドルを切り足せば曲がるのは、CFが増えてラインが保てるのではなく
“CRが増えて速度が落ちる”から円を小さく出来るというのが、本当の理由。
正しく走らせるには切り足さなくても良いように、進入スピードをピタリにコントロールすることだ。
つまりはサーキット走行といえども、タイヤに行き先を尋ねて走らせるのではなく、
タイヤが発生しうる上限Gを、行き過ぎないスピードに合わせる事で、
CRの少ないおいしいタイヤの使い方ができるのだ。
その訓練がG-BOWLでできるのだが・・・。
「速度の管理」「ライン取り」がピタリでなければ実現しないが、
サーキット走行でタイヤグリップの上限付近なら
それ以上のGが出ない(勝手にリミッターが掛かる)から、
乱暴な運転をしてもGは揃っていると言える。
この時にライン取りと合致していれば良いタイムが出るはずだが、
タイヤのグリップの上限辺りでは、うまい使い方と、まずい使い方があるから、
そこを知る必要がある。
一つはフロントタイヤ、リヤタイヤにうまく荷重を掛ける事(ヨーコントロール)と、
もう一つ、タイヤのスリップアングル(舵角)の管理。
タイヤは進行方向に対して角度を付けていくと、横力(コーナリングフォース、CF)が発生します。
同時に抵抗(コーナリング抵抗、CR)がスリップアングルに比例して増えて行き、
進行方向に直角になった時、最大(フルブレーキと同じ)でほぼ直線のグラフになります。
CFの最大値の発生は“数度”のスリップアングル付近に丘のようにゆるやかなピークがあります。
つまりCFピーク付近は多少手を動かして舵角を変えてもグリップの変化を感じない領域があるのに対して
CRは指一本分動かして確実に変化します。
一番美味しいのはCFの最大値の出る領域の中のCR値の少ないスリップアングルと言う事になります。
指一本分切り過ぎた走りをすれば、増えたCRが旋回速度を下げ、駆動力を奪います。
グリップの高いタイヤ程、このCR値も大きく、スリップアングルに敏感になります。
タイムアタックに際して、気合を入れれば入れるほどタイムが落ちる(上がらない)又は、
コーナーに突っ込めば突っ込む程タイムが出ないのは、このCRの存在を知らないか、
甘く考えているから、オーバースピードでコーナーに進入した時、ハンドルを切り足せば曲がるのは、CFが増えてラインが保てるのではなく
“CRが増えて速度が落ちる”から円を小さく出来るというのが、本当の理由。
正しく走らせるには切り足さなくても良いように、進入スピードをピタリにコントロールすることだ。
つまりはサーキット走行といえども、タイヤに行き先を尋ねて走らせるのではなく、
タイヤが発生しうる上限Gを、行き過ぎないスピードに合わせる事で、
CRの少ないおいしいタイヤの使い方ができるのだ。
その訓練がG-BOWLでできるのだが・・・。



















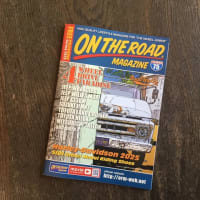
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます