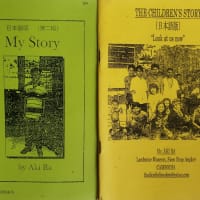カンボジアで仏像を見ていると、首のないものに出くわすことも少なくない。これには大きく二つの出来事が関係しているが、その一つは、仏教を大々的に保護したジャヤバルマン7世の後に起こった廃仏による。
彼の治世には、それまでヒンドゥー教が宗教の中心を占めていたところに仏教を据え、アンコール・トムの中でも有名なバイヨン寺院などを建造している。このような政策は、彼の両親とも王家の本流出身ではなく、かつ前代までの戦乱で王都が荒廃するなどしていたから、自らを「新しい秩序により王国を立て直す者」として正当化・権威化しようとしたことによるらしい(なお、宗教による現体制の否定に関しても、太平道の黄巾の乱、白蓮教徒による紅巾の乱、上帝会が始めた太平天国の乱など枚挙に暇がない)。
その取り組みを見ていると、王都テーベでの神官団の権力伸長を嫌ってアトン一神教を掲げつつ遷都も行った、エジプト新王国のイクナートン(アメンホテプ4世)が思い出される。要するに、宗教と政治や権力闘争が密接に結びついていたわけで、中華王朝では北魏の太武帝が寇謙之の新天師道=道教を国教として廃仏を行ったことに始まる中華王朝の「三武一宗の法難」が有名だし、日本でも、近世移行期には天文法華の乱や一向一揆が生じていたわけで、幅広く見られる現象と言える(なお、そういった事象を等閑視して、日本を宗教的に寛容と評価するのは、いささか大雑把に過ぎるというものだろう)。
ただ、こういう政策転換(宗旨替え)は既得権益側からの反発も当然起こるわけで、イクナートン亡き後は元のアモン・ラー信仰が復活してイクナートンの像は顔が削りとられることとなったし、ジャヤバルマン亡き後は一代空いてヒンドゥー教側による大規模な廃仏が行われ、冒頭のような仏像が多く生み出されることとなった。なお、同時代の仏像には無傷のものも残っており、それらは仏教を信仰する民衆が「匿った」ものであるらしい。こういう点も、(当たり前ではあるが)権力者の政策と民衆の信仰を同一視しないことが重要となる。
ちなみに、政府や権力者による宗教政策と、民衆の動向の乖離という点では、日本における神仏分離と廃仏毀釈が思い出される。新政府は、王政復古の大号令のもと、神道に基づいた政治(実際には復古というより新しい「伝統の創出」だったのだが)を復活させようと考え、神宮寺のように神道と仏教が混淆したそれまでの状況を不健全と判断し、両者の分離を決定した。この動きが、江戸時代にキリスト教排斥のため檀家制度の形で国教化されていた仏教勢力への反発という形で噴出し、薩摩など特に神道の強い地域では大規模な廃仏毀釈運動へとつながったのであった(なお、戦中でさえも神仏分離の発想が徹底しなかったことは、以前紹介した「九段の母」とそのヒットからも伺える)。
カンボジアに話を戻すと、宗教弾圧という点でもう一つの画期は、クメール・ルージュによるものであった。

これはプノンペンのトゥール・スレン虐殺博物館で展示されているものだが、ポル・ポト派による宗教施設の破壊や信徒の虐殺の様が描かれており、同じ共産主義の中国による文化大革命を想起することは容易だろう。
こういった行為はいかにも「野蛮」なように思われるかもしれないが、しかし前述のように明治維新=近代化に伴って廃仏運動を起こした日本は言わばその「先達」であって、要はイデオロギーに基づいて広域に強権的な体制を作ろうとすれば、どこでも同じようなことが起こることを示している(例えばナショナリズム及び近代市民社会の始まりとも目されるフランス革命についても、その理性崇拝から宗教が抑圧され、結果として古代の神の名前を冠した月の名前でさえ、ブリュメールやテルミドールなどに変えられたのである)。
こうした様々な国の事例と日本の過去の現象を比較してみれば、その凡庸さというものが認識されるのであり、それをちょっとした特徴からすぐに善かれ悪しかれ唯一無二の性質のように言うのは、まさに島国根性(視野狭窄による無知・偏向)のなせるわざと言えるのではないか。何度か指摘している「脱亜入欧的ナショナリズム」、すなわち欧米を鑑としてそれとは違う日本の特性を謳いながら、その実アジアについては(仏像とナーガの結合といった宗教的混淆など含め)ほとんどが全く無視してしまうものの見方は、その最たるものだと思われる。
・・・なんてことをまあカンボジアで改めて思ったわけだが、帰国してから前に買った『日本人無宗教説』を読み始めたらこれがまたおもしろいことおもしろいこと!日本人の根拠なき自己像というか、よくここまで断言というか安易に決めつけられるなと呆れを通り越して感心さえするのだが、実は日本人無宗教説がすでに明治期から政府高官や知識人の発言、さらに横浜毎日新聞・東京日日新聞・郵便報知などの社説で当たり前のように流布されていたことは、強く私の興味を引くものであった(50%以上がある特定の宗教を信仰しているという結果が出た、1952年の統計調査などとの乖離がおもしろい)。
このあたりは、今ちょうど読み進めているところなので、6月に入ったら書評を書きたいところである。