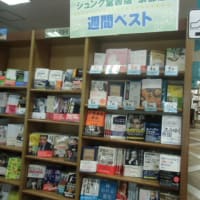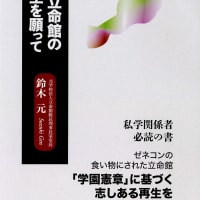NO67 (NO66の補足)
立命館の常任理事ならびに関係各位へ
常任理事会は教職員の批判にこたえて、川崎昭治常務と陰山英男校長顧問の解任、ANUとの共同学位学部構想中止の決断が求められている
2017年3月7日 元立命館総長理事室室長・ジャーナリスト・ 鈴木元
※この原稿は、立命館問題専用のブログ( スズキ ゲンさんのブログ )にも掲載しています。
目次
はじめに
(1)川崎昭治一貫教育担当常務理事の解任は避けて通れない。
(2)陰山英男立命館小学校校長顧問の解任は立命館の社会的責任である。
(3)足羽問題、長岡京問題
(4)学部長理事の半数が疑問を呈しているANUとの共同学部構想(国際教養学部)は止める決断を下す時である。
(5) 選挙で選ばれた学部長理事の立場を自覚した態度表明を期待する。
はじめに
2月11日付けのNO66の「はじめ」において以下の要旨で記した。――7月に予定されている理事改選を前に、現在の立命館の理事会体制の問題点と克服方向について提起しようとしたが、学内的には附属校問題が焦点となっているので、附属校の管理問題に絞って記した。続いてNO67で全体像を描く予定している――。
ところが、あまりにも自明な立命館小学校校における陰山英男校長顧問のパワハラ、川崎常務のセクハラ発言に対して、教職員組合などからリアルに問題が提出され解任を求める要望が提出されてから既に2カ月以上が経っている。常任理事会の対応はあまりにも遅すぎる。
近く開催される常任理事会で両名の解任の決断を下すべきである。またこの二つの件とは関係がないが、年度がかわることとかかわって、予てから学内の多数から批判・危惧が発せられてきたANUとの共同学位学部(国際教養学部)が、2017年度においても既定事実のごとく進められようとしているが、これも取りやめる決断を下すべきである。
改めて常任理事会・学部長理事の決断、さらに総長・副総長の判断が求められている。その点で、その後明らかになったことを含めて補足提起する
(1)川崎昭治一貫教育担当常務理事の解任は避けて通れない。
3月1日の理事のみ会議において役員懲戒審査委員会が設置された。これが川崎昭治常務を対象としたものであることは翌日3月2日の部次長会議で報告されている。そして一連の問題で、川崎昭治常務が一貫教育担当常務理事としては不適格であるにも関わらず即刻の対処が行われないことをみて、9名の学部長理事が意見を提出したことによってようやく役員懲戒審査委員会の設置が提起されることになったことも明らかなになった。
しかし①川崎昭治常務は守山高校教諭の不適切行為への対応問題でも役員懲戒審査委員会の対象ともなっており、近くその報告が提出される予定となっている。その人が附属校教職員を対象とした新年祝賀会において学園を代表して行った挨拶においてセクハラ発言をし、役員懲戒審査対象となったのである。同一人物が同じ時期に2つの役員懲戒審査委員会の対象となっても、役職手当の半額返上で常務理事の地位にとどまっている。②しかもその審査委員長が①の事件で、人事担当の総務担当常務理事として、森島朋三専務、川崎昭治一貫教育担当常務とともに、その責任が問われている志磨慶子総務担当常務である。その点が糾されたのに対して「ほかに適当な人材がいない」との趣旨の答弁が行われている。ここに現在の立命館が長田豊臣ならびに森島朋三と言うどこにも選出基盤の無い人間たちによって占拠され、自壊作用・劣化現象を起こしていることが明瞭に表れている。このことだけでも学園の、役員体制の在り方の抜本的改革による人事刷新が避けて通れないことを示している。なお今回の事態で常務会の「コアメンバー」が機能不全に陥っていることが改めて明らかになった。抜本的な役員体制の改革・人事刷新をまつまでもなく常任理事会メンバーを中心に役員懲戒審査委員会などを構成すべきであろう。
(2)陰山英男立命館小学校校長顧問の解任は立命館の社会的責任である。
陰山英男校長顧問が行ってきたパワハラ行為については、ここでは繰り返さない。彼が立命館小学校において教育者そして人間としての尊厳を踏みにじり教育現場を破壊してきたことは明白である。しかも彼は校内にとどまらず、社会的に父母に対しても立命館の教職員を侮辱してきただけではなく、最近では自分の解任を恐れ父母に対してあることないことを吹聴し、あおっていることが伝えられている。このような人格的に問題のある人物は一刻も早く解任しなければ立命館の評価を下げるだけでなく、引き続き立命館小学の運営に重大な支障をきたすことは明白である。
NO66において陰山英男を立命館に招聘したのは森島朋三専務であると記した。その際、森島朋三専務は、彼を校長就任で招聘しようとしたが、本人から①立命館の大学教授にすること②小学校は副校長とすることを条件として要求し実行された。当時、森島朋三次長は私の下にいて小学校開設の事務局を担当していたが、私が守山市立女子商業高校の合併問題で手を取られていたこともあったが、まったくなんの相談も報告もせず、川本八郎理事長の指示のもとで行動し、陰山英男の大学教員採用は長田豊臣総長の再配で実行に移された。私がこれらを知ったのは開設直後の事であった。いずれにしても陰山英男の人事は当該の立命館小学校の関係者のあずかり知らぬことであり、森島朋三専務ならびに長田豊臣理事長が責任を負うべき問題である。
今となっては3月末(年度内)までの解雇手続きが時間的に間に合わなくとも、まず校長顧問を解任し、自宅謹慎とし、その後に手続きに即して大学教員身分を含めて立命館から解職しなければならない。
(3)足羽問題、長岡京問題
この二つの件は重大であるがNO66で必要最小限の事は記しているので省略する。
ただ一点補足すると、長岡京キャンパスの汚染問題を巡っての立命館による大阪成蹊に対する訴訟は、森島朋三専務らの責任回避のためのプレーであるが、相手側にとっては何のメリットもない裁判であり「和解」の可能性もある。例えそうした措置が取られても、立命館中高等学校の長岡移転により当初予算と比較しても25億円にも及ぶ出費増をもたらしたという森島朋三専務、志方弘樹現総務部長、長田豊臣理事長等の責任は消えない。
(4)学部長の半数が疑問を呈しているANUとの共同学部構想(国際教養学部)は止める決断を下す時である。
開設構想がうちだされてから既に4年以上が経っている。いまだにカリキュラムの基本も、主たる責任を負う教員も、そして財政見通しも立っていない、英語で専門教育を受ける学部であるにもかかわらず、当初の入学資格を下げトーフル550点でも入学させ、入学させてから英語力を向上させて英語での専門科目を受けさせるようにするとの変更も提起されている。そこに到達しない場合は立命館大学の学位だけで卒業との方針が出されている。ANU側がこうした措置に妥協したのは外貨獲得の為であって教育的な判断だとは思われない。
カナダのUBCプログラムの場合、1年間の語学研修の上、専門科目を英語で受講できる水準に達していれば専門課程に編入できるが、100名の定員の内、1年間で専門課程に進級できるものは10名前後である。しかし大半の学生は最初から1年間の「語学研修」として位置付けて参加している。ANUとの提携は共同学位学部を売りにしている学部である。まさに詐欺のような行為と批判されてもやむをえない。
もういい加減に止める決断を下す時である。それに対して「国際約束だから進める以外にはない」との発言も行われている。しかしこの構想は学内での合意の上に交渉が開始されたものではなく川口清史前総長が常任理事会にも諮らず勝手に約束したものである。安倍首相が、日豪安保提携の強化・潜水艦の売り込みのためにオーストラリアを訪問し首相間合意を図った(その後、潜水艦はフランスが受注した)。その際、学術のオブラートで包み、軍事の臭いを和らげるために、全国の大学学長の中でただ一人政府専用機に同乗し安倍首相立会いの下でANUとの協力協定に調印したのが始まりである。しかしその時の協定には共同学位学部設置は明記されていなかった。その後、彼が立命館東京オフィスで記者会見を行った際に明らかにしたものである。何時までもこんなことに振り回されている必要はない。既に立命館大学の14名の学部長のうち7名の学部長が「もう止めるべきである」との意思を表明されている。以前から言ってきたように川口清史前総長(現顧問)の責任で謝罪し取り止めてくるべきものである。
(4) 選挙で選ばれた学部長理事の立場を自覚した態度表明を期待する。
2005年の一時金1ヵ月カット以来の立命館での混乱の主たる責任は川本八郎前理事長、長田豊臣前総長、川口清史前総長、森島朋三総務担当常務理事によって引き起こされ、2007年に長田豊臣理事長、森島朋三専務理事体制になって以降は、大阪茨木キャンパス購入強行にはじまって主として、この両名によって引き起こされてきた。
しかし2010年の茨木購入に際して5学部長が常任理事会ならびに理事会において反対を表明した以降は、学部長理事からは批判的意見が述べられることはあっても、議決に際して明確に反対の意思表示がなされてこなかった。これが長田豊臣理事長ならびに森島朋三専務理事に「教員、学部長などは、あれこれ意見は述べても、最後は反対せず従う。それどころか、あれこれの学部要求を頼みに来る」とつけあがらせてきた。
今回の川崎昭治常務理事ならびに陰山英男校長顧問の問題についても、あれこれ論議するが結局あいまいにしたり、また明確に持続できる教育構想も財政計画も提出できずにいるANUとの共同学位学部構想をずるずると継続審議を繰り返し、止める決断をくださない態度が長田豊臣理事長や森島朋三専務理事の居直りを許している。
この点で選挙によって選ばれている学部長理事の責任も大きい。せっかく学部教授会を基礎に教員・職員・そして学生も参加した学部長理事制度の主旨・意義を自覚し、その場で判断が難しい場合は「学部執行部会議や教授会の意見を聞いてからにしたい」と持ち帰るなどして、明確な態度表明ができるようにすべきである。また全学構成員の選挙によって選ばれた吉田美喜夫総長が全学の学園正常化の期待に応えて行動する為にも、学部長理事の明確な対応、さらに、その構成員を社会的、全学的な視点で啓蒙し、学部・職場を励まし運動を高める教職員組合などの果たす役割も大きいと指摘せざるを得ない。そうでなければ折角、学園の正常化を願って実現した吉田総長体制、に対して失望感を広げ「学園全体の事は言うても始まらない学部(学科等)中心で行こう」と言う気風が広がり始めている。学部長理事の奮起を期待したい。
鈴木元。立命館大学総長理事長室室長、大阪初芝学園副理事長、中国(上海)同済大学アジア太平洋研究センター顧問教授、JICA中国人材アドバイザリー、私立大学連盟アドミニストレ―タ研修アドバイザリーなどを歴任。
現在、日本ペンクラブ会員、日本ジャーナリスト会議会員、かもがわ出版取締役、国際環境整備機構理事長。
『像とともに 未来を守れ』(かもがわ出版)『立命館の再生を願って 正・続』(風涛社)『もう一つの大学紛争』(かもがわ出版)『大学の国際協力』(文理閣)など著書多数。
立命館の常任理事ならびに関係各位へ
常任理事会は教職員の批判にこたえて、川崎昭治常務と陰山英男校長顧問の解任、ANUとの共同学位学部構想中止の決断が求められている
2017年3月7日 元立命館総長理事室室長・ジャーナリスト・ 鈴木元
※この原稿は、立命館問題専用のブログ( スズキ ゲンさんのブログ )にも掲載しています。
目次
はじめに
(1)川崎昭治一貫教育担当常務理事の解任は避けて通れない。
(2)陰山英男立命館小学校校長顧問の解任は立命館の社会的責任である。
(3)足羽問題、長岡京問題
(4)学部長理事の半数が疑問を呈しているANUとの共同学部構想(国際教養学部)は止める決断を下す時である。
(5) 選挙で選ばれた学部長理事の立場を自覚した態度表明を期待する。
はじめに
2月11日付けのNO66の「はじめ」において以下の要旨で記した。――7月に予定されている理事改選を前に、現在の立命館の理事会体制の問題点と克服方向について提起しようとしたが、学内的には附属校問題が焦点となっているので、附属校の管理問題に絞って記した。続いてNO67で全体像を描く予定している――。
ところが、あまりにも自明な立命館小学校校における陰山英男校長顧問のパワハラ、川崎常務のセクハラ発言に対して、教職員組合などからリアルに問題が提出され解任を求める要望が提出されてから既に2カ月以上が経っている。常任理事会の対応はあまりにも遅すぎる。
近く開催される常任理事会で両名の解任の決断を下すべきである。またこの二つの件とは関係がないが、年度がかわることとかかわって、予てから学内の多数から批判・危惧が発せられてきたANUとの共同学位学部(国際教養学部)が、2017年度においても既定事実のごとく進められようとしているが、これも取りやめる決断を下すべきである。
改めて常任理事会・学部長理事の決断、さらに総長・副総長の判断が求められている。その点で、その後明らかになったことを含めて補足提起する
(1)川崎昭治一貫教育担当常務理事の解任は避けて通れない。
3月1日の理事のみ会議において役員懲戒審査委員会が設置された。これが川崎昭治常務を対象としたものであることは翌日3月2日の部次長会議で報告されている。そして一連の問題で、川崎昭治常務が一貫教育担当常務理事としては不適格であるにも関わらず即刻の対処が行われないことをみて、9名の学部長理事が意見を提出したことによってようやく役員懲戒審査委員会の設置が提起されることになったことも明らかなになった。
しかし①川崎昭治常務は守山高校教諭の不適切行為への対応問題でも役員懲戒審査委員会の対象ともなっており、近くその報告が提出される予定となっている。その人が附属校教職員を対象とした新年祝賀会において学園を代表して行った挨拶においてセクハラ発言をし、役員懲戒審査対象となったのである。同一人物が同じ時期に2つの役員懲戒審査委員会の対象となっても、役職手当の半額返上で常務理事の地位にとどまっている。②しかもその審査委員長が①の事件で、人事担当の総務担当常務理事として、森島朋三専務、川崎昭治一貫教育担当常務とともに、その責任が問われている志磨慶子総務担当常務である。その点が糾されたのに対して「ほかに適当な人材がいない」との趣旨の答弁が行われている。ここに現在の立命館が長田豊臣ならびに森島朋三と言うどこにも選出基盤の無い人間たちによって占拠され、自壊作用・劣化現象を起こしていることが明瞭に表れている。このことだけでも学園の、役員体制の在り方の抜本的改革による人事刷新が避けて通れないことを示している。なお今回の事態で常務会の「コアメンバー」が機能不全に陥っていることが改めて明らかになった。抜本的な役員体制の改革・人事刷新をまつまでもなく常任理事会メンバーを中心に役員懲戒審査委員会などを構成すべきであろう。
(2)陰山英男立命館小学校校長顧問の解任は立命館の社会的責任である。
陰山英男校長顧問が行ってきたパワハラ行為については、ここでは繰り返さない。彼が立命館小学校において教育者そして人間としての尊厳を踏みにじり教育現場を破壊してきたことは明白である。しかも彼は校内にとどまらず、社会的に父母に対しても立命館の教職員を侮辱してきただけではなく、最近では自分の解任を恐れ父母に対してあることないことを吹聴し、あおっていることが伝えられている。このような人格的に問題のある人物は一刻も早く解任しなければ立命館の評価を下げるだけでなく、引き続き立命館小学の運営に重大な支障をきたすことは明白である。
NO66において陰山英男を立命館に招聘したのは森島朋三専務であると記した。その際、森島朋三専務は、彼を校長就任で招聘しようとしたが、本人から①立命館の大学教授にすること②小学校は副校長とすることを条件として要求し実行された。当時、森島朋三次長は私の下にいて小学校開設の事務局を担当していたが、私が守山市立女子商業高校の合併問題で手を取られていたこともあったが、まったくなんの相談も報告もせず、川本八郎理事長の指示のもとで行動し、陰山英男の大学教員採用は長田豊臣総長の再配で実行に移された。私がこれらを知ったのは開設直後の事であった。いずれにしても陰山英男の人事は当該の立命館小学校の関係者のあずかり知らぬことであり、森島朋三専務ならびに長田豊臣理事長が責任を負うべき問題である。
今となっては3月末(年度内)までの解雇手続きが時間的に間に合わなくとも、まず校長顧問を解任し、自宅謹慎とし、その後に手続きに即して大学教員身分を含めて立命館から解職しなければならない。
(3)足羽問題、長岡京問題
この二つの件は重大であるがNO66で必要最小限の事は記しているので省略する。
ただ一点補足すると、長岡京キャンパスの汚染問題を巡っての立命館による大阪成蹊に対する訴訟は、森島朋三専務らの責任回避のためのプレーであるが、相手側にとっては何のメリットもない裁判であり「和解」の可能性もある。例えそうした措置が取られても、立命館中高等学校の長岡移転により当初予算と比較しても25億円にも及ぶ出費増をもたらしたという森島朋三専務、志方弘樹現総務部長、長田豊臣理事長等の責任は消えない。
(4)学部長の半数が疑問を呈しているANUとの共同学部構想(国際教養学部)は止める決断を下す時である。
開設構想がうちだされてから既に4年以上が経っている。いまだにカリキュラムの基本も、主たる責任を負う教員も、そして財政見通しも立っていない、英語で専門教育を受ける学部であるにもかかわらず、当初の入学資格を下げトーフル550点でも入学させ、入学させてから英語力を向上させて英語での専門科目を受けさせるようにするとの変更も提起されている。そこに到達しない場合は立命館大学の学位だけで卒業との方針が出されている。ANU側がこうした措置に妥協したのは外貨獲得の為であって教育的な判断だとは思われない。
カナダのUBCプログラムの場合、1年間の語学研修の上、専門科目を英語で受講できる水準に達していれば専門課程に編入できるが、100名の定員の内、1年間で専門課程に進級できるものは10名前後である。しかし大半の学生は最初から1年間の「語学研修」として位置付けて参加している。ANUとの提携は共同学位学部を売りにしている学部である。まさに詐欺のような行為と批判されてもやむをえない。
もういい加減に止める決断を下す時である。それに対して「国際約束だから進める以外にはない」との発言も行われている。しかしこの構想は学内での合意の上に交渉が開始されたものではなく川口清史前総長が常任理事会にも諮らず勝手に約束したものである。安倍首相が、日豪安保提携の強化・潜水艦の売り込みのためにオーストラリアを訪問し首相間合意を図った(その後、潜水艦はフランスが受注した)。その際、学術のオブラートで包み、軍事の臭いを和らげるために、全国の大学学長の中でただ一人政府専用機に同乗し安倍首相立会いの下でANUとの協力協定に調印したのが始まりである。しかしその時の協定には共同学位学部設置は明記されていなかった。その後、彼が立命館東京オフィスで記者会見を行った際に明らかにしたものである。何時までもこんなことに振り回されている必要はない。既に立命館大学の14名の学部長のうち7名の学部長が「もう止めるべきである」との意思を表明されている。以前から言ってきたように川口清史前総長(現顧問)の責任で謝罪し取り止めてくるべきものである。
(4) 選挙で選ばれた学部長理事の立場を自覚した態度表明を期待する。
2005年の一時金1ヵ月カット以来の立命館での混乱の主たる責任は川本八郎前理事長、長田豊臣前総長、川口清史前総長、森島朋三総務担当常務理事によって引き起こされ、2007年に長田豊臣理事長、森島朋三専務理事体制になって以降は、大阪茨木キャンパス購入強行にはじまって主として、この両名によって引き起こされてきた。
しかし2010年の茨木購入に際して5学部長が常任理事会ならびに理事会において反対を表明した以降は、学部長理事からは批判的意見が述べられることはあっても、議決に際して明確に反対の意思表示がなされてこなかった。これが長田豊臣理事長ならびに森島朋三専務理事に「教員、学部長などは、あれこれ意見は述べても、最後は反対せず従う。それどころか、あれこれの学部要求を頼みに来る」とつけあがらせてきた。
今回の川崎昭治常務理事ならびに陰山英男校長顧問の問題についても、あれこれ論議するが結局あいまいにしたり、また明確に持続できる教育構想も財政計画も提出できずにいるANUとの共同学位学部構想をずるずると継続審議を繰り返し、止める決断をくださない態度が長田豊臣理事長や森島朋三専務理事の居直りを許している。
この点で選挙によって選ばれている学部長理事の責任も大きい。せっかく学部教授会を基礎に教員・職員・そして学生も参加した学部長理事制度の主旨・意義を自覚し、その場で判断が難しい場合は「学部執行部会議や教授会の意見を聞いてからにしたい」と持ち帰るなどして、明確な態度表明ができるようにすべきである。また全学構成員の選挙によって選ばれた吉田美喜夫総長が全学の学園正常化の期待に応えて行動する為にも、学部長理事の明確な対応、さらに、その構成員を社会的、全学的な視点で啓蒙し、学部・職場を励まし運動を高める教職員組合などの果たす役割も大きいと指摘せざるを得ない。そうでなければ折角、学園の正常化を願って実現した吉田総長体制、に対して失望感を広げ「学園全体の事は言うても始まらない学部(学科等)中心で行こう」と言う気風が広がり始めている。学部長理事の奮起を期待したい。
鈴木元。立命館大学総長理事長室室長、大阪初芝学園副理事長、中国(上海)同済大学アジア太平洋研究センター顧問教授、JICA中国人材アドバイザリー、私立大学連盟アドミニストレ―タ研修アドバイザリーなどを歴任。
現在、日本ペンクラブ会員、日本ジャーナリスト会議会員、かもがわ出版取締役、国際環境整備機構理事長。
『像とともに 未来を守れ』(かもがわ出版)『立命館の再生を願って 正・続』(風涛社)『もう一つの大学紛争』(かもがわ出版)『大学の国際協力』(文理閣)など著書多数。