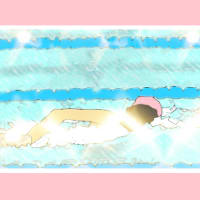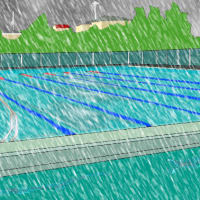十分の休憩中、梨花と若本はベンチで隣りあっていた。この三日間で初めてのことだ。梨花は緊張しながらも、泳ぎのコツについて若本に質問するつもりだった。太ももや上半身を隠せるバスタオルでもあればよかったのだけれど、そこはビート板でごまかしていく。
「あの、さ。どうしてあんなにうまく泳げるの?」
「ああ。小学校から中学ん時まで、スイミングクラブに通ってたの。最初は下手くそだったけどね」
「それで、なんだ。でも、なんで補習受けてるの? 私みたいに仮病使いまくってたの?あんなにうまければ必要ないじゃん?」
「甲田サン、仮病が原因で補習になっちゃったの?」
「うん。水泳苦手だったし」
「ああ、それは見ていてわかる」
「ひどい。苦手なのは本当だけど……」
「ははは。しょげないでよ。で、えーと、そうそう。前期の記録会の授業の日? そのときだけ休んじゃって記録を出してないのよ。実は」
「風邪かなんかで?」
「まさか。ま、ここだけの話だけど。甲田サン、内緒にしてくれる?」
「う、うん。なに、どうしたの?」
「実はさ、俺さ……」
「うん」
「あの日、外国のバンドのライブが市内のアリーナであってさ、で、それ目当てで朝からズル休みしたの」
「えー? 朝からコンサートがあったの?」
「声でかっ! ここだけの話だっつーのに」
若本が口に指を当てて、周囲をうかがっている。休憩中、下田はいつもどこかに消えている。絶対泳ぐなよ、とくぎをさして。問題が起こってからでは遅いのに、どうも言動が矛盾している。まあ、休憩中まで監視されるよりはいいけど。
若本は額に垂れた前髪をかきあげていた。
「あのねー、甲田サン。興行的に考えてみなよ。朝からライブがあるわけないじゃん」
「あ、そうなの? そういえばそうか。だいたい夜だよね、コンサートって。あ、でも歌謡コンサートとか、昼の部とかなかったっけ? 二部構成のやつ」
「硬派のロックバンドが昼の部なんかやらないから。あのね、とにかく俺は、当日券しか手に入らなかったんで、朝からプレイガイドに並んでたの! どこまで天然なのよ、甲田サン」
「あ、そうなんだ。あの、私天然じゃないからね」
「いや、そう念押しするところが天然っぽいんだけどね」
「そうなの? ちがうと思うけど。馬鹿っぽいもん、天然って。言葉のひびきが」
「甲田さぁーん……。ま、それはおいおい語るとして。んでね、チケットがゲットできて、日中マックだとか本屋で時間つぶして、夜からはじけたわけさ」
「後悔してないの? 記録会、休んだ価値があるくらい、コンサートはすごかったの?」
「そりゃ、もう。甲田サンに言ってもわかんないだろうけど」
「音楽が好きなんだ。私、特定のアーティストのファンになったことないからなあ」
「そこはもう運命でしょ。出会いってやつだと思うね。聴いた瞬間、ハマったかどうかだから」
「へえ。どんなジャンルの音楽なの?」
「だからロック」
「うるさいやつでしょ?」
「まあ、それなりに。で、俺バンドもしてるからさ。あの豪快な音圧が風になる瞬間がやみつきになるの。ロックはたまらないのよ」
「バンド? 楽器できるの?」
「うん。親戚連中と四人組でね。俺はギター担当だけど」
「すごーい。じゃあ、それこそライブ観たら自分たちもライブをやりたくなるよね」
「おっ、その指摘はまともじゃん。そうそう、そのために練習しまっくてんのよ」
「そうなんだあ。すごいね」
そこまでで、二人の会話はいったん途切れた。思いのほか、梨花はすらすらと言葉を繰りだせていた。若本には話しやすい雰囲気があるのだろう。彼には誰をも無下に拒絶しない、懐の広さがあるんだと思う。もちろん、心の中ではいろいろ考えているのだろうけど。
梨花は浅く腰をかけて得意げにしている若本の横顔を密かに見ていた。なるほどね。彼のお調子者の風袋(ふうたい)は、彼の好きなことにも大きく影響されていたんだね。
バンドマンだもんね。目立ってナンボだよね、多分。夢中になれることがあるなんてうらやましい。梨花には一つもない。どうやって見つけるんだろう。
ベンチの屋根の下で日陰になっているせいもあるが、若本の全身の肌はほどよく焼けて見える。もう少しこんがりしていたら、完全に健康体って感じがする。呼吸しているのが一目でわかるお腹の動き。なんか、かわいい。
おへそから水がこぼれ落ちていく瞬間をたまたま見ていた。そのままビキニパンツの生地に吸収されていったみたい。その時、若本の視線を何となく感じた。いけない。自分も変態扱いされたら困る。無言の空間は気まずさを生みやすい、と思った。

努めて冷静に正面を向いてみる。外気温は目で見て感じられるくらい高そうだ。太陽を浴びつづけるプールの水面が、とろとろとうごめいていた。ここに二人だけで浸かっているんだよね。あらためて不思議に思う。広いもんね、二人だと。若本が補習にずっと来なかったら寂しかったかも。
心の中でぼんやり考えていると、若本の左ひざが梨花のももの上のビート板に当たった。若本はわざとではなかったのだろう、あ、という顔をしたまま何も言わなかった。梨花とそのまま数秒間見つめあう。梨花はくすぐったい、と思った。
「そろそろ休憩、終わりかな」
若本は後頭部を忙しそうにかくと、梨花から視線をはずした。彼の耳が赤い。梨花も頭部全体が熱っぽい。若本はこの補習とか、梨花のこと、感じるものはあるのかな。大げさに意識しているのは、梨花だけなのかな。ももの上のビート板のすれた感触は、まだ消えないで残っていた。
「よしっと。あと二秒縮めるかな」
若本がそう言いながら立ちあがったとき、梨花はあることを思いだしていた。
「ああっ!」
「びっくりした。何?」
「クロール。クロールをうまく泳ぐコツを教えてほしいの」
「なんだ、そんなこと? 突然絶叫するから。やっぱ天然だよなあ」
「そんなことどうでもいいから、教えて。休憩終わっちゃう」
「せかすなあ。初めから聞いてくれればよかったのに」
若本は困惑した顔を見せたが、黙って梨花の手を取り、立つようにうながしてくれた。若本に手をつかまれたその感触が、とても生々しかった。ずうっとそこにとどまる温度。お尻が触れ合ったときみたい。このきゅん、ってどこから生まれるんだろう。
「下田に何て言われているのか分かんないけど、甲田サンのクロールのフォームは基本的に問題ないと思う。ただ、もう少しスピードをうまくコントロールできれば、二十五メートルを泳ぎきれると思うんだ」
「うん」
「体に余計な力が入ってるんじゃないかな。まずキックは水面を強くたたくんじゃなくて、しなやかにたたくの、鞭みたいに。そしたら、自然と手の動きのリズムに合ってくるから」
若本は上体を折り曲げて、クロールのかきとバタ足の動きを連動させて説明してくれる。
そういえば、梨花のバタ足はたたきつけてばかりだったかもしれない。足が異様に疲れるのもそれが原因だったのか。コンビネーションね。梨花も見よう見まねで若本の動きを反復する。
「で、手のかきなんだけど。水中で水をとらえる時の肘の使い方が重要なの。指先から入水させたら、手の平を下に向けて肘を伸ばすでしょ。肘の骨は外側に向いているよね。そこから、肘を九十度回転させて肘の内側を下向きにするの。肘が上に来るようにするんだ。これで効率的に水をとらえられるの」
若本が熱心に教えてくれる。梨花は大きく肘を曲げてみた。水中でのイメージをしっかり意識して、と。ここはもう実践して、身体にたたきこむ部分だと感じた。
≪つづく≫
「あの、さ。どうしてあんなにうまく泳げるの?」
「ああ。小学校から中学ん時まで、スイミングクラブに通ってたの。最初は下手くそだったけどね」
「それで、なんだ。でも、なんで補習受けてるの? 私みたいに仮病使いまくってたの?あんなにうまければ必要ないじゃん?」
「甲田サン、仮病が原因で補習になっちゃったの?」
「うん。水泳苦手だったし」
「ああ、それは見ていてわかる」
「ひどい。苦手なのは本当だけど……」
「ははは。しょげないでよ。で、えーと、そうそう。前期の記録会の授業の日? そのときだけ休んじゃって記録を出してないのよ。実は」
「風邪かなんかで?」
「まさか。ま、ここだけの話だけど。甲田サン、内緒にしてくれる?」
「う、うん。なに、どうしたの?」
「実はさ、俺さ……」
「うん」
「あの日、外国のバンドのライブが市内のアリーナであってさ、で、それ目当てで朝からズル休みしたの」
「えー? 朝からコンサートがあったの?」
「声でかっ! ここだけの話だっつーのに」
若本が口に指を当てて、周囲をうかがっている。休憩中、下田はいつもどこかに消えている。絶対泳ぐなよ、とくぎをさして。問題が起こってからでは遅いのに、どうも言動が矛盾している。まあ、休憩中まで監視されるよりはいいけど。
若本は額に垂れた前髪をかきあげていた。
「あのねー、甲田サン。興行的に考えてみなよ。朝からライブがあるわけないじゃん」
「あ、そうなの? そういえばそうか。だいたい夜だよね、コンサートって。あ、でも歌謡コンサートとか、昼の部とかなかったっけ? 二部構成のやつ」
「硬派のロックバンドが昼の部なんかやらないから。あのね、とにかく俺は、当日券しか手に入らなかったんで、朝からプレイガイドに並んでたの! どこまで天然なのよ、甲田サン」
「あ、そうなんだ。あの、私天然じゃないからね」
「いや、そう念押しするところが天然っぽいんだけどね」
「そうなの? ちがうと思うけど。馬鹿っぽいもん、天然って。言葉のひびきが」
「甲田さぁーん……。ま、それはおいおい語るとして。んでね、チケットがゲットできて、日中マックだとか本屋で時間つぶして、夜からはじけたわけさ」
「後悔してないの? 記録会、休んだ価値があるくらい、コンサートはすごかったの?」
「そりゃ、もう。甲田サンに言ってもわかんないだろうけど」
「音楽が好きなんだ。私、特定のアーティストのファンになったことないからなあ」
「そこはもう運命でしょ。出会いってやつだと思うね。聴いた瞬間、ハマったかどうかだから」
「へえ。どんなジャンルの音楽なの?」
「だからロック」
「うるさいやつでしょ?」
「まあ、それなりに。で、俺バンドもしてるからさ。あの豪快な音圧が風になる瞬間がやみつきになるの。ロックはたまらないのよ」
「バンド? 楽器できるの?」
「うん。親戚連中と四人組でね。俺はギター担当だけど」
「すごーい。じゃあ、それこそライブ観たら自分たちもライブをやりたくなるよね」
「おっ、その指摘はまともじゃん。そうそう、そのために練習しまっくてんのよ」
「そうなんだあ。すごいね」
そこまでで、二人の会話はいったん途切れた。思いのほか、梨花はすらすらと言葉を繰りだせていた。若本には話しやすい雰囲気があるのだろう。彼には誰をも無下に拒絶しない、懐の広さがあるんだと思う。もちろん、心の中ではいろいろ考えているのだろうけど。
梨花は浅く腰をかけて得意げにしている若本の横顔を密かに見ていた。なるほどね。彼のお調子者の風袋(ふうたい)は、彼の好きなことにも大きく影響されていたんだね。
バンドマンだもんね。目立ってナンボだよね、多分。夢中になれることがあるなんてうらやましい。梨花には一つもない。どうやって見つけるんだろう。
ベンチの屋根の下で日陰になっているせいもあるが、若本の全身の肌はほどよく焼けて見える。もう少しこんがりしていたら、完全に健康体って感じがする。呼吸しているのが一目でわかるお腹の動き。なんか、かわいい。
おへそから水がこぼれ落ちていく瞬間をたまたま見ていた。そのままビキニパンツの生地に吸収されていったみたい。その時、若本の視線を何となく感じた。いけない。自分も変態扱いされたら困る。無言の空間は気まずさを生みやすい、と思った。

努めて冷静に正面を向いてみる。外気温は目で見て感じられるくらい高そうだ。太陽を浴びつづけるプールの水面が、とろとろとうごめいていた。ここに二人だけで浸かっているんだよね。あらためて不思議に思う。広いもんね、二人だと。若本が補習にずっと来なかったら寂しかったかも。
心の中でぼんやり考えていると、若本の左ひざが梨花のももの上のビート板に当たった。若本はわざとではなかったのだろう、あ、という顔をしたまま何も言わなかった。梨花とそのまま数秒間見つめあう。梨花はくすぐったい、と思った。
「そろそろ休憩、終わりかな」
若本は後頭部を忙しそうにかくと、梨花から視線をはずした。彼の耳が赤い。梨花も頭部全体が熱っぽい。若本はこの補習とか、梨花のこと、感じるものはあるのかな。大げさに意識しているのは、梨花だけなのかな。ももの上のビート板のすれた感触は、まだ消えないで残っていた。
「よしっと。あと二秒縮めるかな」
若本がそう言いながら立ちあがったとき、梨花はあることを思いだしていた。
「ああっ!」
「びっくりした。何?」
「クロール。クロールをうまく泳ぐコツを教えてほしいの」
「なんだ、そんなこと? 突然絶叫するから。やっぱ天然だよなあ」
「そんなことどうでもいいから、教えて。休憩終わっちゃう」
「せかすなあ。初めから聞いてくれればよかったのに」
若本は困惑した顔を見せたが、黙って梨花の手を取り、立つようにうながしてくれた。若本に手をつかまれたその感触が、とても生々しかった。ずうっとそこにとどまる温度。お尻が触れ合ったときみたい。このきゅん、ってどこから生まれるんだろう。
「下田に何て言われているのか分かんないけど、甲田サンのクロールのフォームは基本的に問題ないと思う。ただ、もう少しスピードをうまくコントロールできれば、二十五メートルを泳ぎきれると思うんだ」
「うん」
「体に余計な力が入ってるんじゃないかな。まずキックは水面を強くたたくんじゃなくて、しなやかにたたくの、鞭みたいに。そしたら、自然と手の動きのリズムに合ってくるから」
若本は上体を折り曲げて、クロールのかきとバタ足の動きを連動させて説明してくれる。
そういえば、梨花のバタ足はたたきつけてばかりだったかもしれない。足が異様に疲れるのもそれが原因だったのか。コンビネーションね。梨花も見よう見まねで若本の動きを反復する。
「で、手のかきなんだけど。水中で水をとらえる時の肘の使い方が重要なの。指先から入水させたら、手の平を下に向けて肘を伸ばすでしょ。肘の骨は外側に向いているよね。そこから、肘を九十度回転させて肘の内側を下向きにするの。肘が上に来るようにするんだ。これで効率的に水をとらえられるの」
若本が熱心に教えてくれる。梨花は大きく肘を曲げてみた。水中でのイメージをしっかり意識して、と。ここはもう実践して、身体にたたきこむ部分だと感じた。
≪つづく≫