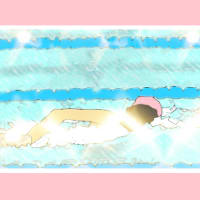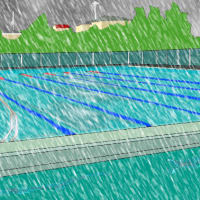あいつを見守るような女子班員たちの顔は、どれもやわらかなものだった。クラスに溶け込もうとして起こしたあいつのアクションに触れられて、嬉しかったのかもしれない。
他の男子班員も手を動かしながら、その光景を長く見届けていた。彼らの胸にも、同様の感情が去来していたのだろう。信次は膝をついたまま、完全に手を止めていた。
信次が幾度となく起こそうとして躊躇しつづけてきたアクション=行動。あいつは勇気を振り絞る形で、見事にそれを発露させていた。
信次はあいつのその瞬発力に、そのいさぎよさに魅せられる思いだった。信次にもあんな瞬間はいくつもあったはずなのに、見送りつづけていた。
勇気を持ち、それを使う覚悟はあるのか。
そんな直言を今一度、突きつけられたような思いだった。
少なくとも、あいつはお手本のようなスタートを切っていた。同じ匂いがしたなんて、信次のただの思いすごしでしかなかった。そうはっきりと、確信していた。
「ねー、信次君。そこ、まだ掃いてなかったんだけどなあ……。もしかして拭いちゃった?」
動きを止めていた信次は完全に面食っていた。あいつと一緒にいた女子班員が、困った顔で聞いてきたからだ。
信次は一瞬、何のことだか分からず、あいつに定めていた視線を女子班員の方へ慌ててずらしたほどだった。
信次はその時初めて、不自然な輝きを発する床の表面に気づいていた。とある範囲だけ、ほこりが拭きとられた跡が異様に残っていたのだ。
すぐさま雑巾を裏面に返した。その異様な黒さに凝視せざるを得なかった。
あいつは遠慮がちに信次を見ていた。焦ったが、もはや過去に戻れるわけでもない。信次はばつの悪さを感じ、観念して謝っていた。
「ごめん。拭いちゃってた……」
机を拭いていた一人の男子班員が、ぷっと吹いていた。その男子班員の反応に目を丸くしていたのはあいつ。それは驚きからだったのか、単なる物珍しさからのものだったのか。
いずれにせよ、いつものこと、というような感じで信次に相対してくる冷静な班員たちの様子は、新入りには異様に映るのかもしれなかった。
「ちゃんと確認してね」
「分かった。気をつける……」
女子班員は苦笑いしながら、再びモップ型のほうきを動かしはじめていた。あいつは目を泳がせながら、不器用な感じで信次から目線をそらしていった。その瞬間、不可知なことなのに、あいつの心の中を覗いた気分だった。
それはこんな感じだ。
信次と呼ばれた男子は変なやつで、事あるごとにどじを踏む存在なんだ。分かりやすすぎるくらいだったけれど、覚えておこう――。
いや、最後の「覚えておこう」なんて感情は、あいつにはなかっただろう。それは信次自身の身勝手な願望の現れでしかなかった。
あいつにはいい印象を持っておいてもらいたかったという、嘆願にも似たものだ。
あいつの目前で恥をかくのは必然だったのかもしれない。あいつを尊重することもなく、早々に同類とみなし、どこか相手を見下したような態度でいたこと。
それを神様か誰かに見透かされたのだと、信次は邪推していた。
こそこそと他人を盗み見ながら、実効性も無い、実現もしない指南を妄想し続けていたのだ。信次本体から醸し出された「妨害電波」みたいなものが、遠隔操作によって遠巻きにあいつを傷つけようとしていた。
それを相手が知らなくても、信次に罪の意識がなければ、その報いは当事者と相対する形で不意にやってくるものだ。罪深さを思い知らされるために。
となれば、そこでの己の見苦しさ、いやしさからは逃れられない。後悔して、自責の念を覚え、相手への怒りをちらつかせながら、自分への怒りを抱えつづける。信次はまた同じことをくりかえしていた。
信次は雑巾の汚れを落とすために(本当はその場から逃げるために)、誰を見ることなく立ちあがっていた。
信次が教室前方のドアの方へ向かうと、なぜか朝見たきりだった担任が顔を覗かせていた。そこにいつからいたのか、見当もつかなかった。
担任が一連の事の顛末を目撃していたのだとしたら、信次は恥の上塗りをしていたことになる。
担任は意気消沈する信次には目もくれず、ひび割れた声であいつの名を呼んでいた。あいつからの返事はなかった。
「あのな、掃除は当番が決まっているから今日はやらなくていいぞ。その気持ちだけでも十分、十分。でな、悪いんだけど帰りに職員室へ寄ってくれるか?」
担任はもちろんのこと、信次すら、あいつから何らかの返答があるものと思って待っていた。だけど、あいつからの返答は何もなかった。
担任は怪訝(けげん)そうな表情すら見せず、うん、とうなずくだけで、早々に背中を見せていた。
信次は少なからず驚き、振りかえってあいつの方を見やった。あいつはいつの間にか自分の席に戻り、鞄やら紙袋やらを手中にたぐりよせていた。
自分の名前を呼ばれても、用件を頼まれても声を発しない、特異な習性―――。
あきらめの悪い信次が復活。あいつとの同類項をまた探しだそうとしていた。しかし実際は、直前の己の失敗をどうにかして帳消しにしようともがいていただけだった。
都合の悪い自意識は急にどこかへ飛んでいったりしない。溶けはじめた氷の融解を止められないのと一緒だ。信次はやるせない思いで教室を出ていた。
洗い場で雑巾をゆすいでいると、背後でたったったっ、という小走りの足音が聞こえ、遠くに離れていった。大荷物を抱えたようなあいつの、廊下を走っている姿が見えた。
信次はそれをうらめしそうに目で追いかけていた。あいつが角を曲がっていなくなるまで、ずっと。短かった半日が、長く感じられた瞬間だった。
これから交流する機会はいくらでもあるだろう。
今の情けない信次を取りつくろう機会だって訪れるかもしれない。
でも、まちがっても気の置けない存在になるわけでもない。
勝手にしやがれ。
信次は憤慨する相手を見誤ったまま、蛇口を全開にしていた。
雨を落としそうな鉛色の雲。
あの日の昼過ぎ、それが空一面に渡っていた。それは忘れようもない。信次は校門を出ながら、大気がそれ以上不安定にならないことを望んでいた。
陽炎が踊らない市街地の渋滞。それを横目に行く頃も、天気は変わっていなかった。
道中、信次が考えていたことは、翌日の試験科目、それぞれの不安要素について。そして、帰宅後のひまつぶしについて。
でも、結局それらの思考は長つづきせず、ふがいない午前中の自分と得体の知れないあいつのことを思い返していた。
信次は白い運動靴の底を滑らせながら、歩道の車道側を歩いていた。それなのに、信次の左側(つまり、さらに車道側)を何台もの自転車がすり抜けていった。
危ないなあ、と感じながらもようやく気づいていた。信次が歩道上の自転車レーンを歩いていたことを。注意が働かないほど、信次はぼんやりしていたのだ。
無かったことにできない自らの立ち振る舞い。普段よりも時間があるからこそ、その後悔を引きずることになる。
気持ちを切り替えることができないまま、翌日に突入することが何よりも怖かった。でも、後悔の振り切りかたを知らなかった。初めての体験ではないのに、悩みもだえていた。
「よう」
突如、右肩に鈍い圧力を受けた。見れば、信次よりも数センチ背の高い男子が横にいた。掃除が始まる前、机を早く下げろとうながしていたあのクラスメートだった。
早々に帰宅したはず。
なぜ今ここにいる。
いつから信次の後をつけてきたのだ。
信次の頭の中ではいくつかの疑問が錯綜した。だが、それを男子にぶつけることはできなかった。
「ああ、よう」
信次はぎこちない返事を返しただけだった。それでも、男子はそれに不満を感じている様子はなかった。
しばらく無言で並び歩いた二人。なぜか意気揚々としていたのは男子。彼とは普段でもあまり話したことがなかった。息がつまりそうになっていたのは、信次だけだっただろう。
「明日、数学と社会と、あと何だったっけ?」
出しぬけに男子が聞いてきた。相手の質問に何かの作為があるようには思えなかった。だが、信次は警戒を解くことができず、慎重に、慎重に答えをたぐりよせていた。
「たしか、たしか、保健体育だったと思う。ちがっていたらごめん」
「そうか。じゃあ一応、自分でも確認しとく」
男子はそう言うと、右肩にかついでいた鞄を左肩にかつぎ直していた。いきおい、鞄は信次の右上腕に当たった。それは明らかに意図的だったように思う。
「じゃあな」
男子はそう言うと、片側二車線の道路に架かる、歩道橋の階段を上っていった。信次が男子の尻のあたりを見上げている間、相手は一度も振りかえることがなかった。
信次は不思議な気持ちに包まれたまま、階段の脇を歩きはじめることしかできなかった。
ここで道路を渡るってことは、意外と近所に住んでいるのかな。
それにしても、なぜ声をかけてきたのだろう。
からかうことでも企んでいたのかな。
今しがたの男子の様子を思い返すにつれ、信次の謎は深まるばかりだった。ただ、うまく対応できずにしくじった、という、おなじみの自責の念はなかった。
それよりも、しだいに心の奥底でざわついていったものがある。それはかすかな清涼感、と言うべきもの。相手方を、そして今しがたの自分を何度も再現したい。そんな願望にとらわれていった。
信次はマンホールの蓋を踏みながら、高揚感を隠しきれなかった。何かが控えめに始まりそうで、心が震えそうだった。
相手が信次にもたらしたものを、何でもいい、感じたかったのだと思う。下り側の階段の前に出たら、歩道橋上にいる男子の姿を見てやろうと心に誓っていたほどだ。
急く気持ちを落ち着かせることはできなかった。歩道橋を支える白い円柱を、急ぎ足で追い越していた。
しだいに、水色の階段の側面が角度をつけて下ってくる。階段の底部を支える、かさ上げされたコンクリートの段が、日陰の中でも膨張して見えた。信次は固唾をのんでその時を待った。
薄いえんじ色に塗られたアスファルトが途切れた瞬間、ななめ左上を仰ぎ見た。横に伸びる水色の鉄板、その上に並ぶ格子状の手すり。
手すりから上には、水平移動する男子の後頭部が見えているはずだった。
でも、見えていたのは湾曲して垂れる電線や、ビルの谷間の曇り空だけだった。視界を狭める窮屈な角度から脱しようと、足もとをあまり見ずに距離を稼いだ。そして何度も仰ぎ見た。
それでも、男子の姿は見えなかった。
歩道橋を駆け渡り、駆け下りた後だったのか。道路の反対側を見ても、渋滞の車列の隙間を覗いても、それらしい人間はいなかった。信次は放心状態のまま、後ずさりするように歩道上を移動していた。
≪つづく≫
他の男子班員も手を動かしながら、その光景を長く見届けていた。彼らの胸にも、同様の感情が去来していたのだろう。信次は膝をついたまま、完全に手を止めていた。
信次が幾度となく起こそうとして躊躇しつづけてきたアクション=行動。あいつは勇気を振り絞る形で、見事にそれを発露させていた。
信次はあいつのその瞬発力に、そのいさぎよさに魅せられる思いだった。信次にもあんな瞬間はいくつもあったはずなのに、見送りつづけていた。
勇気を持ち、それを使う覚悟はあるのか。
そんな直言を今一度、突きつけられたような思いだった。
少なくとも、あいつはお手本のようなスタートを切っていた。同じ匂いがしたなんて、信次のただの思いすごしでしかなかった。そうはっきりと、確信していた。
「ねー、信次君。そこ、まだ掃いてなかったんだけどなあ……。もしかして拭いちゃった?」
動きを止めていた信次は完全に面食っていた。あいつと一緒にいた女子班員が、困った顔で聞いてきたからだ。
信次は一瞬、何のことだか分からず、あいつに定めていた視線を女子班員の方へ慌ててずらしたほどだった。
信次はその時初めて、不自然な輝きを発する床の表面に気づいていた。とある範囲だけ、ほこりが拭きとられた跡が異様に残っていたのだ。
すぐさま雑巾を裏面に返した。その異様な黒さに凝視せざるを得なかった。
あいつは遠慮がちに信次を見ていた。焦ったが、もはや過去に戻れるわけでもない。信次はばつの悪さを感じ、観念して謝っていた。
「ごめん。拭いちゃってた……」
机を拭いていた一人の男子班員が、ぷっと吹いていた。その男子班員の反応に目を丸くしていたのはあいつ。それは驚きからだったのか、単なる物珍しさからのものだったのか。
いずれにせよ、いつものこと、というような感じで信次に相対してくる冷静な班員たちの様子は、新入りには異様に映るのかもしれなかった。
「ちゃんと確認してね」
「分かった。気をつける……」
女子班員は苦笑いしながら、再びモップ型のほうきを動かしはじめていた。あいつは目を泳がせながら、不器用な感じで信次から目線をそらしていった。その瞬間、不可知なことなのに、あいつの心の中を覗いた気分だった。
それはこんな感じだ。
信次と呼ばれた男子は変なやつで、事あるごとにどじを踏む存在なんだ。分かりやすすぎるくらいだったけれど、覚えておこう――。
いや、最後の「覚えておこう」なんて感情は、あいつにはなかっただろう。それは信次自身の身勝手な願望の現れでしかなかった。
あいつにはいい印象を持っておいてもらいたかったという、嘆願にも似たものだ。
あいつの目前で恥をかくのは必然だったのかもしれない。あいつを尊重することもなく、早々に同類とみなし、どこか相手を見下したような態度でいたこと。
それを神様か誰かに見透かされたのだと、信次は邪推していた。
こそこそと他人を盗み見ながら、実効性も無い、実現もしない指南を妄想し続けていたのだ。信次本体から醸し出された「妨害電波」みたいなものが、遠隔操作によって遠巻きにあいつを傷つけようとしていた。
それを相手が知らなくても、信次に罪の意識がなければ、その報いは当事者と相対する形で不意にやってくるものだ。罪深さを思い知らされるために。
となれば、そこでの己の見苦しさ、いやしさからは逃れられない。後悔して、自責の念を覚え、相手への怒りをちらつかせながら、自分への怒りを抱えつづける。信次はまた同じことをくりかえしていた。
信次は雑巾の汚れを落とすために(本当はその場から逃げるために)、誰を見ることなく立ちあがっていた。
信次が教室前方のドアの方へ向かうと、なぜか朝見たきりだった担任が顔を覗かせていた。そこにいつからいたのか、見当もつかなかった。
担任が一連の事の顛末を目撃していたのだとしたら、信次は恥の上塗りをしていたことになる。
担任は意気消沈する信次には目もくれず、ひび割れた声であいつの名を呼んでいた。あいつからの返事はなかった。
「あのな、掃除は当番が決まっているから今日はやらなくていいぞ。その気持ちだけでも十分、十分。でな、悪いんだけど帰りに職員室へ寄ってくれるか?」
担任はもちろんのこと、信次すら、あいつから何らかの返答があるものと思って待っていた。だけど、あいつからの返答は何もなかった。
担任は怪訝(けげん)そうな表情すら見せず、うん、とうなずくだけで、早々に背中を見せていた。
信次は少なからず驚き、振りかえってあいつの方を見やった。あいつはいつの間にか自分の席に戻り、鞄やら紙袋やらを手中にたぐりよせていた。
自分の名前を呼ばれても、用件を頼まれても声を発しない、特異な習性―――。
あきらめの悪い信次が復活。あいつとの同類項をまた探しだそうとしていた。しかし実際は、直前の己の失敗をどうにかして帳消しにしようともがいていただけだった。
都合の悪い自意識は急にどこかへ飛んでいったりしない。溶けはじめた氷の融解を止められないのと一緒だ。信次はやるせない思いで教室を出ていた。
洗い場で雑巾をゆすいでいると、背後でたったったっ、という小走りの足音が聞こえ、遠くに離れていった。大荷物を抱えたようなあいつの、廊下を走っている姿が見えた。
信次はそれをうらめしそうに目で追いかけていた。あいつが角を曲がっていなくなるまで、ずっと。短かった半日が、長く感じられた瞬間だった。
これから交流する機会はいくらでもあるだろう。
今の情けない信次を取りつくろう機会だって訪れるかもしれない。
でも、まちがっても気の置けない存在になるわけでもない。
勝手にしやがれ。
信次は憤慨する相手を見誤ったまま、蛇口を全開にしていた。
雨を落としそうな鉛色の雲。
あの日の昼過ぎ、それが空一面に渡っていた。それは忘れようもない。信次は校門を出ながら、大気がそれ以上不安定にならないことを望んでいた。
陽炎が踊らない市街地の渋滞。それを横目に行く頃も、天気は変わっていなかった。
道中、信次が考えていたことは、翌日の試験科目、それぞれの不安要素について。そして、帰宅後のひまつぶしについて。
でも、結局それらの思考は長つづきせず、ふがいない午前中の自分と得体の知れないあいつのことを思い返していた。
信次は白い運動靴の底を滑らせながら、歩道の車道側を歩いていた。それなのに、信次の左側(つまり、さらに車道側)を何台もの自転車がすり抜けていった。
危ないなあ、と感じながらもようやく気づいていた。信次が歩道上の自転車レーンを歩いていたことを。注意が働かないほど、信次はぼんやりしていたのだ。
無かったことにできない自らの立ち振る舞い。普段よりも時間があるからこそ、その後悔を引きずることになる。
気持ちを切り替えることができないまま、翌日に突入することが何よりも怖かった。でも、後悔の振り切りかたを知らなかった。初めての体験ではないのに、悩みもだえていた。
「よう」
突如、右肩に鈍い圧力を受けた。見れば、信次よりも数センチ背の高い男子が横にいた。掃除が始まる前、机を早く下げろとうながしていたあのクラスメートだった。
早々に帰宅したはず。
なぜ今ここにいる。
いつから信次の後をつけてきたのだ。
信次の頭の中ではいくつかの疑問が錯綜した。だが、それを男子にぶつけることはできなかった。
「ああ、よう」
信次はぎこちない返事を返しただけだった。それでも、男子はそれに不満を感じている様子はなかった。
しばらく無言で並び歩いた二人。なぜか意気揚々としていたのは男子。彼とは普段でもあまり話したことがなかった。息がつまりそうになっていたのは、信次だけだっただろう。
「明日、数学と社会と、あと何だったっけ?」
出しぬけに男子が聞いてきた。相手の質問に何かの作為があるようには思えなかった。だが、信次は警戒を解くことができず、慎重に、慎重に答えをたぐりよせていた。
「たしか、たしか、保健体育だったと思う。ちがっていたらごめん」
「そうか。じゃあ一応、自分でも確認しとく」
男子はそう言うと、右肩にかついでいた鞄を左肩にかつぎ直していた。いきおい、鞄は信次の右上腕に当たった。それは明らかに意図的だったように思う。
「じゃあな」
男子はそう言うと、片側二車線の道路に架かる、歩道橋の階段を上っていった。信次が男子の尻のあたりを見上げている間、相手は一度も振りかえることがなかった。
信次は不思議な気持ちに包まれたまま、階段の脇を歩きはじめることしかできなかった。
ここで道路を渡るってことは、意外と近所に住んでいるのかな。
それにしても、なぜ声をかけてきたのだろう。
からかうことでも企んでいたのかな。
今しがたの男子の様子を思い返すにつれ、信次の謎は深まるばかりだった。ただ、うまく対応できずにしくじった、という、おなじみの自責の念はなかった。
それよりも、しだいに心の奥底でざわついていったものがある。それはかすかな清涼感、と言うべきもの。相手方を、そして今しがたの自分を何度も再現したい。そんな願望にとらわれていった。
信次はマンホールの蓋を踏みながら、高揚感を隠しきれなかった。何かが控えめに始まりそうで、心が震えそうだった。
相手が信次にもたらしたものを、何でもいい、感じたかったのだと思う。下り側の階段の前に出たら、歩道橋上にいる男子の姿を見てやろうと心に誓っていたほどだ。
急く気持ちを落ち着かせることはできなかった。歩道橋を支える白い円柱を、急ぎ足で追い越していた。
しだいに、水色の階段の側面が角度をつけて下ってくる。階段の底部を支える、かさ上げされたコンクリートの段が、日陰の中でも膨張して見えた。信次は固唾をのんでその時を待った。
薄いえんじ色に塗られたアスファルトが途切れた瞬間、ななめ左上を仰ぎ見た。横に伸びる水色の鉄板、その上に並ぶ格子状の手すり。
手すりから上には、水平移動する男子の後頭部が見えているはずだった。
でも、見えていたのは湾曲して垂れる電線や、ビルの谷間の曇り空だけだった。視界を狭める窮屈な角度から脱しようと、足もとをあまり見ずに距離を稼いだ。そして何度も仰ぎ見た。
それでも、男子の姿は見えなかった。
歩道橋を駆け渡り、駆け下りた後だったのか。道路の反対側を見ても、渋滞の車列の隙間を覗いても、それらしい人間はいなかった。信次は放心状態のまま、後ずさりするように歩道上を移動していた。
≪つづく≫